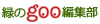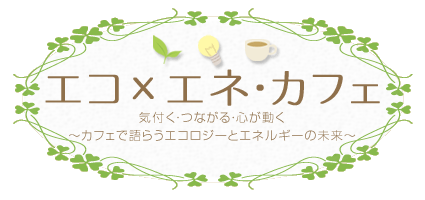第11回 「サイエンスリテラシーから見たエコとエネ」古田ゆかり 氏
冒頭で話したように、私たちは今これだけ科学技術に囲まれた生活をしているわけですから、自分で考えて、しっかり議論していくことが大切なのだなと思います。
例えばBSE(牛海綿状脳症)は、どう発生してどんな健康被害があるかは分かっていますが、それが他国で起こった場合に、牛肉の輸入をすべてストップすればいいのか、輸入をストップすれば安全は守られるかもしれないけれど、牛肉業界の打撃は相当なものになる、そういった社会的コストをどうするのか考えなくてはなりません。そういうことを考えると、BSEの科学的特性だけをみて食肉を扱うことはできない。リスクをどこまでとどめて、自分の生命をどうやって守るのかということにもつながってきます。
車についても、ハイブリッドだったら全部いいというわけではないですよね。高速を長距離走るとハイブリッドの特性がでていいかもしれませんが、スーパーの買い物や幼稚園の送り迎えなど短距離で乗ることが多い人にとって重い電池を積んだハイブリッドに乗ることがほんとうに環境によいのか。そういうことを知った上で考えていくことが必要なのではないかということを、今日の私からの投げかけにしたいと思います。


森:
ここで、藤木さんに、参加者を代表して質問に入っていただきましょう。
藤木: 自分の生命や財産を守るためにいろいろなことを知る必要があるというのはよく理解できますが、例えばエネルギーの問題も、その裏側にある社会や生活のことを考えていくと複雑な事情があります。そこまですべて考えていくのは難しいことだと思うのですが、それについて古田さんはどう考えますか。


古田: 私も実際にはとても難しいことだと思います。エネルギーの政策に関する意見表明は、民主主義の原則に従ってそれぞれ必要だと思うことを言う、いわば投票のようなものだと思うんですね。だからこそ「人任せ」「気分任せ」にはしないで、もう少し自分で裏にある背景まで考えてみることが大切なのかなと思います。逆にいうと、これまであまりにもお任せ状態だったことを、自分たちの手に取り戻すというマインドを持つことが大切ということなのだと思いますね。
藤木:
いろいろなことを知った上で、自分で判断していく。そういう積み重ねは大事ですよね。民主主義はもともとそういうものだったのかなと思います。
古田:覚悟しなくてはならないのは、民主主義は合意形成に時間がかかるということです。民主主義を考える上での社会との距離の取り方、他者の意見の受け入れ方のようなことも同時に身につけていかなくてはならないのかなと思いますね。
藤木:
全員一致というのはなかなか難しいのでしょうね。
古田:
ないでしょうし、あると危ないですよね。

古田さんからの問題提起を受けて、これからはワールドカフェでの対話の時間です。