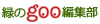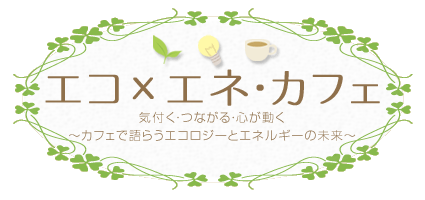第14回 「森林再生で日本の未来を変える!?」佐々木 豊志 氏
問2 森林資源の活用が広がると、日本の未来はどう変わるだろうか?

2問目は更に掘り下げた問いに
森林が私たちの生活の質の向上に結びつくという意見がありました。
「森林がある空間は大事。そこから新鮮な空気が得られる。健全な森林が増え、環境に配慮した木材の利用が広まったら、シックハウスのような症状が減り、健康増幅にも役立つと思います」「都会にも小さな森ができて、人々が気軽に森林浴を楽しめるようになっていくといいですね」


森林の活用を阻む課題についての指摘もありました。
「国産材を使うことが大切だと思うのですが、輸入材と比べて値段が高い。一般の消費者にとっては、いくら価値があるものでも、購入には価格の壁が大きな障害になっています」「北欧諸国では、森林と人の共生した暮らしが実現されているそうですが、日本の森林は勾配が急で、手がつけにくく、整備が難しい点も多いと聞きます。いずれにしても、行政の政策が変わることが、森林と人との関係が変わるキッカケになるということは言えると思います」「自分たちの親の世代にとって、山や森林は危険な場所というイメージが強いような気がする。森林に対するイメージや理解を変えていかなくてはいけない人たちの層は厚いと感じます」


また、多くのテーブルで「森林資源の活用が広がる」こと自体をイメージすることが難しいという意見も見受けられました。
一方、「森に誰も手を加えなくなったら、益々荒れていってしまう。そうすると、益々森が私たちにとって遠い存在になる。使わないことのマイナス点なら想像できるのですが、どうしたらいいか、具体的なアイデアが見いだせません」といった意見もありました。
森林について理解が深まれば、将来の姿も変わってくるかもしれないという意見もありました。
「佐々木さんから、震災時に、森林資源をつかった木質ペレットが役立ったという話がありましたが、こういうことがもっと知られていったら、防災の観点からも森林の利用を考えようという発想がもっと広がるような気がします」「佐々木さんと話しているといろいろなアイデアに気づかされるのですが、そもそも気づくための想像力が自分にはないし、多くの人たちにとってもそれは同じだと思う。森林について理解するための情報や教育が必要なのではないでしょうか。知ることで、考え方がきっと変わるように思うのです」
森をつくるには時間がかかる。だからこそ先ずは想像力を広げ、イメージを抱くことが大切なのだというコメントもありました。