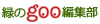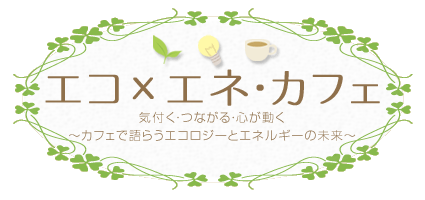第14回 「森林再生で日本の未来を変える!?」佐々木 豊志 氏
震災に木材を役立てる
佐々木:日本の森バイオマスネットワークでは、木質ペレットストーブの普及を通じて、木材の活用を目指していました。東日本大震災では、停電により体を温めることができず、低体温症が課題となっていましたので、木質ペレットストーブを各地の避難所に届けたのです。さらには、地元の木材で仮設住宅を建てようと申し出たのですが、残念ながら法律的制約からそれは難しく、代わりに共生住宅「手のひらに太陽の家」をつくることにしました。放射線量が高い福島の子どもたちが保養のためにショートステイできる施設として、寄付金に支えられ運営しています。ここは、燻煙乾燥木材を活用、断熱材もウールを使っていて、化学物質が全然ない。太陽光パネルや木質ペレットも使っている、環境に良い、循環可能なエネルギーを使った施設でもあります。






佐々木:昔の人は森から薪をとって、エネルギー源にしていたんです。震災の後、エネルギーへの関心が高まりました。これで考えて欲しいのですが、エネルギーは50%が電気、20%が都市ガスで提供されています。利用についてみると、約1/3は熱なんですね。例えば、東北電力と北海道電力のピークは冬。それは熱エネルギーを電気で供給するケースが増えているからなんです。


佐々木:木材は熱エネルギーに向いています。だから、熱エネルギーを木質バイオマスからとるように変えていけたら、地域の森林資源の活用にもなるし、エネルギーの課題の解決にも結びつくし、とても良いと思いました。 日本は国家予算の1/3-1/4ものお金を、石油のために海外へと支払っています。日本にある資源を活用したエネルギーを使うことことができれば、お金を日本の国内で、あるいは地域でまわしていけるのではないかと思うのです。


佐々木:実は、東北とオーストリアを比較すると、面積も人口もとても似ています。2009年、オーストリアでは再エネがエネルギー供給に占める割合が28%、バイオマスも17.3%ありました。彼らは国策として、2020年までに1/3は再エネにする政策を打ち出しています。ですから、オーストリアでは、政策に裏付けされて、森林資源の活用に向けたいろいろな方策がでてきています。合板木材で、橋やビルを造るといったことも行なわれているんです。

オーストリアと東北地方

合板木材の橋の写真
佐々木:また、条例で、ガスの他に必ず木質エネルギーを使うようにと定められている村もあるそうです。熱エネルギー供給は、地域に燃料倉庫を持つことで、小規模なネットワークで実現することもできるんですね。日本は技術があっても、仕組みが無い。これを、東北で実現できないかと考えています。


佐々木:オーストリアのザルツブルク州はエネルギーの6割が農家によって発電されています。日本は電力会社のほとんどが大手企業です。バイオマス燃料を使うことによって、地域に多くの雇用も生まれると言われています。つまり、地域経済の活性化にもつながるんです。小さな規模のエネルギー供給のしくみは今の日本にはないけれど、なんとか広めていきたいですね。