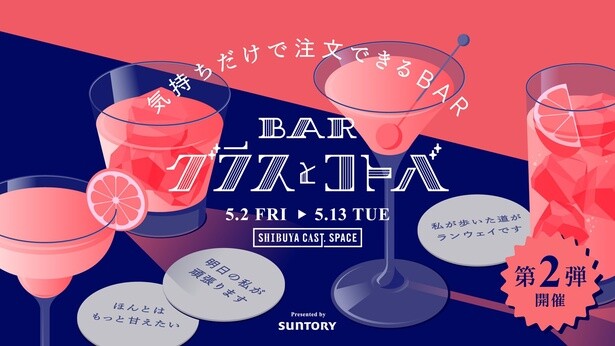宇宙飛行士・若田光一さん、岡山の関西高校で講演 民間主導の宇宙産業へ

宇宙飛行士の若田光一さんの講演会「日本人初のISS船長(コマンダー)若田光一氏が語る宇宙開発と産業の未来」が4月28日、関西高校(岡山市北区西崎町)の体育館で開かれた。主催は、空飛ぶ車の実用化を目指す航空宇宙産業クラスター「MASC」。(岡山経済新聞)
若田さんは1996(平成8)年、日本人初のミッションスペシャリストとしてスペースシャトル・エンデバー号に搭乗。2000(平成12)年にスペースシャトル・ディスカバリーに搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)の建設に関わる。2009(平成21)年から日本人初のISSの長期滞在し、2013(平成25)年から188日の長期滞在で後半は日本人初のISS船長も務めた。2022年には民間企業スペースXのクルーとして5度目の宇宙へ。通算504日の宇宙滞在時間は日本人最長記録を更新した。
当日は、同校吹奏楽部の「宇宙戦艦ヤマト」の演奏と共に登場。会場は高校生200人、一般参加者200人の計400人余りが参加した。1969(昭和44)年のアポロ11号月面着陸が幼少期の若田さんに与えた影響などから、NASAの訓練、1992(平成4)年に初めて宇宙飛行士として選ばれた時の記者会見の様子などについて話した。
若田さんは、尿や汗から水を作る技術や小型化や自動化が進み、クルーの訓練軽減により前澤友作さんのような民間宇宙飛行者が増えていること、2030年に現在15カ国で運用されているI SSの運用終了とともに民間主導での宇宙産業の可能性について話した。
若田さんは「ISSでの微少重力や真空に近い環境下を生かした経済活動ができる。ガンの治療薬などの創薬やIPS細胞を使った人工臓器の製造、半導体の製造なども可能性がある。ファッションブランドのプラダとは宇宙服の共同開発、フィンランドの通信機器メーカー・ノキアとは地上との通信の共同開発をするなど、民間だからできる国を超えた国際協力が生まれている」と話す。
後半は一般社団法人「宇宙旅客輸送推進協議会」代表理事の稲谷芳文さんと対談。アルテミス計画など月や火星への探査や人類滞在についても話した。「主体性のあるチームづくり」「UFOやエイリアンの存在について」「宇宙でのヒヤリとした体験」など参加者からの質問にも応えた。
あわせて読みたい
-

- 水星からダイヤモンドがざくざく採掘できるかもしれない説
- 水星からダイヤモンドがざくざく採掘できるかもしれない説Image: NASA / Johns Hopkins University Applie…
- (Gizmodo Japan)[航空・宇宙開発,宇宙]
-

- 週間天気予報 GW4連休は天気の移り変わり早い 最終日は広範囲で雨
- 2025/05/02 05:28 ウェザーニュース 【 この先のポイント 】・4連休前半は北日本や北陸を中心に雨・GW最終…
- (ウェザーニューズ)[天体観測]
-
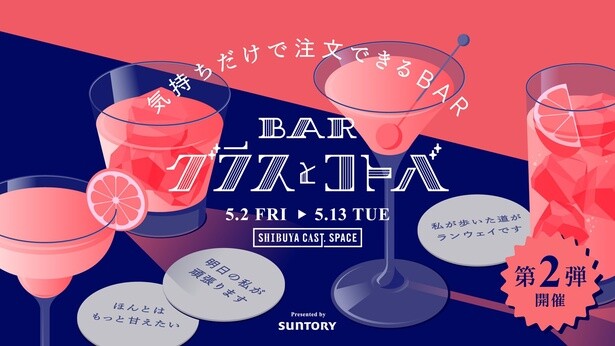
- 「ほんとはもっと甘えたい…」その気持ちがカクテルに。昨年即完の「BAR グラスとコトバ」第2弾が渋谷で開催
- 2024年にSNSで話題となった「BAR グラスとコトバ」が今年も渋谷に登場する。2025年5月2日から13日(火)まで…
- (Walkerplus)[東京都]
-

- 発達した雨雲は近畿から東海へ 関東も一部で雨が強まる
- 2025/05/02 10:18 ウェザーニュース今日5月2日(金)は低気圧の通過に伴い、局地的に雨が強まっています。活…
- (ウェザーニューズ)[愛知県]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[岡山県]
-

- 青梅の中学生・野崎日向さん、来季アルペンスキー世界大会目指す
- 青梅市立霞台中学校3年生の野崎日向さんがアルペンスキー2025-26ユースAの全日本強化指定選手となり、来季…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[みんなの経済新聞ネットワーク]
-

- 【フブ】Vネック&チームロゴがポイント!ユニセックスで着用可能な注目アイテム、Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[ファッション]
-

- ヒュー・グラント主演のホラー映画「異端者の家」を鑑賞。若いシスターたちを監禁して信仰心を試す初老男性に震え上がる!
- 2025年4月25日より全国公開された「異端者の家」。スタジオA24が新たに仕掛ける異端の脱出サイコスリラー…
- (Walkerplus)[新商品]
キーワードからさがす
Copyright (c) 2025 みんなの経済新聞ネットワーク All Rights Reserved.