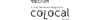10年以上の月日を経て、陸前高田にワイナリーを誕生させるまで。
岩手県は三陸海岸の南東部に位置する陸前高田(りくぜんたかた)市。牡蠣の産地として知られる広田湾の、美しく静かな青色を望む、高台のブドウ畑まで、海のリフレクションが眩しく届く。

美しい広田湾のリフレクション。実はこれもまたワイナリーにとっての恵みとなる。
この地で2021年、新しいワイナリーが立ち上がった。
〈ドメーヌミカヅキ〉。
立ち上げたのは陸前高田で生まれ育ったひとりの青年。及川恭平さん、当時27才。
設立の目的は、ワインそのものの文脈でいえば、「陸前高田のテロワールを生かして、地元の美味である牡蠣や魚介に合うワインを造る」こと。

広田半島と唐桑半島の2つの半島に挟まれた穏やかな湾には、気仙川からプランクトン豊富な水が流れ込む。海と山の恵みがすばらしい牡蠣を育む。

牡蠣漁師の大和田晴男(はれお)さんとともに海へ。広田湾で最大面積を誇る牡蠣養殖一家である大和田さんは及川さんのワインツーリズムの理解者。お互いの信頼感をもとに、牡蠣漁船に乗り、牡蠣を食べワインを飲み、船からテロワールを感じてもらうプランを進めている。
テロワール。ワイン業界では一般的に使われている用語で、ブドウが育つための気候、土壌のことを指し、それゆえに生まれる産地の個性や品質を生かし、楽しむこと。
陸前高田のテロワールをざっと書けば、複雑なリアス式海岸からの海風。冬でもそれほど極寒にはならないが、1日の寒暖差はしっかりある気候。海からすぐに高台へと続く斜面があるので日照も十分。広田湾からの照り返しも日照のひとつだ。
ワイン好きの人に向けて例えるなら、「スイスに似ていると感じます」と及川さん。スイスのワイン造りには「3つの太陽」があるという。太陽、石垣が蓄える輻射熱、美しい湖の照り返し。
広田湾の静かで入り組んだ海は、確かにスイスの湖にも似ている。地質は氷上花崗岩(ひかみかこうがん)という、大陸移動説の時代から日本の一部となっていった地層。

陸前高田のユニークな土壌、地質を活かす。一口に氷上花崗岩といっても畑によって質は変わる。畑を増やしていくことは容易ではないが、そのなかでも良質なワインを求めて土壌を探る。

「ゴツゴツした花崗岩、スベスベした花崗岩、ピンクの花崗岩、フワフワの花崗岩」と及川さんのインスタグラムで紹介されるさまざまな岩。土、岩のニュアンスはワインの風味にとって大切な要素。
花崗岩は良きワインを生む土壌のひとつとして知られているが、そのひとつの産地が、スペインの北西部にあるリアス・バイシャス。陸前高田が太平洋なら、リアス・バイシャスは、大西洋に向けて続くリアス式海岸に広がる地域だ。ここで栽培されている主要なブドウ品種はアルバリーニョ。及川さんは陸前高田で造るワインのブドウを、アルバリーニョに絞った。

アルバリーニョの実。水はけのいい乾燥しやすい土壌を好むが、耐病性が高いため湿度のある地域、海に近いエリアに適する。スペインのガリシア地方やポルトガルの北部で注目されるほか、日本でも良質なワインが生まれている。
海のワインとも異名をとるブドウで、主要な産地は海に近い場所。味わい、酸、香り、テクスチャーなど、アルバリーニョから生まれるワインは、海を連想させるものが多い。
「地層、日照、さまざまな要素を考えても、海の幸にはまるワインに仕上がる確信があります」
及川さんの言葉には確信が溢れている。
すべてが流され、新しい物語が始まったとはいえ、陸前高田はワイン産地としては、知られた存在ではないし、なによりまだ、及川さんのファースト・ヴィンテージ、つまり“デビュー作”が生まれているわけではない。

虫も生き生きと暮らす畑。手をかけながら自然に育つ環境を整える。
2021年、小さな畑に植えたアルバリーニョは、ようやくワインになるための結実を迎え、2024年10月1日、「空気が澄んだ秋晴れの日」に収穫された。
「ふだんは淡々と作業しているのですが、これまでのことを振りかえって、いろいろな感情がこみ上げてきまして……。まずは収穫できたことが大切だなという思いです」

今年はスケジュールを優先しひとりでの収穫。今後はいろいろな人と収穫の喜びを分かち合いたいという。
もちろんこれはゴールではなくスタートだ。ワインは、もっと先まで続く及川さんのヴィジョンを実現する、最も適した手段として選ばれた。
「陸前高田に、未来へと続く新しい産業をつくる」それが及川さんの強い思いだ。今でこそ故郷のために奮闘する及川さんだが、中学、高校と、ここから出ていくことばかりを考えていた。「昔ながらの閉鎖的な雰囲気」がある狭い世界から、もっと広いどこかの世界へ。

高校卒業直後に校門にて撮影。「新生活へ若干の不安はありつつも、開放的で前向きな気持ちでいっぱいでした」(及川さん)。刻まれた日付がさまざまなことを物語る。
人生を一変させたのは、2011年3月11日。東日本大震災。
及川さんは当時隣町の大船渡高校の2年生。学校からの帰路、もう少しおしゃべりして帰ろう。それが命を救った。
「予定どおりの電車に乗っていたら波にのまれていましたね。高校は高台にあったので、僕らは無事。3日ほど学校に泊まって父の迎えを待っていました」
家への帰路、信じられない光景を目の当たりにする。
「まちが大変なことになっているという情報はあったのですが、帰ってみると本当に何もなかった」
公民館など複数ある安置所に毎日向い、友人知人を探した。
「まるで戦場でした。遺伝子鑑定しないと身元がわからないような状態の遺体を、100人とか見る経験は、普通の高校生にはないでしょうね」
このまちを出よう。その目的は変わった。
「生徒会長になったタイミング。1本遅れた電車。流されてきた卵パックに手を出すような食べるもののない日々、受験勉強どころではない状況。どうして自分が生かされたんだろう?震災以降、このまちで僕は何ができるのかを考えて生きてきました」
陸前高田に帰ってきてなにかをするために、一度、このまちを出よう。そして10年後に戻ってこよう。
「この10年は復興のために、もともと陸前高田の主要産業だった建設業がある。でもその先は? 思い浮かんだのは果樹栽培でした」
経済を支える主要な産業ではなかったが、リンゴやブドウの栽培は盛んだった。
「まったく新しい産業を持ってきても持続しないという事例は多い。地域に根付いたものが良いと考えました」
「農地は宝」と及川さんは言うが、その宝物が高齢化、後継ぎなどの問題で失われてしまう危惧があった。自らが学び、知見を高めていくことで持続させたい。
「大学時代に、ブドウ、ワインでいこうとは思ったのですが、でも、まだほわほわした感じでした」
卒業後、大手ワイン商社に就職。ソムリエ、海外の資格などにチャレンジし、フランス・アルザスでの修行へ。その過程で、ワイン産地としての陸前高田のテロワールの可能性を確信した。

商社時代、名門ワイナリーの前にて。栽培、醸造だけではなく、流通、消費者側の視点などワインにかかわる学びを重ねた。

アルザスでの修行時代。ワイナリーに住み込みで働いていたときのルームメイト、アルザス人のヴィヴィとブラジル人のジュース。休日は彼らとひたすら山に登ったという。
知識を広げ、深め、経験を重ねて帰郷し、地元の地権者の理解と信用を少しずつ積み重ね、畑を購入した。
「まちの人が果樹に理解があって歴史的にも知見もたまっている。ワインが真新しいものではないという受け皿があった。むしろ、がんばってつくれ、つくれという感じで」
取り組みを進めていくなかで気づいたことがあるという。

現在の陸前高田のまち。すべてが流されて当時の面影は残されていない。
「震災で何もかもがなくなってしまったことで、しがらみや古い価値観も流されていったように感じました」
失ったものはあまりにも大きいし帰ってくることはない。まちを出ていこうとしていたあの空気は一新された。前を向いてやるしかない。取り返すのではない。できることが生まれ、新しい物語が始まった。
あの時、生かされた答えを求めて
醸造所の予定地にて。一緒にいるのはワイン商社時代の上司で、第10回(2023年)全日本ソムリエコンクール6位(日本人4位)という実績を持つ松永文吾さん。及川さんの活動を知って駆けつけてくれた。

醸造所予定地の目と鼻の先にある宿泊施設〈箱根山テラス〉。山から望む広田湾は絶景。ワインと宿泊を組み合わせるツーリズムの核となる場所のひとつ。

醸造所予定地の目と鼻の先にある宿泊施設〈箱根山テラス〉。山から望む広田湾は絶景。ワインと宿泊を組み合わせるツーリズムの核となる場所のひとつ。

醸造所予定地の目と鼻の先にある宿泊施設〈箱根山テラス〉。山から望む広田湾は絶景。ワインと宿泊を組み合わせるツーリズムの核となる場所のひとつ。
ワイン造りと並行して進めているのは、陸前高田を訪れ、留まっていただくための取り組み。
「もともと通過されてしまう場所。でも、ここに酒と食があれば留まっていただける。そのためのプランを立てているところです」
ひとつの施策は自前の醸造所とオーベルジュ。目玉はドメーヌミカヅキのワインと海の幸を生かした鮨のペアリング。
「フレンチやイタリアンもいいのですが、ここにはせっかく鮨の大将がいる。生かさない手はない」

地元の名店「鮨まつ田」にて、大将の松田光代さんと、盛岡のワインバー〈アッカトーネ539〉のオーナー&ソムリエ、松田宰(つかさ)さん。ワインツーリズム構想を熱く語り合い、応援もいただいている。

畑にて陸前高田出身のイタリアンシェフ、菅原和麻さんと。及川さんと同じく震災をきっかけに、星付きレストランで修行して帰郷。この春、陸前高田で自身のレストランをオープン予定。つらいきっかけを持つ同士が新しい風を吹かせる。
及川さんがドメーヌにこだわる理由がここにもある。ドメーヌとは自社畑を所有し、栽培から瓶詰までの工程を行う生産者のこと。
「立ち上げ段階ではどこからかブドウを買ってきてワインを造るほうが経営的にもいいのですが、それならどこでやっても一緒。ブドウ自体でテロワールが決まるということに魅力を感じていて、陸前高田でやるという意味にこだわりたい」
さらにドメーヌ・オイカワのように自分の名前を冠するのではなく、広田湾を見下ろすとその地形が三日月に見えることから名づけたミカヅキという名にも意味を込める。

箱根山展望台からの広田湾。ドメーヌ名のミカヅキはこの形からとられた。ドメーヌは欠けていくミカヅキではなくこれから美しい満月へと向かう。
「どこかのタイミングで誰かに譲らないと産業としては続きません。それを考えると自分の名前をつけるのは悪手ではないか」
「すべては手段なんです」と及川さんは言う。陸前高田にこれからも続く産業を造る、それが目的なのだ。
ワインのブドウ品種はなんでもよかった。陸前高田の過去と未来をつなぐことができるもの。ベストなものとして選択したのがアルバリーニョだった。

苗木が地層に根をはりはじめ、ワインになるために相応しい力を宿した実が結実し、4年を経て満を持して収穫されたアルバリーニョは、すでにワインとなって眠っている。

発酵中のワイン。今夏のリリースを待つ。
今夏のデビューで、まず、ワインそのものの評価は冷静に下されるだろう。高評価でも、厳しい声があっても、そこから、及川さんも、アルバリーニョも成長し、地元の皆さんの期待も広がっていく。
「脳裏から離れない震災の光景」は、今でも自分を苦しめる。ワインと陸前高田を結ぶ挑戦を、及川さんはこんな言葉で表現する。
「あの時、生かされた意味の答え合わせを……しているのかもしれないですね」
ワインを味わいながら、その歩みを追いかけてみたい。

profile
及川恭平
おいかわきょうへい●1993年、陸前高田市出身。高校2年生のときに東日本大震災を経験。地元に戻り事業を起こすことを決意し、海外修行、ワイン商社勤務の後、2021年にワイナリー起業。持続可能性と関係人口、温暖化対策をテーマに、当地発の世界に誇るワイン造りを目指している。
information
ドメーヌミカヅキ
WEB:ドメーヌミカヅキ(Domaine Mikazuki)|海のワイン
Instagram:@domaine_mikazuki
writer profile
Daiji Iwase
岩瀬大二
いわせ・だいじ●国内外1,000人以上のインタビューを通して行きついたのは、「すべての人生がロードムーヴィーでロックアルバム」。現在、「お酒の向こう側の物語」「酒のある場での心地よいドラマ作り」「世の中をプロレス視点でおもしろくすること」にさらに深く傾倒中。シャンパーニュ専門WEBマガジン『シュワリスタ・ラウンジ』編集長。シャンパーニュ騎士団認定オフィシエ。「アカデミー・デュ・ヴァン」講師。日本ワイン専門WEBマガジン『vinetree MAGAZINE』企画・執筆。
credit
写真提供:ドメーヌミカヅキ/及川
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS]
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品,ESG]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材,旅]
-

- がんばるキュリオシティ。火星が暖かく、水も流れていたかもしれない証拠を発見
- がんばるキュリオシティ。火星が暖かく、水も流れていたかもしれない証拠を発見Image: NASA/JPL-Caltech/M…
- (Gizmodo Japan)[ジオパーク]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒]
-

- 【台湾】現地コーディネーターおすすめ! 地元で人気のパン屋さんで味わう、台湾ならではの絶品パン
- 一つ一つのサイズが大きいのが、台湾のパンの特徴。圧倒されるような存在感です。 台湾には数多くのパン屋…
- (CREA WEB)[ご当地グルメ]
-

- 日本橋三越内に「サーティワン三越」が期間限定オープン!日本橋の老舗や人気パティシエと夢のコラボフレーバーも誕生
- 「日本橋三越本店」と「サーティワン アイスクリーム」が初の協業をし、2025年4月30日に日本橋三越 本館1…
- (Walkerplus)[秋グルメ]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[果物]
-

- ゴールデンウィーク後半 2日は本州で激しい雨や雷雨に注意 3日と5日は行楽日和に
- ゴールデンウィーク後半は天気や気温の変化が大きくなりそうです。2日(金)は本州付近は雨や雷雨で激しい雨…
- (tenki.jp)[海]
-

- 3,000円台でこの拡張力!UGREENの7in1USBハブ、正直“買い”です #Amazonセール
- 3,000円台でこの拡張力!UGREENの7in1USBハブ、正直“買い”です #AmazonセールImage:Amazon.co.jp こちらは…
- (Gizmodo Japan)[昆虫]
-

- 部屋干し派必見、生乾きを逃さない衣類乾燥除湿機!カビ対策を強化した、三菱電機「サラリ」3モデル
- 三菱電機は、衣類乾燥除湿機の新製品として「サラリPro」MJ-PV250YX、「サラリ」MJ-P180YX、MJ-M120YXの3…
- (GetNavi web)[気候変動]
-

- 宇宙飛行士・若田光一さん、岡山の関西高校で講演 民間主導の宇宙産業へ
- 宇宙飛行士の若田光一さんの講演会「日本人初のISS船長(コマンダー)若田光一氏が語る宇宙開発と産業の未…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[天体観測]
-

- 旭川で一番高いこいのぼり 地域の思い乗せクレーン社で空高く55匹
- 旭川のクレーンリース会社「渋谷クレーン工業」が現在、同社が運営するレンタル整備工場「ビークルベース…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[岩手県]
-

- 飯田に「信州飯田アルプス食堂」 信州福味鶏など地元食材メニューを看板に
- 飲食店「信州飯田アルプス食堂」(飯田市中央通り3)が4月29日にオープンする。(飯田経済新聞) 長野県産…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東日本大震災]
-

- あっ地震…そのときゾウが子どもを守るためにとった行動に愛を感じた
- あっ地震…そのときゾウが子どもを守るためにとった行動に愛を感じたImage: Shutterstock 本能に訓練なんて…
- (Gizmodo Japan)[地震]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.