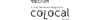建築、カフェ経営、地域の情報発信… 山形から新しいまちづくりに挑む
建築家で東北芸術工科大学教授の馬場正尊さんが推薦したのは、山形市で建築プロジェクトを行う〈OF THE BOX〉の追沼翼さん。
推薦人

馬場正尊
オープン・エー代表取締役/建築家/東北芸術工科大学教授
Q. その方を知ったきっかけは?
山形にある東北芸術工科大学で彼が学部3年生(建築・環境デザイン学科)のとき、僕の研究室の学生として入ってきました。大学院在籍中に起業。僕の仕事を手伝ってもらったり、彼の仕事をサポートしてみたり、いろんなトライを横で見守っていました。
Q. 推薦の理由は?
彼のようなタイプを、「新しい日本人」と呼んでいます。なんだか行動のモチベーションがサラサラしているんですよね。周りの人を楽しませながら自分も走っている、というような。仕事のつくり方や進め方も、僕らの世代とはまったく違う。仕事の内容も場所も、横断的かつ離散的。例えば、カフェをやりながら、設計事務所を並行して経営していたり。プロジェクトを動かすとき、クラウドファウンディングで数百万円集めることから始めたり。クライアントが全国にいて、ほとんどのコミュニケーションをオンラインでこなしていたり。なんだかよくわからないけど、でもそれらの活動はちゃんとつながっていて、なおかつ時代の要請に素直に対応している。軽やかで、しなやかで、でもちゃんと経営につなげていく。そんな感性を持った人たちを「新しい日本人」と呼んでしまっているのですが。追沼くんは僕の身近にいる人のなかで、その代表選手かな。
東北芸術工科大学在学中から、大学のある山形市を中心にまちの課題を解決するようなプロジェクトを展開。現在は日本各地にその舞台が広がっている、追沼翼さん。推薦者の馬場正尊さんは、彼の進路を方向づけたひとりといえる、大学時代の恩師だ。その推薦文を読んだ追沼さんは、「新しい日本人」という言葉に反応した。
「馬場さんからはよく、『宇宙人』って言われていたんですよね。もう少しやさしい言い方にすると、こうなるのかな(笑)」
仙台市出身の追沼さんは、大学進学を機に山形市へ。そもそも専攻した建築・デザイン学科は第一志望ではなかったが、未知の世界だったからこそ、可能性は四方八方に散らばっていた。
「〈みかんぐみ〉の竹内昌義さんが学科長だったこともあり、全国の大学でも珍しいんですけど、エコハウスやエネルギー関連の授業に力を入れていたんです。ほかにも、自分たちの食べているものが、どこから来ているのかを考える哲学寄りの授業があったりして、建築に徐々に興味を持つようになっていきました」
まちや地域のコミュニティに入り込むきっかけとなったのが、大学3年生のときに馬場さんのゼミで取り組んだ夏休みの課題。「空き物件のリノベーションを妄想せよ」というテーマを与えられて選んだのが、山形市七日町の通称「シネマ通り」にある〈郁文堂書店〉だった。

かつての〈郁文堂書店〉
リノベーションブームの先駆けといえる〈とんがりビル〉の隣で、ひっそりとシャッターを閉ざしていたこの書店を、ブックカフェにするアイデアがまず浮かぶ。
オーナーにヒヤリングを行うと、閉店してすでに10年ほど経つこと、シネマ通りはかつて映画館が6つも立ち並ぶ文化の拠点だったこと、斎藤茂吉や井上ひさしなど名だたる文化人が足を運び、「郁文堂サロン」と 呼ばれていたことなどが判明。そんな夢のような空間が現代に蘇ったら……と希望を抱いた追沼さんは、妄想を妄想のままで終わらせず、ブックカフェの案を練り直すことに。
「あのときまちの人たちと接して、山形を知ることができたのは大きかったと思っています。オーナーの原田さん(故人)は、僕らが出会った頃すでに80代でしたが、界隈で知らない人はいないくらい顔が広く、住民との関係の築き方を教えてもらいました。結局、半年くらいほぼ毎日、片付けなどに通ったのですが、表からは見えにくい地道な活動の積み上げが大事だというのも、実践しながら学ばせてもらいました」
2016年9月、山形ビエンナーレで書店の1日限定オープンを成功させたあと、追沼さんたちは郁文堂サロンの本格的な復活を目指す。
その際に活用したのが、当時はまだ認知度の低かったクラウドファンディングだった。資金力のない学生ゆえにたどり着いた選択ではあったが、お遊びでやっていると思われたくないプライドや、周りに迷惑をかけたくないというプレッシャーが交錯。不安をよそに目標金額を達成できたことは、自信と励みになっていく。
「設計料や活動費を自分たちで集めていくようなやり方は、このときの経験が原点になっているのだと思います」
店舗からストリートへ、エリアリノベーションを展開電気工事など専門的なところは職人にまかせ、それ以外の部分は学生とまちの人たちのDIYによって完成した〈郁文堂書店TUZURU〉。書店とサロンの機能を持つ、まちに開かれた空間は、メディアなどに取り上げられて注目が集まり、住民にも喜ばれた。

書店とサロンの機能を持つ〈郁文堂書店TUZURU〉。(撮影:斎藤哲平、吉木綾)
「一方で、学校で勉強しているだけでは接点を持てなかった人たちと出会い、それぞれの世代ごとに抱えている課題が具体的に見えてきたことで、まちについてもっと真剣に考えたいと思うようになりました。それが〈山形ヤタイ〉や〈シネマ通りマルシェ〉のプロジェクトへとつながっていったんです」
山形ヤタイは、木枠にレジャーシートの屋根を張った、シンプルかつおしゃれな佇まいの屋台。ホームセンターで揃えられる材料と工具で、DIY初心者でも簡単につくることができるのがポイントだ。チャレンジショップのようなビジネス利用から、町内のイベント、あるいは庭先でのピクニックでも活躍する汎用性の高さが受けて、設計やつくり方を実践的に学ぶワークショップを全国で展開する。
その山形ヤタイを活用したのが、2017年〜19年に年2回のペースで開催された、シネマ通りマルシェ。コーヒー、パン、野菜、アクセサリーなど、毎回2〜30店舗が出店し、多いときは約2000人が来場。さらにマルシェに合わせて山形リノベーション協議会の協力のもと「空き物件ツアー」を行い、新たな実店舗の開業へとつながる動きも生まれた。

汎用性が高い〈山形ヤタイ〉。

シネマ通りマルシェの様子。東北芸術工科大学と山形大学の有志も協力した。
2018年、大学院に進学した追沼さんは、こうしたプロジェクトを行ってきた〈OF THE BOX〉を法人化。さらにその翌年には〈株式会社デイアンド〉を設立して、店づくりにも着手する。山形駅近くの通称「すずらん通り」に、コーヒースタンド〈Day & Coffee〉をオープンさせたのだ。

安土桃山時代から続く老舗呉服店〈とみひろ〉の旧本社ビルを、2019年にフルリノベーション。1階がコーヒースタンド、1、2階がオフィス、2、3階がメゾネット住居になっている。

〈とみひろビル〉の奥に立つギャラリー。山形副市長の定例朝会などに利用されている。
「Day & Coffeeが入っているのは、老舗呉服店の本社ビルだった建物で、10年くらい使われていなかったんです。オーナーさんが芸工大の理事だったこともあり、学生やまちの人と関わりながらリノベーションして、若者が来るような場所にしたいという相談が大学にあって。芸工大の先輩である〈リトルデザイン〉代表の佐藤あさみさんから声をかけてもらい、プロジェクトに参加することになりました」

Day & Coffeeのコンセプトは「すべての日に特別なひと時を」。特別感のあるリボンをモチーフにロゴをデザインしてもらった。

世界各地の豆を丁寧に店内で焙煎し、ハンドドリップなどで提供。テイクアウトもOK。

そして、すずらん通りもかつては様相が違っていたことを、プロジェクトを通して知るように。
「もともとは文房具屋さんや呉服屋さんなどが立ち並ぶ商店街だったのですが、僕が山形に来た頃には夜の繁華街のイメージが強くなっていました。もちろんそれも悪くないのですが、駅から徒歩数分の立地なので、昼間、外から訪れた人には暮らしが見えないうえに、お店も開いていないので、“何もない場所”という印象になってしまう。僕自身も外から来た人間だから、もったいないなと思ったんです」
暮らしの息づかいが聞こえるような、昼夜問わず人がいる状態をつくりたいと考えた追沼さんたちは、オフィスと飲食、住居の機能を持ち合わせたビルにリノベーション。まちに新たな人の動きを生み出した。ちなみにオープン時からカフェの店長を務めている北嶋孝祐さんも、芸工大の出身者だ。
「彼は高校時代からスペシャルティーコーヒーの店でバイトして、バリスタトレーニングを受けるほどのコーヒー好きなんです。もともとの出会いは、郁文堂書店の再生プロジェクトを手伝ってくれたからなんですけど、コーヒーの道具を現場に持ってきて、毎日いろんな種類のコーヒーを振る舞ってくれました。『自分が受けた感動を味わえるような、スペシャルティーコーヒーの店が山形にもあったらいいのに』と話していたのが印象に残っていて、一緒にお店をやることになりました」
一方、学生時代から追沼さんを見てきた北嶋さんは、その印象をこう語る。
「理想と現実のバランスがいい人だと思います。社会がこうなったほうがいいという理想をしっかり持ちつつ、理想のままで終わらせないというか、現実的に自分ができることを常に考えて、継続してアクションを起こしている。いろんな活動をしているので、一貫性がないように見えるかもしれないし、たぶん本人もそう言われがちだと思うのですが、理想に対して一歩ずつ近づいている印象は、そばで見ていて変わりません。一見飄々としていますけど、内側には熱いものを持っているんですよね」

芸工大の後輩で、Day & Coffeeの店長を務める北嶋孝祐さん。コーヒーが飲めなかった追沼さんを、コーヒー好きにした人物でもある。
SNS時代の仕事のやり方、つながり方最近、まちの課題で特に気にかけているのが、再建築不可物件。建築基準法で定められた、道路と敷地が接する幅を満たしていないため、現存する建物を取り壊しても、新たに建て直すことができない、いわば使い勝手のない土地のことだ。
「更地にもせず、とりあえず空き家のまま残しているような場所が、実は意外と多いんです。そういう建物をリノベーションして付加価値をつけることで、まちの魅力向上につなげられないかと探っているところです」
その事例のひとつが、2024年3月にオープンした〈DENIM HOUSE BON〉。国産デニムの産地、岡山県倉敷市児島にある、築90年以上の日本家屋を改装した、1日1組限定の宿だ。
「デニムのショールーム&ギャラリーが併設しているんですけど、デニムブランドやゲストハウスの運営を兄弟で手がける〈ITONAMI〉(旧EVERY DENIM)がクライアントなんです。僕と同世代で、彼らも学生時代に起業しているんですけど、そういった人たちと一緒に仕事をする機会が徐々に増えてきて、うれしいですね」


日本家屋を改装した、1日1組限定の宿〈DENIM HOUSE BON〉。(撮影:堀内敦央)
追沼さんのもとには、「場所はあるけど、使い道が決まっていない」「人が集まるようなひらけた場所をつくりたい」などと、日本各地から依頼や相談が舞い込んでくる。面識がなくても、SNSやウェブサイトでその活動を知って声をかけてくる人が少なくないのも、なんだか今っぽい仕事のやり方だ。
「建築の仕事は、竣工して専門誌などに掲載されて、フィードバックを受けるという流れが、昔から一般的だと思うんです。その点、僕らの世代は企画やそのプロセスも含めてSNSで発信すれば、反応がすぐに返ってくるので、感触をつかむことができる。学生の頃なんかは特に、仕事をどう受けたらいいのかさえわからなかったし、自分たちのやっていることが正しいかどうかもわからなかったけど、反応や評価が瞬時に得やすい環境だったのは、勇気をもらえるという意味でもありがたかったですね」
全国を飛び回りながら、山形に拠点を置き続けているのも、挑戦のひとつといえる。
「全国の仕事を受けるのだったら、東京を拠点にしたほうがいいんじゃないかってアドバイスもたくさんいただいたんですけど、僕はそれに違和感があって。リモートでのやり取りがこれだけ進んだ今だからこそ、東京の人たちと同じように、地方にいながら全国の仕事ができると信じているんです。
書店の再生やコーヒースタンドの開業と一緒で、自分たちが実現させたい状況を主体的につくっていくことに意味があると思って、山形を拠点にしているっていうのはありますね。僕が学生の頃は、起業がちょっとしたブームになっていたんですけど、そのときの仲間がどんどんいなくなっているのも事実で。自分たちはそこをなんとかこらえたいというか、しっかり続けてかたちにしていくことで、あとに続く人たちが働き方を考えるきっかけになったらいいなと思っています」
「ない」ことも可能性のひとつそんな山形に感じている可能性について尋ねると、言葉を選びながら「課題先進地域であること」と返答。人口減少や高齢化、過疎化など、どの地域も直面しつつある社会課題を、少しだけ早く体感することは、アドバンテージにもなりうるのだ。
「デパートが閉店するなど、他地域よりも先行して、まちからいろんなものがなくなっていたりします。こうした現象に対するアプローチを考えることは、将来的な全国の課題に向き合うことにもつながります。なので、あれもない、これもない、とネガティブに捉えるのではなく、考え方や価値観自体を変えていきたいんです。人が少ないっていうのも同様で、人が少ないから密な関係性をつくりやすくなるのだと考えたら、もっとハッピーになれそうですよね」
冒頭の「宇宙人」もとい「新しい日本人」と呼ばれる理由について、あらためて自己分析してもらうと、「よくわからない」と笑いながらも、ちょっと意外な一面が見えてきた。

「大学3年生くらいまでは、漠然と気に食わないことがいっぱいあって、いつもイライラしていたんです。正論ばかり言うようなタイプだったと思うんですけど、すずらん通りのビルのリノベーションを一緒に手がけた佐藤あさみさんから、『正論はときとして人を傷つけるよ』と言っていただいて。正しさを押し通すだけが仕事のやり方じゃないと知って、性格もだんだん変わり始めた気がします。その結果、何が楽しくてやっているのか、周りの人にはわかりにくくなってきたのかなって(笑)」
建築、イベント企画、カフェ経営、シティプロモーションなど、一見脈絡がなさそうでも、追沼さんのなかではすべてつながっている。しかしながら、いろんなことを器用にできてしまうことに、引け目を感じた時期もあったようだ。
「建築一本のほうが、職人っぽくてかっこいいじゃないですか。だけど大学院にいた中国からの留学生に、『追沼くんは“一専多能”だね』と言ってもらったことがあったんです。ひとつの専門に対して多くの能力を持っている人っていう意味らしいんですけど、だったらまちを軸にして、いろんなノウハウを身に着けていこうってそのときに決めました。とはいえ20代半ばくらいまでは、建築設計事務所に就職して、修業したほうがいいかな、などとずっと悩んでいて……。本当に吹っ切れたのは、つい最近なんですけどね」
まちという境界があるようでない広大なフィールドで、吹っ切れてからの活動範囲は一体どこまで広がっていくのか。追いかけていこう。
Profile
追沼翼
株式会社オブザボックス代表 / 株式会社デイアンド代表。1995年宮城県生まれ。2020年東北芸術工科大学大学院デザイン工学専攻地域デザイン領域修了。2016年にオブザボックスを設立し、2018年に法人化。2019年にデイアンドを創業、〈Day & Coffee〉を開業。〈郁文堂書店再生プロジェクト〉〈山形ヤタイ〉を皮切りに、山形市におけるエリアリノベーションに取り組む。全国各地での公共空間活用・リノベーションに従事する傍ら、カフェ経営やシティプロモーションに取り組む。近作『すずらん通りリノベーションプロジェクト』LOCAL REPUBLIC AWARD 2020 優秀賞受賞。
information
Day & Coffee
住所:山形県山形市香澄町1-11-18
営業時間:8:30〜18:30(18:00L.O.)
定休日:火曜
Web:Instagram(@dayandcoffee)
writer profile
Ikuko Hyodo
兵藤育子
ひょうどう・いくこ●山形県酒田市出身、ライター。海外の旅から戻ってくるたびに、日本のよさを実感する今日このごろ。ならばそのよさをもっと突き詰めてみたいと思ったのが、国内に興味を持つようになったきっかけ。年に数回帰郷し、温泉と日本酒にとっぷり浸かって英気を養っています。
photographer profile
Mikako Ito
伊藤美香子
いとう・みかこ●岩手県宮古市生まれ。スタジオ勤務を経て位田明生氏に師事。2007 年、フリーのフォトグラファーとして活動開始。東京を拠点に雑誌・広告などで活動。2018 年秋、結婚を機に山形に移住。東日本大震災をきっかけにワークショップ「しゃしんおえかき」も継続的に開催している。https://www.mikakoito.com/
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 「ふたりでうまいもんが食べたい」土曜日の幸せな過ごし方/てだれもんら1(2)
- 土曜日に少し肴を作って飲む / (C)中野 シズカ/KADOKAWA週末に家飲みをする仲の小料理割烹「薫風」板前の…
- (レタスクラブニュース)[カフェ・スイーツ]
-

- CREA表紙プレイバック【2004年10月号〜12月号】自腹で買うならこのコスメ!!、愛しの韓国、恋する映画
- 創刊まもない頃の表紙に並ぶのは、ニュースな話題。CREAが創刊した1989年は、世界史的に見ても、エポック…
- (CREA WEB)[温泉]
-

- 東京農大「食と農」の博物館で通年企画展「いきもの研究所の舞台裏」
- 東京農業大学「食と農」の博物館(世田谷区上用賀2)で4月25日、企画展「いきもの研究所の舞台裏」が始ま…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント,芸術]
-

- 「シゲに教えてもらった」NEWS小山慶一郎が加藤シゲアキからおすすめされたキッチングッズとは?
- にんにくが効いたソースがおいしい「あさりでエスカルゴ風」。バゲットを忘れずに! / 調理/みきママ 撮…
- (レタスクラブニュース)[お酒]
-

- 深谷ねぎを自分で作って食べる「深谷ねぎオーナー」 今年も
- 農業を体験する企画「深谷ねぎオーナーになろう!」が5月11日、馬場ファミリー農園の野菜圃場(深谷市樫合…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[旅,野菜]
-

- 八戸「かぶーにゃ」がリニューアル おにぎり、酒かす使ったジェラートも
- みちのく潮風トレイルの玄関口「蕪島」に隣接する蕪島物産販売施設かぶーにゃ(八戸市鮫町)が5月1日、リ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 初夏の紫外線対策に新提案!肌と髪を守るスプレー登場
- マルチな日やけ止めスプレー数量限定発売株式会社シーボンは5月1日、日やけ止めスプレー「シーボン マルチ…
- (美容最新ニュース)[果物]
-

- 天気痛予報 GW明けにかけて警戒ランクの日多い
- 天気痛予報 GW明けにかけて警戒ランクの日多い2025/05/02 13:00 ウェザーニュース今日5月2日(金)は低気圧…
- (ウェザーニューズ)[気象]
-

- 旭川で一番高いこいのぼり 地域の思い乗せクレーン社で空高く55匹
- 旭川のクレーンリース会社「渋谷クレーン工業」が現在、同社が運営するレンタル整備工場「ビークルベース…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[寄付]
-

- 習志野・谷津で「ローズフェスタ谷津」 バラの街で出会う婚活イベントも
- 「ローズフェスタ谷津2025」が5月10日・11日、京成谷津駅北口で開催される。(習志野経済新聞) コンサー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[エコ]
-

- アウトドアからビジネスシーンまで幅広く活躍!【シチズン】の腕時計がAmazonにて登場!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[エネルギー]
-

- 仙台市が「ハイキュー!!」デザインマンホール設置 富沢駅から市体育館の道に
- 仙台市が4月30日、仙台ゆかりのスポーツ漫画「ハイキュー!!」のイラストをあしらったデザインマンホールを…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[岩手県,宮城県]
-

- 富士山こどもの国で初の「ザクっとコロッケフェス」 ご当地コロッケ9店
- 「ザクっとコロッケフェス」が5月5日・6日の2日間、富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎)で初めて開催さ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[山形県]
-

- もっと真剣に考えて! 息子の中学受験に向け、意見が割れる夫婦
- まだ5年だし平気じゃない? / (C)窓際三等兵、グラハム子/KADOKAWA憧れのタワマン生活。ここに住めば、…
- (レタスクラブニュース)[東京都]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[岡山県]
-

- 大阪・関西万博に韓国パビリオン AI技術を活用した参加型展示も
- 2025年大阪・関西万博会場内に「韓国パビリオン」が4月13日、オープンした。(大阪ベイ経済新聞) AIを使…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[エネルギー(ぼんやり学会)]
-

- 【今だけ】Amazonの音楽聴き放題サービスが3か月無料!旅先で、お家で、GWは音楽を無料楽しむチャンス!(5月7日まで)
- 音楽を思いっきり楽しもう! / KiRi / PIXTA(ピクスタ)待ちに待ったゴールデンウィーク!旅行やレジャー、…
- (レタスクラブニュース)[ピクニック]
-

- 「生成AI」×「塗り絵」が、子どもの創造力を育む!?自分だけの塗り絵が生成できる知育アプリが誕生
- 子どもの創造力を育む!自分だけの塗り絵が生成できる知育アプリが誕生 / pearlinheart / PIXTA(ピクスタ)…
- (レタスクラブニュース)[宇宙]
-

- 飯田に「信州飯田アルプス食堂」 信州福味鶏など地元食材メニューを看板に
- 飲食店「信州飯田アルプス食堂」(飯田市中央通り3)が4月29日にオープンする。(飯田経済新聞) 長野県産…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東日本大震災]
-

- 調布・柴崎に釣り人が居酒屋新店 一本釣りの黄金アジ・天然フグを売りに
- 東京湾で一本釣りした鮮魚を提供する「釣人酒場ぷくぷく」(調布市菊野台1、TEL 042-457-0804)が4月18日…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ESG]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.