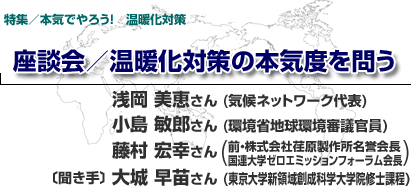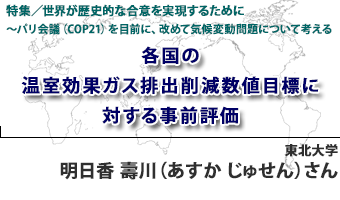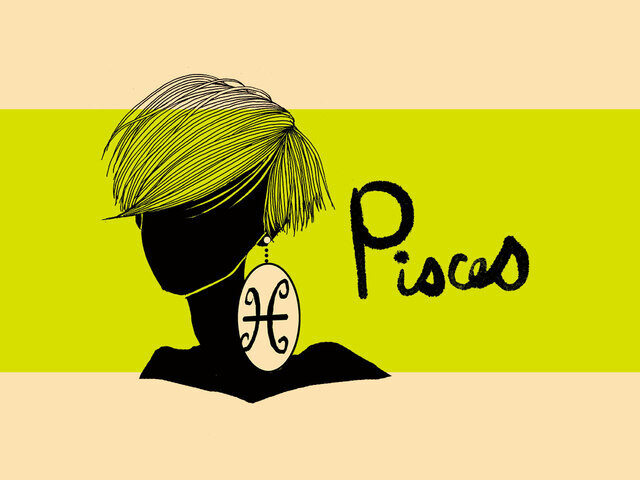このコンテンツは、地球・人間環境フォーラム発行の「グローバルネット」と提携して情報をお送りしています。
第48回 座談会/温暖化対策の本気度を問う
- 2008年1月10日
|
このコンテンツは、「グローバルネット」から転載して情報をお送りしています。 |
|
|
→参加メンバー紹介 |
|
|
経済活動や日常生活に起因して排出されるCO2は気象災害をもたらす。いわばこれは「外部不経済」なのですが、そのコストを原因者が負担していない。では、誰が負担しているのか。それは気象災害の被害者が全部負担しているということです。気候変動枠組条約の締約国会議での交渉も原因と結果の因果関係を基本にすれば「大量排出国」対「主として被害を受ける国」という交渉になりますが、現実には途上国側は「責任は先進国。われわれは南」という主張で議論がかみ合いません。先進国側も責任論を避けています。責任論を議論するまでには因果関係は明らかではないということでしょう。 |
|
藤村 |
私はフルコストの考え方が非常に大切だと思います。しかし、環境に与える負荷をなかなか計算できない。一つの考え方として、例えばダイオキシンを分解する費用や、1kgのCO2を固定化するだけのバイオマスを育成する費用は計算できます。 |
|
大城 |
「今、日本が何をすべきか」というグローバルなテーマについて、例えば国際貢献、バイオ技術、NGOの連携など、ローカルな視点とグローバルな視点を合わせて、お答えいただきたいと思います。 |
|
小島 |
2050年に排出量と吸収量をバランスさせる社会を実現させる。50年あれば建物もインフラも入れ替わります。低炭素社会づくりに向けての投資をすべきだと思います。将来への明確なビジョンがあれば企業も投資しやすくなります。 |
|
浅岡 |
社会的に影響力の大きい人が早く動き、重い責任を担うのはいつの時代も一緒で、そういう意味で大規模排出事業者に税や排出権取引など排出削減が価値をもつ仕組みを受け入れていただくことは不可避だと思っています。行政や政治には、それを制度化する役割、責任を自覚して欲しい。私たちNGOも参加していきます。消費者は最終的なコストの引受者であり、環境税の考え方を受け入れていかなければなりません。 |
|
藤村 |
バイオマスニッポンが2006年に改定されました。バイオマスを資源として化石燃料に置き換えていこうとするものです。想像ですけど、2050年頃に20%ぐらいの置き換えができるのではないか。 |
|
大城 |
次世代の当事者である若者がどのように考えて、どう行動していくのか。若者の価値観と行動が社会を変えていくと信じているのですが、そのためには今の若者たちは何をすべきなのか、何を期待されますか。 |
|
浅岡 |
いつの時代も大きな問題を抱えていました。問題のない時代も国もきっとないでしょう。今、世界共通の問題として、温暖化問題があります。共通なだけに世界中の人たちが協力し、克服していくことが期待されるし、それなくして解決できないと思っています。影響も対応もグローバルな時代の挑戦はやりがいもあると思います。 |
|
小島 |
現在に生きていながら将来を見通すことができる、あるいは、日本に住んでいながら世界を見ることができる、こういう力が、気候変動問題には必要です。今は、昔と違っていろんな情報が入ってきます。情報が多くて思考停止になっては困りますが、情報を生かして人間の能力をもっと高めていく。科学技術が発展して人間性が失われるのではなく、人間の感性も磨かれていく。若い人には、それを期待したいですね。 |
|
藤村 |
私は昨日のNHKの番組で、幕張を元気にしようという若者たちの取り組みを見て元気づけられました。われわれは竹やり持って暴れたんだけど、今の学生は先を見る感性が強いんでぜひ大いに発展していただきたい。 |
|
大城 |
私は若者が今持っている問題意識をちゃんと集約して、声を届けること、まちを歩いている「関係ない」と思っている人たちと関われるようなアクションの仕方を提供していくことを、戦略的にやっていきたいと思います。学生の中で環境や、それらのことを考えて動けるリーダーが揃ってきていて、それをもっと広げていけるチャンスだと思っています。洞爺湖でのG8サミットに向けてどうするのか、この1年をしっかりやっていきたいと思っているので、いろいろご教示いただけたらうれしいです。ありがとうございました。 |
|
(2007年6月26日東京都内にて) |