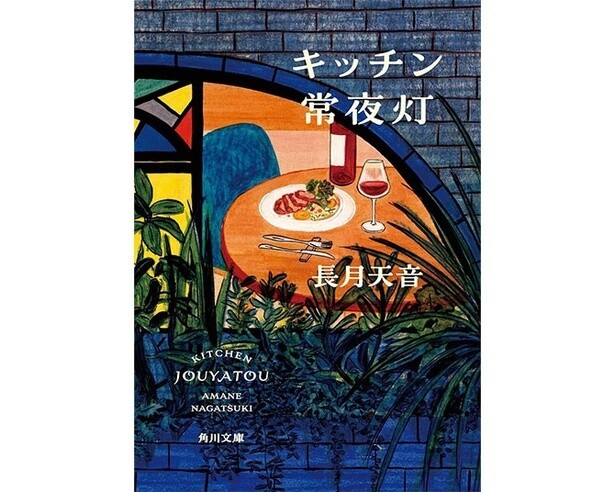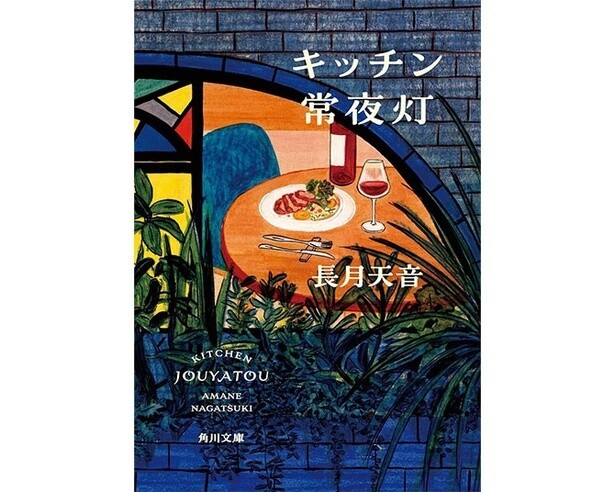
「キッチン常夜灯」(長月天音/KADOKAWA)第5回【全6回】
チェーン系レストラン「ファミリーグリル・シリウス」の浅草にある店舗で店長を務める南雲みもざは、ある冬の日、住んでいるマンションで火事に遭い、部屋が水浸しになる。住んでいるところに困っていると会社の倉庫の1室を借りられることになるが、勝手の違う生活に疲労はさらに溜まっていく。そんな時、みもざが訪れたのは路地裏で夜から朝にかけて営業するレストラン「キッチン常夜灯」だった。寡黙なシェフが作るのは疲れた心を癒してくれる特別な料理の数々で――。「キッチン常夜灯」は、美味しい料理とともに、明日への活力をくれる心温まる物語。
※2023年10月8日掲載、ダ・ヴィンチWebの転載記事です。
それから3日後のことだ。その日は私にとって週に1度の休日だった。
私はたいてい火曜日に休みを取るようにしている。本当は週に2度休まなくてはいけないけれど、欠けたバイトの穴を埋めるのも店長の大事な仕事である。しかし、それではいっこうに休めないので、週に1日だけはバイトをかき集めて手堅いシフトを組むようにしている。
休日になると、ストンと電源が落ちたように体が動かなくなる。不眠気味の体のせいだ。
眠れない時間の辛さと、いつまでも消えない疲労感は応えるが、病院に通うほどでもないと自分を納得させて数年間をやり過ごしてきた。
まったく眠れないというわけではない。寝つきが悪いだけだ。だから大丈夫だと、いつの間にか曳舟のマンションには、バスソルトと癒し系のグッズが増えていった。
昼過ぎに起き出した私は、買いそびれていた日用品の買い出しがてら蕎麦屋で鴨南蛮をすすり、夕方には帰宅して、帰ってきた金田さんに先日訪れた「キッチン常夜灯」のことを報告した。
「よかった。今もちゃんとあったんだね。あの後、本当は幻でも見たんじゃないかって急に心配になっちゃってさ」
「大丈夫、ちゃんとありましたよ。私は牛ホホ肉の赤ワイン煮を食べました」
「ははは。夜中にずいぶんガッツリ食べたねぇ」
そんな会話を交わし、金田さんが誘ってくれた夕食を「さっきお蕎麦を食べました」と遠慮して、ゆっくりとお風呂に浸かった。ラベンダーの香りに包まれ、今夜こそたっぷり眠るぞ、と、いつもはまだ働いている時間にベッドにもぐり込んだ。
静かだった。
目を閉じているのに、目の奥に夜の青い闇が入り込んでくるように、くっきり意識が冴えている。眠ろうと思えば思うほど目が冴えて、いつの間にか横になっているのも苦痛になっていた。いつもならそのうちに朝がやってくる。しかし、ずいぶん早くベッドに入った今夜の私にとって、朝はまだまだ果てしなく遠かった。
急に不安になってきた。
いつまでこんな生活が続くのだろう。
このストレスは私が店長である限り、ずっと付きまとうのだろうか。眠れないまま?
不意にサイレンの音が聞こえてきた。このあたりには大きな病院が多く、絶えずどこかで聞こえるサイレンの音が、真夜中の私の不安をさらに搔き立てる。
私はたまらずに飛び起きた。
迷いはなかった。ルームウェアを脱ぎ捨て、セーターを被り、ジーンズに足を通す。階段だけは足を忍ばせて下り、外に飛び出した。明るいところへ、温かい場所に行きたくてたまらなかったのだ。
2度目の「キッチン常夜灯」。ぼんやりとした看板に導かれるように、ステンドグラス越しの明かりが夜にこぼれる路地を歩いて入口にたどり着いた。
そっと扉を開くとドアベルが鳴り、堤さんがひょっこり顔をのぞかせた。
「あらっ、いらっしゃい。どうぞ、どうぞ」
満面の笑みが大歓迎だということを示している。彼女を見た途端、ほっと肩の力が抜けた。
頰に触れる温かな空気と、美味しそうな香り。そして優しく店内を包み込む、ほどよい照明。カウンターの中のシェフが、顔を上げて「いらっしゃい」と言ってくれた時には、涙が出そうになった。
私の他に客は一人。以前スープらしきものを食べていた女性が今夜もカウンターの奥にひっそりと座っていた。平日の夜とはいえ、今夜も客が少ない。落ち着けるのは嬉しいが、同業者として経営は大丈夫だろうかと心配にもなる。
「今日はいかがいたします?」
堤さんがにこにこしながらメニューを差し出した。
どうしよう。次は何を食べようと考えていたはずなのに、とっさに頭に浮かばない。
「ワイン、お願いします。1杯だけでいいんです」
それから壁に掲げられた黒板を眺めた。
「シャルキュトリー盛り合わせがいいです」
ゆっくりとここで過ごしたいと思ってメニューを選ぶ。
「ワインは白と赤、どちらがお好みですか」
「どちらが合いますか」
そう詳しいわけではない。洋食店の店長といっても所詮はファミレスである。客から入るオーダーもアルコールならざっくりとワインかビールかというだけで、客もワインの質を求めているわけではない。「ファミリーグリル・シリウス」はそういう店だ。
ただ、今夜はどうしてもアルコールが欲しかった。そしてソムリエの堤さんにワインを選んでほしかった。
「合うかと言われれば、私の好みになってしまいますけど、それでもよろしいですか」
「はい、お任せします」
と言いながら、ついドリンクメニューを確認してしまった。ボトルワインは値段のばらつきが大きいが、グラスで注文できるものは限られているのか、1000円ちょっとの値段だったので安心した。
「アルザスの白にしました」
グラスに注がれる淡く黄色がかったワインを眺めるだけで、特別な空間にいるような錯覚に陥った。さっきまで暗い部屋で必死に目を閉じていたというのに。
それからすぐにシェフが大きな皿を運んできた。
「お待たせいたしました。上から時計回りに、ジャンボンブラン、ピスタチオ入りの豚モモ肉のソーセージ、スモークした鴨のハム、ココットの中は豚肉のリエットです。バゲットと一緒にどうぞ」
薄紅色のバラの花を盛り合わせたような皿を見たとたん、先ほどまでの気持ちがうそのように高揚してきた。
それにこれなら、ゆっくりとここで時間を過ごすことができそうだ。
小さい頃からおやつに魚肉ソーセージを与えられていた私にとって、大人になって覚えた肉の加工品、シャルキュトリーは、子供の頃の常識を覆す贅沢なおつまみだ。大皿に盛り合わされたこれらを独り占めできるのも大人なればこそ。
シェフはじっと私を見つめていた。
私は気づかぬふりで、「いただきます」とフォークに手を伸ばした。
華やかな香りに反してキリッとした飲み口のワインと、ハムの塩気がよく合った。
弾力のある嚙みごたえは、子供の頃に食べたソーセージと当然ながらまったく違う。嚙みしめるたびに旨みが広がり、それをワインで洗い流すように飲み込むと、さらに違った美味しさに脳が痺れた。さっきまでの言いようのない不安を押しやるように、私はワインを飲み、シャルキュトリーを嚙みしめた。
「お客様、ナイスチョイスです。ウチのシェフのシャルキュトリー類、なかなか人気なんですよ。さぁさ、リエットも食べてみて下さい」
堤さんに促され、大事にとっておいたリエットをすくい、薄くカットされたバゲットにのせた。バゲットも軽く焼いてあり、カリッとした食感と滑らかな味わいが口の中に広がった。
「美味しい!」
「でしょう!リエットやパテは特にシェフが得意としているんです。今度はぜひパテ・ド・カンパーニュも食べてみて下さいね!」
ふとシェフを見ると、手元の作業に集中しながらも、口元だけがわずかにほころんでいる。ああ、やっぱりここに来てよかった。ここがあってよかったと、私の体からゆるゆると力が抜け、そのとたん、久しぶりに飲んだアルコールで急に顔が火照ってきた。
でも、この気持ちのままでいたくて、私はもう1杯ワインを注文した。
「お客様は近くにお住まいなんですか?」
ワインを注ぎながら堤さんが訊ねた。
「ほら、このお店、わかりづらい場所にあるじゃないですか。お客さんは常連の方ばかりなの。この前も遅い時間にいらっしゃったでしょ?」
「はい、この1本裏の通りに住んでいます。と言っても、まだ10日くらいなんですけど」
火事でマンションを焼け出されたことは、すでに職場でもスタッフや常連客の何人かに話していた。同情してほしいわけでも、手を差し伸べてほしいわけでもないが、ただ聞いてほしかったのだ。
でも、笑い話にでもしないとやっていられなかった。だから、苦しいくせに平気な顔をして、へらへらと他人事のように語った。これからのことを考えると、途方に暮れて不安で仕方がないくせに、困っていると思われたくなかった。
今夜も、そんなふうにこれまでのことを話した。
堤さんの表情がみるみる曇っていく。
「そうだったの」
「そうなんです。ほら、今日もこの前と同じセーターでしょう。今のところ、これしかなくて」
私は自分のセーターをつまんで見せた。そう。本当に何もかも失ったのだ。
「大変でしたね」
いつの間にか城崎シェフが目の前に立っていた。
「さぞ途方に暮れたことでしょう。でも、行くべき場所があってよかった。本当によかったです」
シェフの言葉に私は頷いた。倉庫があった。会社と金田さんに救われた。
「でも、まだ落ち着かないでしょう。ちゃんと眠れますか。いつでもここに来るといい。ここはそういう場所なんです」
私はシェフの顔を見上げた。
眠れない。火事に遭ってから、ますます夜が怖くなった。
不意に熱いものがこみ上げてくる。
慌てて私は指先で目元をこすった。おかしい。涌井総務部長に電話した時も、金田さんに迎えに来てもらった時も、一度も涙など流さなかったというのに。
堤さんが「あらあら」と肩をさすってくれた。その手の温かさに、とうとうこらえきれず涙がこぼれた。
気を許すことができたのは、きっと、堤さんやシェフが私にとって他人だからだ。
涌井さんや金田さんの前では、私は「ファミリーグリル・シリウス浅草雷門通り店」の店長、南雲みもざでいるしかない。
昔から私は「真面目」だと言われてきたけれど、「店長」という鎧は、真面目な私にとっては本当に呪いでしかなかった。店では分不相応な責任感を与え、店を出ても緩やかに私を締めつづけて、少しの弱音も吐かせてくれないのだ。
堤さんの手があまりにも優しくて、私はこれまで誰にも打ち明けられなかったことまで話してしまった。おそらく彼女が同業者だから、理解してもらえると思ったのだろう。これまでため込んできたものをすべて、聞いてもらいたかったのだ。
「火事だけじゃないんです。私、洋食店の店長なんです。あっ、洋食店といっても、こんな素敵なお店ではなくて、はっきり言ってファミレスなんです。場所もシブい浅草だし」
「まぁ、若いのに店長なんてすごいじゃない。いくつ?」
「34、店長になったのは2年前です。店長なんてやりたくなかったのに、無理やり押し付けられたんです。社長がいきなり、女性が活躍する企業を目指すなんて言い出して、既存店の半分を女性店長にしたんです。中には張り切って引き受けた人もいるけど、私は昔から人前に立つタイプじゃない。自分が上に立つより、2番手として支えるほうがぴったりなんですよ。それなのに強引な人事で……」