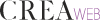「金剛力士立像は圧巻! 背中はちょっとぷっくりと…」佐々木蔵之介と巡る、東京国立博物館・常設展「東博コレクション展」
「東博コレクション展」のスペシャルサポーターに佐々木蔵之介さんが就任

東京・上野公園にある「東京国立博物館」は、日本で最も長い歴史を持つ博物館。これまで、「総合文化展(常設展)」として、所蔵品・寄託品合わせて常時3,000件を展示していたが、2025年4月1日より名称を「東博コレクション展」に変更。スペシャルサポーターとして俳優・佐々木蔵之介さんが就任し、展覧会を盛り上げる。今回は佐々木さんが東京国立博物館の副館長・浅見龍介さんや研究員の案内のもと、館内をめぐる。

東京国立博物館が1872年に創立して以来、150年にわたって受け継がれてきた収蔵品は12万件以上。そのうち国宝89件、重要文化財653件(2025年4月現在)と、世界有数の日本・東洋美術コレクションを誇る。
「常設展といっても、常に同じ作品を展示しているわけではありません。季節や作品の状態などに合わせて常に展示替えをしていて、年に約400回展示替えをしています。展示されていない作品を納める収蔵庫のことを、“蔵”と呼んでいるんですよ」と浅見さん。
その言葉を聞いて佐々木さんは「なるほど、それで僕をスペシャルサポーターに選んでいただいたんですね(笑)。光栄です」と笑顔を見せた。
歴史の授業で学んだ記憶がよみがえる
まずは本館2階の1室「日本美術のあけぼの―縄文・弥生・古墳」へ。ここでは考古担当の研究員・山本亮さんが案内人に。

弥生時代に造られた「袈裟襷文銅鐸(けさだすきもんどうたく)」を前に、「教科書で観て想像していたものよりも大きいですね」と驚く佐々木さん。
「弥生時代のお祭りのときに使うもので、今でいう“ベル”ですね。初めは手で持って鳴らせるサイズでしたが、時代の変化につれて大きくなり、鳴らせなくなっていったので、研究者の間では『聞く銅鐸から、見る銅鐸へ』と表現します。現在錆びて緑色に変色していますが、ブロンズ製なので、もともとは10円玉のように光り輝いていたんですよ」(山本さん)

「埴輪 大刀を佩く男子(はにわ たちをはくだんし)」が作られたのは古墳時代。2本の刀を佩いているのが特徴だ。
「よく見ると、胴体にストライプのような白い筋が入っていますよね。はにわに色が塗られていることが最近注目されるようになってきました」(山本さん)

佐々木さんは「頭にもストライプの色が付いているということは、被り物をしているんですね。刀だけでなくネックレスも着けている。表情に愛嬌がありますね」と興味深げにはにわを見つめる。
さらに展示は「仏教の興隆―飛鳥・奈良」へと続く。日本の文化は仏教の受容とともに飛躍的に進歩を遂げていった。このエリアでは、日本仏教黎明期の彫刻や書跡・典籍、工芸などが紹介されている。
きらびやかな宝玉や仏像を前に、「縄文、弥生から一気に雰囲気が変わりますね」と佐々木さん。
国宝と1対1で向き合う、特別な空間


次に案内された「国宝室」に展示されているのは1件のみ。
こちらの展示室では、季節を感じさせる作品を中心に紹介しており、桜が満開だった取材当日に展示されていたのは、国宝の「花下遊楽図屏風(かかゆうらくずびょうぶ)」。
「今から約400年前、江戸時代の初め頃の作品です。多くの屏風は右から左に向かってストーリーが描かれているのですが、右下は大きな桜の下で三味線を弾いたり、花を摘んでいる女性が描かれていますね。真ん中の空白になっている部分は、残念ながら関東大震災で被災し、失われてしまったのですが、佐々木さんだったらここにどんな場面が描かれていると想像されますか?」と案内人の絵画担当・土屋貴裕さんの問いかけに、佐々木さんは「それはもう、お花見をしながらお酒を飲んでいるシーンですね!」と即答。

一方、左側の屏風に描かれているのは、桜ではなく海棠(かいどう)の花見を楽しむ人々の姿。男装姿の女性たちが歌舞伎踊りを舞う姿や、暗幕の裏側で支度をする人などが描かれている。佐々木さんは、解説に耳を傾けながら、ガラス越しに屏風を眺めたり、展示室中央に置かれたソファでじっくり向き合ったり――。
「この空間では集中して一点と向き合うことができるので、没入感がありますね。僕は今、こうして鑑賞しているわけですが、実際に間仕切りとして使われていた様子も想像します」(佐々木さん)
約3メートルの金剛力士立像が出迎える彫刻室
次は、彫刻作品が展示されている1階11室へ。

扉を入ってすぐの場所に設置された「金剛力士立像」の迫力ある姿に圧倒され、思わず息をのむ佐々木さん。実は、こちらの展示室は、2025年4月にリニューアルされたばかり。案内人の彫刻担当・増田政史さんが時代背景などを解説。



「こちらは平安時代後期、12世紀に造られた貴重な金剛力士立像です。“仁王”ともいいますね。もともとは滋賀県栗東市にあった蓮台寺に安置されていたのですが、昭和9年の室戸台風で門と像が倒壊しバラバラになってしまいました。昭和43年に国宝、重要文化財をはじめ仏像の修理を行う財団法人美術院に引き取られ、仮に組み立てた状態で保管していました。近年、約2年かけて修理され、縁あって2022年2月に当館が購入することになりました」(増田さん)

平安時代に造られた金剛力士立像は力強さがありながらも、どこか穏やかさがあり、どっしりとした体型が特徴。また、通常、金剛力士立像は寺院の「仁王門」に安置されているため、正面から見ることしかできないが、ここでは背面が見られるのもポイントだ。「背面は丸みがあって、正面から見る印象と全く違いますね」(佐々木さん)
展示室のリニューアルにあたり、ガラス製の展示ケースも刷新。透明度が高く、映り込みを極限まで抑えた特殊ガラスで作られており、LED照明を導入したことでスポットライトも細やかに設定できるようになったという。

「こちらの『菩薩立像(ぼさつりゅうぞう)』は目に水晶がはめ込まれていて、光を当てることできらりと光ります。これまでの展示ケースでは視覚的な演出が難しかったのですが、リニューアルしたことで水晶が輝く様子をご覧いただけるようになりました」(増田さん)
「本当だ、光っていますね。間にガラスがあることを感じさせないくらい、細部までリアルに観えて、より身近に感じます」(佐々木さん)
作品の魅力とともに、博物館を支える人々の想いも伝えたい
改めて佐々木さんに、「東博コレクション展」スペシャルサポーターとしての意気込みや見どころについて聞いた。
「普段はひとりで観に来ることが多いのですが、今日は研究員の方々とご一緒させていただいて、一つひとつの作品がグッと身近に感じられました。また、研究員の皆さんが、それぞれ担当されている美術品に対して熱い想いを持たれているので、お話を伺うのも楽しかったです。さまざまな作品を収集して、保存して、展示して、修復して、また調査研究が続けられて……展示室よりも、バックステージで行われている作業の大変さを思い浮かべたりもしました。

今回、僕が最も印象的だったのは『金剛力士立像』。はじめ、どこに配置しようか悩まれたそうなんですが、お寺の守り神だからやはり入り口だろう、と。本当に圧巻でした。ところが裏側を観たら、背中はちょっとぷっくりしていて――言ってみればぜい肉ですよね(笑)。平安時代と鎌倉時代で体型に差があるということも発見でした。
驚いたのは、約12万件の所蔵品の中で展示されているのは約3,000件、つまり40分の1しかない。ということは、最短でも4年かけないと所蔵品すべてを観ることはできないんですね。ほぼ毎週どこかで展示替えされているから、いつ来ても新しいものが見られるのは魅力だと思います。夏には国宝室で『納涼図屏風』(久隅守景筆、江戸時代・17世紀、2025年7月23日[水]〜8月17日[日]展示予定)が展示されると伺ったので、夕涼みに来てみたいですね。

展示されている作品を観るだけでも、もちろん面白いのですが、その裏側にある歴史や背景を知ることで、見え方が変わるということも教えていただきました。こうしたきっかけを与えていただいたので、僕も新しく発見したり、楽しく学んだり、皆さんと一緒に共有できたらと考えています」(佐々木さん)
佐々木蔵之介(ささき・くらのすけ)
1968年2月4日生まれ 京都府出身。神戸大学在籍中、劇団「惑星ピスタチオ」の旗揚げに参加。退団後、2000年NHK朝の連続テレビ小説「オードリー」で注目を集めその後テレビ・映画・舞台など数多くの作品に出演。2005年には自身がプロデュースを務める演劇ユニット「Team申」を立ち上げ不定期で公演を開催している。主な出演作にNHK大河ドラマ『光る君へ』(2024年)、『映画 マイホームヒーロー』(2024年)、『ゴジラ −1.0』(2023年)、舞台『冬のライオン』(2022年)、『守銭奴 ザ・マネー・クレイジー』(2022年)など。舞台『ヨナ』5月下旬にルーマニア・シビウでワールドプレミア、東欧5カ所ツアーの後、6月下旬のシビウ国際演劇祭に参加。10月、11月は東京芸術劇場をはじめとする、各地で公演予定。
佐々木蔵之介FCサイト『TRANSIT』:https://sasaki-kuranosuke.com/
東博コレクション展
会場 東京国立博物館(東京都台東区上野公園13-9)
開場時間 9:30〜17:00(金・土は9:30〜20:00)
※入館は閉館の30分前まで
休館日 月曜日 ※ただし、月曜日が祝日または休日の場合は翌平日
観覧料(東博コレクション展示) 一般1,000円、大学生500円
※高校生以下及び満18歳未満、満70歳以上は無料。入館の際に年齢がわかるものを提示
※障害者とその介護者1名は無料。入館の際に障害者手帳等を提示
※特別展、有料イベント等は別途料金が必要
問い合わせ 050-5541-8600(ハローダイヤル)
https://www.tnm.jp/
文=河西みのり
撮影=平松市聖
あわせて読みたい
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント,芸術,地域の魅力]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒]
-

- 5月2日の月が教えてくれるヒント 親しくなりたい人を誘う
- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと11日。 月は蟹座で満ちていきます…
- (CREA WEB)[まち歩き,CREA WEB]
-

- 部屋干し派必見、生乾きを逃さない衣類乾燥除湿機!カビ対策を強化した、三菱電機「サラリ」3モデル
- 三菱電機は、衣類乾燥除湿機の新製品として「サラリPro」MJ-PV250YX、「サラリ」MJ-P180YX、MJ-M120YXの3…
- (GetNavi web)[気候変動]
-

- 2日 近畿から関東は局地的に激しい雨も 体感ガラッと変化 外出時の服装に注意
- 今日2日は、近畿や東海、関東を中心に雨が降るでしょう。局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。最高気温…
- (tenki.jp)[気象,東京都]
-

- 弘前で「森カリオペ」のリキュール販売延長 弘前城の缶バッジを同梱
- 津軽藩ねぷた村(弘前市亀甲町)で期間限定商品だったバーチャルアーティスト「森カリオペ」のリキュール…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[花見]
-

- 土浦に助産師常駐の「産前産後ケアハウスmamacocochi」 ネスカフェと連携
- 「産前産後ケアハウス mamacocochi(ままここち) supported by NESCAFE」(土浦市中村南)が4月16日、オ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[茨城県]
-

- 伊勢で映画「ペイル・ブルー・ドット」上映会 西嶋航司監督らのトークも
- ドキュメンタリー映画「Pale Blue Dot(ペイル・ブルー・ドット) 君が微笑(ほほえ)めば、」の上映会が4…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[三重県]
-

- 彦根の四番町スクエアで初の「ホラーナイト」 クイズイベントも
- 夜の商店街を「お化け」が徘徊(はいかい)する「ホラーナイト」が5月11日、四番町スクエア(彦根市本町1…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[滋賀県]
-

- 竜王のアウトレットパークで「パンマルシェ」 全国のパン店が出店
- 全国のパン店が出店するイベント「パンマルシェ」が5月3日~5日、三井アウトレットパーク滋賀竜王(竜王町…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[京都府]
-

- がんばるキュリオシティ。火星が暖かく、水も流れていたかもしれない証拠を発見
- がんばるキュリオシティ。火星が暖かく、水も流れていたかもしれない証拠を発見Image: NASA/JPL-Caltech/M…
- (Gizmodo Japan)[宇宙]
-

- 「台風」去年に続き今年も4月まで発生なし でも油断せず
- 南の海上は年間を通して暖かく、冬や春も台風が発生することは珍しくありませんが、今年に入ってから、ま…
- (tenki.jp)[台風]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.