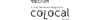渋谷区の商店街にある“屋根のある公園”のような居場所とは? 民間の地域福祉拠点

この連載は、日本デザイン振興会でグッドデザイン賞などの事業や地域デザイン支援などを手がける矢島進二が、全国各地で蠢き始めた「準公共」といえるプロジェクトの現場を訪ね、その当事者へのインタビューを通して、準公共がどのようにデザインされたかを探り、まだ曖昧模糊とした準公共の輪郭を徐々に描く企画。
第8回は、2024年度グッドデザイン賞を受賞した、東京都渋谷区にある〈笹塚十号のいえ〉を訪ねた。
ここは、渋谷区の笹塚十号通り商店街にある元八百屋を活用し、複数の民間団体が協働して運営する地域福祉拠点だ。「屋根のある公園」をコンセプトに、地域に暮らす人が自由に休憩ができる場を提供するほか、地域団体の連携促進を目的に、福祉作業所の商品販売、フードパントリー、生涯学習企画、学生ボランティアなどの活動拠点としても活用されている。
同プロジェクトの中心人物である戸所信貴さん(一般社団法人〈TEN-SHIPアソシエーション〉代表理事)と、左京泰明さん(一般社団法人TEN-SHIPアソシエーション理事兼、一般社団法人〈マネージング・ノンプロフィット〉代表理事)のふたりから話を聞いた。
複数の非営利組織が維持管理費を分担し、都心に常設の活動拠点をつくった事業モデルと、サービスの提供と享受、有料と無料の境界を取り払うことで、目的がなくても立ち寄れる日常の居場所創出を通して、「準公共」の最新の意義を探る。

〈笹塚十号のいえ〉は京王線笹塚駅北口下車、徒歩約5分。笹塚十号通り商店街の真ん中にある元八百屋を活用。
〈笹塚十号のいえ〉をつくった理由矢島進二(以下、矢島): 最初に、戸所さんが〈笹塚十号のいえ〉をつくるまでの話を聞かせてください。
戸所信貴さん(以下、戸所): 東京で店舗関連の建築設計・施工の会社に勤めていましたが、群馬に住む父と母と祖母が要介護状態になったことがきっかけで、福祉関連の活動を30歳のときに始めました。
老人ホームのケアワーカーをやり、その後、笹塚の地域包括支援センターに移り、そこで多くの疑問に直面しました。公的サービスでは、必要だと思っても余計なことはしてはいけないルールがたくさんあるのです。サービス業として顧客への対応という面からみても不思議なことが多かったです。
例えば、家の中で動けなくなった方のサポートでは、玄関やベランダの掃除、窓拭き、エアコンの掃除、衣替え、電球交換などはやってはいけない。買い物も最寄りのスーパーに限定されるなど、「してはいけないこと」が「していいこと」より多いのです。
地域包括支援センターに12年勤務し、最後はセンター長を務めましたが、センター長として「これはしてはいけない」とスタッフに言う立場は、心苦しいものがありました。
行政的には、公平性の問題や税金の使用という観点から、最低限度のことに絞られてしまう。地域的には、かつての「向こう三軒両隣」のような助け合いのつながりが希薄になり、そこに大きな“隙間”が生まれてしまっています。
その隙間を埋めるために、一般社団法人〈TEN-SHIPアソシエーション〉を立ち上げました。確実なニーズがあることはわかっていましたが、具体的な方法を模索しているときに左京さんと出会いました。

一般社団法人〈TEN-SHIPアソシエーション〉代表理事の戸所信貴さん。「家族の要介護3人の暮らしを目の当たりにし、超高齢社会では介護者だけでは対応できない課題が多数あることを知り、思い切って退職」。笹塚十号のいえの2軒隣で「まちのお手伝いマネージャー」という活動もしている。
矢島: 次に左京さんのプロフィールと戸所さんとの出会いを教えてください。
左京泰明さん(以下、左京): 2006年に特定非営利活動法人〈シブヤ大学〉を立ち上げました。地域のNPOの方々から運営や企業との連携についての相談を持ちかけられたことをきっかけに、NPOの経営支援に興味を持ち、行政や企業とNPOの協働の仕組みづくりを行うために、一般社団法人〈マネージング・ノンプロフィット〉を2017年に設立しました。
渋谷区の事業では、例えば「渋谷おとなりサンデー」という、渋谷で暮らし、働き、学ぶ人々をつなぐ地域の交流事業を企画・実施しました。そこで戸所さんと出会い、個人としてリスクをとってまで個人でお年寄りのサポートを始める理由を知り、救うべき人を知る戸所さんの知見を、いかに継続的に発展できるかたちにするか、という役割で参画することになりました。戸所さんとは最初に社団設立の趣意書を一緒に作成しました。
メディアを通して語られる社会問題は表層的になりがちです。戸所さんは日常の仕事を通じて、本当に困っている方々と数多く出会っています。しかし行政の立場では、対応できないことが多すぎることがわかりました。
当初私は、行政サービスでカバーできていない“隙間”を埋めることが必要だと考えていましたが、実は逆でした。行政が対応できているニーズはごく一部で、ほとんどのニーズが満たされていないことを戸所さんから教わりました。

一般社団法人〈TEN-SHIPアソシエーション〉理事兼、一般社団法人〈マネージング・ノンプロフィット〉代表理事の左京泰明さん。2006年にNPO法人〈シブヤ大学〉を立ち上げ、14年間学長を務めたが、若い人たちに譲り、現在はNPOの経営支援や地域づくり活動を行っている。
笹塚十号のいえ運営の仕組み矢島: ここは運営委員会形式で運営していますが、委員10人の構成はどのようにして決まったのでしょうか。
左京: 私は、自分の役割として、戸所さんをはじめ運営メンバーの方々が「何とかしたいこと」「理想だと思うこと」について実現可能なかたちや仕組みを考えることだと思っています。
最初は、98年間愛されながら閉店が決まった八百屋さんから、地域のために活用してほしいと相談がありました。戸所さんは地域の人々の居場所となるような場をつくりたいと考えていましたが、京王線の笹塚駅から徒歩5分の一等地なので、家賃負担が大きな課題でした。
どうしようかといろいろな関係者と話しているときに、同じ地域で活動している福祉作業所の所長から「全額は難しいけれど、これくらいなら負担できるかも」という話を聞いたのです。その金額が家賃の10分の1だったことから、同じような思いを持つ団体を10組集めれば実現できると思いつきました。すぐに地域福祉を軸に活動し、共感とメリットを見出せる団体に声をかけました。

営業は火・木・土曜の11時30分から18時30分。外にベンチを置き、買い物途中の高齢者が休息すると、スタッフやお客さんが声をかける。
矢島: 具体的にはどんな組織が参加していますか?
左京: 笹塚で活動する高齢者福祉、障害者福祉、フードバンク、そして大学などです。大学の授業を通じて活動を知った学生が、その後個人的にボランティアとして参加し、お年寄りへのネイルケアやスマートフォンの使い方を教えたりという事例もあります。
各団体が独自のイベントなどを企画し、2週間ごとの運営会議で活動内容を共有しています。福祉の専門家が多く参加しているので、「気になる利用者がいる」といった相談にも、すぐに適切な解決策が示されます。居場所となりえるような場を提供すると同時に、健康状態や生活状態を見守りながら、必要な支援につなげていく場所としても機能しています。
矢島: 10の組織が関わることで、方向性や運営方針について意見が合わないことはありませんか?
戸所: 最初は活動イメージが各々少しずつ違っていましたが、運営会議で議論を重ねることで「地域共生」という共通の方向性が定まってきました。
左京: 「まちの中心に自分たちが自由に使える場所ができたら?」という問いかけに、各団体からさまざまなアイデアが出てきました。フードバンクはフードパントリーの受け渡し場所として、大学は学生の地域活動拠点として、というように。単独では難しくても、10団体で運営をシェアすることで実現可能になりました。

「『スイミーモデル』と言っていますが、小さな魚が集まってひとつの大きな魚になるようなことは、これまでなかったはずですし、どこでも真似ができるはずです」と左京さん。(写真提供:笹塚十号のいえ)
民間主体の地域福祉の実践左京: 2023年夏に借りることを決め、冬に内装費などの初期費用をクラウドファンディングで集めました。目標額360万円に対して211人から443万円の支援が集まりました。
クラウドファンディング運営会社の方からは目標額が高いのではと指摘されましたが、10団体それぞれのネットワークを通じて呼びかければ可能だと考えました。実際、各団体が積極的に呼びかけ、目標を上回る支援が集まりました。
矢島: 行政からの助成金は受けていますか?
左京: 商店街活性化の助成金で改修費の一部を賄いましたが、運営は独立採算です。
矢島: となると、完全な「民間主体の地域福祉の居場所」ということですね。そこに至った経緯を教えてください。
戸所: 開設までの1年間、地域の課題をじっくり考えました。部屋の片づけができない、電球の交換ができないなど、ちょっとした困りごとを抱えるお年寄りが大勢いることがわかりました。その原因は病気や認知症などさまざまですが、「ちょっとしたことを人に頼めない」ことがきっかけになるケースが多いのです。例えば、ゴミの分別方法がわからず、溜まっていってしまうようなことがあります。

「都心は家賃が高いので、まちの中心に場所を持てるのは体力のある大きな法人しかない。私たちのような小さな団体が複数集まって展開しているのは、極めて都市的で珍しいはずです」と左京さん。
矢島: 依頼者はひとり暮らしの方が中心ですか?
戸所: いえ、家族と同居していても、家族に草むしりや片づけを頼めないので私たちに依頼がきます。息子たちは仕事が忙しく、孫は勉強が大変なので、といったように。
かつては「もうひとりの家族」のような存在が補ってくれましたが、現在はプライバシーの問題もあってそうした関係性が失われています。郊外や地方とは異なる、渋谷区特有の孤立のかたちがあります。意外だと思われがちですが、渋谷でもゴミ屋敷や孤独死の問題は深刻で、実際にゴミ屋敷と呼ばれる家を私は数百軒見てきました。
矢島: 渋谷区ならではの特質があるのでしょうか?
戸所: 渋谷は戦後、地方からの転入者が多く、都営住宅やアパートが増えていった地域です。そのため地元の人々のつながりが薄く、隣人の様子もよくわからないという方々も多いのです。

戸所さんのもとには、月に約300件の相談が入り、そのうち120件ほどを実際にサポート。本人や家族からだけでなく、保健所や障害福祉課など行政からの相談も多いという。
「屋根のある公園」というコンセプト矢島: 「屋根のある公園」「まちのリビング」というコンセプトはどこから生まれたのでしょうか?
左京: ここをつくる前に、老朽化で閉鎖が決まった施設〈敬老館〉を使い、3か月間の社会実験「まちのリビングをみんなでつくろうプロジェクト」を行いました。
すると、これまで来たことのない幼稚園の送迎後の母親たちや子どもたち、もともとの利用者だった高齢者などが大勢集まりました。特に小さな子どもを持つ母親たちは、日中無料で自由に過ごせるのは公園しかない。炎天下でも公園で過ごさざるを得ない状況です。屋根があり冷暖房の効くその場所は、人気スポットになりました。
この経験から、予約することなく、いつでもふらっと立ち寄れる場所を必要とする人が多いこと、そしてこういう場所があれば多様な人々が集まることを確信しました。
矢島: 開設から1年が経ちましたが、どんなイベントを行ってきましたか?
戸所: 特別なイベントを私たちが企画するというより、来場者自身が主役になるものが多いのが特徴で、1年間で約120回のイベントを行いました。ハーモニカの演奏会、けん玉、踊りなど、地域の方々の特技を生かした企画が自然と生まれています。大学生によるクリスマスカードや、手づくりアクセサリーのワークショップも定期的に開いています。スタッフによるハンドマッサージや足湯もとても好評です。
また2か月に1回、夕食を持ち寄って一緒に食事をする会も開いています。普段は18時半までの営業ですが、この日は時間を延長し、「もうひとりの家族の集まり」のような雰囲気で、常連の方々が集まっています。

矢島: 大学生がスタッフで参加している意味合いはどこにありますか?
戸所: 高齢者だけ、あるいは子どもだけの場所だと入りづらい雰囲気になってしまいます。学生がいることで安心感が生まれ、特定の層に偏ることなく、世代間交流のきっかけになるのです。聖心女子大学は「地域づくり演習」の授業の一環として、また青山学院大学はボランティアセンターのスタッフとして「青学カフェ」を毎月開催しています。

学生が開いている無料のネイルサロンも人気。(写真提供:笹塚十号のいえ)
日常のなかで気軽にひと休みできる場矢島: 通り過ぎる人からはどのように見られているのでしょうか?
戸所: 「あそこは何だろう?」と不思議そうに見られることが多いです。カフェのようでいて飲み物は100円、子どもたちが自由に遊んでいる様子など、一見するとわかりにくい場所かもしれません。当初は説明の文章を掲示していましたが、しっくりこなかったので、自由に捉えていただくことにしました。
左京: 開設当初は怪訝な表情で見られていましたが、1年を経て「そういう場所なんだ」という認識が定着してきたのではないでしょうか。商品やサービスの売り買いではない、独特の場所として受け入れられつつある。外から人を呼び込む商店街ではなく、生活動線上にある場所だからこそ、いい意味で「変わった場所」として定着してきたように感じます。

コーヒーや紅茶は100円で、外に置いてあるむぎ茶は熱中症予防も兼ねて無料。利益が目的ではなく、あくまで会話のきっかけのためのサービスだ。また、雑貨など寄付品が並んでいるのもコミュニケーションを生むための仕かけ。
矢島: ここは商店街にどのような効果をもたらしていますか? また今後の課題は何でしょうか?
戸所: かつての商店街は人通りが絶えないほどの賑わいがありましたが、最近は個店が減少し賑わいも減っています。ここは商店街の曲がり角という立地を生かし、賑わいの維持には貢献していると思います。現在は週3日の営業ですが、営業日を増やしてさらに賑わいを創出できればと考えています。
左京: 家賃などの固定費は各運営団体の負担でまかなっていますが、行政や企業では届きにくい部分への活動を充実させていくために収入を増やしていく必要があります。継続的なサポーターを募るとともに、活動の本質を損なわないかたちでの収益事業も検討していきたいです。

かつてよりは賑わいが減ったとはいえ、人通りは多い十号通り商店街。(写真提供:笹塚十号のいえ)
戸所: この場所は社会に必要不可欠だと考えています。渋谷区に限らず、都市部の多くの地域が同じような課題を抱えています。私たちがすべてを担うのではなく、その必要性に気づいた人々がチームを組んで活動を広げていってほしい。そのネットワークが社会に広がることを願っています。
左京: 同じような空間があれば同じことが起こるわけではありません。この場所の本質は、同じ地域の中で異なる分野で活動する10の団体が協働していることにあります。戸所さんがいるから高齢者が安心して来られ、障害の専門家がいるから障害のある方も気軽に立ち寄れる。運営する側の多様性が、来場者の多様性を生んでいます。
ふらっと立ち寄った人の気がかりな様子に気づいたとき、さまざまな専門性を持つ団体が関わっているからこそ、適切な支援につなげることができます。この10団体のつながりこそが最も重要なのです。

ケアマネージャーなど、約20名のボランティアが空き時間を使って運営。プライバシーの問題もあり、適切な距離を保つために近所の方には依頼していない。
矢島: 笹塚から今後、いろいろなところに広がっていくといいですね。ほかの地域から、うちでもやりたいといった具体的な話はきているのでしょうか?
左京: はい、すでにいくつか声は上がっていますし、近いことを考えたり、やっている人たちが増えているので、広がってほしいなと思います。地域に新たに場をつくるというと、すごくお金がかかりそうと思われますが、ここのようなささやかな場所をみんなで営んでいくのは、どこでもできるはずです。
矢島: 最近のエピソードがあれば教えてください。
左京: 近隣の小学校の子どもたちへの学習支援と居場所づくりの活動が始まりました。青山学院大学と聖心女子大学の先生と学生ボランティアによって、夏休みの宿題のサポートをしたのが好評で、現在は毎週水曜日の放課後の活動へと広がっています。

利用者の中心は高齢だが、幼稚園児とお母さんや、小学生も多く、シャボン玉やゲームなどで自由に遊ぶ。「滞在時間が長く回転率が極めて悪い状態です」と戸所さんは笑う。
左京: また、最近話し合っているのは「8050問題」と呼ばれる、80代の親、50代の引きこもりや障害のある家族をいかに支えるかという課題です。親の入院をきっかけに残された人が孤立してしまうケースが多く、居場所やサポート態勢が不可欠です。
このように、ここは、さまざまな分野の人々が出会い、それぞれの現場で起きている課題を共有し、知恵や資源を持ち寄りながら、新たな解決策を生み出すためのプラットフォームのようなつながりになってきています。このプラットフォームに参加すれば、 自分たちだけでは無理だとあきらめていたようなことが実現できるような仕組みになればと思います。
戸所: 場所があることで、人は変わります。承認が自信につながっていく。子どもの成長に「安全安心な基地」が必要なように、大人も高齢者も同じです。そうした機能を最も大切にしていきたいと考えています。
先日も、常連の方が転倒され、みんなに心配されて病院に行ったところ、脳梗塞が見つかりました。この場所に来ていなければ、発見が遅れていたかもしれません。そんなかたちでの見守りも、自然と生まれています。
左京: この1年で、多くの人々の変化を目にしてきました。地域で変わり者扱いされていた高齢者が、ここで居場所を見つけて変わっていく。そんな感動的なシーンが数多く生まれています。
行政との理想的な関係矢島: 行政との関係性はどのようにあるべきでしょうか?
左京: 行政は、民間に比べると迅速な対応が難しく、緊急の課題に対しても、検討に数か月を要することがあります。行政を“大動脈”とすれば、私たちの活動は“毛細血管”のような存在です。両者が補完し合うことが重要です。
行政は、前例がなく結果が事前にわかりづらいことを始めるのは特にハードルが高く、トライ&エラーしにくいです。なので、課題やニーズの発見から新規プロトタイプの開発までを民間でやり、その結果を行政にフィードバックして、行政側が事業化してほかの地域にも展開していくみたいな、そういう関係になっていくのが理想です。
現在の長谷部健渋谷区長は、地域の人々やNPOが活躍できる場をつくることを重視しています。すべてを行政が担うのではなく、地域の人々が主体的に参画するかたちを目指す。それをコーディネートするのが行政の仕事だと捉えていますが、この役割分担は渋谷らしいと思っています。

厚生省は、2020年に「重層的支援体制整備事業」を始めた。これは1世帯の中に、高齢者の問題と生活困窮の問題など複合的な課題があるのが実態でありながら、縦割り行政では一括で対応できなかったのを、ワンストップの扱いとするもの。「戸所さんからしてみたら、とっくに気がついて、そこに問題意識を持って活動を始めたので、制度が追いついたようなものです」と左京さん。
「準公共」という概念矢島: この連載では、行政と市民の新しい関係性を「準公共」と呼んでいます。官と民の役割を明確に区分けするのではなく、重なり合い、相互に補完し合うあり方です。「準公共」という言葉をどう受け止められましたか?
左京: 行政だけで地域を支えることはもはや不可能です。一方で特に渋谷のような都市部、昔からの地域コミュニティが衰退、変容するなかでは、新しいかたちの地域コミュニティや公共のあり方が求められます。渋谷には、そうした背景のなかで、住民の必要から生まれた多くの実践の蓄積があると考えています。
私自身も、シブヤ大学の設立以来、いわば、ずっと準公共の領域で活動してきたとも言えます。
戸所: まさに私たちが目指してきたもので、20年前に福祉の世界に入ったときからの問題意識と重なります。
官でも民でもない準公共が意図する「もうひとつの」という考え方にも共感します。私たちも「もうひとりの家族」「もうひとつの居場所」「もうひとつの地域」という言葉を使っています。本来の家族や公共では対応が難しい部分を、「準」というかたちで補完できるのではないでしょうか。
矢島: 笹塚十号のいえという名称には、「もうひとつの家」という意味も込められているのですね。

戸所さんがやっている「まちのお手伝いマネージャー」では、30分300円で草むしりや荷物整理などをしている。そこからほかの悩みや課題を見つけて、ほかの団体に相談したり、必要に応じて行政につなぐこともしている。
左京: イタリアのトリノ市周辺に「地区の家」という取り組みがあります。工場跡地や公衆浴場をリノベーションした、NPOや建築家たちによる民設民営の公民館のような場所で、彼らの活動から多くを学びました。
政策として上から下りてくるのではなく、目の前の困っている人のために即座に行動を起こす。まさにもうひとりの家族のような関わり方です。イタリアから視察に来てくれ、自分たちの活動がここで引き継がれていることを喜んでくれました。

「住宅地の一軒家でやることも考えられますが、知っている人しか行かない場所になってしまう。通りすがりの方が気軽に立ち寄れる場所でありたい。日常会話が交わせると、困ったときにSOSを気軽に出せますから。公園は誰でも来られますが、一軒家には入りにくいですよね」と戸所さん。
準公共だからこそできること全国で人口減少が続くなか、東京都は過去最多の人口になったと報道されている。コロナ禍で移住や2拠点生活などが広がったように感じているが、実際は一極集中の流れが加速しているようだ。
しかし、東京都の1世帯当たりの人員は1.92人で全国で最も少なく、単独世帯が50%を超えている(2020年の国勢調査)。当然、学生を含む若い世代と高齢者の比率が高いはずだが、ある意味「東京の標準はひとり暮らし」といえよう。以前は「4人家族」を標準として、プレハブ住宅や、乗用車、ファミレスなどさまざまなものが企画されたが、もはやそのモデルは成立しない。
成立しないのは行政サービスも同じで、集めた税金で市民のニーズをすべて叶え、地域を支えることは困難だ。左京さんが語ったように、民間が主体で市民の課題やニーズを発見し、まずはプロトタイプをつくり、その結果を行政にフィードバックして、行政側が事業化する、というのが即効性もあり、現実的だと思う。
このプロトタイプづくりや社会実験こそが「準公共」の真髄で、従来の慣習や発想から逸脱するには創造力が必要で、さらに多くの人から共感を得るにはクリエイティビティも必須だ。そしてプロトタイプをブラッシュアップしたものが「公共」に変容し、一般解になっていくのだと思う。
過去7回の連載も、皆プロトタイプや社会実験を経て、新しい「公」のあり方を見出したものだ。官と民の境界が曖昧になり、その狭間や隙間に、課題と同時に未知なる可能性も感じるために、「準公共」という視座に注目が集まっていることを強く感じた。

information
地域福祉拠点 笹塚十号のいえ
住所:渋谷区笹塚2-41-18
アクセス:京王線笹塚駅北口下車徒歩約5分
営業時間:火・木・土曜 11:30〜18:30
web:Instagram
writer profile
Shinji Yajima
矢島進二
公益財団法人日本デザイン振興会常務理事。1962年東京生まれ。1991年に現職の財団に転職。グッドデザイン賞をはじめ、東京ミッドタウン・デザインハブ、地域デザイン支援など多数のデザインプロモーション業務を担当。マガジンハウスこここで福祉とデザインを、月刊誌『事業構想』で地域デザインやビジネスデザインをテーマに連載。「経営とデザイン」「地域とデザイン」などのテーマで講演やセミナーを各地で行う。日本デザイン振興会
photographer profile
Hajime Kato
加藤 甫
写真家・Studio oowa主宰。記録・ドキュメント・アーカイブの考え方をベースに、アーティストやクリエイターとの協働プロジェクトや企業・福祉施設などの中長期プロジェクトに伴走する撮影を数多く担当している。2022年横浜にStudio oowaをオープン。自身のアートプロジェクトとして知的障がいのある子どもたちとアーティストとの協働プロジェクトの企画や居場所づくりなど、場のひらきかたを模索している。
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS,スローライフ]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ,お茶]
-

- タケノコの皮で簡単おやつ「チューチュー梅」 熱中症対策にも
- 2025/05/02 04:53 ウェザーニュース今が旬のタケノコ。この時期、店頭には皮付き生タケノコが並びます。生…
- (ウェザーニューズ)[自然化粧品]
-

- 豊田ルナ、「温泉旅行」をテーマにぬくもり感じるグラビア披露
- 豊田ルナが、4月28日(月)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)の「グラビアン魂」に初登場した。 豊田ルナ「週…
- (GetNavi web)[温泉]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント,芸術]
-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ
- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 2日 近畿から関東は局地的に激しい雨も 体感ガラッと変化 外出時の服装に注意
- 今日2日は、近畿や東海、関東を中心に雨が降るでしょう。局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。最高気温…
- (tenki.jp)[気象,東京都]
-

- 調布・神代植物公園で「春のバラフェスタ」 早朝開園やコンサートなど
- バラの花が咲き始めた都立神代植物公園(調布市深大寺元町5、TEL 042-483-2300)で5月3日、「春のバラフェ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ボランティア]
-

- 船橋FCがオーナー・キックオフ・ミーティング 地域と共にJ3目指す
- サッカークラブ・船橋FCが4月26日、船橋市勤労市民センター(船橋市本町4)で、新体制となるオーナー会議…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[寄付]
-

- 万博でも注目! CO2を栄養源に“プラスチック”を作る“細菌”って?
- 2025/04/18 05:00 ウェザーニュース桜のシーズンは1年のうちでも特に天気が気になる時季です。このまま地…
- (ウェザーニューズ)[ゴミ問題]
-

- 高松で「ガーデンプロムナードフェスティバル」 香川の食と文化を発信
- 「ガーデンプロムナードフェスティバル」が4月27日、サンポート高松(高松市サンポート)の「サンポートガ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[NPO・NGO]
-

- 週間天気予報 GW4連休は天気の移り変わり早い 最終日は広範囲で雨
- 2025/05/02 05:28 ウェザーニュース 【 この先のポイント 】・4連休前半は北日本や北陸を中心に雨・GW最終…
- (ウェザーニューズ)[健康]
-

- 【フブ】Vネック&チームロゴがポイント!ユニセックスで着用可能な注目アイテム、Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[ファッション]
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ESG]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.