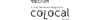能登半島地震と、伝統工芸。石川県の漆芸文化を伝える企画展を加賀市美術館で開催
石川県では、「塗りの輪島」「蒔絵の金沢」「木地の山中」といわれるそれぞれの特色を生かした漆芸が受け継がれてきました。しかし、2024年1月1日に起きた能登半島地震で、輪島の漆芸は甚大な被害を受けます。
石川県加賀市の山中温泉や山代温泉では現在も、二次避難先として輪島の漆芸にかかわる職人たちが生活されています。しかし、家屋や工房の倒壊で生活再建に追われるなか、道具を失い、制作する場もない職人たちは、仕事の再開のめども立っていない状況です。
そんななか〈加賀市美術館〉では、同じ漆芸の産地として漆芸界を応援する企画展を実施しようと、学芸員の洞口寛(ほらぐちゆたか)さんを中心に、約4か月という短いスケジュールのなか、開催へとこぎつけました。そこには、伝統工芸である漆芸の火を絶やしてはいけないという強い思いと、不思議な縁に引き寄せられた出会いがありました。
「企画展を開催するにあたり、最初は〈石川県輪島漆芸美術館〉に相談しましたが、『美術館の被害が大きいため、貸し出せる状況ではない』といわれました。あの被害状況のなかではそうだろうと思いますし、輪島の作家さんも被災している状況なので、作品を出してとほしいといえず、企画自体が難航してしまいました」と洞口さん。

〈加賀市美術館〉での展覧会の様子。
そんなとき、京都の古美術店が立ち上げたプロジェクトに、輪島の〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉の名前を見つけたといいます。
「〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉の代表である若宮隆志(わかみやたかし)さんのことは、世界的にも有名な鍛金家・山田宗美(やまだそうび)の『鉄打出兎置物』をモチーフにした作品を乾漆でつくられたのを見て気になっていました。山田宗美の『鉄打出兎置物』は加賀市美術館が所蔵していることもあり、これも縁ではないかと、声をかけさせていただいたんです。すぐに快諾をいただき、そこから、山中漆器の工房や作家さんにも依頼し、何とか開催にこぎつけることができました」と洞口さん。

『ごあいさつするうさぎ』〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉。
復旧もままならないなか、手探りで動き始めたことが、漆芸界の応援への一歩となりました。これは“ウサギがつないだ縁”といえる出会いだったようです。
「今回、この展覧会でふたつのウサギの作品を並べて展示しています。山田宗美のウサギは鉄でできているのに鉄に見えず、若宮隆志さんのウサギは漆でつくっているのに鉄に見えるんです。ふたりの技が時空を超えて、実感できる貴重な展示となっています」と、洞口さんは熱く語ってくれました。
先のことはわからないが、まず一歩踏み出したい。〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉がすぐに活動を再開できた理由能登半島地震の被害は、孤立した地域や、二次災害による輪島の朝市周辺の全焼など、全貌さえもなかなかつかめない状況が続きました。何からスタートしたらよいのか、日々の生活さえままならないなかで、〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉は、すぐに職人への義援金を立ち上げたといいます。それが震災発生から5日後のことでした。
〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉でマネージャーを担当する台湾出身の高禎蓮(たかていれん)さんは、こう話します。
「震災後すぐに、これまで支援をいただいていた国内外のお客様から『支援したい』『何を送ればいいか』という問い合わせをいただきました。そこで若宮とも相談し、確実に職人さんの手に届けられるよう、支援をお金に限定し、時間がかかってもいいので、漆に関した返礼品ができるようにと考えました。これも漆の仕事を再開するひとつの方法になるんじゃないかと思ったんです」

久々に集まった〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉のメンバー。
いち早く動き出した結果、職人さんたちに義援金を渡すことができ、アパートを借りるなど、生活の基盤を整えてもらうことにつながったそうです。さらに、県外に帰省中だったため被災していなかった若い職人の女性ふたりが、すぐにSNSでのサポートを開始。テレビや新聞ではキャッチできない職人さんたちの安否確認や、避難所の情報などを調べてくれたのだとか。
彼女たちの素早い行動もあり、職人さんたちへすぐに義援金を渡せたことが新聞などで大きな反響を呼ぶことに。支援する側も目に見えたかたちで職人さんたちを支えることができ、日本の伝統美である漆芸に関心を持ってもらうきっかけにもつながりました。

『琺瑯若冲 棗1』〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉
活動を再開の中心になったのは、〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉に勤めて7年目になる若手職人・生田圭さんSNSでのサポートをしていた若手職人のひとり、生田圭(いくたけい)さんは、震災からの日々をこう振り返ります。「震災当日は実家の京都にいたのですが、帰る場所がなくなったことが一番不安でした。マネージャーの高さんの活動拠点が金沢だったことから、私もすぐに金沢に家を借り、高さんの仕事のサポートをしようと考えました。輪島にいたときは、ものづくりに集中できていたのですが、金沢では事務作業もあり、助成金の申請に多くの時間を取られるなど、ものづくりの時間を確保するのが大変で、もどかしくもありました」
彼女たちのこういった頑張りもあって、〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉は、ほかに類をみないほど早く、震災後のイベントなどに出展できるようになります。
キャンセルした展覧会はいくつもありましたが、以前から決まっていた香港での展示会は、若手の研修も兼ねて彼女たちを連れて行ったといいます。
「海外でもたくさんの方々が心配してくださり、ご支援もいただきました。それが終わってからは、つくり手の中心である生田たちの生活を安定させ、仕事を再開できる状況にしなければと、金沢に作業場も借りたんです。今は、彼女たちには、制作だけでなく、展示会やイベントなどにも関わってもらっています。それが私たちにも大きな強みとなりました」と高さん。

香港The Gallery By Soil初個展でデモンストレーションをする生田圭さん。
震災が若手職人たちの技術や感性を見てもらうきっかけにも〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉には、見立漆器といって、漆器には見えないものを漆芸の技術を使って表現する作品が多数あります。それらは、伝承されてきた技術だけでなく、今の自分たちが生きているなかで感じるもの、それを、漆を使って表現していくことを目指しているのだといいます。
「ここでは、一から十まで教えてくれるわけではありません。出されたテーマに対して、若宮さんや職人さんたちと対話を繰り返しながら、自分の中に落としこみ、自分の持っている知識や感覚で表現できるよう、実験しながら自分のものにしていきます」と生田さん。
今回、出展されている「変わり塗り」の技法で制作されたシリーズ作品の一部は、生田さんの作品となっています。

工具として仕えない、何の役にも立たないものを漆でつくる。そこに面白みや新しい漆の技が生きています。『工具箱』〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉

『トンカチ』〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉
マネージャーの高さんは、次のように語ります。「『輪島塗』というように伝統工芸としてブランド化されたのは、日本の伝統工芸に関する法律に基づいた『伝統的工芸品』の指定ができてからです。それ以前の輪島にあった漆芸の技術は、こんなことを表現したい、こんなかたちを実現させたいという、職人同志の技の競い合いにより、実験を重ね、生まれてきたものです。そういう漆を切磋琢磨しながら塗りの技術や蒔絵表現を伝承してきたものが輪島の漆芸だと思います」

蜷川べにさん(和楽器バンド)とのコラボレーション・プロジェクトで誕生したエレキ三味線Lycoris。〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉
今までにない産地を越えたつながり。漆の技術を高め合う展示会に「〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉のように若い方たちの才能を発掘し、新しいことに挑戦している人たちがいる。それが漆という素材の持つ可能性であり、漆という素材の持つ表現の無限性だと思い、そこから『うるしを紡ぐ未来』というタイトルが生まれました」と、企画者の洞口さん。
山中漆器の組合に声をかけたところ、初めは戸惑いの声も聞こえたそうです。しかし、洞口さんが山中漆器の作家さんと話し、作品を見ていくにつれ、産地のなかで新しい表現をしようとしている人たちの作品をぜひ、一緒に紹介したいと強く思ったそうです。

山崎夢舟_鷹蒔絵箱(個人蔵)
「古い文献や記録を踏まえ、伝統の技法を受け継ぎながら、新たな表現をしている方々に出会いました。今回の出展には、山中漆器の人間国宝の川北良造先生をはじめ57点を展示。私たちにとっても山中漆器をあらためて見直すきっかけにもなりました」と、洞口さんは語ってくれます。

川北良造 欅造針杢提盆 (作家蔵)
90歳になられた川北先生も、〈漆芸アート集団 彦十蒔絵〉の作品をご覧になり、「これすごいね、どうやってつくるんだろう?」と、好奇心を持って見られていたとか。新しい技法を知ろうとする欲求にものづくりの真髄を見た気がします。大変な状況のなか、開催にこぎつけた『うるしで紡ぐ未来』展は、産地を超え、お互いに刺激をしあいながら、職人さんたちの魂が共鳴しあっているようにも感じます。

針谷祐之『四季草花蒔絵香炉(阿古陀)』(作家蔵)
「石川の漆ということで新たなページをつくっていけるんじゃないか、という希望を持てた」と語る洞口さんたちのまさに一歩を踏み出した展示会となっています。能登半島地震への支援のひとつとしても、ぜひ、多くの方に漆の作品を見ていただきたいと思いました。
information
〈うるしで紡ぐ未来〉展
住所:石川県加賀市作見町リ1-4 加賀市美術館
会期:2024年 7月27日(土) 〜 9月1日(日)
時間:10:00〜18:00(入館は17:30まで)
観覧料:一般500円、高齢者(75歳以上)250円、高校生以下無料・障がい者の方及び付添1名まで無料
休館日:火曜
Web:漆芸アート集団 彦十蒔絵
クラウドファンディング:能登半島地震復興祈念 「漆能」プロジェクト
Podcast:「漆チャンネル」
writer profile
Naomi Kuroda
黒田 直美
くろだ・なおみ●愛知県生まれ。東京で長年、編集ライターの仕事をしていたが、親の介護を機に愛知県へUターン。現在は東海圏を中心とした伝統工芸や食文化など、地方ならではの取り組みを取材している。食べること、つくることが好きで、現在は陶芸にもはまっている。
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- スープもジュースもNG。飲み物すら制限するようになった「声」の命令
- 「食べるな」「口に入れるな」 / (C)もつお/KADOKAWA中高6年間を女子校で過ごした作者のもつおさん。元…
- (レタスクラブニュース)[健康食材]
-

- 豊田ルナ、「温泉旅行」をテーマにぬくもり感じるグラビア披露
- 豊田ルナが、4月28日(月)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)の「グラビアン魂」に初登場した。 豊田ルナ「週…
- (GetNavi web)[温泉]
-

- 周南でeスポーツと職業フェア 地元企業12社が中高生にアピール
- eスポーツ大会と企業紹介イベントを組み合わせた「eスポーツフェス&職業発見フェア」が5月11日、トクヤマ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント]
-

- 今帰仁・湧川に「海鮮食堂くろちゃん」 名護漁港で競り落とす魚売りに
- 食堂「海鮮食堂くろちゃん」(今帰仁村湧川、TEL 0980-56-3919)が4月10日、オープンした。(やんばる経済…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ご当地,地域の魅力]
-

- 京丹後「五箇の朝市」が10回目 300人超参加、抽選の賞品にタイも登場
- 「第10回 五箇の朝市」が4月27日、ウッディいさなご(京丹後市峰山町五箇)で開催された。主催は五箇地域…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[朝市]
-

- 京都・吉田山の青もみじさんぽ、新緑に輝く神楽岡から京大キャンパスへ♪ 隠れ家カフェや庭園美術館も
- 桜の花びらが舞い散ると、次にやってくるのが青もみじの季節。銀閣寺近くの吉田山は一帯が吉田神社の境内…
- (ことりっぷ)[芸術]
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[旅]
-

- 「博多町家」ふるさと館物産棟がリニューアル カフェ新設や限定土産も
- 「博多町家」ふるさと館(福岡市博多区冷泉町)の物産棟がリニューアルし、4月26日、観光交流拠点「hakata…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[地方創生]
-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ
- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 部屋干し派必見、生乾きを逃さない衣類乾燥除湿機!カビ対策を強化した、三菱電機「サラリ」3モデル
- 三菱電機は、衣類乾燥除湿機の新製品として「サラリPro」MJ-PV250YX、「サラリ」MJ-P180YX、MJ-M120YXの3…
- (GetNavi web)[気候変動]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[動物]
-

- 春の「八王子古本まつり」開催へ 32回目は「映画」を特集
- 「八王子古本まつり」が5月2日、八王子駅前の西放射線通り商店街(ユーロード)で始まる。(八王子経済新…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[寄付]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東京都,愛知県]
-

- 今日1日は日本海側で30℃に迫る暑さ 明日2日は気温低下で寒暖差に注意
- 今日1日は、フェーン現象の影響で、日本海側を中心に気温が上昇しています。鳥取県境港市や新潟県魚沼市、…
- (tenki.jp)[石川県]
-

- アウトドアや災害時にきっと持ってて良かったと思える“三角形”
- アウトドアや災害時にきっと持ってて良かったと思える“三角形”Photo: SUMA-KIYO 2024年6月3日の記事を編…
- (Gizmodo Japan)[いざというときのお役立ち]
-

- あっ地震…そのときゾウが子どもを守るためにとった行動に愛を感じた
- あっ地震…そのときゾウが子どもを守るためにとった行動に愛を感じたImage: Shutterstock 本能に訓練なんて…
- (Gizmodo Japan)[地震]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.