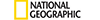「持続的幸福度」の最新の調査結果が明らかに、日本は最下位

「グローバル幸福度調査(Global Flourishing Study)」という、22の国と地域の20万人以上が参加する5年間にわたる野心的な研究の最初の成果が2025年4月30日付けで学術誌「ネイチャー・メンタルヘルス」に発表された。国別で幸福度が最も高かったのはインドネシア、最下位は日本だった。また、若い人の幸福度が低い傾向が多くの国で見られた。
以下では、この結果が意味するものや、幸福度を高めるために何ができるのかをひもといていく。
今回の調査で測った「幸福度」とは?
米ハーバード大学のタイラー・J・バンダーウィール教授は、「真に充実した人生とは何か?」という問題を何十年も考え続けてきた。
氏は米シカゴ大学の生物統計学者だった頃に、科学者たちが人間のウェルビーイング(健康で幸福な状態)を定義する方法やその測り方に不満を感じていた。うつ病などの臨床症状や、幸福感や不安感などの感情の状態など、具体的な指標を測る研究はたくさんあった。血圧や睡眠の質など、健康の客観的な指標や経済状況が健康に及ぼす影響も追跡されてきた。
しかしバンダーウィール氏には、これらの指標は、人生の喜びや問題を具体的に捉えている一方で、人生の意味と目的といった、人間が本当に追い求めているものの全体像を見落としているように感じられたのだ。
氏のチームはそれ以来、人々の心と体、スピリチュアリティー(信仰など)の状態を「フラーリッシュ(flourish、持続的幸福)」というより包括的な概念を用いて測定する手法を開発してきた。
バンダーウィール氏は2017年の論文で、フラーリッシュを「人生のあらゆる側面が良好な状態」として定義したが、その後定義を広げ、人々が生きる状況やコミュニティー、環境も含むものとした。
持続的幸福を達成する方法はさまざまであるため、人生の充実度の指標として有用だ。人生において測定が可能な要素のすべてが完璧である必要はないのだ。そこにはまた、人々が重視するもの(つまり人生に意味と目的を与えるもの)は、その人の最も深い価値観と共鳴するものでなければならないという視点もある。
最初の気づきから数年、バンダーウィール氏は持続的幸福についてより深く研究するために、米ベイラー大学のバイロン・R・ジョンソン氏とともに、科学的に調整したフラーリッシュの尺度を作成した。そして、米調査会社ギャラップと米非営利団体センター・フォー・オープンサイエンス(COS)と共同で「グローバル幸福度調査」に着手した。
今回の結果は、世界の人々の持続的幸福について、刺激的な疑問を投げかけている。
彼らの研究は、コミュニティーの重要性を明らかにした。人々の持続的幸福度は、お互いに助け合うことで高まるのだ。論文を査読した英オックスフォード大学の開発経済学者のイアン・ゴールディン氏は、「私たちに深い満足感やウェルビーイングの感覚を与えてくれるのは、所有物やバーチャルな関係ではなく、個人やコミュニティーによる選択なのです」と言う。
次ページ:年齢と持続的幸福度
年齢と持続的幸福度
グローバル幸福度調査の目標は、さまざまな国の人々の5年間の持続的幸福度を測ることにある。測定は、参加者が自分の人生について毎年回答するアンケート調査(「人生の目的を理解している」「あなたの身体的な健康状態はどれくらいですか」「通常の月の生活費が足りるかどうか心配する頻度はどれくらいありますか」などの質問に0〜10で答える)にもとづいて行われる。
研究では、幸福感と生活への満足感、心と体の健康、人生の意味と目的、人格と美徳、親密な社会的関係、経済的・物質的な安定という6つの主要な領域に着目している。それぞれの領域の質問に対する回答を集計することで、その人の持続的幸福度を知ることができる。
今回発表されたデータは、18歳から29歳の人々は総じて持続的幸福度が低いことを示している。バンダーウィール氏は、「政策に大きく関わってくる発見です」と言う。「私たちは若者の幸福を優先できているのでしょうか? 彼らのために十分な投資をしているのでしょうか?」
ウェルビーイングの研究者の間では、人生への満足度は、若者と高齢者で高く中年期に低いU字カーブを描くというのが常識だった。しかし、今回得られた持続的幸福度は18歳から49歳まで平坦で、それ以降は上昇していた。
「オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ドイツ、スウェーデン、米国、英国など多くの国で、いちばん若い人たちの持続的幸福度がいちばん低くなっていました」とバンダーウィール氏は言う(編注:日本はU字カーブを描いていた)。
以前と今とで何が変わったのだろう? 多くの原因が考えられる。社会科学者は、現代の若者たちは、生活費の問題やコロナ禍の影響、将来の仕事への不安、宗教や政府などの社会制度のほころびといった問題に頭を悩ませているのではないかと言っている。
他の研究も、若年層の苦境に警鐘を鳴らしている。ギャラップ社の世論調査データにもとづいて2025年3月に発表された「世界幸福度報告書(World Happiness Report)2025」によると、2023年には世界の若年成人の19%が「社会的支援を期待できる人はいない」と回答しており、2006年に比べて39%も増えていたという。
経済的な豊かさと持続的幸福度
グローバル幸福度調査の最も刺激的な発見の1つは、人々が感じる人生の意味と持続的幸福度は、その国の1人当たりGDP(国内総生産)と逆相関しているというものだった。
バンダーウィール氏は、「経済的に豊かな先進国の人々は、経済的な安定については高く回答していますが、人生の意味や人間関係や社会志向(社会全体や他者の利益になる行動を取ろうとする傾向)についてはそれほど高く回答していません」と言う。
ジョンソン氏は、「人生の意味と目的については、常に第三世界の人々の方が高く回答しています」と補足する。なお、今回の研究では最貧国の人々は調査対象になっていない。
米ウェイクフォレスト大学の心理学教授であるエランダ・ジャヤウィックレム氏は、今回のデータは経済的な豊かさが持続的幸福度の低下の原因であることを示したものではなく、因果関係について結論を出すにはさらなる追加調査が必要だと指摘している。なお、氏は今回の研究に関与していない。
次ページ:幸福なインドネシア人と困難に直面する日本人
幸福なインドネシア人と困難に直面する日本人
グローバル幸福度調査の対象となった22の国と地域の中で、持続的幸福の多くの側面で平均スコアが最も高く、総合で1位だったのは、イスラム教徒が多く、2025年の1人当たりGDPが約5250ドル(約75万円)で下から3番目のインドネシアだった。
インドネシアの人々は、なぜ持続的幸福を感じられるのだろうか? ジョンソン氏は、「インドネシアは民族も言語も文化も宗教も、驚くほど多様性に富んでいる島国です」と言う。
「もちろん衝突はありますが、国として融和を大切にしようと懸命に努力しています」と氏は話す。伝統的な村や部族は、歴史的に、信仰を含め自分とは異なる人々との間で平和的な関係を構築しようとしてきた。インドネシアの持続的幸福度の高さは、こうしたところから説明できるかもしれない。
バンダーウィール氏は、「経済的に本当に苦しい場所には、社会志向の感覚や人生の意味に対する感覚が深く残っているのです」と言う。
持続的幸福度が最も低かったのは、1人当たりGDPが約3万5600ドル(約510万円)の日本だった。日本は2025年の「世界幸福度報告書」でも147の国と地域中55位で、GDPが日本の約10分の1であるウズベキスタン(53位)より下だった。これは、日本が多くの社会的な緊張を抱えていることを示唆している。
ハーバード大学人間フラーリッシュプログラムの研究副部長であるブレンダン・ケイス氏は、「日本は、急速な経済発展がもたらすリスクについて警鐘を鳴らしています」と言う。
氏は、日本の出生率の低下、家族形成の難しさ、社会的に孤立している男性の多さなどの問題や、宗教行事に参加する人の少なさが、日本人の持続的幸福度の低さに影響を及ぼしている可能性があると指摘する。
「日本は、過去150年間に経験した急激な経済的、文化的な変革のせいで、持続的幸福の多くの領域で比較的高い犠牲を払うことになったように思われます」
次ページ:何歳になっても持続的幸福を感じるために
何歳になっても持続的幸福を感じるために
今、持続的幸福度に関する知見が、緊急に必要とされている。社会的な孤立、孤独、不安など、社会から乖離する傾向の指標は急上昇している。いったい何が、こうした活気のない状況を引き起こしているのだろうか? 対策はあるのだろうか?
これらの社会的な大問題に対する答えはまだ出ていない。しかし、私たち一人ひとりが持続的幸福に向けて努力することはできる。バンダーウィール氏のグループは、小さな変化が持続的幸福への一歩になるというメッセージを広めたいと考えている。彼らが推奨するのは、グループ活動への参加だ。
宗教的な礼拝に毎週参加する人は持続的幸福度のスコアが高い傾向があるが、ボランティア活動やボウリング大会などの世俗的なコミュニティー行事も、スコアを大きく上昇させる。グループ活動に参加することは、社会的つながりの感覚を高め、私たちがよりよく生きる助けとなるからだ。
誰かと一緒に食事をすることも、幸福感と強く関連していることが知られている。
オックスフォード大学ウェルビーイング研究センターの所長で、2025年の「世界幸福度報告書」の共同編集者であるヤン・エマニュエル・デ・ネーブ氏によると、2023年には米国人の4人に1人が前日の食事はすべて1人で食べたと報告しており、この割合は2003年から53%も増加したという。また韓国と日本では、過重労働文化の影響か、誰かと夕食を共にするのは1週間に1、2回だけという人の割合が大幅に増えているという。
食事などで誰かと一緒に過ごす時間を増やし、自分とは何者であり、どうすればより良い自分になれるのかを改めて考えることは、私たちの持続的幸福度を高めるのに役立つ。しかし現実には、世界の多くの場所で、現代の経済的、社会的な圧力がその邪魔をする。
それでもあきらめる必要はない。この研究の科学者たちが指摘するように、持続的幸福とは静的な状態ではなく、プロセスなのだ。そもそも完璧に達成するようなものではない。いつでもバランスをとるチャンスはある。
あわせて読みたい
-

- コンクラーベに「沸いた」バチカン、質素倹約路線はどうなる?
- コンクラーベに「沸いた」バチカン、質素倹約路線はどうなる? カトリック教会の教皇選挙コンクラーベが始…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 幸せな新婚生活が一変!赤ちゃんの誕生と妻の死、絶望の先にあった希望。夫が守ると決めたもう一つの命【作者に聞いた】
- 新婚夫婦に突然訪れた悲劇新婚夫婦に突然訪れた悲劇 / 画像提供:ナース専科幼少期から絵を描くことが大好…
- (Walkerplus)[LOHAS,スローライフ,健康]
-

- 気を使ってばかりの実家から逃げたかった私。彼とは違っていた実家への意識/子ども部屋おじさんの彼と一緒に住みたい私の100日間戦争(10)
- 気を遣ってばかりの実家を逃げたかった / (C)かどなしまる/KADOKAWAアラサーOLのかどなしまるさんは、…
- (レタスクラブニュース)[ボランティア]
-

- 小芝風花&佐藤健W主演!日本版『私の夫と結婚して』はいつ、どこで見られる?
- 日本版『私の夫と結婚して』は6月27日配信開始! / (C) 2025. CJ ENM JAPAN / STUDIO DRAGON all rights…
- (レタスクラブニュース)[ESG]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社