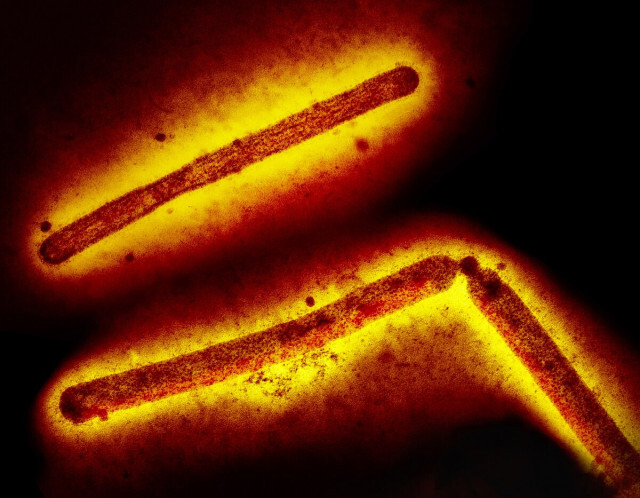
H5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが中国南部の水鳥から発見されたのは1996年だが、米国では最近、家禽から家畜のウシへの感染が確認されたことで再び懸念が高まり、汚染された食料が米国全土に出回らないか心配する声が上がっている。
鳥から畜牛への異種間感染は過去に例がなかったが、牛乳の汚染はわずか数週間のうちに広まった。米食品医薬品局(FDA)によれば、米国内で販売されている牛乳のうち、PCR検査した少なくとも20%でウイルスの断片が検出された。
「このウイルスは長い間存在してきましたが、米国に住んでいる人にとっては対岸の火事でした」と、米セントジュード小児研究病院のインフルエンザウイルス学者で、世界保健機関(WHO)動物におけるインフルエンザ生態学共同研究センターの責任者リチャード・ウェビー氏は言う。「いよいよ米国に上陸したことで、鳥インフルエンザはウシという新しい宿主を大量に発見し、大暴れしているのです」
このウイルスがもたらす脅威と、米国の食料供給が危機に直面しているのかどうかを理解するために、ウェビー氏に話を聞いた。
主に鳥に感染するウイルスであるH5N1は、ヒトにも感染する可能性がある。しかし、そうした例はまれであり、2003年にデータを集め始めて以来、世界中で報告されたヒトの感染例は889件にとどまっている。
ただし、確認された感染件数こそ少なくても、その致死率は恐ろしく高く、感染した889人の半数以上が死亡している。
感染者の大半は、生きた家禽を売る市場がたくさんある地域に出入りしていた。感染している個体は、唾液、血液、粘液、糞を通じてウイルスを排出することが知られており、そうした市場ではヒトへの感染が起こりやすくなっているとウェビー氏は言う。
しかし、そのような家禽市場に通う人の多さや、このウイルスが30年近くにわたって各市場にまん延してきただろうことを考慮すると、ヒトへの感染は比較的まれだったと言える。また、ウェビー氏によると、このウイルスが「重い病気を引き起こし、死に至らしめる能力」を持っていることは間違いないが、感染しても軽症であったり、まったく症状が出ない場合もあるという。
「こうした家禽市場が多い東南アジアの人々の血液を調べると、かなりの割合がウイルスへの抗体を持っていることがわかります。これは、彼らの多くがすでに鳥インフルエンザに感染したものの、それに気づかなかったことを示唆しています」
次ページ:ウシを殺処分すべきか
鳥インフルエンザウイルスが世界の新たな地域で人々に影響を与え、ウシ、ゾウアザラシ、ホッキョクグマを含む哺乳類48種に感染したことで、事態は従来とは異なる局面に入った。
ウシは一般的な食料源であるため、ウイルスがウシに感染してその体内で複製されるという事実は「大いに懸念すべき」ことだとウェビー氏は言う。
WHOは現在、ウシから一般のヒトへのウイルス感染による公衆衛生上のリスクは「低い」としているが、この評価は「さらなる疫学的あるいはウイルス学的な情報が手に入れば見直されるだろう」と付け加えている。
まず理解すべきは、ウシの感染が米国内でどの程度広がっているかはわかっていないということだ。感染したウシが死亡したケースがある一方、無症状のウシも存在することから、このウイルスは、ウシにとっては鳥の場合ほど致命的ではないと考えられる。したがって、「多くの群れが感染していながら、明確な病気の兆候を示していない可能性があります」とウェビー氏は言う。
また、WHOによれば2022年には67カ国で1億3100万羽を超える鳥がH5N1ウイルスにさらされたために処分されているが、今のところ米国内では、ウイルスに関連するウシの殺処分は行われていない。その理由は、このウイルスがウシから発見されたのは2024年3月末であり、処分に関する方針がまだ存在しないうえ、家禽の場合とは異なり、ウシには「全身にわたる感染」が見られない点だ。
事実、感染したウシは大半のケースで軽度の症状しか示さず、ほとんどが1週間から10日以内に回復している。
米農務省は4月末までにテキサス州、ニューメキシコ州、サウスダコタ州、コロラド州、アイダホ州、ミシガン州、オハイオ州、カンザス州、ノースカロライナ州の乳牛でH5N1の感染を確認しているが、ウェビー氏によると、全国的な検査は今のところ行われておらず、ほかの州も汚染されている可能性が高いという。
また、ウシ同士の間で感染がどのように起こっているのはまだわかっていない。今のところ有力なのは、搾乳のプロセスに用いられる機器を介して広がっているという説だ。「感染がどのように広がっているかを把握できれば、それを食い止められる可能性は十分にあります」
また、牛肉製品のウイルス汚染を示す証拠はなく、たとえ汚染されたとしても、冷凍や調理によって残存するウイルスはすべて死滅する可能性が高い。
「このウイルスは事実、かなり弱いのです」とウェビー氏は言う。「加熱やpH(酸性やアルカリ性を示す指数)の変化に敏感で、宿主の体外にいることが非常に苦手です」。このため現在、食料関係でウェビー氏が唯一懸念しているのは、殺菌していない牛乳を飲むことから生じる問題だという。
FDAは4月下旬、米国内の市販向け牛乳の供給はまだ「安全」と考えられるとの声明を発表した。なぜなら、牛乳は低温殺菌処理を施されているためだ。また、病気のウシから絞れられた牛乳は、念のため廃棄処分されている。
米農務省はウイルスのさらなる拡大を防ぐために、国内に800万頭いると推定される乳牛全頭に対し、州境を越える際にはH5N1の検査を行うよう義務付けている。
また、ウェビー氏と協力する米オハイオ州立大学の研究者チームが実施した市販の乳製品150品以上を対象とした検査では、「集めたサンプルの約40%」からウイルスの粒子が発見されたと氏は言う。
陽性の試料と比較するための陰性対照(ウイルスが含まれていない)試料をチームに提供しようと、ウェビー氏がメンフィス市にある地元のスーパーマーケットで牛乳を1瓶購入したところ、その中にもウイルスの粒子が含まれていたことに驚かされたという。この例からも、乳製品の汚染がどれだけ広がっているかがわかる。
次ページ:人間への影響は
ただし、さらに詳しい検査を通じて、低温殺菌処理によってウイルスが実際に不活性化されているとわかり、そのためウイルス粒子が牛乳に入っていても危険はないことが確認されている。「その牛乳はまだうちの冷蔵庫にありますし、私は今もそれを飲んでいます」と氏は言う。
一方で、低温殺菌処理をしていない牛乳は事情が異なる。「まだ実例は見つかっていませんが、もし低温殺菌処理をしておらず大量のウイルスが含まれた牛乳を飲んだ場合、その人は感染する可能性が高いでしょう」と氏は言う。「そのため、低温殺菌処理をしていない牛乳を飲むことについて、わたしは現在、非常に大きな懸念を持っています」
米疾病対策センター(CDC)によると、2024年に米国内でH5N1のヒトへの感染が1件だけ報告されており、その人物は感染したウシの近くで仕事をしていたという。症状は、結膜炎を中心とするごく軽いものだった。
2022年には、別の米国人1人がこのウイルスに感染しているが、当時はまだウシへの感染は発見されておらず、おそらくは家禽の近くにいたことが原因だったとみられている。米国内でヒトへの感染が確認されたのは、今のところこの2件にとどまる。
CDCによると、ヒトへのH5N1の感染は一般に、活性ウイルスを含んだ飛沫やエアロゾル粒子を吸い込んだり、「ウイルスに汚染されたものに触れた人が、自分の口、目、鼻に触れた場合」に起こるという。
そのため、現時点で最も行動に注意を払うべきは、感染したウシを扱う可能性がある酪農家と、低温殺菌処理をしていない牛乳や乳製品を摂取している人たちだとウェビー氏は言う。
ただし、状況が変わる可能性もあると氏は述べている。なぜなら、このウイルスは長い間、感染する対象が鳥に限られていたため、ウシへの感染をきっかけとして、より感染性の高い変異が生じるかもしれないからだ。
「今のところ、これは鳥に感染するウイルスと言ってよく、鳥の体内での増殖を好みます。しかし懸念されるのは、このウイルスはこれまで主に鳥の中でしか複製してこなかったため、よりヒトに感染しやすく変化する圧力が存在しなかったという事実です」と氏は説明する。
「しかし、こうしてウイルスが哺乳類に飛び火した今、理論的には、ヒトを含む哺乳類により感染しやすいように変異する機会が増えたことになります」
とはいえ、そうしたことが起こらない限り、また一般への牛乳の供給が安全でないと判断されない限りは、警戒する必要はないと氏は言う。「今のところ、ウシの間で広まっているウイルスの方が、約30年にわたって鳥の間で広まっていたものよりもヒトに感染しやすいという証拠はありません。そして、ヒトへの感染リスクが非常に低いことはすでにわかっています」



