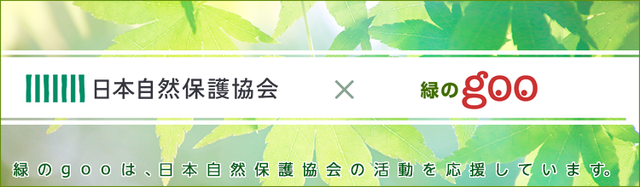日本は、海に囲まれた島国ですが、砂浜の自然についてはあまり研究が進んでおらず、わからないことが多くあります。一方、世界ではいろいろとユニークな研究が行われています。
そこで、最先端の砂浜研究の紹介を交えながら、砂浜の自然とはいったいどんな環境なのか、シリーズで紹介していただきます。
今回は魚のお話です。砂浜は、釣りのスポットとして人気がありますが、魚の世界を研究するのはなかなか大変なようです。
白浪騒ぐ外海に面した砂浜のサーフゾーンは、魚が棲むにはたいへん厳しい環境にみえますが、そんな場所にも実に様々な魚が暮らしています。
砂浜のサーフゾーン
砂浜の岸近くの波立つ領域をサーフゾーン(surf zone)と呼びます(図1)。サーフゾーンの特徴は砂浜のタイプ(シリーズ第1回『浜を読む~砂浜という環境の多様性』
https://www.goo.ne.jp/green/column/nacsj_080.html 参照)によっても異なり、沖から何度も繰り返して波が砕けるもの(逸散型)、海底の砂州の上で波が一気に砕けるもの(中間型)、汀線際で急に波が高くなるもの(反射型)など、様々です。

▲図1 サーフゾーン
沖で波が砕けている場所から岸までの領域がサーフゾーン(宮崎海岸)
私たち人間との関係では、海水浴やサーフィンなどのマリンレジャーはサーフゾーンが舞台ですし、離岸堤や潜堤など海岸防護のための構造物が置かれるのもサーフゾーンの中です。地曳網やストルト漁(波打ち際に立てた棒の上から小魚を釣るスリランカの伝統漁法)などの漁業や投げ釣り(サーフキャスティング)など、サーフゾーンの魚をターゲットにした人間活動もあります。
ハビタットとしてのサーフゾーン
魚たちがハビタット(生息場所)としてのサーフゾーンをどのように利用しているのか考えることは、砂浜の保全計画にもつながる大事なことです。サーフゾーンは、餌場、隠れ家、産卵場、生育場などとして利用されています。
【餌場として】
サーフゾーンの魚は、食べている餌のタイプからいくつかの食性グループに分けることができます。研究によっても異なりますが、主に動物プランクトン食、アミ・ヨコエビ類食、底生動物食、魚類食、昆虫食、デトリタス食などに分けられます(Inoue et al 2005; Nakane et al 2011)。
全体的にみればプランクトン食やアミ・ヨコエビ類食に分類される魚種が多く、残りに分類されるのはそれぞれ数種です。アミ類はとくに重要な餌生物で、シロギス、ヒラスズキ、ヒラメなどの稚魚~未成魚の消化管内容物には、サーフゾーンに固有のアミ類(図2)が多く含まれます。トウゴロウイワシやサヨリは、砂丘植生から風で飛ばされたりして海面に落下したハエなどの昆虫を食べていることがあります。
サーフゾーンの魚にとって昆虫は主食ではありませんが、餌生物を介したサーフゾーンと砂丘とのつながりを示す一つの例です。

▲図2
【隠れ家として】
サーフゾーンには多くの仔稚魚が生息することから、仔稚魚の隠れ家(shelter)になっていると言われてきました。水深が浅いため大型の魚食魚が進入できないとか、波が砕けることで生じる砂や気泡による濁りが捕食者の視界を妨げるなどと考えられているのですが、十分には確かめられていません。
むしろ、魚食魚にとっては餌場となっている可能性があります。東シナ海に向かって開けた鹿児島県の吹上浜で、シロギスの稚魚(平均全長34mm)を実験用の餌として用いた捕食実験(生きた状態で釣り針に掛ける)を行なったところ(Nakane et al 2009)、ギンガメアジ、キチヌ、コトヒキの全長100~150mmの個体が釣り針に掛かりました。実験区の周囲では、大型のダツ、マゴチ、スズキ、ヒラメなどの魚食魚も観察されています。
【産卵場所として】
サーフゾーンには、産卵可能な大きさまで成長した個体も現れますが、多くの場合、実際の産卵はサーフゾーンの中ではなく、沖合や近くのエスチュアリなどで行われると考えられています。しかし、数は少ないですが、砂浜の波打ち際で産卵する浜辺産卵魚がいます(Martin 2014)。
例えば、北米のカリフォルニア州で見られるトウゴロウイワシ科のカリフォルニアグルニオンは、春から夏にかけての満潮時の夜間、波が打ち上げる遡上波帯に集まり、砂の中に産卵します。キュウリウオ科のカラフトシシャモは、4~7月の夜間、波打ち際に集まり、寄せる波に乗って浜の上方へ飛び跳ね、そこで産卵します。
同じくチカは3~5月頃の夜間、波打ち際ぎりぎりの場所で産卵します(Hirose and Kawaguchi 1998)。カナダ太平洋岸のイカナゴの仲間は、冬の夜間の満潮時に潮間帯上部にやってきて、小さな穴を掘って卵を産みます。砂利浜で行われるクサフグの産卵は、日本の初夏の風物詩にもなっています。
【稚魚の生育場として】
生育場(nursery)とは、子供時代の魚介類が成体になるまでの期間を無事過ごすためのハビタットのことで、保育場とも呼ばれます。古くからサーフゾーンは仔稚魚の生育場だと言われてきましたが、それは、サーフゾーンに多くの仔稚魚が見られるという単純な理由に基づくものでした。
しかし、その場所が仔稚魚の生育場なのかどうかを判断するには、その場所での成長や生残、成魚が暮らすハビタットへの移動などに関する分析が必要です(Beck et al 2001)。研究例はごくわずかですが、ボラの仲間、コバンアジの仲間、ブルーフィッシュ(オキスズキとも呼ばれる;スズキとブリを足して2で割ったような体型;日本には分布しない;漁業・遊漁の重要種)などにとっては、サーフゾーンが生育場として機能していることを示す証拠が得られています(Able et al 2013; Whitfield and Pattrick 2015)。
でも、生育場であるかどうかは別として、仔稚魚や未成魚がたくさん見られるということは、サーフゾーンがそれらの魚種の生活史のとくに前段階において、重要な役割を担っていることを示しています。
文・写真:須田有輔/元水産大学校校長