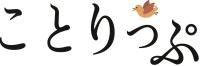滋賀「ラ コリーナ近江八幡」を手がけるたねやが「LAGO 大津」を琵琶湖の畔にオープン

滋賀県の人気観光スポットとして8年連続で1位に輝く、和菓子舗「たねや」と洋菓子舗「クラブハリエ」のフラッグシップショップ「ラ コリーナ近江八幡」。そのラ コリーナを手がけるたねやが、県内で唯一単独展開する新店舗「LAGO 大津(ラーゴ おおつ)」が、2025年3月24日、琵琶湖の畔にオープンしました。琵琶湖のパノラマビューや湖上を渡る爽やかな風を感じながら、四季折々の和菓子が楽しめますよ。
JR大津駅から近江鉄道バスの近江大橋線(イオンモール草津行)に乗って約20分、「木の下町」で下車し、歩いて8分ほど。JR膳所駅からは、徒歩のみで約20分。目印となる高層のびわ湖大津プリンスホテルに向かって右手方面を目指します。
土・日曜日と祝日には、大津港と琵琶湖博物館のある草津烏丸半島港の2つの港から、LAGOにほど近いにおの浜観光桟橋までクルーズ船も運航しています。
1872(明治5)年、近江八幡で創業した「たねや」。「ラ コリーナ近江八幡」が、和菓子のたねやと洋菓子のクラブハリエをそろえるのに対し、「LAGO 大津」はたねやの単独展開で、店舗限定や季節限定の和菓子が堪能できます。ちなみに、「ラーゴ」はイタリア語で湖、「ラ コリーナ」は丘。どちらも滋賀の豊かな自然と共存しているのです。
砂のお城をイメージした建物の外壁にはコグマザサの苗が植えられていて、これから枝葉が育てばゆっくりと緑が広がり自然に馴染む設計です。
レイクサイドに広がる「琵琶湖の森」では、苗木が日々すくすくと成長しています。大津出身であり、写真家、切り絵作家、里山保全など多方面で活躍する今森光彦氏をプロデューサーに迎え、これから10年、20年先を見据えながらゆっくりと森を育てていくとのこと。人と自然が共存する里山を再現するため、地面を踏みしめたときの質感にまでこだわり、落ち葉や木の枝も運んできたのだとか。
刻一刻と豊かさと潤いを増していく森の風景が、訪れるたびに楽しみになりそうです。
洞穴を思わせる正面入口からほの暗い店内に入って、視界が開けると青いレイクビューが広がる。そんなストーリーを描いて空間づくりをしたのだそう。ショーケースの割り木には滋賀県産のモミジの木を使用、篆刻をあしらった木の立て板は、琵琶湖に沈んでいた舟の底板で、火除けの意味があるそう。京提灯の老舗・小嶋商店が手がけた大小の提灯にはLAGOのロゴや和の文様が描かれていて、スタイリッシュさのなかに遊び心が光ります。
カフェは、入口のセルフオーダーレジを使って注文を済ませ、カウンターで受け取るスタイルです。店内のカフェスペースのほか、琵琶湖の森に点在するベンチやスタンド式のカウンターでいただくことができます。
「焼きたてたねやカステラ」は、ふんわりとした食感が特徴。しっかりと泡立てたメレンゲをつぶさないよう小麦粉と混ぜ合わせ、20分ほどかけてじっくりと焼き上げるのがふんわり食感の秘密です。オープン当初は滋賀・土山産の抹茶を使用した「抹茶」を楽しめましたが、現在は、「瀬戸内レモン」に。今後も季節の移ろいとともに新しいフレーバーがお目見えする予定。
瑞々しく甘さ控えめに炊き上げた粒餡と生クリームを合わせた「あんふわクリーム」を、小豆皮を織り交ぜたクッキーシューにたっぷり詰めた「あんパフ」も人気。オリジナルブレンドのコーヒーに、あんふわクリームとあわせていただく「あんふわコーヒー」もおすすめです。
甘いものだけでなく、軽食も。近江牛や近江軍鶏のおこわ3種のほか、特別に小豆皮を混ぜ込んだ近江八幡名物の赤こんにゃくと野菜がたっぷり入った「赤こん汁」など、滋賀県産素材を生かしたグルメが味わえます。
最中種と餡を食べる直前に合わせていただく、代表銘菓「ふくみ天平」。琵琶湖をイメージさせるLAGO限定パッケージは、滋賀みやげにぴったりです。
「瀬田夕照」「堅田落雁」「三井晩鐘」など、古来語り継がれてきた近江八景をテーマに、地元の大学と共同開発した新商品「近江八景」も。たとえば「石山秋月」をあらわした「石山あんやき」は、黄色く染めた白餡を粒餡で包み、石山寺から望む中秋の名月に見立てているといったように、湖国近江の美景に思いを馳せたくなる逸品です。全種の詰め合わせ、4景ずつに分けた「右隻」、「左隻」のほか、1個単位でも購入できます。
打ち寄せるさざ波や風の音、鳥のさえずりを聴きながら、できたてやここだけの和菓子と琵琶湖のパノラマビューを楽しんでくださいね。
あわせて読みたい
-

- 名古屋・新栄の「AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY」で、洗練された建築とデザイン、コーヒーを味わう
- 「AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY(アオイセレスティコーヒーロースタリー)」は名古屋市の中心部、新栄に…
- (ことりっぷ)[カフェ・スイーツ,まちグルメ,ことりっぷ]
-

- ウィルミナのBBファンデーションがパワーアップしてリニューアル!
- カバー力をアップし、より使いやすく株式会社ウィルミナの「ベルシーオ BBファンデーション プロテクトUV…
- (美容最新ニュース)[自然化粧品]
-

- 横浜のベイエリアで身体の内側からきれいになる♪資生堂こだわりの薬膳でリトリート「Shiseido Kitchen Lab」
- 資生堂がプロデュースする「Shiseido Beauty Park(シセイドウ ビューティー パーク)」は、美しさを科学…
- (ことりっぷ)[お茶]
-

- VIRCHE銘品オイルに大人の“ゆるみ”にアプローチする「マルラブレンドオイル クリア」誕生
- 「マルラオイル」にハリケアの新商品が仲間入りエイジングケアブランド「VIRCHE(ヴァーチェ)」を代表す…
- (美容最新ニュース)[健康食材]
-

- 今日5月4日(日)の天気予報 北日本や沖縄で雨 関東も急な雷雨に注意
- 2025/05/04 05:50 ウェザーニュース【 天気のポイント 】・北日本は断続的に雨 雷も注意・関東は晴れても…
- (ウェザーニューズ)[観光]
-

- 船橋大神宮近くにイタリアン「レ オルメ」 DIC川村美術館から移転
- イタリアンレストラン「Le Orme(レ オルメ)」(船橋市宮本1)が5月8日、船橋大神宮近くの本町通り沿いに…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術,野菜]
-

- 【カシオ】ワールドタイム&オートLEDライト搭載!普段使いもアウトドアも活躍するG-SHOCK腕時計がAmazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[旅]
-

- オイル漬けやポップコーンが話題。“注目度No.1”台湾フードコーディネーターが手がけるモダンな食品雑貨店
- 国内外の美食家に注目される「Neighbour by LOUU」豊かな感性でネオ台湾フードを作り出しているスロー・チ…
- (CREA WEB)[里山里海]
-

- コンビニおにぎり、カップラーメン。外国人にも便利な仕掛けに北欧女子が感動!
- カップラーメンのフタを閉じておけない / (C)オーサ・イェークストロム/KADOKAWA子ども時代に日本のア…
- (レタスクラブニュース)[田舎暮らし]
-

- 彦根・滋賀大講堂で戦禍のウクライナの女性たちを描いた映画の上映会
- ウクライナ戦争で犠牲になっているウクライナの5人の女性たちを描いた映画「PEOPLE」の上映会が5月17日、…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[滋賀県]
-

- 負けっぱなしで退場なんてできない。夫の浮気を目撃した妻の激昂/闘う翼に乾杯を。(4)
- 夫の浮気現場を目撃して… / (C)東洋トタン/KADOKAWA「生きたい」と願うことの何が悪い。DV夫からの脱出…
- (レタスクラブニュース)[新商品]
キーワードからさがす
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.