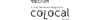築120年の京町家の建築様式を、現代風に解釈した住宅リノベーション
京都を中心に関西で建築設計をしながら、紀伊半島の熊野エリアでも地域に関わる活動をする多田正治(ただ まさはる)さんの連載です。
今回は築120年以上の歴史がある京町家の住宅リノベーションについてお届けします。
町家を引き継ぐ京都市の主要な東西の通りのひとつ、丸太町通りから少し北に上がったところにある町家。この建物をリノベーションしたのが、今回ご紹介する〈丸太町の町家〉です。
建築主はぼくの古くからの友人。彼のお祖父さんの住まいだったこの町家を引き継ぎ、夫婦と小さなお子さんの3人で住むにあたり、現代的な住まいを提案してほしいという依頼が2014年にありました。

工事前の様子。ファサードの青い瓦が特徴。
築120年以上の歴史をもつ町家。道路に面して母屋があり奥に庭があるという一般的な京町家の構成です。間口約6メートルに対して奥行が35メートルほどあり、極端に奥深く敷地の半分以上は庭でした。
この町家の履歴を調べるために、彼のお父さんにヒアリングをしました。お父さんが子どもの頃に住んでいた家でもあるからです。
明治時代から建っていたこと、昔は奥に長屋があって複数の家族が住んでいたこと、隣との間に昔は路地があってその長屋へとアクセスできていたことなど、町家とその周りの環境の変遷がわかってきました。
また、お祖父さんは食品関係の仕事で道路に面した部分をビジネスに使っていたこと、2階に使用人が住んでいたこと、またお祖母さんが庭の奥に茶室を建てたり、庭や座敷に名物を並べたりと、趣向を凝らした道楽をされていたこともわかりました。

敷地の奥にある庭(工事前)。お祖母さんの趣味の気配が残りながら、木々や草花が野生化していた。
それから時を経て、昭和50年代に1階の道路に面した部分を大きく改装しました。一部減築をして駐車スペースを設け、外装をタイル張りにし、室内には応接間をつくりました。
そんな一家の歴史と町家の歴史を知ったうえで、設計プランを提案していきました。次第に彼ら自身もどのような家に住んでいくのかイメージが固まっていったようです。
突然のチェコさあ、方針も決まり本格的に設計を進めて行こう! というところで、彼から連絡が入ります。
「仕事の関係で、2年ぐらいチェコに家族で移住することになった」
チェコ!?突然の話に動揺しつつも、彼が望んで決めたことだったので、成功と無事を祈り、送り出しました。
家のプロジェクトは凍結です。結局、彼のチェコ移住は4年に及び、帰国したのは2018年。その間に僕も彼らを訪ねてチェコに遊びに行きました。
チェコの首都は芸術の都プラハ。1992年まで共産国家だったため資本主義による急激な開発を免れており、いまも中世のまち並みがしっかりと残っています。

2017年のクリスマス前のプラハの様子。

チェコといえば、アドルフ・ロースやミース・ファン・デル・ローエといった歴史的な巨匠建築家の作品がある国。こちらはミースの名作住宅「トゥーゲンハット邸」。
帰国して約1年後に彼は言います。「あの家のリノベーション計画を再開したい」
長期間にわたって凍結していたプロジェクトが再始動することは稀なので、再オファーはとてもうれしかったことを覚えています。
この4年間にいくつかの町家リノベーションを手がけたので、経験値やノウハウもしっかりと蓄えました。こうして数年前の計画案を引っ張り出し、もう一度新しく設計をやり直すことになりました。
京町家特有の「火袋」を復元する今回の改修のキーワードとなったのが、「火袋」と「通り土間」。度重なる改築で失われていた、火袋や通り土間といった京町家特有の構成を復元することを意識しつつ、空間のなかにキッチンや子ども室、書斎スペースなどの機能が点在するように設計していきました。
火袋とは、炊事などで発生する煙や湯気を高く広い空間に逃がすための空間で、京町家特有の建築様式です。
既存のキッチンは1階にあり、その真上(2階)には床があり納戸となっていました。ところが、インタビューでの話や町家の一般的な形式から推測すると、かつてのキッチンには火袋があり、吹き抜けになっていたはず。
それをカタチや形式は違えど、復活させることにしました。解体工事後に躯体の状態をみると、キッチンの上部は増床していたことがあらためて確認できました。

既存図面。玄関から続く「通り土間」、その上の床を撤去して「火袋」として復活させる。

解体後の写真。床の一部を解体してかつての火袋が姿をあらわした。
キッチンを備える「通り土間」続いて、通り土間。通り土間とは、玄関から土足のまま入ることができる廊下状の土間のこと。京都の町家の多くは奥に深いつくりで、玄関を入ると真っ直ぐ奥まで空間が続き、そこにだいたいキッチンがあります。
今回の物件では、これまでの度重なる改修によって、通り土間の場所に床が張ってあり、システムキッチンがしつらえてありました。ところが、かつては土間が奥まで続き、そこにカマドや井戸があり、カマドの煙を出すために吹き抜けていて(火袋)、屋根の一部に煙出しの窓がついていたのです。
通り土間も、現代風に解釈しながら復活させることにしました。

既存図面。1階の玄関から厨房にかけてが通り土間。

工事前のキッチンの写真。かつての通り土間の場所には床が張ってありました。規模の大きな町家なので通り土間の幅も広いです。

この空間は町家の奥へと続いていきます。
「通り土間」によって家の表から裏を一直線に通る動線ができ、「火袋」によって光や音、匂いなどが上下階でゆるやかに共有されます。
さらに、空間のなかにキッチンや子ども室、書斎スペースなどをつくり、それらを機能ごとに独立したまとまりとして“機能のボリューム”と考えます。
たとえば、こちらはキッチンのボリューム。完全な個室とはせず、一部がくり抜かれた白いキューブにキッチンを収めました。

リビングにあるキッチンのボリューム。
こうしたボリュームの残余部分が、家族のスペースとなります。
大きさも高さも異なるボリューム群、そして火袋や通り土間、既存の柱梁や壁面、床のつくりだす隙間や抜けを生かして、家全体をゆるやかにつなげていくことを目指しました。

完成後の断面図。大空間に“機能のボリューム”が点在しています。

改修後の図面。町家の構成を意識しながら、新しい住まいへとリノベーションした。
看板町家のファサードについて考えるこの建築はファサードが改修された、いわゆる「看板町家」です。(看板町家については多田正治アトリエvol.7でも紹介しています)
ご両親へのインタビューとこの近辺に残る古い町家から、この建築がかつてどんな姿をしていたか想像できます。
こちらが工事前の写真です。

上の方の奥の壁も同じタイル。ちなみにお隣も同じタイルが使われています。
タイルが張られていますが、よく見ると上階のタイルと下階のタイルが異なります。上のタイルは古い時代のもので、下のタイルは比較的新しいものです。今回は、古い部分を尊重して、新しい部分にのみ手を入れることにしました。
屋根を葺き替える既存の屋根には青い「釉薬瓦(ゆうやくがわら)」が用いられていましたが、痛んでいたのでほぼ全面を葺き替えることに。町の通りから見えるところはそのまま釉薬瓦に、それ以降の見えないところはすべて金属屋根に葺き替えました。
重い瓦屋根を軽い金属屋根にすることで、耐震性能のアップも期待できます。

葺き替え途中。瓦と土を撤去していくと空が見えてしまいました。

葺き替え途中。この木の軸組は、建築のための下地ではなくて天井の工事をするための足場。大きな町家で屋根が非常に高く、専用の足場を組む必要があったのです。
大きな町家で、奥に深く大きな敷地ゆえの問題などもありながら、なんとか工事を完了することができました。
「火袋」と「通り土間」の現代的な解釈開放的に空間がつながる家こうして〈丸太町の町家〉が完成しました。
ファサードは、新しい部分を漆喰で白く仕上げ、それ以外の部分は既存をそのまま生かしたデザインにしました。青い釉薬瓦も見た目は昔のままです。

ファサードの写真。タイルは昔のまま。下の部分だけ漆喰で白い抽象的な空間にしています。

道路側の1階の洋間は、畳敷きの和室に。仏壇を置いて、法事やお彼岸、お盆行事に対応します。
1階にある田の字型プランの居室は、大きくリビング・ダイニング・キッチンとしました。既存の力強い梁が剥き出しになっています。

かつての座敷2間分のリビング・ダイニング。奥の庭まで見通せるのは昔のままです。

キッチンのボリュームの中には、収納や機器類などが収まっている。
キッチンの裏側が、空間的に復元された通り土間と火袋になります。昔の通り土間と火袋は壁に囲まれた奥に・垂直にのびる空間でしたが、今回は現代的に解釈し、開放的な空間となりました。

2階。右側にある吹き抜けがかつての火袋で、玄関やキッチンとつながっている。

かつて通り土間だった空間。壁で区切らず、リビングやキッチンとつながる開放的な通り土間として再現。上階の気配などが下にも伝わってくる。
庭は小さく区切って手前をきれいに設えています。奥は家庭菜園やキャンプなど、自由に使える場所としました。

リビングから見た庭。お祖母さんがしつらえた灯籠やお社はそのままに、それ以外の石を組み替えて新しいお庭にしました。
2階には子ども室があります。子ども室の床は、600ミリメートルだけ高く設定しました。床を少し持ち上げることで、1階〜2階で視線の行き来が増えます。

床が600ミリ持ち上がった子ども室。足元の淡い緑色は、この部屋の主であるお子さんと一緒に選びました。

子ども室の床下を通して下階とつながる。
子ども室の周り三方は、すべて建具にしました。閉じて完全個室をつくることもできますが、全開にして、ほかと一体的に使うこともできます。

子ども室の前のスペースはスタディスペース。
このようにして友人家族の住まいが完成しました。
2014年に設計を依頼されて、竣工したのは2021年。実に7年もの歳月をかけてひとつの建築にたずさわったのは、初めてのことでした。
その7年に加えて、120年以上にわたり彼と曾祖父母の4世代によって脈々と住み継がれてきた町家。今回はそれを現代的にリノベーションしましたが、その背後にある家族の歩みに思いを馳せながら、町家の構成や形式なども重要視して設計を行いました。
小学校就学前だったお子さんは、もうすぐ中学生になります。この〈丸太町の町家〉が家族の成長とともにあってほしいと思います。
writer profile
Masaharu Tada
多田正治
ただ・まさはる●1976年京都生まれ。建築家。〈多田正治アトリエ〉主宰。大阪大学大学院修了後、〈坂本昭・設計工房CASA〉を経て、多田正治アトリエ設立。デザイン事務所〈ENDOSHOJIRO DESIGN〉とシェアするアトリエを京都に構えている。建築、展覧会、家具、書籍、グラフィックなど幅広く手がけ、ENDO SHOJIRO DESIGNと共同でのプロジェクトも行う。2014年から熊野に通い、活動のフィールドを広げ、分野、エリア、共同者を問わず横断的に活動を行っている。2024年より武庫川女子大学生活環境学科准教授。主な受賞歴に京都建築賞奨励賞(2017)など。
credit
編集:中島彩
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 週間天気予報 GW4連休は天気の移り変わり早い 最終日は広範囲で雨
- 2025/05/02 05:28 ウェザーニュース 【 この先のポイント 】・4連休前半は北日本や北陸を中心に雨・GW最終…
- (ウェザーニューズ)[キャンプ]
-

- スヌーピーデザインのレトロモダンなテーブルウェアを「PEANUTS Cafe」で手に入れよう
- 「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」のグッズコーナーに、1960年代のムードを漂わせるマグカップとガラス…
- (Walkerplus)[芸術]
-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ
- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 竜王のアウトレットパークで「パンマルシェ」 全国のパン店が出店
- 全国のパン店が出店するイベント「パンマルシェ」が5月3日~5日、三井アウトレットパーク滋賀竜王(竜王町…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[京都府]
-

- 名匠ジョン・ウー監督の最新作「サイレントナイト」を鑑賞。全編セリフなしの壮絶な復讐劇にハラハラドキドキが止まらない!
- 2025年4月11日より全国公開された「サイレントナイト」。「男たちの挽歌」(1986年)や「フェイス/オフ」(1…
- (Walkerplus)[クリスマス]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.