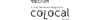シェアキッチンやカフェを備えた“団地キッチン”とは? 管理会社による食プロジェクト
この連載は、日本デザイン振興会でグッドデザイン賞などの事業や地域デザイン支援などを手がける矢島進二が、全国各地で蠢き始めた「準公共」といえるプロジェクトの現場を訪ね、その当事者へのインタビューを通して、準公共がどのようにデザインされたかを探り、まだ曖昧模糊とした準公共の輪郭を徐々に描く企画。
第5回は、2023年度グッドデザインを受賞した、埼玉県のJR西浦和駅前にあるコミュニティ型複合施設〈「団地キッチン」田島〉を訪ねた。
お話を聞いたのは、「“食”や“本”を通じたコミュニティ拠点の運営」でもグッドデザイン・ベスト100を受賞した〈日本総合住生活(JS)〉の住生活事業計画部の中野瑞子さんと、上野雅佐和さんのおふたり。
「団地キッチン」田島は、コミュニティ形成を目的として、銀行の支店跡地を、カフェ・シェアキッチン・ブルワリーに改装し、2022年8月にできた複合施設だ。テーマを「食」に絞ることで、多様な属性を持つ市民の日常生活の延長線上にありながら、サードプレイス的な場に育っている。
団地の存在価値が変わらざるを得ない状況のなか、その先行的な取り組みを通じて、今後、団地及び地域社会に求められる「準公共」の役割を探る。

〈「団地キッチン」田島〉は、JR西浦和改札から徒歩2分、田島団地の入口に位置する。(写真提供:JS)
食のプロジェクトを田島団地からスタートした理由矢島進二(以下、矢島): ここは、JR西浦和駅の近くの「さいたま市桜区」ですが、なぜ食のプロジェクトをこの田島団地からスタートしたのですか?
中野瑞子(以下、中野): まずは立地です。団地は駅に近いものは少なく、バスを使うところが多いのです。飲食系の施設は、やはり駅から近くないと不利ですので。
そして、西浦和駅周辺のまちづくりに関する基本合意を市とUR都市機構が結んでいることと、UR田島団地にて団地再生事業が進められていること、さらにURグループである当社の技術研究所が近くにあることもここに決まった要因です。
「浦和」の名がつく駅は全部で8つあるのですが、ほかと比べ西浦和駅周辺は特徴があまりないといわれているなか、“食”に着目すれば、魅力を出せると考えました。食には地域の歴史が反映されるので、食材や料理の仕方なども地域の魅力を伝える機会になると、コンセプトをまとめていくなかで見えてきました。
ここのステートメントは「いえの味をまちの味へ」です。家の中で閉じられていたものをまちに開き、自分たちで育て、結果まち自体を育てていくことを目指しています。

〈日本総合住生活〉住生活事業計画部の中野瑞子さん。建築系の出身で、都市計画やまちづくり、農村計画を学び、学び直しをした際はコミュニティを研究した。
矢島: それで“住”の専門組織であるJSが、“食”にチャレンジしたのですね。
上野雅佐和(以下、上野): はい。まずは誰もが気軽に立ち寄れるカフェを2022年8月末にオープンしました。次はつくり手にフォーカスしたかったので、はやり始めてきたシェアキッチンを検討しました。
シェアキッチンは、ルールづくりがかなり大変で、厳密にしすぎてしまうとコミュニティ拠点としては機能しないという悩みを抱えながら、年明けの2023年にオープンしました。正直、いまでも運用は試行錯誤の連続です。
さらに、自分たち自らがつくり、ここから発信する機能も必要だと考え、ブルワリー(地ビール醸造所)も加えました。こうして、シェアキッチン・カフェ・ブルワリーの3機能を融合したユニークな施設「団地キッチン」田島ができました。

上野雅佐和さん。サブゼネコンを経てJSに。「最初の仕事がキッチンカーの設計で驚きましたが、まさか私がビールをつくることになるとは、夢にも思いませんでした」と笑う。
初めてのシェアキッチンとお酒づくり矢島: シェアキッチンやお酒づくりは、過去にJSとして手がけたことがあったのですか?
上野: いくつかの団地内でコンビニを自主運営しているので、酒類販売業免許は持っていますが、お酒づくりもシェアキッチンも初めてのことです。ビールを醸造するには、酒類製造免許もとらないといけないので、当社の定款を変更しました。
矢島: なんと、定款を変えたのですか! 定款は会社の憲法みたいなものですから、それは一大事だったのかと。そこまでして、社としても実現したかったプロジェクトなのですね。次に、空間の特徴を教えてください。
上野: 銀行の支店だった建物ですので、天井が高く、柱が少ないので、とても明るく広く開放的な空間になりました。開放的ではありますが、用途にあわせて各エリアを緩やかに仕切れるのが特徴です。誰でも気軽に使っていただき、この場所の気持ち良さを口コミで発信してほしいと思っています。
一番大きなイベント用キッチンは、内部を少し高くしてステージのようにしています。最初は恥ずかしい、という声もありましたが、もう風景として馴染んできたので、気持ちよく使っていただいています。

銀行が閉鎖となり、ATMだけを残して空き店舗となっていた築50年になる建物を、JSが2020年に買い取り改装した。カフェでは一汁三菜の定食や、ハンドドリップしたコーヒー、クラフトビールが楽しめ、平日も周辺から訪れる客が絶えない。
矢島: カフェはキッチン側に向かって座り、料理する様子を見ながらごはんを食べる人が多そうですね。キッチンは、サイズが違うものが3つあるのですね。
上野: はい。一番大きなイベント用キッチンは、ホームパーティーや料理教室など、コミュニティの核になる空間です。ほかに菓子製造許可に対応したキッチンでは、焼き菓子やパンなど、さらに惣菜製造許可に対応したキッチンもあります。どちらも営業行為が可能なキッチンですので、屋号を持ち、ここで調理から包装までして、ネット販売やお店に卸すことができます。
矢島: この場所で保健所の許可をとっているので、製造元になれるのですね。

最大20名まで利用できるメインのキッチン。気軽に使ってもらうため、このキッチンを使用するための入会金は1100円、利用料は1時間2750円とリーズナブルな価格設定。
約90万戸を管理する住まいのインフラ企業矢島: そもそも、日本総合住生活とはどんな組織で、何をしている会社なのですか?
中野: 昭和30年代の深刻な住宅不足を解消することを目的に発足したのが、日本住宅公団(現〈都市再生機構 UR〉)です。ダイニングキッチン(DK)という概念をはじめ、洋式トイレやステンレス製流し台など、さまざまな近代的な住まいの様式を日本に導入する契機となったのが、団地です。
その団地の入居後のアフターサービスをする会社として設立されたのが、〈団地サービス〉で、現在の日本総合住生活(JS)になります。ですので、当社も「国の住宅政策に寄与する」という目的で設立されたので、一般的な民間企業とは成り立ちやミッションが少し異なります。株式会社という形態ではありますが、パブリック性の高い事業体として設立されたのです。
現在は、URが供給した賃貸住宅と分譲マンション、合わせて全国で約90万戸を管理しています。

隣の田島団地は1965年に54棟、戸数1906戸(現在は約1800戸)で完成。建て替え前の草加松原団地(約6000戸)、千葉の海浜ニュータウンの団地(約4000戸)と比べると、標準的な規模の団地。高齢化が進み、入居者の半数以上が65歳以上だという。
矢島: 約90万戸というと想像がつかない大きなスケールです。日本の住まいのインフラを築いている存在といえそうですね。JSはどんな事業を具体的にやっているのですか?
中野: メインは賃貸住宅と分譲マンションの管理で、緊急事故の受付など、居住者のサポートと、入退去に伴う空き家の補修工事などを行っています。
URは、「地域福祉医療拠点化(ミクストコミュニティ)」という表現ですが、多様な世代が生き生きと住み続けられる団地を目指します、というビジョンを掲げています。当社はその実装の一翼を担うために「コミュニティ形成支援」など、従来の管理会社の枠にとらわれない新しい事業を展開し、私たちが所属する事業計画課は、その部門にあります。
ここの運営を含め、地域のまちづくりに寄与することや、コミュニティ再生に役立つことを、私たちはリアルな場面で試行錯誤しています。
団地は日本社会の縮図矢島: 現在の団地における最大の課題は何ですか?
中野: 国の政策によって、昭和40〜50年代に団地が大量に建設されました。当時からお住まいの方々に長く住んでいただいているがゆえに、高齢化が進んでいるのが大きな課題です。また、コミュニティの希薄化も一般の地域より顕著で、喫緊の課題と捉えています。
日本は高齢化がさらに進んでいきますが、団地は一歩先にいっているので、団地の未来を考えることは、10年先、20年先の日本のコミュニティのあり方、まちのあり方を考えることに近しいと思っています。
団地は非常に広く、数千戸単位の住居があり、敷地内に商店街や小学校、公共施設などもあり、ひとつの“まち”だと捉えています。つまり、いまの団地の現状は“高齢化したまち”そのものなのです。こうしたことが、建物の老朽化と併せて「団地は日本社会の縮図」と言われるゆえんです。

写真提供:JS
矢島: 一般の賃貸住宅は、住民の入れ替わりがあり新陳代謝が進みますが、団地は異なるのですね。
中野: この田島団地は、基本台帳で調べると、65歳以上が半数以上になっています。そうなると若い世代は関心を持ちづらくなってしまいます。そうしたなかで、新たな居住者層を呼び込んで混じりあい、活動に広がりを持たせることが、団地エリアのコミュニティ再生に不可欠と考えています。
シェアキッチンで小商いをスタート矢島: こちらを製造元として、“小商い”をしている方は何人くらいいて、どのような活動をしているのですか?
上野: 7人の会員は、ここで小商いを1年以上続けていますね。
中野: 今日パンをつくっている会員は、とある駅の駅長から声がかかり、「えきパン」という大きなイベントに出店されます。1年以上継続していると、いろいろなところから声がかかり、商いも大きくなっています。当初、そういう人が出たらいいなと思っていましたが、実際に少しずつ生まれてきています。

この翌日開催するマルシェで販売するパンをつくる会員の方。このキッチンの月額会員定員は5名。現在は時間貸し会員もいっぱいで、空き待ちの状態。
上野: 最近は自分でシェアキッチンをやりたいという方からの問い合わせや、視察が増えています。
中野: 働き方も変わってきて、副業をライトに始める動きがたくさん出てきました。シェアキッチンなら設備投資がいらず、小さな商いをすぐにスタートできるので注目されています。

「食品の製造販売は許可を得た場所でつくる必要があります。自宅で勝手にというわけにはいきません。シェアキッチンで自分の屋号を登録することによって、自分のお店の名前で販売することができます」と中野さん。
上野: いまは地域色あふれるクラフトビールがとても人気なので、住民を巻き込んで“田島団地ビール”をつくる計画もあります。またここ、さいたま市桜区はシンボルフラワーがサクラソウなので、サクラソウに関連する地ビールをつくる話も、まちづくり協議会と進めています。
矢島: いろいろなチャレンジができる場は重要ですね。やはり食をテーマにすると広がりますね。
中野: 食にこんなにパワーと可能性があるとは思っていませんでした。この1年半で実感しています。

少量生産だからこそ可能なマイクロブルワリーの特徴を生かしたクラフトビール。カフェで味わうことができる。
マルシェの効果と広がり矢島: 隣の駐車場で毎月マルシェを開いているのですよね。
上野: 何か、にぎわいになるものが必要だと考え、毎月第4土曜日にマルシェを開いています。多くは県内の農家さんが新鮮な野菜や果物などを売っています。キッチンカーが出ることもありますよ。
矢島: シェアキッチンの会員もここでつくったお菓子や惣菜を販売できるのですね。
上野: そうです。徐々にそういう機会が増え、販路がどんどん広がっていくので、会員になって本当に良かったという声をいただきます。マルシェの日は、ここのキッチンではワークショップを行い、この場所をPRしています。

店舗敷地内の駐車スペースを使い、毎月第4土曜日にマルシェを開催。県内の農家による採れたての野菜や果物が人気。(写真提供:JS)
中野: ワークショップの講師も、埼玉県内の方にメインで来ていただいています。4月は和菓子職人さんによる柏餅づくりや、5月は狭山茶と茶揉み体験を行いました。
上野: さいたま市と連携してワークショップを開くこともあります。最初の1年間は自分たちで出店者を集めていましたが、最近は自ら出店したいという方が増え、いまでは調整しながらやっています。7月には、不登校の子どもたちが野菜などを育てている組織〈コドモ農業大学〉と連携して、そこで育てたお芋でつくったポテトチップスを販売する予定です。

ピザづくりの親子ワークショップ。「若い世代に団地の良さを気軽に知ってもらう手立てが必要で、こういう施設ができ、まちの雰囲気が変わっていく姿を近隣の方に見てもらうことがとても大事なのです」と中野さん。(写真提供:JS)
矢島: マルシェにはどんな効果がありますか?
中野: 参加者同士のコラボレーションが進んできました。出店者の農家さんから野菜を仕入れて惣菜をつくる会員や、あんこをつくる方とパンをつくる方が一緒になってあんバターパンを売ったりとか、自発的につながっていくのがとてもうれしいです。
コミュニティマネージャーの役割矢島: そうしたつなぎ役は、組織の中にいるのですか?
上野: はい。それが私たち、コミュニティマネージャーの役割です。
矢島: コミュニティマネージャーをJSの施設で設置したのはいつ頃からですか?
上野: 2021年からなので、まだ3年です。ほかの施設でコミュニティマネージャーをひとり常駐させたら、うまく回り始めました。デジタル化の推進など、人手がかからない方向に社会は動いていますが、それと真逆で、アナログ的に地域の人の声を直接聞いてイベントをやっていたら、参加者がどんどん増えていき、場も活性化したのです。
中野: “顔の見える関係”をつくることで成果も生まれるので、当社のコミティマネージャーは、いまでは4人に増えました。コミュニティマネージャーとともに私は会員同士の交流会や勉強会などを企画し、地域の住民同士が知り合う機会を緩やかにつくっています。

「昨年、アンケートで『田島団地でお気に入りの場所はどこ?』と聞いたら、団地キッチンを挙げる方が一番でした。『うちのまちには、こんないいところがあるのよ』と団地の住人に認めていただけているのが、とてもうれしかったです」と中野さん。
上野: そういう結びつきがおもしろいですね。先日は、会員3者共同の試食会があったのですが、自主的に会員同士が企画していました。
矢島: おふたりはこの場をそういう場にしたかったのですよね。単なるシェアキッチンでなく、交流が生まれる場に。そうしたことがコミュニティをつくるということなのですね。コミュニティマネージャーとして活動して、自分自身が変化したことはありますか?
上野: コミュニティマネージャーとして外部と接していると、仕事の関係者ではあるけど、どちらかというと友人に近いような感覚に不思議となるのです。また、それまでのかっちりした仕事と違って、仕事のなかに“柔軟さ”が出てきたように思います。

「実は私はまちづくりの活動には参加しないタイプでした。自分の住んでいるまちに愛着心も特になくて。ですが、子どもができると、地域密着の活動はとても大事だと思うように変化しました」と上野さん。
コミュニティと団地の未来矢島: 中野さんが考えるコミュニティはどういうもので、どう捉えていますか?
中野: コミュニティを直訳すると「共同体」で、“つながり”がとても重要だと感じています。豊かな暮らしを送るには、他者とのつながりが必要です。深く知り合うとかではなく、顔見知りでいいので、関係性があることがコミュニティかなと思います。
「ワークライフバランス」と言われますが、仕事も生活も大事ですが、そこにコミュニティがないと、生きていくためのバランスがとれないと思うのです。当社としては、拠点を開き、人が集まり、そこでつながりができ、さらにまちに広がっていくのがコミュニティだと考えています。

会員同士が自然と交流し、情報交換から共同で商品開発を始めることもある。
矢島: JSは「団地が新しい故郷となる地域コミュニティづくり」と謳っていますが、どのような意図でしょうか?
中野: 団地には若い世代にも住んでいただきたいのですが、いきなり「住む」のは難しいと思っています。ですので、まずは若い人が関わりたいと思う“活動場所”や“居場所”を先につくっていきます。それが私たちの使命だと思っています。
将来的には、団地を自分たちのホームベースと捉えてほしいのです。そうした“帰っていく場所”に団地がなれれば、従来とは概念が違う“故郷”と言えるかと思っています。
矢島: そうした意味でも、やはり食はキーになるわけですね。
中野: 郊外の団地の特徴として、都市農地が近くにあることが多いのです。私自身もそうでしたが、地域の食を知ることは、地域の歴史や地理、生産物や名物、ひいてはつくり手となる“人”など、地域の特性や魅力を知ることにつながることに気づきました。その魅力を知るきっかけづくり、地域への愛着、いわゆるシビックプライド醸成を、マルシェやワークショップで目指しています。
矢島: ビールで「乾杯!」という行為だけで、関係性は変わりますからね(笑)。定款を変えてまで実現させたのは正解でしたね。

矢島: 今後の団地はどうなっていくべきだと思っていますか?
上野: 私は、団地がもっとオープンに、みんなが緩やかに出入りできる場に変わると、おもしろい状態になってくると思います。

カフェは30〜40代の利用者が多いが、子連れでも訪れやすい空間のため、特に休日は小さい子どもを連れたファミリーでの利用が多いという。
矢島: それこそ、このシェアキッチンが認識を変える契機になるかもしれませんね。ところで、団地の敷地内には広場がいくつもありますが、誰でも使っていいのですか?
中野: URの団地は、普通の分譲マンションと違って、敷地に入るのは禁止していません。
団地というと羊羹型の建物がずらっと並び、見えないバリアがあるようで入りにくいかもしれませんが、実は敷地内に誰でも入っていいんです。共用の広場が多くあり、豊かな緑に囲まれているのが団地の大きな魅力で、この恵まれた環境を、住人だけでなく近隣の方々ともシェアできると、地域の魅力資源になるように思います。当然、住人の権利もあるので、騒音などについてのルールは必要ですが。
矢島: そうした意味でも、団地キッチンは意義がありますね。
中野: そうなのです。誰でも自由に楽しそうにしている姿を目にすると、認識は変わりますね。そうした契機に団地キッチンがなっていくとうれしく思います。

矢島: 最後に「準公共」という概念に関して、おふたりはどんな印象を持っていますか?
中野: 準公共という言葉は、今回初めて聞いたのですが、私がずっと考えてきたテーマに近いように感じました。“公(パブリック)”と“私(プライベート)”の間に“共(コモン)”という概念がありますが、“共”を大事にする価値観が日本の文化だと思うのです。
団地は特に共用空間、共用部など、開いている場がとても多いのですが、完全に公共の場ではないので、「準公共」と言えるはずです。そして共用空間の魅力が、その団地全体の魅力、愛着醸成に通じると思っているので、これからは準公共という視点でも、考えを深めていきたいと思います。
上野: 私も準公共に近い仕事をしたいと思ってこの仕事に就きました。意義があり、社会貢献もできる仕事に。
分譲住宅の改修などをやってきたので、“私”の側、資本主義のほうに傾倒していくと、みんな自己利益のみの選択肢を選んでしまうことを経験上、知っています。そうしたことを考え直すきっかけに、準公共がなるのではと思いました。

本来、団地自体は、“公”でもあり“私”でもある領域に属するものだったはずではないのか。さらに、中野さんが強調された、数多い共用空間が生みだす曖昧な“共”(=コモン)がマンションとの違いであり、団地の魅力のはずだ。
しかし、高度経済成長期に個人主義が進み、その曖昧な空間を使いこなすリテラシーを私たちは忘れてしまったのかもしれない。日本の住宅から縁側を排除してしまったのと同じように。
そうした意味で、地域に開いている「団地キッチン」田島は、まさに準公共と呼べるデザインであり、団地のイメージを変える可能性を感じる。
JSは、何と言っても全国で90万戸を管理しているので、この大規模なインフラを活用することで、団地に限らず社会の価値観を変えることができるかもしれない。昭和の時代に、私たちの生活様式を一変させたように。

写真提供:JS
information
「団地キッチン」田島
住所:埼玉県さいたま市桜区田島6-1-20
TEL:048-767-6404
カフェ営業時間:11:00〜20:00(ランチ13:45L.O.、カフェ19:00L.O.)
定休日:水・日曜、年末年始
「団地キッチン」田島
writer profile
Shinji Yajima
矢島進二
公益財団法人日本デザイン振興会常務理事。1962年東京生まれ。1991年に現職の財団に転職。グッドデザイン賞をはじめ、東京ミッドタウン・デザインハブ、地域デザイン支援など多数のデザインプロモーション業務を担当。マガジンハウスこここで福祉とデザインを、月刊誌『事業構想』で地域デザインやビジネスデザインをテーマに連載。「経営とデザイン」「地域とデザイン」などのテーマで講演やセミナーを各地で行う。日本デザイン振興会
credit
撮影:加藤甫
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[スローライフ]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ,果物,東京都]
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品,ESG]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材,イベント,地域の魅力]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒,野菜,ビール]
-

- 葉山・木古庭の「はやま里山ファーム」で「自然菜園」体験 ゲスト講師招き
- 「はやま里山ファーム」(葉山町木古庭)が4月27日、講演会&体験会「葉山の里山で自然菜園を体験しよう」…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[農業]
-

- 「祝英台が高校生に?」「青髭がラスボス化?」 神話×漫画の化学反応に読み手もびっくり!古典のぶっ飛びアレンジがクセになる【作者に聞く】
- 1700年前の中国がまるで現代の高校のよう!少女漫画テイストで昔話をアレンジゴールデンウィークのおうち…
- (Walkerplus)[花]
-

- 弘前で「森カリオペ」のリキュール販売延長 弘前城の缶バッジを同梱
- 津軽藩ねぷた村(弘前市亀甲町)で期間限定商品だったバーチャルアーティスト「森カリオペ」のリキュール…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[花見]
-

- 豊田ルナ、「温泉旅行」をテーマにぬくもり感じるグラビア披露
- 豊田ルナが、4月28日(月)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)の「グラビアン魂」に初登場した。 豊田ルナ「週…
- (GetNavi web)[埼玉県]
-

- 「夫との旅行はムリ!」“店構えでおいしいか分かる”と言い張る夫と2時間歩いた後の悲劇
- ゴールデンウイークを控え、旅行の計画を立てている人も多いだろう。だが、中には日常生活では問題がなく…
- (All About)[まちグルメ,コンビニ]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.