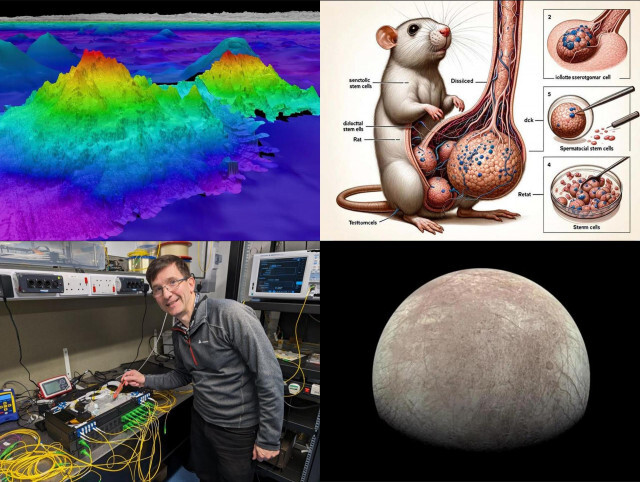この連載は、日本デザイン振興会でグッドデザイン賞などの事業や地域デザイン支援などを手がける矢島進二が、全国各地で蠢き始めた「準公共」といえるプロジェクトの現場を訪ね、その当事者へのインタビューを通して、準公共がどのようにデザインされたかを探り、まだ曖昧模糊とした準公共の輪郭を徐々に描く企画。
第4回は、2023年度グッドデザイン・ベスト100を受賞した、豊島区のベッドタウン東長崎の駅前にあるコーヒー店〈MIA MIA(マイアマイア)〉を訪ね、オーナーのアリソン理恵さんとヴォーンさんのおふたりに話を聞いた。
デザインといっても、スタイリッシュで斬新なインテリアのカフェでもなく、流行りのコワーキングスペースでもなく、いわゆるサードプレイスでもない、不思議な佇まいの小さなまちのコーヒー店だ。
オープンしてちょうど4年となるが、懐かしくて居心地が良く、世界中から集まる多くのお客さんでいつもにぎわう、まちのコモニング拠点に育っている。
行政による公民館ではないが、なぜかパブリック性と界隈性を感じるMIA MIAから、「準公共」の新たなスタイルと役割を探る。

矢島進二(以下、矢島): おふたりはどこで出会ったのですか?
アリソン理恵(以下、理恵): ヴォーンとは学生時代に半年インターンしたオーストラリアのメルボルンで出会いました。
ヴォーン: ライブハウスで会ってひと目惚れしたのです。
理恵: 帰国するときに、ヴォーンを連れて来ました。行きはひとり、帰りはふたりで(笑)。ヴォーンは日本に来て、英語の講師やモデル、音楽プロモーターなど、いまでもいろいろ好きなことをやっています。特にコーヒーが大好きで、コーヒーに関するブログを続けていました。
完全に趣味なのに、締め切りを決め、フォトグラファーに撮影してもらうとか、ロゴを毎月デザインするとか、日英2か国の記事を書き続けていたのです。そうしたら、コーヒーを紹介するメディアの立ち上げや、雑誌のコーディネーター、インタビュー、さらにカフェのアドバイスなど、趣味が徐々に仕事になってきました。
私は帰国後、設計事務所で働き、2015年に友人と共同で建築設計事務所〈teco〉を設立しました。福祉施設関連の設計を数多く手がけさせていただいたのですが、子育てしながらだったこともあり、2019年に過労で倒れてしまいました。
それでまず休むことにして、家族でメルボルンに帰りました。その際に、これからどう生きていくのかをふたりで話し合い、メルボルンにあるようなコーヒー屋を一緒に東京で始めたらどうかな? ということになったのです。
メルボルンの市民は、1日に何度もコーヒー屋に行き、コーヒー屋が情報とネットワークのハブになっています。ガイドブックやネットで検索するより、コーヒー屋で聞くのが一番いい情報が得られることを知り、「こういう場所が日本にあるといいよね」と話して、物件を探し始めました。

一級建築士事務所〈ara〉のアリソン理恵さんと、モデル活動や音楽プロモーターなど多彩な活動をしているヴォーンさん。現在ふたりは全国のファミリーマートで展開されている「コンビニエンスウェア」のモデルでもある。
矢島: どのようにしてこの物件と出合ったのですか?
理恵: 偶然、魅力的な賃貸物件だけを集めた不動産紹介サイト『DIYP』で見つけました。写真をみてカワイイと思い、すぐに東長崎に来てまちなかを歩いたら、すごくいいなと。都心でありながら人の営みが見えて、こんな便利な商店街が残っているのに驚きました。
ヴォーン: 東長崎はまったく知らないまちでしたが、ひと目惚れしました。なんかチャーミングで一瞬で気に入りました。
矢島: 大家さんはどんな方で、借りるにあたって条件はあったのですか。
理恵: 私たちと同世代で、ずっとこのエリアに住み続けている方です。自分の子どもが産まれ、昔と比べて元気がなくなったので、親としてこのまちを盛り上げたいと思っていらして、「地域を盛り上げてくれる人」と「面談して決める」が条件だったのです! 私たちも大家さんに会って決めたいと思っていたので、もうこれは運命だな、完璧だ、とふたりで声を上げました。

矢島: ヴォーンさんは、日本で1000店以上のコーヒー店を巡ったそうですが、見本となるお店はあったのですか?
ヴォーン: 日本には参考になる店が少ないですね。少ないというか、ないのです。
理恵: その理由は、おそらく日本では「ターゲット」や「マーケティング」という考え方が浸透しすぎているからだと思います。そうするとデザインも障壁になります。「◯◯風」にデザインしてしまうと、それ以外の人が入りにくくなりますし、マーケティングが先鋭化するあまり、排除される方も出てしまうのです。
メニューにしても、コーヒーに詳しくないとオーダーもしづらかったりする店がありますよね……。かと思えば、コミュニティが強すぎて、敷居が高く、入りにくいお店も多いです。
矢島: 昔の「喫茶店」の時代はどうだったのでしょうか。
ヴォーン: 昔の喫茶店は、すごくいいところがあったのですが、いまは個人の店はすごく少なくなって、みんなチェーン店に変わってしまいました。コンビニや自動販売機のようなコーヒー屋が多くなり、カルチャーを生むような店はありません。オーストラリアやヨーロッパは、個人経営で個性のある店が多数あって、それがまちのインフラになっています。
理恵: チェーン店と個人店の両方あったら、個人店にお金払いたい、というのがオーストラリア人の気質です。顔の見える人にお金を払うと、自分たちの周辺に回ってくるのが見えやすいけれど、チェーン店で払ったお金は、どこに行くかわかりませんよね。メルボルンでは、そうしたことに敏感な人が多いのです。

〈MIA MIA〉とは、オーストラリアの先住民の言葉で、家族や友人、通りがかった人などが集うシェルターとして建てられた小屋という意味。
全員80代の職人が集まり工事が始まる矢島: 改装するときに近所の工務店さんを探したと聞きましたが、すぐに見つかりましたか?
理恵: こんな小さな商店の改修なので、その費用はこの地域に落としたほうが絶対いいと思ったのです。ですので、近所の工務店さんに片っ端から電話をかけたんですが、どこからも断られてしまったのです。建売と比べて割に合わないので……。
そんななか、商売を始めるなら、まずはご近所に挨拶をしないとと思って、商店街の端から1軒ずつ挨拶をしながら、併せて「大工さんを知りませんか?」と聞いて回りました。そうしたら偶然、食堂にいたおばあちゃんが「知り合いにいるわよ」と言ってくれて、翌日連れてきてくれたのですが、それは大工さんではなく、カギ屋のおじいちゃんだったのです(笑)。
そのおじいちゃんが知り合いの大工さんを呼んでくれて、その大工さんが水道屋さんや電気屋さんも呼んでくれて……と、ひと通り全部つくれるチームができたのです! でも、なんと全員80代(笑)。誰もメールが使えないので、工事中は手紙で連絡をとり合っていました(笑)。
図面どおりにやってくれなくて困ったのですが、ふと思ったのです。この人たちは50年くらいここで暮らしているので、何でも知っているし、地縁も深い。なので、「あれ、何やってんの?」と言いながら、工事中にいろいろな人が勝手に入ってくるんです。お弁当の差し入れをしてくれる人が出てきたり。

お店の近くにあるこのスペースは、平日は理恵さんが設計事務所として使い、週末はギャラリーとなる〈I AM(アイアム)〉。住宅地に文化的な拠点があることで、みんながプロジェクトを起こしやすい環境にしたいと願い設計した。
矢島: 初めてのお店で、採算面の不安はなかったのですか?
理恵: この辺は若い人がいないから、コーヒー屋でなくスナックのほうがいいよ、とオープン前にはよく言われました。たしかに若い人は全然歩いていなくて、 やめたほうがいいのかと、毎晩ヴォーンと話していました。
収支計算をしたら、1日80杯コーヒーを売らないと採算がとれないのですが、毎日15人くらいしか人が通ってなかったんです。

矢島: 3か月の工事で、2020年の4月にオープンしたのですね。
ヴォーン: MIA MIAのコンセプトは、「ひとつの大きなテーブルにお客さんが座って『はじめまして』と挨拶をする。バリスタも会話をしながらコーヒーをつくる。子どももおじいちゃんやおばあちゃんも、オシャレな人もそうでない人も、みんな一緒にひとつのテーブルに座って同じ時間を過ごす」でした。
ところが、2月になったらコロナが始まり、4月にオープンした翌週が、なんと緊急事態宣言になってしまったのです。
矢島: まさにあのタイミングだったのですか!
ヴォーン: コンセプトが「最もしてはいけないこと」になってしまったのです。ソーシャルディスタンスの対極ですので。

ヴォーンさんはミュージシャン仲間もたくさんいるので、コンサートをやったり、ゲストバリスタを呼んだりと、イベントも数多く展開している。
理恵: さらに「人が集まる場所をつくるのは悪いこと」のような印象も出てきたので、本当に悩みました。
ですが、よく来てくれる70代のおじいちゃんに相談したら「自分の住んでるまちでおいしいコーヒーが飲めなくなったら、私たちは死んじゃうよ」と言われたんです。つまり「まちに必要な場なのだから、堂々と開けなさい」と。それを聞いて私たちは泣きました。
改装を手伝ってくれた人の親戚や、知り合いのそのまた知り合いのようなお客さんが立ち寄って、コーヒー代を払ってくれ、さらに野菜をタダでくれるという、摩訶不思議なビジネスモデルの日々でした(笑)。
でも以前から「モノをつくる瞬間を共有した強さ」は、理論上あるはずと思って建築をやってきたので、本当にあると実感しました。

「実家もお店をやっていたので、どこからがプライベートなのかわからない環境で育ちました。家族だけで食事したことがほとんどなく、いろいろな人と混じる生活のほうが落ち着きます」と理恵さん。
プロジェクトが生まれるきっかけの場矢島: MIA MIAは、コミュニティの場ではなく、プロジェクトが生まれるきっかけの場にしたいとお聞きしていますが、具体的にどういうことでしょう。
理恵: 私自身は、コミュニティはつくれないと思っています。ですが、人が溜まりやすい場所や、誰もいなくても立ち止まれる場所をつくっておけば、結果的にコミュニティになると考えています。コミュニティはつくろうとしてつくれるものではなく、モノや場を介在すれば自然と生まれると。
私たちは、お店に「2回来るきっかけ」をつくろうと意識しています。いまの日本では、写真を撮りに1回だけ来て終わり、という店が多いのですが、リピートしてもらうためにホスピタリティをとても大事にしています。自分の居場所にしてもらうように。そうした思い入れを持ってもらうには、コミュニケーションがとても大事になります。
無理に話をする必要はなく、お客さんに自然にしゃべってもらえる空気さえつくればいい。何気ない会話で、何か縁を感じて、気がついたら友だちになっているような、簡単なことでいいのです。無理やりファシリテートするのではなくて。
うちのお店はよく主客が逆転するのです。お客さんに店番をしてもらったり、サーブしてもらったりと。最初の頃は、頼んでもいないのに毎朝両替をしてくれる方もいたり(笑)、みんなが何かの役割を見つけて動いてくれました。こういうのが「顔の見えるビジネス」の醍醐味なのです。

矢島: そうしたことをやりたくてMIA MIAを始めたんですよね。あと「日常生活を豊かにする」ための条件に、挨拶のできる顔見知りがいること、自分と異なる立場の人とコミュニケーションできることを挙げていますが、もう少し具体的に教えてください。
理恵: 私はハード側から、ヴォーンはソフト側から説明しますね。飲食店は窓辺側に客席を設けるのが通常ですが、MIA MIAは窓側を調理場にしています。それは「外を含めた空間の真ん中」に、バリスタがいるという考えからなのです。そして、窓越しに外を歩く人と挨拶するために、もともとはフィックスだったアーチ型の窓を、開閉できるように変えました。

「ヴォーンがコーヒーのこと、私が前職で福祉のことをやってきた、そんなふたりだから生まれた不思議な空間なのかもしれません」と理恵さん。

隣の駐車場では、毎週水曜日の朝に、ラジオ体操をしている。取材した日も寒かったが、若い人もお年寄りも10人以上が参加していたという。
ヴォーン: ソフト側は、すべて挨拶から始まるのです。見知らぬ通りすがりの人にも挨拶をします。ずっと3年間挨拶し続けている人がいるのですが、一度もコーヒーを飲みにきてくれない人もいます(笑)。でも、それでいいんです。自分たちが住んでいるまちに元気がないのは嫌。挨拶だけでまちの雰囲気が元気になります。私たちは、人が好きなのです。
理恵: 日本は災害も多い国なので、顔見知りが近くにいることはとても重要です。イギリスやイタリアにおけるまちづくりの研究をしているのですが、ソーシャルイノベーションが起こるきっかけは、近隣で人と顔を合わせることだと言われています。
社会変革ですら、小さなコミュニケーションからしか生まれません。コミュニケーションは、まず人と会わないと生まれませんし、会って挨拶するのが、極めて大事なのです。
イギリスの雑誌『MONOCLE』の編集者さんが東長崎にいらしたときに「屋外に居場所があるまちは健康である」と言っていたのですが、外で顔を合わせて小さなコミュニケーションを交わすことや、顔見知りがいるだけで、人を健康にすると本当に思うのです。
外に畑やブックポストをつくったのも、立ち止まっても怪しい人に見えないため、挨拶をするきっかけのためなのです。お店やギャラリーはちょっと入れないけど、ブックポストなら近づける人はいる。多くの人は、家以外にまちのどこかに関われる場所を求めているのだと思います。

事務所の前にあるブックポスト。傍らには小さな畑もある。まちとの接点を設けるための装置でもある。
まちは誰のもの?矢島: 理恵さんは「まちの営繕」といった活動もしていますが、どんなことですか?
理恵: このまちに来て、「まちは誰のものなんだろう?」と思い始めたのです。たとえば、道路に穴を見つけたら、普通は区役所に電話して直るのを待ちますよね。それでは私たちは「まちの消費者」になってしまい、とてもつまらないなと。自分たちで楽しく直そうという「自治のあり方」を探っていきたいのです。
人口減少が続くこれからの時代、すべてを行政に任すことはありえませんし、もうちょっと「みんなが手の力を取り戻していく」ことが大事だと思うのです。このまちで暮らしているのだから、まちは自分たちのものだと考えたときに、まずできることはメンテナンスだと思って「まちの営繕」という活動を始めました。
あるとき、店先のコンクリートにヒビが入っていたので、私がバールで剥がしたんです。そうしたら近所のおばあちゃんが来て、こんな土では何も育たないからと言って、勝手に土壌改良を始めて、植物を植えてくれたんです。
そのとき、こんな小さな場所でもまちへの関わり方が増えることに気づいて、めちゃくちゃおもしろいなと思ったのです。「まちを自分ごとにしよう」と言われても、触ったら怒られそうとか、何をやっていいかわからない人がほとんどですが、 木が1本あるだけで、関わりしろができることを知りました。

コンクリートを剥がした場所に植えた木は徐々に生長。店の一部が駐車場部分へはみ出ているが、大家さん所有の私道で、「2メートルは使っていい」という覚書きを交わしている。
まちを使いこなす理恵: 「まちへの関わり方は、私もまだわからないけど、きっかけはつくるから、みんなでまちを使いこなそうよ」とよく言います。
前職で福祉施設のデザインに関わる現場にいてよくわかったことは、条例や法律は実例主義で、前例さえつくれば、いろいろな決まりごとは変えられる。まちの使い方も同じで、いまは禁止になっていても、前例をつくれば覆せるものがあるのです。
駐車場へのはみ出し方や、店先の車止めをテーブルにしてしまうことは、限りなくグレーに近いと思うのですが、「グレーゾーンを使いこなす練習」をみんなでしているとも言えます。

近くにあるイタリアンの〈Cadota〉。店先にある車止めのポールを使ってテーブルとして、店主がパスタを手づくりしていると、通り過ぎる人の多くが「何つくっているの?」と声をかけてくる。
宿をつくり、まち歩きを始める矢島: 店ができる前は、若い人は来ないと言われたと聞きましたが、今日も若い人ばかりですよね。変わってきたのですか?
理恵: 人はいたのですが、場所がなかっただけだったのです。このエリアはベッドタウンなので、実は若い人もかなり住んでいるんですが、「寝るだけ」のまちでした。それが、コロナ禍で散歩に出るようになり、自分の住んでいるまちに初めて目を向けたのだと思います。「こんなエリアだったんだ」「こんなところにお店があった」「私の居場所がここにある」とか。

矢島: この3年で変わったことと、おふたりが次にやりたいことはなんですか?
ヴォーン: すぐ近くには、僕たちが手伝ったイタリアンのお店〈Cadota〉ができて、人気のお店になりました。本屋さんもできましたし、自転車屋やパン屋さんもできる予定です。次は宿をつくって、まち歩きをやってみたいです。実は近々、物件の契約をする予定なのです。
理恵: MIA MIAにはいろいろな人が集まるし、私たちが常に何かやっている姿を見える状態にしているので、みんなが「これをやりたい」と言い出しやすい雰囲気にしたいとは思っています。大学で教えていて、地域で何かをしたい学生が最近すごく多いと感じるのですが、そういう仕事がまだ少ないのです。
でも、こうしてまちに出てみると、建築的知性とか、建築的な動きや振る舞いが必要とされている場面がとても多くあるので、今後はそうしたフィールドを仕事として耕していくこともできると思っています。その結果「建築家がいるとまちが良くなる」みたいな未来を描けるといいなと。

矢島: 最後の質問です。「準公共」や「コモン」をどう捉えていますか。
理恵: 「公」と「共」と「私」があるとすると、「共」と「私」の間の隔たりが大きい時代にいると感じています。「私」は消費するだけになってしまっていて、手を動かし、誰かと一緒に何かつくる機会が非常に奪われています。もっと「私」が積極的にまちに関わったり、働きかける力を高めて「共」につないでいくことが大切なのかなと。
私は「プロジェクト中心民主主義」を提唱しているイタリアのデザイン研究者エツィオ・マンズィーニが好きなのですが、彼は「日々の選択が、日常の政治をつくり、それがコモンをつくる力になる」と言っています。日々選択する力を練習する場所が、「準公共」だと思います。
そして、どこの世界も同じですが、似ている人だけで集まると問題が精鋭化してしまい、問題意識が尖っていきますが、いろいろな人と日々会っていると、すごく重要だと思っていたことが問題とすら思えなくなる瞬間が多々あるのです。そんな開かれた、コモンズをつくる練習をする場をつくっていきたと思っています。
MIA MIAが放つ“パブリック性”これまでこの連載では、「公」の側が「共」の一部を取り入れ、従来の領域・概念から「はみ出した」プロジェクトを取り上げてきた。
MIA MIAは逆で、従来「私」の側で完結していたものを恣意的に解き放ち、「共」側にはみ出してしまったものとも言える。そこに現代の人々が希求する「パブリック性」が確実にあることを、MIA MIAに行って肌感覚で実感した。
これまで公共的なものというのは、自分たちがつくるものではないと思い込んでいたのではないか。単に受け取る、消費する一方通行の関係だったものを、最近になって「私たちもつくっていいのだ」とわかってきたのだ。
さらに、それをやってみるととても楽しく、すごくクリエイティブなことだと徐々に知れ渡ってきたように思う。この連載では今後もそれをひもといていきたい。

information
MIA MIA マイアマイア
住所:東京都豊島区長崎4-10-1
営業時間:8:00〜20:00(金・土・日曜〜22:000)※水曜は6:55〜ラジオ体操
定休日:火曜
Web:MIA MIA
writer profile
Shinji Yajima
矢島進二
公益財団法人日本デザイン振興会常務理事。1962年東京生まれ。1991年に現職の財団に転職。グッドデザイン賞をはじめ、東京ミッドタウン・デザインハブ、地域デザイン支援など多数のデザインプロモーション業務を担当。マガジンハウスこここで福祉とデザインを、月刊誌『事業構想』で地域デザインやビジネスデザインをテーマに連載。「経営とデザイン」「地域とデザイン」などのテーマで講演やセミナーを各地で行う。日本デザイン振興会
credit
撮影:加藤甫