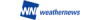”サメ肌”航空機がカーボンニュートラルに貢献? 空気抵抗を減らす新技術に注目
2025/03/09 05:00 ウェザーニュース
強烈な春風に、普段は意識することのない空気の力を感じることが増えます。空気の力を利用し、かつ空気と闘う乗り物が航空機です。
2025年1月10日、日本航空(JAL)は、新しい技術を使った機材を世界で初めて国際線に導入することを発表しました。新しい技術とは航空機表面を“サメ肌”にすることで、燃料消費量とCO2排出量の削減が可能になるといいます。
航空機は人や物を短時間で長距離運べるとても便利な交通手段ですが、環境への負荷が課題となっています。
「従来、機体の保護や美観を目的としていた塗装に、空気のコントロールの役割が加わり、カーボンニュートラルにも貢献します」(JALエンジニアリング技術部・緒方さん)
“サメ肌”の秘密、効果など詳しく紹介します。
航空分野でもCO2排出量が課題に

気候変動問題の解決に向け、世界各国でCO2削減が待ったなしの課題となっています。
2022年度の日本のCO2排出量は約10億3,700万t、そのうち自動車や飛行機などの運輸部門が占める割合は18.5%、そして運輸部門での国内航空は5.1%となっています。
CO2排出量も全体からみれば、航空分野の大きな割合ではないように感じるかもしれません。しかし、輸送量当たり(人km=輸送した人数に輸送距離を乗じたもの)の二酸化炭素排出量で考えると、飛行機のCO2排出量は決して低くはありません。

航空機の輸送量当たりのCO2排出量は101gと、鉄道の約5倍で自家用乗車に次いで多いのです。
サメ肌が空気抵抗を減らす?
“サメ肌”航空機の国際線への導入もCO2排出量削減に役立つ取り組みの1つです。カギとなるのは機体表面に施されたリブレットと呼ばれる構造です。
「サメの皮膚表面の形状をヒントに開発された微細な溝構造です。深さ50μ(ミクロン)程度の溝を機体表面に設けています」(緒方さん)
わさびに鮫(さめ)皮おろしが使われるように、サメの皮膚表面が細かな凹凸があります。サメが速く泳げるのは、この構造が水の抵抗を減らしているからです。自然の生物の優れた構造や機能から学ぶ生物模倣技術(バイオミメティクス)の1つですが、競泳水着の生地に応用されたことで世間の注目を集めました。
「航空機では燃費を上げるためにも、いかに空気抵抗を減らすかが重要です。飛行中は機体表面付近で空気の渦が発生して、まとわりつくような摩擦抵抗になります。
リブレット形状があることで、縦溝によって空気の渦が機体表面から遠のき、表面摩擦抵抗を減らすことができます。実は飛行中の抵抗のうち、最も大きな影響があるのが表面摩擦抵抗なので、その効果が期待されるのです」(緒方さん)

ただ、リブレット形状を航空機の外板に使うには難しさもあったといいます。
「溝の深さ50μとは、髪の毛の太さ程度です。それほど微細な形状を機体の塗膜上に加工し、上空での過酷な環境に耐えうるものとするのには技術的な困難がありました」(緒方さん)
スギ約27,000本の年間CO2吸収量に相当
オーウエル株式会社が改良を重ねた新技術を使って、機体外板にリブレット形状の塗膜を施し、2023年から風洞試験による空力性能の評価や国内線機材での検証などを重ね、耐久性や美観性、燃費改善効果を確認してきました。
「今回はボーイング787-9型機の機体の大部分にリブレット形状塗膜を施しました。これにより巡航時の抵抗低減率は0.24%となります。これは年間約119トンの燃料消費量と約381トンのCO2排出量の削減が期待できるもので、スギ約27,000本の年間CO2吸収量に相当します」(緒方さん)
空の旅を持続可能な手段に

CO2排出量削減は、世界中の航空業界で課題とされています。各国の航空会社や航空機製造メーカーが、SAF(Sustainable Aviation Fuel/動植物や廃棄物由来原料を含む持続可能な航空燃料)の使用や、電動航空機や水素航空機の開発などから解決に向け取り組んでいます。
「JALでは2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指し、従来機より燃費のよい航空機(省燃費機材)への更新、国産SAFを使用した定期便の運航 、軽量化コンテナの採用などによる搭載重量の削減、エンジンクリーニングによる燃費向上などさまざまな取り組みを行っています。
ルートの気象情報や貨物重量などもとに1便ごとに飛行計画を作成することも、燃料消費を少なくしCO2排出量削減に効果を上げています」(JAL)
春は移動の多いシーズンでもありますが、交通機関でも環境負荷を減らすためのさまざまな取り組みが行われていることを考える機会となるかもしれません。
ウェザーニュースでは、気象情報会社の立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、みなさんと一緒に地球の未来を考えていきます。まずは気候変動について知るところから、一緒に取り組んでいきましょう。
あわせて読みたい
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS]
-

- 春の「富士サファリパーク」へ!ふれあい体験で動物たちの知らなかった姿に会える!GWはイベントや動物体験がいっぱい
- 自然の中でたくさんの動物たちに出合える富士サファリパーク。1年中楽しめるが、動物の赤ちゃんも生まれる…
- (Walkerplus)[自然化粧品,旅]
-

- 部屋干し派必見、生乾きを逃さない衣類乾燥除湿機!カビ対策を強化した、三菱電機「サラリ」3モデル
- 三菱電機は、衣類乾燥除湿機の新製品として「サラリPro」MJ-PV250YX、「サラリ」MJ-P180YX、MJ-M120YXの3…
- (GetNavi web)[気候変動,地球温暖化]
-

- 水星からダイヤモンドがざくざく採掘できるかもしれない説
- 水星からダイヤモンドがざくざく採掘できるかもしれない説Image: NASA / Johns Hopkins University Applie…
- (Gizmodo Japan)[航空・宇宙開発]
-

- 関東や東海は雨で今日は気温上がらず 日本海側も昨日より大幅に気温低下
- 関東や東海は雨で今日は気温上がらず 日本海側も昨日より大幅に気温低下2025/05/02 08:13 ウェザーニュー…
- (ウェザーニューズ)[気象,ウェザーニュース]
-

- シンプルで飽きの来ないデザイン!【シチズン】の腕時計がAmazonにて登場!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[エネルギー]
-

- 夏レジャーにぴったり! 抜群のフィット感で風にも強いキャップ「J-FIT ACTIVE」の先行セールが終了間近
- 夏レジャーにぴったり! 抜群のフィット感で風にも強いキャップ「J-FIT ACTIVE」の先行セールが終了間近Im…
- (Gizmodo Japan)[環境用語]
キーワードからさがす
Copyright (c) 2025 Weathernews Inc. All Rights Reserved.