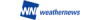気候変動下の生物多様性、水、食料、健康問題。同時に解決はできる?
2025/03/07 05:00 ウェザーニュース
世界はいま、気候変動の影響で生物の生息環境が変わって多様性が失われたり、干ばつなどによる水不足で食料不足が引き起こされるなど、さまざまな危機に直面しています。
気候変動、生物多様性、水、食料、健康問題はそれぞれが密接につながっていて、その関係性を理解したうえで、総合的な対策を同時に取らなければなりません。
国際的な科学者組織「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学・政策プラットフォーム(IPBES=イプべス)」は2024年12月、さまざまな問題を同時解決するための具体策、「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価報告書(ネクサス評価報告書)」を公表しました。
報告書の執筆に携わった国立環境研究所社会システム領域(地球持続性統合評価研究室)主任研究員の土屋一彬(つちや・かずあき)さんに、報告書の内容や同時解決の可能性などについて、解説して頂きました。
「ネクサス評価報告書」って何?
IPBESとはどのような組織なのでしょうか。
「IPBESは2012年、生物多様性についての“世界の知恵”を集めるための国際的なプラットフォームとして誕生しました。2025年1月時点では、世界147カ国の政府が参加し、『気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の生物多様性版』とも呼ばれています。
IPBESの主な役割は、生物多様性に関する知識を報告書の形で取りまとめることです」(土屋さん)
ネクサス評価報告書は、どのような目的、体制で作成されたのでしょうか。
「まず、ネクサスは『結び付き』を意味します。
報告書はSDGs(持続可能な開発目標)達成に向け、『生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価』を目的としています。3年かけて、57カ国165人の研究者によってまとめ上げたものです。
SDGs項目の間の複雑な相互連関について、縦割り型のアプローチではなく、生物多様性の観点からひもといていくことが期待されました」(土屋さん)
報告書のタイトルに、「気候変動」がありませんが。
「執筆にあたり、気候変動の問題抜きでネクサスを議論することの限界が指摘されました。そこで、タイトルになかった気候変動も要素の一つとして扱われることになりました」(土屋さん)
100点満点の未来を実現することは可能?
生物多様性、水、食料、健康、気候変動は、どのような関係性をもっているのでしょうか。
「それぞれの関係性は、ポジティブにもネガティブにもなっています。関係性をまとめた図には、各要素の改善と悪化を示すポジティブとネガティブの矢印が何度も登場しています。
たとえば、食料は他の要素と特に対立する傾向にあることが示されました。食料の増産は水質悪化の原因になったり、森林の消失を招いて生物多様性の劣化をもたらしたりすることがあります。
一方で気候変動の緩和は、適切に実施されれば生物多様性、水、食料分野における改善に大きく貢献することができるなど、ポジティブな相互関係も指摘しています。
SDGs達成に向けてすべてのネクサスを改善していくためには、複雑な関係性の理解に基づいた対策が必要なのです」(土屋さん)
すべての要素が「100点満点」になる未来は、実現可能なのでしょうか。
「残念ながら、生物多様性、水、食料、健康、気候変動のすべてが100点満点の未来を実現するようなシナリオの方向性を見いだすことはできませんでした。
報告書では、科学論文から集めた180以上の『起こりうる未来』のシナリオを精査して、大きく6種類のシナリオ群に分類しました」(土屋さん)

「現在と同じ状況が続くことを想定した『自然の搾取(さくしゅ)』シナリオ群では、生物多様性を含むほぼすべての要素が悪化していきます。生物多様性、気候変動、食料のいずれかを最優先する、『生態系保全ファースト』『気候変動緩和ファースト』『食料ファースト』では、他の要素にネガティブな影響が起きてしまいます。
しかし、『自然志向型ネクサス』と『バランス型ネクサス』では、すべての要素が改善していくことが分かりました。ただし、ネクサスのどの要素をより重視するのかは異なります」(土屋さん)
改善可能な二つのシナリオ群とは、具体的にどのような内容ですか。
「自然志向型ネクサスは保護地域の拡大に加えて、グリーンテクノロジーの強化などを特徴とするシナリオ群です。生物多様性と気候変動と水は改善されますが、食料と健康はそこまで改善されません。
バランス型ネクサスは、保護やテクノロジーよりも自然資源の持続的な利用をより重視するシナリオ群です。食料と健康は良くなりますが、その他の要素はそこまで改善されません。
100点満点は見いだせなくとも、いずれの要素も悪化しないような将来像を見いだせたことで、希望ある未来に向けた議論の材料を提供できたと思っています」(土屋さん)
報告書では、「目指すべき将来像を実現するために必要な71種類の具体的な対策」も紹介されています。

「対策は10の課題別にまとめられています。なかでも『持続可能なかたちで消費する』については、多くの人々の日常生活にかかわる対策が並んでいます。
『洋上風力発電』や『陸上の太陽光発電』などエネルギーに関する対策は、気候変動の緩和にはポジティブな影響を与えますが、生物多様性にはネガティブな影響がありえます。
逆に、『持続可能で健康な食生活』や『肉類の過剰な消費の削減』など食料に関する対策は、水を除くすべての要素にポジティブな影響があり、ネクサス全体の改善につながる可能性があります。
私たちの日々の食事が生物多様性と健康と気候変動の問題に深く関係していることも、繰り返し強調されています。
個別の対策をうまく組み合わせていくことも重要です。たとえば、健康のために水田での野焼きを禁止したことで農業者が冬期の湛水(たんすい)を導入するようになり、それが自然再生の取り組みにつながり、さらに気候変動の影響を軽減するための湿地の創出に連鎖していった事例が紹介されています。
こうした連関や依存関係を問題解決に生かしていく考え方を『ネクサスアプローチ』と呼ぶことにしました」(土屋さん)
すべての要素を同時解決に結びつけるためには、どうすればいいのでしょうか。
「組織の縦割りを超えてビジョンを共有し、生物多様性、水、食料、健康、気候変動に関わるステークホルダー(利害関係者)が協力するネクサスアプローチへの転換が、世界、国、地域のさまざまなレベルで必要です。
持続可能な未来の実現のためには、環境と経済、社会のバランスに注意する必要があります。ネクサス評価報告書が示した71の解決策は、そのための『手引書』になりえるのではないでしょうか」(土屋さん)
土屋さんは「未来を変えようとする多くの人の手に、この報告書が届くことを願っています」といいます。解決策のなかには、私たち一人ひとりができることが、いくつも示されています。物事のネクサス(結び付き)を意識して、まずは自分でできることから実践し、より良い未来を創りあげていきましょう。
ウェザーニュースでは、気象情報会社の立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、皆さんと一緒に地球の未来を考えていきます。
※この記事は以下の資料をもとに再構成しています。
国立環境研究所 社会システム領域「生物多様性、水、食料、健康、気候変動の危機を同時解決するために—IPBES『ネクサス評価報告書』を読み解く」(https://www.nies.go.jp/social/navi/colum/nexus_assessment.html)
あわせて読みたい
-

- あっ地震…そのときゾウが子どもを守るためにとった行動に愛を感じた
- あっ地震…そのときゾウが子どもを守るためにとった行動に愛を感じたImage: Shutterstock 本能に訓練なんて…
- (Gizmodo Japan)[LOHAS]
-

- 教授に結婚報告へ。「結婚するヒマあったんだな」いやいや全然ヒマなんてないです
- 結婚します / (C)さーたり/KADOKAWA属性過多なアメブロトップブロガー・さーたりの原点ここにあり!?オ…
- (レタスクラブニュース)[スローライフ]
-

- 栗東に元Jリーガーが教える知的・発達障害者対象のサッカースクール
- 元Jリーガーの大杉誠人さんが5月3日、栗東市に知的・発達障害者が対象のサッカースクール「Arc Football C…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]
-

- 見頃を迎えたブルー一色のネモフィラの花畑、和カフェ、レトロ建築をめぐる茨城旅へ
- 一面ブルーに丘を埋め尽くすネモフィラの花畑の美しさをこの目で見てみたいと思うなら、茨城県ひたちなか…
- (ことりっぷ)[農業]
-

- 見た目にも履き心地にも拘った一足!【キーン】のスニーカーがAmazonにて嬉しいお値段に!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[生物多様性]
-

- 「台風」去年に続き今年も4月まで発生なし でも油断せず
- 南の海上は年間を通して暖かく、冬や春も台風が発生することは珍しくありませんが、今年に入ってから、ま…
- (tenki.jp)[気候変動]
-

- 北日本は昨日よりも大幅に気温上昇 関東以西は25℃前後に
- 2025/05/01 15:07 ウェザーニュース5月スタートの今日1日(木)は北日本で天気が回復し、昨日よりも大幅に気…
- (ウェザーニューズ)[気象,ウェザーニュース]
-

- 東京日仏学院で食文化の展覧会 フランス国外初開催
- 飯田橋の東京日仏学院(新宿区市谷船河原町)で現在、展覧会「フランス美食の世界」が開かれている。(市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[環境教育]
-

- 雲取山に「五十人平野営場」 都が整備、太陽光発電などで環境に配慮
- 東京都内の最高峰・雲取山(2017メートル)に「五十人平野営場」(奥多摩町)が4月29日にオープンした。場…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然エネルギー]
-

- クールなブラックカラーに、ゴールドの輝きがアクセントをプラス!機能性抜群な【カシオ】の腕時計がAmazonで販売中‼
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[発電,再エネ]
-

- ごはんの冷凍どうしてる?プラスチックの冷凍ご飯容器を卒業した理由
- こんにちは、えりです。愛知県在住の整理収納アドバイザーです。小学6年生と4年生の2児の母をしながら、パ…
- (レタスクラブニュース)[地球温暖化]
-

- 夏レジャーにぴったり! 抜群のフィット感で風にも強いキャップ「J-FIT ACTIVE」の先行セールが終了間近
- 夏レジャーにぴったり! 抜群のフィット感で風にも強いキャップ「J-FIT ACTIVE」の先行セールが終了間近Im…
- (Gizmodo Japan)[環境用語]
-

- 寒暖差が大きい5月 <気温別>オススメの服装は?
- 2025/05/01 14:17 ウェザーニュース5月の昼間は過ごしやすい陽気の日が多いものの、まだ朝晩と昼間の寒暖…
- (ウェザーニューズ)[健康]
-

- セカンド冷蔵庫にもなる! アクアからスリムで大容量な冷凍庫「スリムフリーザー」が登場
- アクアは、スリムな横幅とインテリアと調和するデザインの冷凍庫「スリムフリーザー」シリーズの2025年モ…
- (GetNavi web)[エネルギー(ぼんやり学会)]
-

- 1回できたのに「できない」と言うのは甘え?親の意識と対応を変えてみたら
- ずっとできるって思い込んでました / (C)島村華子、てらいまき/KADOKAWA日々の暮らしの中で困っていた…
- (レタスクラブニュース)[新商品]
-

- 月に長期滞在するための準備に。月の氷が飲料水になる独創的な技術を開発
- 月に長期滞在するための準備に。月の氷が飲料水になる独創的な技術を開発Image: Max Alexander オリンピッ…
- (Gizmodo Japan)[水不足]
-

- 「農」という地域資源を通して、相互扶助で暮らす社会をめざす埼玉・宮代町の「新しい村」
- 自然豊かな田園風景が広がる埼玉県・宮代町(みやしろまち)にある、「農」をテーマとしたコミュニティエリ…
- (Walkerplus)[SDGs]
キーワードからさがす
Copyright (c) 2025 Weathernews Inc. All Rights Reserved.