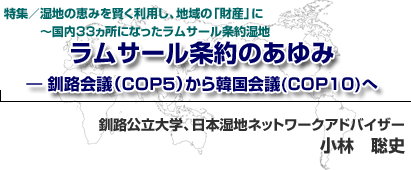|
2005年11月、東アフリカのウガンダでアフリカ地域としては初めてのラムサール条約締約国会議(COP)が開催された。

アフリカで初のラムサールCOPの様子
|
全地球規模で自然環境保全を進めるための枠組みは多くはない。ワシントン条約と世界遺産条約は比較的よく知られているものの、それぞれ対象は限定的だ。そしてラムサール条約も、特定の生態系、すなわち「湿地」に焦点を当てた条約だ。1992年に誕生した生物多様性条約は、これらを踏まえてより包括的な取組を視野に入れたものだが、なかなか個別の生態系保全に貢献できないでいる。種とその生息地である様々な生態系を保護しようとする場合、野生状態、すなわち自然のままの生態系が保護されているのが理想だ。しかし、生態系保全といった場合、土地が絡み、このことは当然各国の国内事情、私有財産権の問題もあり、国際的な枠組みで取り組むのは難しい。そこで、とりあえず今あるカードを使って最大限の効果を生み出す方法が必要だ。湿地という生態系タイプに限られるが、ラムサール条約を活用することによって、地に足のついた個別地域の保全が考えられることになる。さらに世界的な環境問題への取組から、ラムサール条約にいろいろな要請が加わってくる。
そもそも、正式名称が「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地」に関する条約と、その名前の中に水鳥が登場するが、条約誕生の1971年以前から関係者は、水鳥の生息地としての湿地保全を進めつつ、湿地に依存する生物全体を視野に入れることを目指していた。
しかしながら、条約事務の業務はスイスにあるIUCN(国際自然保護連合)そして水鳥や湿地といった科学的な分野はイギリスにあるIWRB(国際水禽湿地調査局)とに分かれた状態で、大きな動きは実現しにくかった。

それが変わったのが、1991年。IUCNとIWRBの職員でそれまでラムサール条約に関わった人間がスイスに集結し、全く新しい体制でラムサール条約事務局の運営が開始された。新しい体制で開催した最初の締約国会議が1993年の釧路会議(COP5)であった。その中心テーマは、条約のフラッグシップ概念と言えるワイズユース(賢明な利用)を掘り下げることであった。そのために特別な検討委員会を作ることにし、世界中の湿地専門家が委員会のメンバーとなった。分析をしてもらうために、世界中から「ワイズユース」の成功例と思われる事例報告を委員会に送ってもらった。この世界中の頭脳を集めて、世界中の事例を分析するという取組はその後、条約の大きな牽引力となっていく。
ワイズユースを進めるためには、湿地を破壊しかねない開発に携わる技術者や政治家にも湿地の「価値」を理解してもらう必要がある。そこで、世界的な環境経済学者達によって世界各地の湿地における経済価値を評価してもらうことになった(1996年COP6)。また、国際条約である以上、湿地の保全責任は中央政府ということになるのだが、個別の湿地の保全においては地域の人々の参加が不可欠である。そこで、世界中から住民参加による湿地管理の事例を集め分析した(1999年、COP7)。

1992年の「地球サミット」に向けて作られた生物多様性条約に協力する形で、ラムサール条約はこういった取組から、湿地における生物多様性保護を推進した。そして21世紀、2002年のヨハネスブルグ地球サミットや国連の取組に呼応する形で、ラムサール条約は水資源確保へも貢献することを打ち出した。湿地は水あってこそ初めて湿地たり得る。特に淡水資源確保のために、世界中の湿地ネットワークを活用することは当然だろう。
2005年、アフリカで最初のラムサールCOPは、ウガンダの首都カンパラで開催され、途上国における環境破壊の最大の要因とも言える貧困対策に、湿地管理を結びつけることが提案された。途上国では多くの人々が湿地の生物資源に動物性蛋白質、衣料品や建築材料、現金収入を依存している。彼らの生活を支えられるよう生態系からのサービスを最大限活用し、一方で短期的な計画によって湿地資源を台無しにしてしまわないよう配慮する、これがワイズユースだ。
また、釧路会議において採択されたワイズユースに関する手引きでは、各加盟国が国内の湿地においてワイズユースを促進するための3本の柱が提唱されている。すなわち、国として明確な湿地政策を持つこと、湿地とその価値に関する知識を高めること、この2つを基に個別の湿地においてワイズユースを進める活動を行うこと、である。
ウガンダは、ラムサール条約加盟国としてはカナダに次いで2番目、途上国としては最初に『国家湿地政策』を採択し、大統領が国民に湿地の価値を理解し保全を進めるよう呼びかけるなど積極的にワイズユースの取組を行ってきた。その努力が認められて、アフリカで最初の締約国開催となった。
残念ながら我が国では、国としての湿地政策はなく「新・生物多様性国家戦略」の中で湿地の重要性にも言及されているにとどまっている。個々の湿地においてはそれなりのワイズユースの取組もされているが、課題は多い。ウガンダの会議(COP9)では、新たに国内20ヵ所の条約登録湿地が追加され、日本における登録湿地の数は33ヵ所となった。新しい登録湿地におけるワイズユースの取組は、地域レベルでの今後の努力が不可欠だ。

次回の締約国会議は2008年11月、アジアで2回目の締約国開催となり韓国昌原市で予定されている。アジアで最初の開催となった釧路会議では、ワイズユースと並んで東アジアにおける干潟(潮間帯湿地)の保全も会議文書に盛り込まれた。日本政府(当時の環境庁)及びNGO代表の発表ともに国内の干潟の喪失を報告し、オランダはじめかつては干拓により沿岸湿地を開発してきた国も、これからは沿岸湿地の再生が重要だという認識に立っていたからだ。しかしながら、それから10年以上がたった現在も東アジアの沿岸湿地喪失は止まらない。日本ではかつて国内最大規模の干潟であった諫早湾(長崎県)や泡瀬干潟(沖縄本島)、そして次回開催国の韓国では、諫早をモデルとし規模は10倍となる世界最大級の干潟喪失、セマングム干潟での干拓事業が進行中だ。
国際条約といっても、個々の湿地における判断は主権国家に任されている。2008年11月のCOP10開催の時点で、諫早も泡瀬もセマングムも工事終了もしくは最終判断が下された後、ということであれば「やむを得ない」で終わってしまうのかも知れない。しかし、全世界から会議のために集まってくる政府関係者、NGO、研究者達はどう思うだろうか。ラムサール条約は個別の湿地保全に目を向けることのできない約束事であると見なされ、その有効性が疑問視されることにならないだろうか。おそらくそのことを十分理解しているからこそ、ウガンダでの決議の中で登録湿地でないにもかかわらずセマングムに言及がなされ、条約事務局長が諫早と泡瀬の問題で個別に日本政府に書簡を提出しているのだ。対立ではなく強調が条約のモットーであるが、日韓政府、関係者やNGOが知恵を出し合って議論を尽くして欲しい。
|