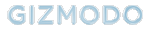ヒュー・グラント主演、A24の新作ホラー『異端者の家』監督インタビュー

泣く子も黙る映画スタジオA24が贈る、泣きたくなるようなサイコスリラー『異端者の家』が4月25日より全国公開されます。
メガフォンを取ったのは、『クワイエット・プレイス』の脚本を手がけたスコット・ベックとブライアン・ウッズのコンビ。ヒュー・グラントを主演に迎えて予測不可能な脱出ゲームを描き、同スタジオの大ヒット作『ミッドサマー』を超える世界興収を記録しました。
舞台はひっそりと佇む小さな家。モルモン教の宣教に訪れた2人の若いシスターを待っていたのは、並外れた頭脳で彼女たちを翻弄する謎の男、ミスター・リード。閉ざされたドアの奥で、“異端者” (Heretic=原題)はシスターたちに究極の選択を迫るーー。
ギズモードでは、脚本・監督を務めた幼なじみで親友の2人組にリモートインタビューを行い、タブーとされる宗教をテーマにした今作の誕生秘話を伺いました。
――今日はお時間ありがとうございます。今はどちらにいらっしゃるんですか?
ブライアン・ウッズ監督(以下、ブライアン):アイオワです。スコットと僕は幼なじみで、一緒にアイオワで育ちました。今はロサンゼルスで仕事をする時間も多いのですが、地元で過ごすのが好きなんです。
スコット・ベック監督(以下、スコット):こちらに家族もいるし、1年ほど前にオープンした映画館の仕事もあるしね(※映画が大好きな2人は地元でアート系シアターを運営している)。
――「パーティーで宗教の話はするな」とよく言われますが、『異端者の家』には普段は聞けないような宗教にまつわる議論が満載で興味深かったです。なぜ宗教をテーマにした映画を撮ろうと思ったのですか?
ブライアン:僕たちの地元アイオワでも、宗教は間違いなくタブーです。子どもの頃は「夕食の席で宗教について話してはいけないよ」と言われて育ちました。とはいえ、僕らの暮らす国では宗教が法律や人生の歩み方と密接に関わっています。ものの善し悪しは時に宗教的な価値観によって定められ、誰もがそれぞれの信念を持っているんです。だからこそ、恐ろしい文脈の中で語るテーマとして面白いと思いました。
――『クワイエット・プレイス』(2018)の脚本家の新作ということで覚悟して観たのですが、ただ怖いだけでなく、観終わってからも考えさせられて、早く誰かと話したくなりました。
ブライアン:いつも怖い物語を書きながら、「自分たちにとって怖いものは何だろう?」と自問するのですが、すべてのホラー映画は死への恐怖と結びついています。『異端者の家』もまた、「死んだらどうなるんだろう?」という疑問や、死について考える時に抱く不安を探究する機会になり得ると考えました。2時間の会話劇を作って、その会話を観客に引き継いでもらうことを望んでいたので、そう言ってもらえてうれしいです。
© 2024 BLUEBERRY PIE LLC. All Rights Reserved. 左/スコット・ベック監督、右/ブライアン・ウッズ監督――2人の宣教師が間違ったドアをノックしてしまう、という物語の始まりは、どのように思いついたのですか?
スコット: 2012年にユタ州ソルトレイクシティで映画を撮る機会があり、ブライアンと僕はモルモン教に興味を持ち始めました。あの街にはLDS(※末日聖徒イエス・キリスト教会=モルモン教の正式名称。本部はソルトレイクシティにある)の関係者が多く、信者や元信者の友だちがたくさんできたんです。モルモン教では19や20歳で家を離れ、宣教師としてドアをノックして回らなければなりません。その若さで自分とは異なる理想を掲げる人を相手に布教するなんて、とても興味深いと思いました。また、スリラーという観点から考えると、彼らは自ら進んで他人の家に入っていくわけです。まるでホラー映画の始まりのように思えて、それをきっかけに今作のアイデアが生まれました。
――脚本を書くにあたって、どのような準備をしましたか?
スコット:無宗教からユダヤ教、イスラム教、サイエントロジー教会まで、さまざまな宗教的背景を持つ友人たちから話を聞いて、約10年を費やしてリサーチしました。それは僕たちに終わりのない会話をもたらし、信仰がいかに人生の選択を左右するかというアイデアが、自然と脚本に落とし込まれていきました。
――ヒュー・グラントが演じるミスター・リードが何とも不気味で恐ろしかったです。それなのに、彼の発言に「一理あるかも」と考えてしまう瞬間もあって、興味深くもあり、ちょっと気まずくもありました。
スコット:ですよね(笑)
ブライアン:いかにも悪そうで共感できない、口ひげをひねっているような悪役は、僕らにとってあまり面白くないんです。だから、ミスター・リードの発言に共感する部分があったと言われると興奮します(笑)。僕らはリードも2人の宣教師も自分たちの一部のように感じていて、すべての登場人物を通して自分たちの考えが伝わるといいなと思っています。
Image: © 2024 BLUEBERRY PIE LLC. All Rights Reserved. ミスター・リード役を演じたヒュー・グラント――“ラブコメの帝王”として名を馳せたヒュー・グラントですが、近年は少し変わった役を選んでいる印象です。なぜリード役にふさわしいと思ったのですか?
スコット:世界中の映画ファンと同じように、僕らもヒューのことは数々のラブコメディを通して知りました。でも、『クラウド アトラス』(2012)を観た時に、彼にもダークな部分があるのだと感じたんです。ヒューの中にはいくつものレイヤーがあって、ここ12年ほどの彼はその闇にアクセスし始め、『パディントン2』(2017)のような映画でも悪役を演じていました。
リードという人物は、シスターたちが家に入る瞬間は魅力的に見える人物でありながら、一度語り始めると相手の心をつかんで離さず、少しずつダークに変化していく。ヒュー・グラントだったら、そのすべてが表現できるとひらめきました。開いたドアの奥に立っているのは、かつてジュリア・ロバーツを魅了したあの男なわけですから、安心して家の中に入ってしまうのです。
――実際にヒューと会ってみて、どのような印象を受けましたか?
スコット:出会った瞬間から、ヒューが哲学的な深い考えの持ち主であることに気づき、リードと通じるものを感じました。役作りのために脚本を読み込み、宿題をたくさんこなして、役の動機となるすべての瞬間を理解しようとするんです。彼は世代を代表する俳優であると同時に、この上ない努力家で、すべての瞬間において自分自身に挑戦し続けていました。
――ちなみにヒューの“宿題”には、ジャー・ジャー・ビンクスも含まれていたと思いますか?
スコット:間違いないです! ヒューは今作に出るまで『スター・ウォーズ』の前日譚(ぜんじつたん)は観たことがなかったはずなので、答えはイエスです(笑)。
――ヒューとはどのようにして、ミスター・リードという人物を作っていったのですか?
ブライアン:ヒューは役についてたくさん質問してくださって、僕たちはミステリーについて永遠に語り合いました。ミスター・リードを生み出す上で影響を受けた、リチャード・ドーキンスやクリストファー・ヒッチェンズのようなイギリスの無神論者についても話しましたし、NXIVM(ネクセウム)のキース・ラニエールのような、現代のカルトリーダーにも目を向けました。賢いだけでなく、知性があるように見せかけることもできる、思慮深い人たちです。
最終的には自分たちの考えをすべて彼に渡して、「ここからは、リードはあなたのものです」と伝えました。ヒューは彼自身の想像力で空白を埋めていき、リードの人物像を作り上げたんです。同じセリフでもテイク毎に異なる演技を見せてくれて、リードという役を生きていたというか、ほぼリードになりきっていました。でも、メガネをかけた猫背なリードと10時間の撮影を終えると、映画スターらしいヒューが楽屋から出てくるんです。歩き方まで違うので、「この人、誰?」という感じで面白かったです(笑)。
Image: © 2024 BLUEBERRY PIE LLC. All Rights Reserved. 左/シスター・バーンズを演じたソフィー・サッチャー、右/シスター・パクストンを演じたクロエ・イースト――宣教師のシスター・バーンズとシスター・パクストンを演じた、ソフィー・サッチャーとクロエ・イーストをキャスティングした理由は?
スコット:オーディションを通して、ソフィーとクロエの演技には、どこか人を惹きつける魅力がありました。ソフィーは強さを表現しつつ、少しばかり謎を秘めていて、シスター・バーンズに近いものを感じました。クロエはとてもオープンな性格の持ち主で、シスター・パクストンと特徴を共有していました。決して演じた役とそっくりというわけではないのですが、彼女たちと役の間には何らかの接点がありました。
――2人とも元モルモン教徒だそうですね。
スコット:いざ2人の顔合わせをしてみると、少しだけ共通点はあるけれど、どこかぎこちなさを感じて、まさに宣教師のように感じられました。というのも、モルモン教の宣教師は、お互いをよく知らないままペアを組まされるそうなんです。彼女たちの話し方も、宣教師の経験がある友人たちを思い出させるものでした。ソフィーとクロエが子どもの頃にLDSの教会に通っていたことを知ったのは、選考過程の終盤になってからです。それはとても頼りになるバックグラウンドで、撮影中に何か疑問が生じても、彼女たちにその場で確認することができました。
――元モルモン教徒として、2人から作品に対するアドバイスはありましたか?
ブライアン:彼女たちは脚本を読んで、とても信用できる内容だと言ってくれました。今も教会に通っている彼女たちのご家族も「正確で敬意が感じられる」とフィードバックをくださって、それは僕たちが求めていたことでした。
ポップカルチャーにおいて、モルモン教徒は冗談のネタとして風刺的に描かれがちです。でも、実際に彼らと接してみると、若くてナイーブな部分もあるかもしれませんが、とても聡明な人たちなんです。だから僕らにとって、バーンズとパクストンが今作のヒーローであること、決して奇妙な女の子たちだと思われないことが重要でした。賢い選択ができる、ユーモアのセンスもある人物として描きたかったんです。2人の演技は、ほぼ脚本通りでしたが、時折かつて教会で得た知識に基づいたアドリブも披露してくれました。
スコット:映画の序盤で2人が自転車を担いで階段を上り下りするシーンは、彼女たちに自由に話してもらったんですよ。
――劇中でミスター・リードは宗教に関する一つの極論を説くわけですが、リサーチから脚本まで、どの段階で彼の極論にたどり着いたのですか?
ブライアン:まず言えることは、あれが果たしてリードにとっての結論かどうかはわかりません。僕らの結論かどうかもわからないですし、宗教に関する今作の結論かどうかも議論の余地があります。ただ、彼が試している仮説であることは確かです。
スコット:さまざまな宗教を研究してきたミスター・リードは、多くの教会や組織は男性優位であり、ジェンダーダイナミクスや女性蔑視などがヒエラルキーに溶け込んでいると考えています。それは間違いなく今作で語られていることであり、自分たちが宗教を勉強するなかで気づいたことでもあります。
でも、僕らが今作で重要視したことの1つは、「確信」という概念に挑むことでした。人は自分の信念には確信を持てるけれど、それ以外のことは間違っていると言いがちで、それでは開かれた会話が生まれません。特に今は多くの人がネット上で議論に参加していますが、それは常に一方的で、誰もが自分の意見ばかり主張し、相手の話はほとんど聞いていません。ですから、研究の果てに唯一の答えにたどり着いたと確信しているミスター・リードのように、今作を観た人が自分の観点を確認するだけで終わるのではなく、思慮深い会話に参加してくれることを願っています。
Image: © 2024 BLUEBERRY PIE LLC. All Rights Reserved.――ミスター・リードは、ボードゲームのモノポリーやレディオヘッドの楽曲など、ポップカルチャーの要素を例に挙げて宗教を解説します。とてもわかりやすかったですが、よく使用許可が下りましたね。
スコット:使用許可が降りなければ映画全体が崩壊してしまうので、実際に制作するまでは怖かったです(笑)。僕たちは宗教を語る上で、あのような比喩を見つけることが重要だと感じていました。リードの解説を面白い大学教授の講義のようにしたかったんです。タランティーノやソダーバーグなどの名作を手がけたプロデューサーのステイシー・シェアが、許可取りに大きな力を貸してくれました。
――映画の舞台であるミスター・リードの家は、物語の展開にも関わる複雑な構造です。あの家の動線について、脚本を書く段階でどれくらい考慮していたのですか?
ブライアン: 2人で脚本を書いていると、微妙に違うものを想像しがちなんです。例えば、僕の脳内ではドアが右側にあって、スコットは左側だと思っていたり。だから、執筆の初期の段階で絵コンテを用意するようにしています。あの家は天才プロダクションデザイナーのフィリップ・メッシーナが、僕たちの脚本や図面をもとに作ってくれました。今作は作品全体がチェスの試合のようなもので、宗教について議論を戦わせる話なので、あの家をチェス盤のように捉え、ミスター・リードに自宅の模型を与えることで表現しました。
――パク・チャヌク監督の作品などで知られる、撮影監督のチョン・ジョンフンによる映像も素晴らしかったです。
ブライアン:チョン・ジョンフンと仕事をするのは僕たちの夢でした。パク・チャヌク監督の『オールド・ボーイ』(2003)や『お嬢さん』(2016)、エドガー・ライト監督の『ラストナイト・イン・ソーホー』(2021)など、名作を数多く撮影してきた巨匠ですので、彼の目を通してこの映画を観ることができて非常にうれしかったです。
――撮影について、どのような提案を受けましたか?
ブライアン:序盤はあまり派手ではない、安定した穏やかなカメラワークにしようと提案されました。それが彼の美しい哲学で、映画を視覚的にゆっくりと盛り上げていくための抑制と忍耐力を与えてくださったんです。
彼と初めてミーティングをした時、「僕はモルモン教について何も知らないし、宣教師がこのような状況に陥ることが、実際にどんなものかはわからない。でも脚本を読んで、この2人の女性に非常に親近感を覚えた」と言われました。「時々悪意をちらつかせるこの男と密室に閉じ込められるということが、どんなものかは想像できる」と。彼は登場人物の立場で物語を感じる人で、カメラに関してだけでなく、物語についても素晴らしいアイデアの持ち主でした。
――撮影監督からのアイデアで印象に残っているものは?
ブライアン:僕たちにとって重要なアイデアとなったのは、シスター・パクストンにメガネを掛けさせることです。ドアをノックする時に、メガネに雨のしずくが落ちてレンズが曇り始め、家の中に入るとさらに曇っていくんです。物語には関係ないかもしれませんが、そういった極小さなアイデアによって、彼女の無邪気さにつながる視覚的なクオリティが生まれました。現場で彼のような巨匠によるアイデアを聞くのは楽しかったですし、僕らはそれらを書き留めて、できるだけ実現するようにしました。
――いよいよ日本でも公開されますが、楽しみにしている映画ファンに伝えておきたいことはありますか?
ブライアン:日本の皆さんの感想を聞くのが楽しみですし、劇中で繰り広げられる会話が、新たな観客に引き継がれることを願っています。また、日本映画から多くを学んだ僕たちが黒澤明や小津安二郎のような巨匠たちから受けた影響を、この映画を通して感じてもらえたらうれしいです。
スコット:今作は宗教について扱った映画であると同時に、大きなスクリーンで観ることを想定して制作しました。見知らぬ人たちと一緒に恐怖を感じたり、感動したりすることほど素晴らしい体験はないので、日本で劇場公開する機会をいただけて、とても感謝しています。いつか日本に行ってみたいです!
『異端者の家』は2025年4月25日より、TOHOシネマズ日比谷ほか全国で公開。
Text: Nao Machida
あわせて読みたい
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術]
-

- がんばるキュリオシティ。火星が暖かく、水も流れていたかもしれない証拠を発見
- がんばるキュリオシティ。火星が暖かく、水も流れていたかもしれない証拠を発見Image: NASA/JPL-Caltech/M…
- (Gizmodo Japan)[Gizmodo Japan]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[新商品]
キーワードからさがす
copyright 2025 (C) mediagene, Inc. All Rights Reserved.