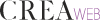《SOPHIA30周年》「いつかじゃなく今頑張れ、と自然と思うように…」松岡充が50歳を越えて見せる“覚悟”
デヴィッド・ボウイが主人公を演じた映画『地球に落ちてきた男』(1976年)の続篇として制作されたミュージカル『LAZARUS』で、主役を演じるSOPHIAの松岡充さんにインタビュー。
今年デビュー30周年を迎えるSOPHIAのことから、松岡さんの死生観まで、たっぷりとお聞きしました。

――松岡さんは普段「日本語で歌う」ことにこだわっていますよね? ミュージカル『LAZARUS』で、英語で歌うことへの抵抗はありませんでしたか?
松岡充さん(以下、松岡) 僕は10代の頃からデヴィッド・ボウイの歌を聞いてきましたが、10代の頃なんて英語はわからないし、正直なところ歌詞の内容なんてまったく理解していなかった。でも、ちゃんと心には届いているんです。
今年デビュー30周年を迎えるSOPHIAですが、200曲以上もの全楽曲の作詞をやってきました。そして、作品を創るたびに、もうこれ以上のものは書けない、と思っていて。日本語、言葉で表現することには自負がありますが、究極は言語を問わず、心に届けられるかどうか? これこそが、歌の力だと思いますし、ボーカリストの表現力でもあると思います。ここに、英語が伝わる・伝わらないというのは、実はあまり関係ないのではないかと思っています。
ただ、オフ・ブロードウェイでニュートンを演じたマイケル・C・ホールは、とても綺麗な英語で歌っていますが、その一方でデヴィッド・ボウイのはクイーンズ・イングリッシュ。本家を尊重するのか、いかにも英語らしいかっこいい発音を重視するのかは、これから演出の白井(晃)さんと相談したいなと思っています。最終的には、「どちらが観客に届くか」ということを考えながら決めたいと僕は思っています。

――松岡さんは、デヴィッド・ボウイに憧れてロック・スターを目指したのですよね。ボウイに惹かれたきっかけがあれば教えてください。
松岡 僕がデヴィッド・ボウイを好きになったのは、まだ16歳くらいの頃です。当時一緒に音楽をやろうと言っていた友人が、「T・レックスのマーク・ボランがかっこいい」と主張して、「デヴィッド・ボウイのほうがかっこいい」と言っていた僕と、めちゃくちゃ喧嘩になった記憶があります(笑)。
今思い返せば、その頃の僕らは本当に子どもでした。今のようにインターネットもなかったので、レコードジャケットの写真を並べて「どれがかっこいい」と言っていたんですよね。デヴィッド・ボウイの本名が「ジギー・スターダスト」だと思っていたり(笑)。何もわかっていなかった。
しかも、当時の日本では、デヴィッド・ボウイが好きだというと、骨太なロックじゃないというか、軟派に見られていた時代で。それでも、ローリング・ストーンズではなく、エルヴィス・プレスリーではなく、「デヴィッド・ボウイやT・レックスがかっこいいんだ!」と言い続けていた僕や友人は、その影響を受けて、その後、僕は日本で、「ビジュアル系」という時代・スタイルで活動をはじめて、そこから30年メジャーで活動を続けている。
もしかしたら、みんなが群がっているものに飛びつくのが嫌で、サイドカウンターに行くことのかっこよさをデヴィッド・ボウイに感じていたのかもしれません。それだけ、デヴィッド・ボウイはインパクトがあったなあ、と今あらためて思います。
見えないからこそ目を凝らしていた
――今年デビューから30年を迎える松岡さん。憧れだったデヴィッド・ボウイの作品で主演を務めるご自分を、どうご覧になっていますか?
松岡 僕らのデビュー前の時代は、見えないから憧れたものがたくさんあったと思います。見えないからこそちゃんと目を凝らし、「来たら逃さないぞ」という臨戦態勢であらゆるものに挑んでいた。
それが今は、情報が溢れすぎて、見えすぎてしまう。わからないことがあってもスマホですぐ検索できてしまうので、それが逆に本質を見えにくくしているように感じています。
だから僕は5年くらい前から、音楽に対しても、ステージに対しても、演劇作品にしても、あえて「見すぎる」のをやめようと決めました。
コロナ禍で、エンタメや芸術が立ち止まるのを目の当たりにして、世の中は決して答えがわかることばかりじゃないと思いました。「いろんな人の意見を聞いて、平和的に」なんて考えが、そもそも「くそくらえ」だし、もうそんなことを言っている時間はない、と気がついたのです。
自分の足で立っている感覚や、声に出して苦しい感覚を味わおう、「見えない未来のいつかのために頑張る」じゃなくて、「今やりたいことをやる」、と決めたら、『LAZARUS』のオファーが来た。これはすごいタイミングだったなと思っています。

――座長としての意気込みはいかがですか?
松岡 気負う部分はないです。今までは共演者の方の不安やプレッシャーを僕が一緒に背負おうと思うタイプだったんですね。なかなかうまく表現できない共演者がいた場合は、「もし僕が彼だったらどうするか」ということを考え、寄り添ってあげることが座長の役割だと思ってやってきました。
でも、僕が全部処置・対応ができるわけではないですし、もちろん僕が完璧なわけでもありません。しかも今回は、僕が稽古期間中に全国ツアーを回っていて、稽古時間が取れず、みんなに迷惑をかける立場です。
だから共演者の方々に助けてもらうという感覚でやっていこう、と肩の力を抜いています。でも、妥協は一切しません。
――なかなか厳しい稽古になりそうですね。
松岡 そうですね。僕はずっと、自分は生業として音楽の世界で生きるアーティストで、作品を創ってツアーに回ることを主体にしているライブアーティストであり、その要素の一部として、「俳優」「役者」という活動があるという感覚がありました。
もちろん、そこで自分ができる限りのことを精一杯やってきたつもりではありますが、「俳優」「役者」という仕事については、実は外様感がずっとありました。でもその活動が15年を過ぎたぐらいのときに、「いや、もう15年やっていて、外様はねえだろう」と気づきまして(笑)。もう逃げるのはやめよう、と考えを変えました。
仮に僕がまだ20〜30代だったら、「いつかのために頑張ろう」みたいな感じでもよかったかもしれません。新型コロナ禍のような予想を超えたことも起こる時代に、50歳を過ぎた自分が、「いつかのために」「何かのために」とか言っている場合ではないのではないか、いつかじゃなく今頑張れ、と自然と思うようになったんですね。
そんな心境の変化を見透かすように、斜め上ぐらいから『LAZARUS』のお話がやってきたのは、やっぱりどう考えても運命だと思います。
「LAZARUS」の意味
――『LAZARUS』は、デヴィッド・ボウイが自身の終活を意識して作られた作品と観る人もいれば、聖書に出てくるラザロ(※キリストにより死から復活したとされる人物)になぞらえ、奇跡の復活を望むミュージカルだと観る人もいます。松岡さんは、どう思われますか?
松岡 人は誰しも、お金や年齢、今までどれだけの偉業を成したかといったことにとらわれがちですが、神様から命をもらった人はみな、この世の中に存在する価値や幸せを持って生まれたはずです。
仮に現世が幸せな人生ではなかった人には、今世とは違うステージに幸せが用意されている。それは、現実社会で言うと、もしかしたら宇宙とか、死後の世界みたいなものなのかもしれませんが、でも確実に僕らの魂は、いろんなところで喜びを感じられる、永遠の幸せの中に存在している――。それをデヴィッド・ボウイはこの『LAZARUS』で描きたかったのではないかと思っています。
人はいつか塵になって、空気や水、土に還っていくわけです。若い頃はその「いつか」は遠い日の話でしたが、50歳を超えて、諸先輩方やまわりの方々が他界されるのを間近で見て、それは寂しいことではあるけど悲しいことではないのではないかと、思うようになりました。
「どうせ人は死ぬ」と思うことも、「どうせ死ぬから何をやってもしょうがない」ではなく、「どうせ死ぬんだったら、もっといろんなことをしたい」というモチベーションにもなっている。だから、「もっとやりたいことがある。もっと見たい景色がある」といつも思っているのかもしれません。

――その考え方のベースにあるのは、デヴィッド・ボウイへの憧憬なのでしょうか。
松岡 どうでしょう。まだこれから稽古を重ねていく段階で、今はまだ雲をつかむような感じですが、デヴィッド・ボウイが言っている「宇宙」や「もう一つの世界」、そして、そこへと導いてくれる存在が何なのかを、僕もこのミュージカルで知りたいと思っています。
そもそも、なぜニュートンが“宇宙人”でなければいけなかったのか、本当の理由も、あの当時デヴィッド・ボウイがどう考えていたかも、わかりません。でも「ジギー・スターダスト」からスタートしている、「この世のものではない」「この地球のものではない」という発想は、僕にとっては“常識”を打ち砕くところから生まれる、新しい人生のステージのように思えるんです。
亡くなる寸前、「これだけは残しておきたい」と『LAZARUS』に遺したのは、何だったのか。有名になりたいとか、お金持ちになりたいとか、みんなに慕われたいとかそういうことじゃなくて、人生にはもっと違うステージがあるんじゃないの? という彼がこの作品に隠した問いに、どこまで答えることができるのか。
僕にとってもすごく楽しみな作品です。決して難しい風に考えずに、みなさんもぜひ、観に来てください。
文=相澤洋美
写真=鈴木七絵
あわせて読みたい
-

- ばね屋の技術を活かした扇風機能付きうちわ「ポップシェード」が登場、人込みでもパッと涼しく!
- キュリオスプリング株式会社は、扇風機能付きうちわ「ポップシェード」を発表。2025年7月18日(金)まで、ク…
- (Walkerplus)[自然化粧品]
-

- 船橋大神宮近くにイタリアン「レ オルメ」 DIC川村美術館から移転
- イタリアンレストラン「Le Orme(レ オルメ)」(船橋市宮本1)が5月8日、船橋大神宮近くの本町通り沿いに…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術]
-

- 「今の日本で、僕以外には、誰にもこの役はできない」デヴィッド・ボウイに憧れてミュージシャンになった松岡充が舞台『LAZARUS』にかける思い
- デヴィッド・ボウイが主人公を演じた映画『地球に落ちて来た男』(1976年)の続篇として制作されたミュー…
- (CREA WEB)[宇宙]
-

- 名作を生み続ける漫画家・志村貴子の“物語のクライマックス”の作り方「遠投したボールを拾いに行くように描く」〈『おとなになっても』待望の実写化〉
- 出会ったその日に恋に落ちた30代の女性ふたり。彼女たちの前には、恋や仕事、家族のことなど考えなければ…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.