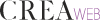「浮気のチャンス」中前結花(エッセイスト)

編集部注目の書き手による単発エッセイ連載「DIARIES」。今回はエッセイストで、初の単著『好きよ、トウモロコシ。』に続き、私家版エッセイ集『ドロップぽろぽろ』が話題の中前結花さん。気持ちが揺らいだ時に引き留めてくれるのは「その人らしさ」なのだと思う、やさしいエッセイです。
転職して4社目の会社に勤めているときのことだった。オフィスの電話が鳴って、わたしは受話器を取り、大きな声で「はい、mixiです!」と、つい8年前に勤めていた会社の名前を間違えて口にした。同僚たちがみな自分の手を止め、覗き込むようにしてこちらを見ていた。
このとき、わたしが考えたこと。それは「自社の名前を間違えるなんて! 」ということもまあ当然そうなのだけれども。それより、もっと強く思ったのは「わたしって、きっと浮気とかできへんのやろうな」ということだった。
こんな初歩的なミスを犯してしまうのだし、それに8年も前のことを未だに切り替えられていないのだ。こんな奴に浮気はできない。すぐさまバレて、木っ端微塵だ。そうに決まっている。それを強く思った。
またあるとき、わたしは友と遅くまで食事をして、当時、彼と同棲していたマンションに上機嫌で帰った。すると彼は言うのだ。
「おかえり。サムギョプサルはおいしかった?」
きょとんとするわたしの胸元を彼は指差す。なんと、わたしはサムギョプサル屋の紙エプロンを胸につけたまま帰宅していたのだ。
電車をいくつも乗り継いだというのに、なんてことだろう。ひとりぐらい教えてくれる人があっても良さそうなものなのに。本当に顔から火が出る思いだった。
そしてこのときも、やっぱり思ったのだった。
「わたしって、きっと浮気とかできへんのやろうな」
結局その彼とは、ほどなくして結婚した。こんなわたしでも許してくれる人と巡り会えた、心からそう思った。
そして、結婚指輪を選ぶときのことだ。
サンプルを見せられて夫は「シルバーがいい」と言った。だけどわたしは本当は「ゴールド」がよかった。散々もじもじしたあとようやく告げると、お店のお姉さんは「それぞれお好きな色を選ばれるご夫婦も多いですよ」とやさしく教えてくれた。けれど、わたしは不安だった。
「金と銀の結婚指輪を光らせて歩いてたら、W不倫カップルやと思われへんやろうか」
違う色やと、違う指輪に見えるんちゃうやろうか……。
けれど、夫が微笑みながらすぐさまこう言う。
「大丈夫だよ。君の顔には、秘密めいたところも背徳感も危なげな感じも何もない。“平和”を丸めて伸ばしたような顔をしてるから、そんなこと思う人はいないよ」
なんじゃそれ。
ああそうだ。たしかに、わたしは昔から事あるごとに「しあわせそうでいいね」と言われて生きてきた。そりゃあ、しあわせはいいことだけれど、わたしにだって悩みも言いたいことも山ほどある。だけどいつだって顔が。どうしても顔が福福しいのだ。これは、もうどうしようもなかった。なにが、“平和を丸めて伸ばしたような顔”だ。
むっとしながら、
「わたしは、ゴールドにします」
と夫とは違う色を選んだ。そんなこんなをしているせいで、結局、両家の食事会のときに結婚指輪の完成は間に合わなかった。このときも、やっぱり要領良くできなかった。
うっかりしている。細かなことに気づかない。いつも洋服にごはん粒がついている。そのうえ、小心者である。こんなわたしに、浮気はできなかろうと思うし、おそらく夫も「こいつにはできなかろう」と高をくくっている。
それでいい。もちろん構わないのだけど、人生で一度でもいい。「器用ですね」「マメですね」だなんて、わたしも言われてみたいものだったし、「浮気されたらどうしよう」「手に負えないな」なんて恋人をハラハラさせる女にも本当はなってみたいものだった。叶わなかった思いばかりが、不器用な胸にしんしんと積もる。
けれど、別に人生でこれっぽっちもチャンスがなかったわけではないのだ。ハラハラするようなシーンが。ハラハラさせるようなシーンが。そう、それはいわゆる「浮気のチャンス」である。
それは20代半ばの頃だった。独立したばかりとあって、その頃のわたしはとにかく夢中で、なんでも仕事の材料にしようと必死だった。そしてその日は、仕事先の人と打ち合わせのあと「親交を深めましょう」と軽くふたりで飲むことになる。クラフトビールが飲める、カジュアルながら雰囲気のある店だった。
浮気のチャンスがふいにやって来た…
話題は仕事のことから、徐々にプライベートな内容に及んだ。あれこれ話すうち、お互い“鎌倉”という土地に憧れを抱いていることがわかった。
「わたし、いつかは住んでみたいと思ってるんです」
「鎌倉にですか?」
「鎌倉は鎌倉でも、長谷(はせ)とかその辺りに。いずれは、海が近くにある暮らしがいいなって。なんだか、ありきたりな夢ですけど」
「ぼくも思っていました。いずれは、って」
「本当ですか? 鎌倉野菜も好きなんです。そういうお店に行くと、うれしいなって」
「鎌倉野菜! 好きだなあ、ぼくも」
いい雰囲気だった。間違いなく、お互いを好ましく思っている感じがあった。それに、彼もわたしも「神社めぐり」が好きだった。「フライドポテト」も好きだった。(しかも、ふたりともケチャップはつけない)しっとりといい雰囲気が流れてしばらく、ついに彼が口火を切ったのだ。
「中前さん、彼氏はいるんですか?」
「え」
わたしは面食らった。わかっていたはずなのに。この流れ、この雰囲気。そりゃあそうなるだろう、と大抵は予想がつきそうなものなのに、わたしはとてもびっくりしてしまった。そんなふうに言われるだなんて。
「いないです」
まっすぐ目を見て答えた。ぼんやりと微笑む恋人の顔を思い浮かべながら。
そのとき、わたしには付き合って3年ほどになる恋人がいた。多少の不満、紆余曲折はあれど、それなりにのんびりと穏やかに付き合いを続けていた。なのにわたしは嘘をついた。そんな、ふたりのかわいい3年間をないものにしたのだ。
「いないんだ。てっきり、誰かいらっしゃると思いました」
「3年ほどお付き合いしていた人がいたんですけど、最近別れたんです」
嘘に嘘を塗り重ねる。悪いことしてるときって、人間こんなもんなんだ。わたしは思った。
「3年って長いのに。やり直そうとは思わないんですか?」
なんだか難しい質問をされた。別れてもない彼との復縁話。嘘話が複雑になってきた。
「考えたこともありませんでした」
思ったことをそのまま口にする。だって、別れたことがないから……。
結局、なんとかその話から遠ざかるように、鎌倉のシラス丼の旨さとか「鳩サブレー」のしたたかさなんかに話を移し、事なきを得た。そう、得たように思っていた。
けれども「では、そろそろお開きにしましょうか」と会計を済ませ、店の階段をトントンと降りているときのことだった。唐突に彼が背後から言ったのだ。
「あの、もし良かったら今度いっしょに鎌倉に行きませんか?」
ここでもわたしは面食らった。わかりそうなものなのに。思えばそんな雰囲気だったのに。
「あ……」
わたしの時は止まった。階段で、足だけ器用に動かしながら、頭は止まっていた。どうすればいいんやろう、こういうときって。恋人以外の人にデートに誘われたときって。きゅるきゅると脳の中で、とんちんかんな部品たちが悲鳴をあげているのが自分でわかった。
「あ……、あの……わたし、鎌倉はいつも同じ人と行ってるんです。鎌倉専用の。鎌倉に行くときは、その人って決めてるんです。すみません」
なんじゃそりゃ。
わたしはそう言って頭を下げた。鎌倉専用の友。なんなのだ、それは。
「そう……ですか」
まったくわけのわからないことを口走ってしまった。だけど彼を裏切るわけにはいかないわけだし、これはこれでまた嘘なのだけれどしょうがない。
「ではまた、今度打ち合わせで」
そんなこんなでわたしの「浮気のチャンス」は未遂で終わった。
けれど帰り道の“あの感じ”は、なんだか忘れない。「嘘をついてしまった」「一瞬でも、恋人候補に思われたいと思ってしまった」。なんだか普段あまり味わうことのない感覚だったのだ。不思議だけれど、「恋人に悪いなあ」という気持ちは特に起こらなかった。だって何もしていないし。わけのわからない文句ではあったけれども、ちゃんと断ったのだし。
それに、わたしにだってもちろん独り身のときはいっぱいあった。もっとひとりのときに。もっともっとひとりのときに声をかけてくれたらいいのに。そんな小賢しいことも、ちょっと思ったりしたものだから、反省の具合は大したものじゃなかったのかもしれない。ただ「自分で自分が卑しくて、ちょっと恥ずかしい」。なんだかそんな気持ちだったのだと思う。ヒールの足元を見ながら「わたしって、こんなとこあるんや」と考えていた。通り道では、聴いたことのないケツメイシの曲が流れていた。
***
そんな顛末をぼんやり思い返しながら、今夜わたしは夫とはじめてデートした店で、ひとり本を読んでいる。夫が「今日は帰りが遅くなるよ」と言うから、「わたしも外食してみようかな」と思い、ひとり仕事帰りに立ち寄ったのだ。静かで、お気に入りのカフェ。
あれから10数年。当時の恋人とは遥か昔に別れ、この店で今の夫と恋に落ちた。
ろうそくの火に照らされながらトマト煮込みをかき込み、本を読む。わたしとは無縁の「不倫」の物語に心乱されていた。大好きな作家の本だから手に取ったのだけど、まさかこんな物語だったとは。本の中では、道ならぬ恋に苦しむふたりが往復書簡をしていて、そこでもやっぱり「ああ、わたしならリビングに手紙を置き忘れたりするんやろうな」とぼんやりと思った。
今日もワンピースの膝にトマトの色のシミなんかをつけてしまって、ああ、わたしには浮気も不倫も完全犯罪も。おおよそ器用な人がやってのける悪事は絶対にできないのだなと確信して、ちょっとさみしい思いをしている。だけどもワンピースの赤い汚れを必死で拭き取りながら、ちらちらと光るゴールドの指輪を眺め、「平和を丸めて伸ばすような毎日も、まあ悪くないか」とほんの少しだけ思っている。その証拠に、夫の帰りが遅いこんな日、わたしはちゃんとさみしい。だって、早く会いたいのだ。
ハラハラなんてさせなくたって、海の近くじゃなくたって。こんな毎日がちょっぴり嬉しく不安でなければ、まあそれで充分じゃあなかろうか。「ああ、きっと浮気はできへんやろうな」とやっぱりわたしは深く思うのだった。
ただ、心配事はある。未だに気にしている。ゴールドとシルバーの指輪で、本当に不倫カップルに見えてないのだろうか……。ふたりで歩くときは心なしか左手を隠しながら、今日もわたしはちょっぴり不安な思いといっしょに歩いている。
中前結花(なかまえ・ゆか)
兵庫県生まれ。エッセイスト。会社員を経て独立し、現在は多数のWebメディアで執筆中。2023年に初の単著『好きよ、トウモロコシ。』(hayaoki books)を、24年に初の私家版エッセイ集『ドロップぽろぽろ』を刊行。目標は、強くてやさしい文章を書くこと。現在、新しい本の準備中。
X @merumae_yuka
文=中前結花
あわせて読みたい
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ,春グルメ,夏グルメ]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒,野菜,ビール]
-

- 5月2日の月が教えてくれるヒント 親しくなりたい人を誘う
- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと11日。 月は蟹座で満ちていきます…
- (CREA WEB)[まち歩き,CREA WEB]
-

- 姫路で保護猫啓発イベント「ひめじ猫友フェス」 雑貨販売やセミナーも
- 保護猫活動啓発イベント「ひめじ猫友フェス」が5月5日、イーグレひめじ・あいめっせホール(姫路市本町)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[兵庫県]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.