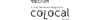岡山と東京の5年間の二拠点生活を振り返る/あかしゆか
フリーランスの編集者・ライターとして活躍し、仲間と手がけた文庫本なども話題を呼ぶ、あかしゆかさん。
2021年4月、岡山県倉敷市の児島にて不定期営業の本屋〈aru〉をスタートさせ、現在は東京と岡山の二拠点暮らしを営んでいます。
それぞれを行き来するなかで、どんなことを思い、なにを大切にし、どのような答えを出し、二拠点生活を続けているのか。あかしさんご本人に綴ってもらいました。
これまでの「二拠点生活」をあらためて見つめ直す「もうコロナ禍から5年も経ったんですね」
知人友人と話していると、そんな話題がちらほらと出るようになった。まちには人気が全然なくて、ほとんどの人がマスクで顔を隠し、飲食店にはアクリル板が設置され、銭湯では話すことも許されない──。いま思い返してみれば異様だったあの日々の光景は、遠い昔のことのように思えるときもあれば、まだまだつい最近のことのように思えるときもある。どちらにせよ、未来が見えず不安を抱えていた日常から5年が経って、大切な人と笑顔をためらうことなく見せ合える日常が戻ってきて本当によかったと思う。
そして私は思うのだ。「コロナ禍から5年が経つということは、私が二拠点生活を始めてからも5年近くが経つということなんだな」と。
2020年7月。コロナ禍になって初めての夏に、私は岡山県倉敷市の児島というまちに2週間滞在し、その滞在をきっかけに東京と岡山との二拠点生活を始めることになった。そしてそれからの5年間、ほとんど欠かさず毎月10日間ほど児島にやってきては、〈aru〉という小さな本屋を営んでいる。
この5年間という期間をひとつの節目として、これまでの私の二拠点生活を振り返ってみることにした。
二拠点生活が続いている理由は何なのか、そのために努力してきたことは何なのか、変わったこと、変わらないこと、楽しかったこと、大変だったこと、そしてこれからのこと。この5年間をいま一度、あらためて見つめ直したいと思う。

2020年は、私にとって鬼門の年だった。5年間勤めた会社を辞めてフリーランスになったタイミングと、当時一緒にいたパートナーとの別れの危機が訪れたタイミング、そして新型コロナウイルスが世界的に流行したタイミングのすべてが重なったのだ。
会社を辞めてもフリーランスで食べていける算段があったから独立したものの、コロナ禍においては多くの仕事が白紙もしくは延期になり、先行きが見えない状態だった。パートナーとの関係も日に日に悪化していって、「もう一緒にいられない」とお互いが結論を出すにはそう時間がかからないだろうことは目に見えていた。
仕事もパートナーシップも、そして生活もすべてがままならない日々が続き、私の精神はどんどん不安定になっていった。
当時は「Zoom飲み会」なるものの流行真っ只中で、私もご多分に漏れず、気持ちを紛らわすためにいろんな人とZoomでお話をしていた。そしてそのなかのひとつに、私の二拠点生活のきっかけをくれた、島田くんと山脇くん──通称「デニム兄弟」との会があったのだ(ふたりは苗字は違うけれど、実の兄弟である)。
「ゆかちゃん、落ち込んでるんやったら、児島に2週間くらい遊びに来てみたら?」
彼らは岡山県の倉敷市・児島というまちでデニムブランドの会社を立ち上げていて、瀬戸内海が一望できる場所で〈DENIM HOSTEL float〉という宿を営んでいる。floatには何度か旅行で訪れたことはあったのだけれど、長くても3泊ほどで、長期滞在をしたことはなかった。「ワーケーション」という言葉が認知され始めたり、緊急事態宣言が解除されて「GO TO キャンペーン」が政府によって実施されたりと、移動が緩和された時期であったのをいいことに、私は彼らの言葉に甘えてfloatを訪れることにした。
児島での2週間。私は瀬戸内海の風景とデニム兄弟をはじめとするまちの人々の存在、児島での生活に心身を救われることとなる。「これから私はひとりぼっちなのかもしれない」と思っていた日々が一変して、朝起きると「おはよう」と言ってくれる友だちがいる生活、何の躊躇いもなく人として「好きだ」と思いあえる人たちがそばにいる日々、価値観の合う人との心の通った会話、おいしいごはん、まるで「どうにかなるから大丈夫だよ」と言ってくれているかのように穏やかでうつくしい瀬戸内海の景色。
滞在中には、当時のパートナーとの関係がいよいよ悪化して、電話で大喧嘩をした日もあった。海の見えるfloatの客室でひとり号泣している私を見るに見かねた山脇くんが、宇野という児島の隣町まで車でドライブに連れていってくれたこともある。行ったばかりの頃は落ち込んでいてまったく食欲がなかったのに、あまりにもおいしそうにごはんを食べる島田くんにつられ、体重が3キロも増えた。島田くんのごはんを食べる写真で私のiPhoneのカメラロールがいっぱいになっていき、それを見るとなぜか力が沸いてくるのだった。
心地よい距離感の共同生活。ただ本を読んで、友人と話して、ごはんを食べて、ぼーっとしながら海を見て過ごす日々。
決定的だったのは、ある日お酒を飲んで酔っぱらったときに島田くんに紹介された、floatのすぐそばにある物件の存在だった。
「ゆかちゃん、floatの近くの物件空いてんで。児島でなんかやろうや!」
失うものがなかった私は、そして自分の場所をつくってみたいとぼんやり思っていた私は、「本屋をやってみたい!」と即座に答えていた。そうしてその次の月から本屋開店の準備のため、東京と岡山の二拠点生活がはじまったのだった。

二拠点生活を始めたばかりの頃と約5年が経ったいまとを比べてみると、「二拠点生活」という事実は同じでも、たくさんのことが変わったなと思う。
始めたばかりの頃は、家もお店もなければ車もなく、関わる人たちもfloatに集まる人たちがほとんどだった。けれどいまでは、お店ができて、アパートを借りて車を買って、新しい交友関係もどんどんと広がっている。
いま、私の二拠点生活は割と快適で「完成形」に近い。けれど、当初はまったくそんなことはなかったのだ。何もかも、足りないものだらけ。正直に言えば不自由はものすごく多くて、いま同じ生活をしろと言われれば難しいと思う。でも、その「足りなさ」が当時の私には必要だった。足りない部分があったからこそ、その分誰かに助けてもらわねばならず、その誰かからの助けがあったからこそ、私とこのまちの結びつきはどんどん強くなっていった。
車がないから、どこへ行くにも誰かに連れていってもらう必要があった(最寄りのコンビニまでは徒歩30分なので、コンビニですら友だちに「連れてって〜」とお願いしていた)。知り合いもあまりいないから、どこへ行くにもデニム兄弟と一緒に行動した。泊まる場所もないから、floatのスタッフ部屋に居候をさせてもらった(ときには押入れで寝たこともあった)。お店のつくりかたもわからないから、島田くんをはじめとして多くの人に助けてもらった。
住む場所がない、移動手段がない、まちに対する知識がない、お店づくりの経験もない。とにかく、あの頃の私はなーんにもなかった。でも、「ない」私に手を差し伸べてくれる人たちが、驚くほどたくさんいたのだ。
「足りない」ということは、一見マイナスなことのように思うかもしれない。お金はあったほうがいいし、知識や経験もあったほうがいいと考える人は多いだろう。けれども、あの頃の私はたしかに「足りない」ことで救われていた。もう少し正確に言うと、「足りない」私に手を差し伸べてくれる人びとのやさしさに救われていたのだ。これが最初から、家もあって、移動手段もあって、お店づくりの経験もあったとしたならば、きっと私はもっと独りだっただろう。いまの私と岡山の関係性は続いていなかったのではないかとすら思う。
人と人、人とまち。何かと関係を築いていくときに、「満たされていること」が必ずしも大事だとは限らない。むしろ少しくらい欠けていたほうが、人と人は仲良くなれるし、助け合えるし、補い合える。その度が過ぎると依存関係になってしまったり、助けてもらうことへの感謝を忘れてしまったら関係性が悪化したりするけれど、限度をわきまえた「足りなさ」は、むしろあったほうがいいのではないだろうか。
二拠点生活をもしこれから始める人がいるとすれば、最初から完璧な状態を求めすぎずに、少し「足りない」くらいがちょうどいいんじゃないですか、とアドバイスしたい。
いま、児島にはどんどん移住する人や二拠点生活を始める人が増えている。そして私は彼ら、彼女らに「足りない」ことがあれば、自分にできる限りのことをしたいと思う。自分が満たされたいま、今度は次の世代へ恩返しする番なのだと思っている。

とはいえ、二拠点生活をしながらお店を営み続けることは大変である。二拠点生活をしながら地方で小さな本屋をやっていると言うと憧れの目で見られることも多いのだけれど、根性と意志と努力がないと続かないと思っている。
これまでは「大変じゃないですか?」と聞かれたときに、なんとなく大変さを表に出すことが憚られて「意外にできちゃいますよ」「最高ですよ」などと答えていた。でも、正直に言うと大変なことはたくさんあった。大変じゃないわけがない。体力も必要だし、事務作業はたくさんあるし、予定の調整も大変だし、お金も必要になる。東京の家賃、岡山の家賃、お店の家賃、通信光熱費、車の保険、オープン時の借金の返済、交通費なども含めると、月々の固定費は30万円以上になる。そのほかに書籍の仕入れ代金なども考えると、さらに多くの支出が毎月あり、それを払い続け、なおかつ自分が健やかな生活を送るためにはまとまったお金を毎月稼いでいく必要がある。
ごくたまに、嫌な言葉を投げかけられることもあった。お店をやっていると、「で、誰がバックについてるの?」とか「旦那さんお金持ちなんですね」といったことを言われることがあるのだ。若い女がひとりでお店をするという事実を見るだけで「ひとりの力でできるはずがない」と思う人が、悲しいかな一定数いるのである。
さらにはお店に不審者が来てしまったり、シロアリやムカデが発生して悲鳴をあげたり、大事な荷物をどちらかの拠点に忘れてきてしまったり、荷物の受け取りがうまくいかなかったり、地方でのイベント出店の移動中に車をぶつけてしまったり……。暮らしのなかでも、書くまでもない小さなトラブルは数多あって、そういった大変さは消えることなくずっとついてまわる。
二拠点生活は、大変だ。
──でも、同時に二拠点生活が「特別に」大変なわけではないとも思っている。都会で店を営むことも、都会で会社員をすることも、地方で店を営むことも、地方で会社員をすることも、子育てをしながら働くことも、もちろん子育てに専念することも。それぞれの生活にはそれぞれの大変さがつきまとう。ただ、私はこの「二拠点生活」という大変さを自ら望んで引き受けただけなのだ。余裕があるからしているわけでは決してなく、あたりまえの大変さを抱えながら、必死に生きている。

周囲の人から最近よく言われることは、「5年間もよく続いていますね」ということだ。たしかに自分でもそう思う。前述のような大変さがあるなかで、なぜこの生活を私は5年間も続けているのだろう?
そう考えたときに思うのは、私は岡山と、岡山にいる人々と、そしてaruという店を営みながら岡山で暮らしている自分のことを愛しているからなのだと思う。そして東京にも、愛するいまのパートナーがいて、都会でしかできない仕事もあるからこそ、まだ東京から離れるわけにはいかない。岡山に完全に移住したいと思う気持ちは実を言うとどんどん強まっているけれど、まだタイミングは来ていないと思っている。
大事な人たちと一緒にいられる自分であるために、変化が必要であれば変化し、変わらないことが必要であれば変わらないための努力をする。「周囲と自分の変化をうまく混じり合わせていく」努力を、私はこの5年間でもっとも大切にしてきたように思う。
例えば前述のように、二拠点生活初期の頃はデニム兄弟に頼りきりの生活だったけれど、コロナ禍が収束するにつれてどんどん彼らの宿は人気になっていき、その変化のなかで私も「そろそろ児島での生活も自立しなければ」と思い、自分で新しく部屋を借り、車を買った。
お店の運営だってそうだ。開店当初はどちらかといえば「私が好きな本を置く」というスタイルだったけれど、大切な常連さんたちができていくなかで、「この本を置いたらあのお客さんが喜んでくれるだろうな」と思ったり、「この本絶対に合うと思うよ」と逆にお客さんから教えていただいたりして、顔が見える関係性が増えるとともにどんどん店が変化していった。常連さんに飽きられないように、常に変化し続けなければと、本屋として成長したいという気持ちも生まれていき、現に初年度と4年目の現在では倍以上の売り上げになっている。

誰と、何をして、どのように生きていきたいか。
私の人生では、「変化」が目的になることはあまりない。変化はあくまでも、大切な人とともに生きていくために取る手段でしかないのだ。そんな私がどんどんこの5年間で変化している──それは、ともに生きたいと心から願える他者に出会えたという証拠にほかならず、そして変化したあとの自分を自分でも「いいな」と思えることは、なんと幸せなことなんだろう。
きっといつか私の命が尽きるときに思い出すのは、瀬戸内海を見ながら穏やかに笑うこの日々のことなんだろうなと思う。
「二拠点生活」というかたちがこれからいつまで続いていくのかはわからないけれど、大事なものを大事にしながら生きるために、変わったり変わらなかったりしながら、これからもいまを見つめて生きていきたい。

profile
Yuka Akashi あかしゆか
1992年生まれ、京都出身。大学時代に本屋で働いた経験から、文章に関わる仕事がしたいと編集者を目指すように。 現在はウェブ・紙問わず、フリーランスの編集者・ライターとして活動をしている。2020年から東京と岡山の二拠点生活をはじめ、2021年4月、瀬戸内海にて本屋〈aru〉をオープン。
text
Yuka Akashi
あかしゆか
credit
写真:田野英知
編集:林貴代子
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 周南でeスポーツと職業フェア 地元企業12社が中高生にアピール
- eスポーツ大会と企業紹介イベントを組み合わせた「eスポーツフェス&職業発見フェア」が5月11日、トクヤマ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒,東京都]
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[旅]
-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ
- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[植物]
-

- 宇宙飛行士・若田光一さん、岡山の関西高校で講演 民間主導の宇宙産業へ
- 宇宙飛行士の若田光一さんの講演会「日本人初のISS船長(コマンダー)若田光一氏が語る宇宙開発と産業の未…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[岡山県]
-

- 「夫との旅行はムリ!」“店構えでおいしいか分かる”と言い張る夫と2時間歩いた後の悲劇
- ゴールデンウイークを控え、旅行の計画を立てている人も多いだろう。だが、中には日常生活では問題がなく…
- (All About)[コンビニ]
-

- アウトドアや災害時にきっと持ってて良かったと思える“三角形”
- アウトドアや災害時にきっと持ってて良かったと思える“三角形”Photo: SUMA-KIYO 2024年6月3日の記事を編…
- (Gizmodo Japan)[いざというときのお役立ち]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.