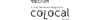ローカルの独立系書店が生きていく術とは? すこしずつスタンダードに移行すること

定休日明けの水曜、午前10時前。〈本屋ルヌガンガ〉の中村涼子さんが店先の植物に水をやり、看板を出して開店の準備をしていると、自転車に乗った高齢の女性がやってきた。「もう開けますから、さあどうぞ!」と軽やかに声をかける涼子さん。常連のお客さんだという。少し立ち話をしたあと、涼子さんは「配達に行ってきますね」と雑誌を手に外へ。常連さんは雑誌が並ぶ平台へ。ほどなくしてひとり、ふたりとお客さんがやってくる。
カウンターでは黙々と本の検品作業を進める、店主の中村勇亮(ゆうすけ)さん。先ほどの常連さんに目を向けると、椅子に腰かけゆっくりと雑誌をめくっていた。

高松市の繁華街に店を構える〈本屋ルヌガンガ〉。田町商店街から1本入った通りに位置し、周辺にはミニシアター系の映画館や古本屋などもある。2017年8月17日に夫婦でオープンした。

看板「本」の描き文字はお客さんだった装丁家・平野甲賀さんによるもの。

香川の伝統的工芸品、高松張子が本棚に飾ってある。
名古屋から高松へUターンして本屋を開く勇亮さんは高松市出身だが、地元を離れていた時間が長い。信州大学を卒業後、「本が好き、本屋が一番身近な場所だったから」という理由で名古屋に本社がある書店に就職。岐阜と大阪の支店で3年ほど働いた後、商社へ転職し、結婚した。書店を辞めても本は変わらず読んでいたが、ライフスタイルが変化するなか、昔のように大型書店でゆっくりと本を選ぶ時間はとれなくなっていた。その代わりにまちの小さな書店に入って、さっと本を選ぶスタイルが定着していたという。

「その頃、世の中に新しいタイプの書店が出てきたのを知ったんです。店主のセレクトが光る、小さな店。まさにぼくもそんなお店を求めていたし、やってみたいと思いました。ただ、会社員から自営業者になるイメージがなかなかわかなくて」
2015年にブックコーディネーターの内沼普太郎さんが主催する本屋講座に参加したことが転機となった。
「会社を辞めずにそのとき暮らしていた名古屋で週末だけ本屋をやろうか、もしくは故郷の高松で誰かを雇って本屋のオーナーになろうかなどと、ぼんやり考えていたんです。でも講座を受けて本屋のプランを考え、少しずつ準備を進めているうちに、やっぱり自分でするほうが楽しそうだからやってみようと気持ちが固まりました。当初、妻は賛成ではなかったのですが、流れのなかでふたりでやろうということに……」

絵本・育児関連の棚を担当している、妻・涼子さん。
「最初は驚きました。ふたりとも会社員を続けていくと思っていましたし、まさか起業するとも、生まれ育った愛知を離れるとも思っていませんでした」
当時は涼子さんも会社員だったが、仕事と子育ての両立に悩み、女性の起業支援セミナーに行き始めていた矢先だったという。
「どちらかというと私がやりたいことを探していて、夫は会社で頑張っていくと思っていたので、ある日、夫が本屋をやりたいと言い出したのでビックリしました。でも、お互いに本が好きでしたし、ふたりで古本市に参加して本を売っていたこともあったりしておもしろそうという思いもありました。私は書店員経験がなかったので、名古屋のまちの書店で修行をすることにして、本屋をやるイメージを膨らませていきました。腹をくくるのに1年以上かかりましたけどね(笑)」と、涼子さん。
そんなふたりが最終的に高松を選んだのは、〈本屋ルヌガンガ〉がある物件との出合いが大きい。ツテを伝い安く借りられそうだったこと、かつ活気のある商店街に隣接する立地だったこと。小さな書店を始めるにはリスクの少ない理想的な条件が揃っていたことが背中を押した。
品揃えは“セレクト”から“スタンダード”へ「オープン当初は大型書店には置いていないであろう少し変わった本をセンスよく並べる、というのを意識していました。“ここはセレクト書店です”と意気込んでいましたね」

最初の2年間はただただ試行錯誤をしていくうちに終わり、その後はコロナ禍に。気づいたら5年くらいが過ぎていたが、店を開け続けていると、徐々に気づくことがあったと振り返る。
「本の看板が目に入ったからとふらっと立ち寄る方、ベストセラーや実用書を求める方など、当店や『セレクト書店』をめがけてきたわけではないお客さんも徐々に増えてきたんです。本棚を少し見て、よくわからない本屋だな? という顔をして出て行かれる方も増えてきました。本屋という看板を見かけたら、多くの方が気兼ねなく入ってきてくださる。結果、客層が思っていたよりも広がっていたんです」
“地元のお客さんに合った品揃えとは?”を改めて考え直した結果、「セレクト」より「スタンダード」を意識するようになった。

約30坪の店内に雑誌からあらゆるジャンルの書籍まで7000冊ほど揃える。
現在ではいわゆる、独立系書店でしか扱っていない本もおさえつつ、一般的な雑誌や定番の本なども幅広く仕入れている。「あの人ならこれが好きかな」という感じで常連さんたちの顔を思い浮かべながら取り寄せ、このまちの本屋ならこういうバランスの品ぞろえが最適なんじゃないかというところを目指すようになった。

香川や四国にまつわる雑誌や書籍も広く取り扱う。
「棚自体は少しずつエッジがなくなってきたと思います。『おもしろい棚ですね』といってもらえることも多いですが、センスでお客さんを引っ張る刺激的な棚というよりは、お客さんの“気になる”に寄り添った棚、というニュアンスが強いように思います。独立系書店の棚を見慣れている方が見ると、意外と普通の本が置いてあるな、と思われるんじゃないでしょうか。ただ、仕事帰りの方やお年寄りなど、うちに強い思い入れがあるわけでもない方が(笑)、ふらっと入って来て、そしてずっと通ってくれ、常連になってもらえる。そういう方たちの日常のなかにあるなと実感できる瞬間が増えてきました」

ロゴは西脇一弘さんによるもの。西脇さんの音楽のファンだったことから依頼した。
客層はさまざま。しいて言うなら30〜40代女性が一番多いが、高齢の常連さんや子連れも多い。また、徳島や愛媛など近県を含めて旅行者も多く、「地元にこういう店がないから」「この店を目指して来ました」などと声がかかることもある。
「もちろん、本屋巡りが好きな方や感度の高い人もいらっしゃいますが、少しずつ客層が変化して、よりすそ野が広がったというような感じでしょうか」
本屋はまちの脇役でいいすっかり認知され、まちに溶け込んでいるように見える〈本屋ルヌガンガ〉。ローカルでの立ち位置はどう考えているのだろうか。

「ローカルのコミュニティというと、結構濃いものを想定しがちだと思うのですが、それはそれで息苦しいんですよね」“おつき合い”やビジネス的な打算から始まった関係性は長続きしないこともあった。
「店をやっていくなかで感じているのは、この店が核となって濃いコミュニティをつくるのではなく、まちで立ち寄る場所のひとつ、くらいの位置づけでいいのではということ。誰にとっても日常的なもので、毎日当たり前に開いている場所。本屋はとりあえず寄ってみるかくらいのまちの脇役でいい。そうあることで結果的にローカルになじみ、コミュニティ、人にもなじむのかなと思っています」
かたや、目に留まるのがイベントの多さ。毎月10本程度、何かしらのイベントが開催されている。

イベントの案内が壁にびっしり貼られている。

取材時、イラストレーター/スケッチャー、タケウマさんのスケッチ展を開催中。
「これは確実に関係するコミュニティが広がってきた証ですね。ただ、この店が強い吸引力で人をひきつけているのではなく、それぞれのイベントにすでにコミュニティがあったり、登壇される著者やテーマに興味を持って人が集まってくれたり、店はあくまで場を提供しているような感覚です。だからこれも、うちを使っている方たちとふんわりつながっている感じでしょうか」
以前は本に関係ないイベントも多かったが、縁が続かず徐々に外していった。お客さんも本とつながりのあるものを求めているため、今では本にまつわるイベントに絞っている。
「地方だと、コミュニティをあまり強く志向しすぎると、知り合いとの狭いおつき合いの内側に閉じてしまう感覚が強いですが、もっと世界が広がってもいい。世界の広さを体感できるのが本であり、それを提供できるのが本屋だと思っています。ローカルになじみながらも、外側の風を吹かせ続けられればいいなと思っています」

日常の視点や世界が広がる、おすすめの2冊。『テヘランのすてきな女』(金井真紀著/晶文社)、『家から5分の旅館に泊まる』(スズキナオ著/太田出版)
理想は気立てのいいおかみさんと寡黙な大将物腰が柔らかく終始にこやかに話を続ける勇亮さんと、常連さんたちと会話が弾む涼子さん。当初から涼子さんは絵本や育児関連本の選書と経理を担当しつつ、店にふたりで立つ。この夫婦というスタイルもローカルにはいいのかもしれない。

「最初はどちらかというと私が前に出ていましたが、次第に妻が主催する絵本のイベントが増えたり、妻に会いに来るお客さんも多くなったりして、今は店主が入れ替わった気がしています(笑)。昔ながらのまちの食堂や商店って、気立てのいいおかみさんが前にいて、その後ろに寡黙な大将がいたりしますよね。そういうバランスの店はなぜか居心地がいいし、安定感がある。商売人として自分が前に出ず、店を後ろから支える側に立つというブレない精神があるように感じます。その愚直な姿勢が大事だなって次第に思うようになって」
また、本好きな人は控えめで繊細な人が多く、必ずしも「濃い」コミュニケーションが求められているわけでもないことに気づいてきた。そういう人が安心して来やすい、いつも心地いい場所であるために、なおさら「自分」が目立たないことを意識するようもなった。
「当初はお客さんとしゃべらなきゃ!自分らしさを出さなきゃ!と力んでいたんですが、それが本屋に求められる本質ではないな、と徐々に気づいていった気がします」

「長く通ってくださるお客さんとは、お店と客という枠を少し超えて、深く接しているなと感じることもあってその関係性が心地いいです。お子さんの成長を見届けたり、ご年配の方の健康を気遣ったり。『ここで出合う本やイベントを通じて、学び直しをしているんよ』と、いってくださる常連さんもいて励みになります。また、私は移住者で毎日ここにいるからまちのことは詳しくない。いつもお客さんが何かと教えてくれるのでずっと新参者でいたいと思っています(笑)」と、涼子さん。
それぞれのやり方でお客さんとの関係性を築き、積み上げている。そこにローカルの本屋としての厚みも生まれているようだ。
本以外の心地よさを追求するローカルの独立系書店も、これまでは都会的で真新しい業態というムードがあったが、文学フリマ(文学作品展示即売会)やブックフェス、シェア型書店も増え、本を手渡す場面もどんどん移り変わっている。移ろう対象にはならず、日常的な場所であり続けるためにはどうすればいいのだろうか。
この夏で8年目を迎えた〈本屋ルヌガンガ〉。ローカルで長く続けていくコツを聞いてみると、しばらく考え込んでから答えてくれた。
「その答えを今も探している最中ですが、しいて言えば、「安心感」でしょうか。例えば、空間の心地よさや、毎日、時間通りに店が開いているという安心感。また、SNSでもお客さんが違和感をおぼえることを言わないようにしています。本を手にするときにノイズとなるような、変なひっかかりは極力ないほうがいい。長く続いている店やモノには絶対的なやさしさ、安心感がありますよね。ぼくもそこをすごく大事にしたいと考えています」

喫茶スペース。奥の階段状のスペースに座って本を読んでもいい。

コーヒーやジュースのほかに、ビールや梅酒なども選べる。
その思想が表れているのが空間。高松にゆかりのある彫刻家イサム・ノグチの照明AKARI(幻のフロアスタンドも!)や、世界中で愛され続けている名作椅子のYチェアなどが使用されている。また、店内のところどころに椅子やスツールを置き、喫茶スペースを設け、トイレにはおむつ交換台も。心地よい空間へのこだわりや配慮が店内にちりばめられている。その設えも時間をかけて少しずつつくり上げてきたものだという。

オープン当初の店内。
空間にある、店の什器もしかり。「オープン当初と同じものはほぼありません」と勇亮さん。壁の棚板、店内の本棚、平台すべてを徐々に入れ替えてきた。使ってみて初めて気づいたという、本が傷つきやすく取り出しにくい材質、見づらい高さなど、自分たちやお客さんにとって見えないストレスになっていた部分は、より収まりのよいものに変えていった。

おもちゃ箱には子ども店長(娘さん)の手書きメッセージが。
店の入口にあるスロープは車椅子ユーザーの方が助成金を利用して自ら設置。子連れでもゆっくり本を選べるようにとおもちゃ箱をつくったり、音のバランスにこだわってスピーカーを入れ替えたりなど、月日を重ねるなかで加わったものも多い。
「お客さんがいろんなかたちや視点でこの店を愛してくれているんです。そんな深い愛を持ってくれているのか!と驚かされることもあります。小学生に『将来はこんな店をやりたい』と言われたときは本好きの子どもの夢のひとつになれたかなと思えてうれしかったですね。もはや、自分たちの価値観だけではコントロールできない店に育ちつつあります。だから、明確なビジョンでお客さんを引っ張っていくというよりは、お客さんがうっすら求めるものを感じ取って、少しずつ愚直に応えていくことを大切にしたいです。これからもこのまちの本屋として心地よさを追求し、10周年を迎えられたらと思っています」
愛されるローカルの本屋は変わらないようでいて、じつはさりげなく、ずっと変わり続けている。そんな〈本屋ルヌガンガ〉に「なんかいい本屋だよね」と、今日も人が通っている。
information
本屋ルヌガンガ
住所:香川県高松市亀井町11番地の13 中村第二ビル1F
tel:087-837-4646
営業時間:10:00〜19:00
定休日:火曜
Web:本屋ルヌガンガ
Instagram:@lunuganga_books
writer profile
Akiko Sato
佐藤晶子
さとうあきこ●編集者/ライター。都内出版社で雑誌、ムック、書籍の編集を経て独立。2011年に結婚を機に徳島へ帰郷。四国、東京を中心に企画、編集、取材&執筆、アテンドなどを行う。長続きしていることは数行日記と短歌。ともに15年以上。
photographer profile
Kanako Mori
森香菜子(KIGIPRESS)
もりかなこ●徳島県在住。タウン誌の編集者として7年勤務後、独立。編集の経験をベースに、取材・執筆・撮影・グラフィックデザインと幅広く活動しながら、「伝えたい」のお手伝いをしています。
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS,スローライフ]
-

- 「水商売やったら化けそう」2丁目で彼女の才能が開花!/29時の朝ごはん〜味噌汁屋あさげ〜(19)
- 水商売やったら花形に化けそう / (C )佐倉イサミ/KADOKAWA眠らない街・歌舞伎町の片隅に、朝5時からひ…
- (レタスクラブニュース)[スローフード]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ,東京都,大阪府]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント,旅,地域の魅力]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒,健康,ビール]
-

- 5月2日の月が教えてくれるヒント 親しくなりたい人を誘う
- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと11日。 月は蟹座で満ちていきます…
- (CREA WEB)[まち歩き]
-

- 「博多町家」ふるさと館物産棟がリニューアル カフェ新設や限定土産も
- 「博多町家」ふるさと館(福岡市博多区冷泉町)の物産棟がリニューアルし、4月26日、観光交流拠点「hakata…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[地方創生]
-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ
- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[植物]
-

- 弘前で「森カリオペ」のリキュール販売延長 弘前城の缶バッジを同梱
- 津軽藩ねぷた村(弘前市亀甲町)で期間限定商品だったバーチャルアーティスト「森カリオペ」のリキュール…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[愛知県]
-

- 使っていない人はソンしてる?「子育て支援パスポート」を使ってお得に楽しもう!
- 子育て中の皆さま、「子育て支援パスポート」をご存じですか? カフェでソフトクリームがついてきたり、店…
- (All About)[徳島県]
-

- 高松・屋島で「OMORI」展 庵治石のプロダクトずらり
- 庵治石を使ったプロダクトを展示する「OMORI(オモリ)」展が現在、高松・屋島山上交流拠点施設「やしまー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[香川県]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.