このコンテンツは、地球・人間環境フォーラム発行の「グローバルネット」と提携して情報をお送りしています。
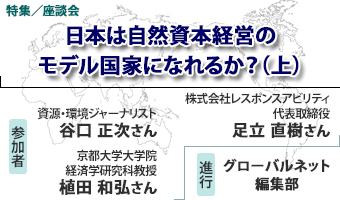
グローバルネットでは昨年(2014年)、わが国の経済運営、企業経営を根本から問い直す「求められる真の自然資本経営」をテーマに連載を行いました。
この分野でさまざまな活動をされている資源・環境ジャーナリストの谷口正次さん、生態学研究者としてマレーシアでの森林研究の経験がある株式会社レスポンスアビリティ代表の足立直樹さんに、自然資本経営の現状、海外の取り組み、今後の見通しなどについてご執筆いただきました。
今回は、自然資本経営の必要性をわが国で初めて提唱された京都大学大学院経済学研究科教授の植田和弘さんにも加わっていただき、期待を込めて「日本は自然資本経営のモデル国家になれるか」というテーマで、神楽サロン(東京・新宿区)にて話し合っていただきました。その内容を2回にわたって特集します。
 谷口 正次 氏
谷口 正次 氏
資源・環境ジャーナリスト 京都大学特任教授
1960年、九州工業大学鉱山工学科卒業。小野田セメント入社。資源事業部長、常務取締役を歴任し、環境事業部を立ち上げる。合併による1998年の太平洋セメント発足時の専務取締役として、環境事業などを担当。退職後は資源・環境戦略設計事務所の代表となり、豊富な現場体験を踏まえた資源・環境問題について、ジャーナリスティックな発言を続けている。NPO法人ものづくり生命文明機構理事。著書に『メタル・ウォーズ』『オーシャン・メタル~資源戦争の新次元』など多数。
谷口 自然資本とは何かというと、「人間が作ったもの以外はすべて自然資本」というのが私の認識です。したがって、人間自身も自然資本という考え方です。地球の生物圏にあるもの、地下の地殻にある地下資源もすべて自然資本です。水とか土地もそれであり、人間性とか文化、伝統といった目に見えない価値も付け加えたい。
鉱山技術者として自然資本の破壊をしていましたが、定年近くになって矛盾に気が付き、自然資本を守る側に心変わりしました(谷口) 私は、生まれた時から自然資本に囲まれた環境で育ちました。1945年に広島で終戦を迎え、焼け野原の中で、食料の配給もない自給自足の生活を送っており、庭先に野菜やイモなどをつくって植えていました。少年時代から青年になるまで自然を肌で感じて生活してきました。
ところが、高度経済成長期、1960年に大手セメント会社に就職して、鉱山技術者として自然資本の破壊を続けてきたわけです。定年近くになって、私は広島における原体験との矛盾に気が付き、自然資本を守る側に心変わりしました。
GN編集部(以下編集部) 日本の復興、高度経済成長を支えた企業人として、自然資本の大切さに気付かれたきっかけは何だったのですか。
谷口 途上国における資源開発に伴うすさまじい自然破壊の現場を見て回ったことです。自然資本という考え方を知ったのは2004年のことです。米国のポール・ホーケン、エイモリ・ロビンズ、ハンター・ロビンズの書いた『自然資本の経済』(原題:ナチュラル・キャピタリズム)という本で自然資本という言葉に出会いました。そのあと、「自然資本経営」という言葉にめぐり合ったのです。2012年、京都大学の経済学者、植田和弘先生との会話の中でしたが、この言葉は植田先生が発明された、世界で初めての概念だと思います。
自然資本は減耗し、劣化し、枯渇します。もう限界に来ているという認識から京都大学に自然資本経営論講座ができました(谷口) 私は人間が作ったもの以外はすべて自然資本と定義しましたが、言い換えればそれらは「資源と環境」であることに気づきました。資源・環境というのは、表裏一体のものです。自然資本をどこまでも人工資源に変えていけば、自然資本は減耗し、劣化してやがて枯渇します。もう限界に来ているのです。
自然資本をサステナブルなものにする、長持ちさせなければいけないということで、私が資源と環境は一体だと言ってきたものを、自然資本と言い換えて世間にメッセージを出そうと、植田先生の指導を受け、京都大学に自然資本経営論講座ができました。
編集部 国立環境研究所(国環研)の生態学の研究者として、マレーシアで、熱帯林の生態や土地利用の研究の経験をお持ちで、現在は経営コンサルタントとしてご活躍の足立さんにとっては、自然資本経営は古くて新しいテーマと言えますか。
 足立 直樹 氏
足立 直樹 氏
株式会社レスポンスアビリティ代表取締役
1989年、東京大学理学部卒。1994年、同大学院理学研究科修了。理学博士号取得。国立環境研究所で熱帯林の研究に携わり、1999年から3年間、マレーシア森林研究所で熱帯林の動態や土地利用の変化などを研究。帰国後、独立して企業向けの環境やCSRのコンサルタント会社を設立し、持続可能なサプライチェーンマネジメントなどを支援する。企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)事務局長なども務める。著書に『生物多様性経営~持続可能な資源戦略』など。
足立 生態学を勉強して大学院を出た後、国環研に勤めました。当時、国環研とマレーシアの森林研究所と共同での熱帯林研究プロジェクトがあり、私は現場の一人として参加し、森林動態を研究しました。1999~2002年までいましたが、暮らしていると見えてくるものがあります。
例えば、マレーシアの森林の割合は公称国土の約50%ですが、実際はそんなにないと思います。日本よりはるかに少なくて、その原因はプランテーションなどにどんどん開発されているからです。わずか100年前までは、森林に覆われていたのです。開発は現在でも続いています。
生態学を研究した観点からビジネスを見ると社会に問題があるのは自然の仕組みから乖離しているため(足立) 2002年に日本に戻り、違う世界に出て仕事をしたいと思い独立しました。生態学をやってきて、その観点でビジネス、社会を見ると、社会に問題があるのは、自然の仕組みから乖離しているためだと思いました。その頃、ナチュラル・キャピタリズムは、まだ一つの概念でしかありませんでした。
編集部 生物多様性が失われたり、生態系が壊れてしまったりすることが、企業活動や人びとの暮らしにも影響することだと理解されるには時間がかかりますね。自然保護活動は広がっても、自然そのものの多面的評価までにはなかなかつながらない。
足立 国際的な動きを少し説明しますと、国連の当時のアナン事務総長の提案で、ミレニアム生態系評価(2001~2005年にかけての全地球の生態系の変化の分析)の報告書が2005年に出ました。生物多様性や生態系に私たちの生活や経済活動が依存していることが「生態系サービス(ecosystem services)」という言葉で説明され、生物多様性の損失は企業にとってのリスクになるということが日本でも注目されるようになりました。
生物多様性の地球規模の損失の経済的影響を分析するTEEBの最終報告が2010年のCOP10で発表。生態系サービスの価値の認識が広がる(足立) 翌年の2006年に開かれた生物多様性条約締約国会議(COP8)で民間参画決議がなされました。生物多様性を保全するにあたって、国にできることには限界があるので、民間企業を参加させようということになったのです。また、2007年にドイツのポツダムで開かれたG8環境大臣会合では、生物多様性の価値をしっかり測ろうというポツダムイニシアティブが採決され、「生態系と生物多様性の経済学(The Economics of Ecosystems and Biodiversity=TEEB)」の研究が始まりました。2008年にドイツのボンで開かれたCOP9ではTEEBの中間報告が行われ、私たちが自然を破壊し続ければ、莫大な経済的損失を被ることを、具体的な数値で世の中に提示しました。
編集部 2010年に名古屋市で第10回の生物多様性条約締約国会議(COP10)が開かれました。日本でも生態系サービスの価値が広く認識されるようになりましたね。
足立 TEEBの最終報告はCOP10の時に発表されました。生物多様性や生態系サービスの価値という言葉が使われるようになり、TEEBの次の考え方として自然資本という言葉が生物多様性の中で使われ始めました。
この言葉は、非常にわかりやすいものでした。生物多様性の価値といっても、企業人には「大切なのかな?」くらいで終わっていました。しかし、経営にも重要な自然資本であると伝えれば、注目せざるを得ません。自分が使っている資本の大きさを測ろう、1年間事業をやってみて増えたのか減ったのか測定しようという流れになりました。
本当の意味での持続可能な経営というのは言葉でわかっていても具体的にどうするかが難しいのですが、持続可能な経営かどうか確かめる物差しとして、自分たちが自然資本をどのように使っているか定量化することでわかりやすくなります。
編集部 植田先生は自然資本経営という概念を日本で初めて使った経済学者だと谷口さんからご紹介がありました。先生は工学で博士号を取ってから経済学に行かれています。谷口さんがよく「生態学を知らない経済学者はダメだ」とおっしゃっていますが、工学から経済学へたどり着いた経緯をお話しいただけますか。
 植田 和弘 氏
植田 和弘 氏
京都大学大学院 経済学研究科教授
1975年、京都大学卒業。1983年に大阪大学大学院で工学博士号取得。1997年には京都大学で経済学博士号も取得。環境経済学の草分け的存在で、1995年にできた環境経済・政策学会の設立発起人となり、同学会の会長も務めた。2012年、再生エネルギー固定価格買い取り制度の調達価格等算定委員会の委員長を務め、画期的な買い取り制度のレールを敷いた。著書に『緑のエネルギー原論』『廃棄物とリサイクルの経済学~大量廃棄社会は変えられるか』『環境経済学への招待』など多数。
公害問題を知る中から経済に関心を持ちました。技術がないから公害が起きたのではなく、経済、経営的要因が技術の使い方を決めていたのです(植田) 植田 私の出発は日本の公害です。工学部には技術を改善すれば問題は解決するという発想をする人が多いのですが、日本の公害を実際に知ってみると、技術がないから公害が起きたのではなく、簡単なことをやらない、すでにある技術を使わないから公害が起きたといえます。
例えば、鉱山開発を考えた場合、廃水をそのまま流さず工場内の池で一度受ければ、重いものは沈むので上澄みを流すということだけでも、そんなにひどい公害にはなりません。でも、それをやらないのです。技術がないからできないのではなく、技術をどう使うかを決めている要因があって、それは経済や経営ではないかと大学院のころに考えていました。それが、経済問題への関心の直接的なきっかけです。1970年代前半からです。
編集部 1972年にスウェーデン・ストックホルムで国連人間環境会議が開かれ、水俣病患者も参加し、当時の大石武一環境庁長官が「GNP神話よ、さようなら」という演説をしました。乱暴な自然の開発に警鐘が鳴らされ、自然保護の気運も高まり始めていましたが、皮肉なことに、この会議の直後から日本列島改造論による開発の嵐が吹き始めました。自然資本が無限にあるような経済最優先の政策が続けられましたね。
植田 日本では公害の原点といわれる水俣病があり、僕が大学に入学したころは公害が大きな社会問題でした。
生産と消費のことだけ考えていた経済学。最も大事な廃棄のことは考えていませんでした。それが、廃棄物学から経済学の研究に移った理由です(植田) 私は廃棄という行為そのものに関心を持ち、廃棄物問題を研究することになります。ここから経済学をかじるようになるわけですが、経済学のテキストの索引を見ると、生産関数と消費関数の項目はありますが、廃棄関数がありません。生産と消費という経済活動からは必ず廃棄物が排出されます。廃棄できなければ生産も消費もできないのです。廃棄はすべて自然が受け入れてくれることになっていますが、本当は受け入れてくれません。
ケネス・E・ボールディングが『来たるべき宇宙船地球号の経済学』(1966年)で鋭く言っているように、地球は宇宙船地球号のように有限な世界の中で回っているのに、経済学はそういう想定にはなっていません。最も大事な現象がないものとして扱われているのです。
編集部 経済の最上流で資源採掘にあたっていた谷口さんと、最下流で廃棄物の研究をされていた植田さんが、自然資本経営という場所でバッタリ会って、意気投合した感じですね。
植田 経済現象の中で、廃棄物問題も重要ですが、経済的価値、とくにマーケットの価値で切ってしまうと、価格がないものは価値がないことになってしまいます。そこに根本の問題があって経済学そのものを考え直さなければいけないと思って、廃棄物学から経済学に進んでいきました。
経済学は自然対人間をどう考えるかという問題になります。しかし、数式を使って経済法則を分析・解明するのが経済学の一番の役目みたいになっているわけです。一方で、歴史上、古典として残るような著作は、法則だけではなくどうやったら世の中を良くできるかという問題を設定します。法則が人間にとって良いことばかりとは限らないですからね。
ですから、経済の法則を明らかにすることと、どうしたらより良い社会ができるかをあわせて考えていく必要があります。経済学は、経済がどうなるかよりも、社会のために経済をどうするか考えるほうが重要だというのが僕のモットーです。
僕は僕の環境学の師から「廃棄物メガネ」という言葉を教わりました。例えば今いるこのような建物も、最後は廃棄物になる。でも私たちは建造物だと思っている。廃棄物メガネをかけて、将来はどんな廃棄物になるかも考えようというわけです。僕はリサイクルを学んでいましたから「資源メガネ」はどうかと思い至りました。廃棄物でもメガネをかけ替えると資源に見えるんですね。このメガネをかけるという行為はとても重要だと思います。
編集部 多面的にものを見ることによって、まったく違う価値がクローズアップされてくるわけですね。
植田 同じ自然を見たときに、資本と見るということは大きな見方の転換です。同じようなことを言っているのだけど、それを自然資本と見ることによって、価値あるストックであるということがわかります。自然資本経営の「経営」の持っている意味合いをよく考えなければいけないと思います。
谷口 ですから、「natural capital management」ではなくて「natural capital economy」をつくりあげるということです。
編集部 皆さんのお話をうかがっていると、世界が直面している地球温暖化対策を進めるにあたって、二酸化炭素(CO2)を廃棄物と見ると、それを排出する公共空間、つまり自然資本、グローバルコモンズがひどく劣化しているということがわかります。自然資本経営がここでも大切なことがよくわかりました。
新年号なので明るい話題もご紹介いただきたいと思います。
京都大学が「森・里・海連環学」という総合学問、文理融合の学問領域を創設し、「森は海の恋人」運動を続けている宮城県・気仙沼の漁師、畠山重篤氏を教授陣に迎え入れていますね。自然資本経営が実践に移されていると受け止めていいのですか。
植田 環境経済学がどのようなものかと聞かれたときに、もちろんオーソドックスに経済学の方法を環境問題に応用するという考え方があります。これは応用経済学の一部としての環境経済学というわけですが、それはそれで一つの体系ができて、わかりやすくなる面もあります。
京都大学にできた「森・里・海連環学」という統合学問。自然資本経営を考える新しい経済学のベースになる(植田) しかし、自然の持っている総合性を扱えるように経済学そのものが変わっていく必要があると思います。経済学がマーケットを対象とした分析を洗練させてきたことは、一面では経済学の発展ととらえることができますが、一方で大きな総合社会科学的な側面が弱っていくということでもあります。
現実には、森の活動が海にも影響していて、しかもその中には人間の活動も含まれている。それをトータルに扱おうとする「森・海・里連環学」というのは、田中克先生(京都大学名誉教授)の考えた大変うまい名称で、今の学問の方向に対する警鐘でもあると同時に、単なる警鐘ではなくて、それに代わるものを何か見つけ出そうとする考えもあって、自然資本経営を考える上でのベースになると思います。
世界銀行が生態系サービスの経済的価値評価のプロジェクトを実施(足立) 足立 よく、自然が身近すぎるとその価値がわからないという話があります。マレーシアに行った時にショックだったのは、ごみをポイポイと皆さん捨てることです。ちょっと前までは、捨てるゴミというのは、例えば、バナナの葉だったり、フルーツの殻だったり、捨てても自然が吸収し、循環していました。しかし今のごみは、プラスチックや金属だったり自然のサイクルでは循環し得ないものになっているので、問題になるのです。森がたくさんあるところに住んでいる人ほど昔とおなじようにやってしまいます。
一方、自然資本経営という考え方についてヨーロッパが日本より進んでいるとしたら、それはより危機感があるからだと思います。ヨーロッパでは国境を越えて公害が来てしまうような越境汚染があって、自分たちの国土だけではなく、周囲国を含めてきちんと解決していかなければならない。言葉も考え方も違う人たちと問題を解決していく必要性から、きちんと定量化して、ロジックに落とし込むということにヨーロッパは長けている気がします。
世界銀行(世銀)の「生態系サービスの経済的価値評価(WAVES)」というプロジェクトが始まり、2015年には結果が公表されます。これから皆さんの意識が大きく変わるかもしれません。今まで、途上国は先進国に比べて経済的に貧しいと誰もが思っていましたが、これからはどれだけ自然資本を持っているかという点で見ると、途上国の方がはるかに豊かな資本を持っているといえます。
投資家のためのリスクヘッジになりかねない欧米の取り組み。われわれの自然資本経営とは 根本的に違う考え方(谷口) 谷口 私は世銀などの取り組みに懐疑的です。いろいろと作っていますが、WAVESにしろ、自然資本宣言(2012年に開かれた国連持続可能な開発会議で採択され、金融機関等に意思決定のプロセスに自然資本の考え方を取り入れるように求めた宣言)にしろ、世銀と民間の金融機関数百社が関わっていますが、結局、自然資本の破壊を企業や地域のリスクとしてとらえ、投資家に対するリスクヘッジのために経営をしろということになると、本来の自然資本経営を矮小化する恐れもあります。
確かに優秀な人材が関わり、いったん決めた融資を自然破壊がひどいとして引き揚げた例もありますが、金融機関主導のリスク回避という面があり、私たちの考える自然資本経営とは根本的なとらえ方の違いがあります。
編集部 ありがとうございました。次回では、世界の動向とともに日本の役割についてお話しいただきます。(次号につづく)