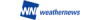地球温暖化で日本茶への影響は? 京都・宇治茶に何が起きている?
2025/05/08 05:11 ウェザーニュース
ゴールデンウィークは暑さ対策が必要なほどの夏日から始まり、後半は日本付近を周期的に前線が通過して曇りや雨の日もありました。
立春から88日目に当たる八十八夜は茶摘みの目安で、これから新茶のシーズンとなります。海外でも年々人気が高まっている日本茶ですが、気がかりな情報もあります。日本を代表する茶産地の一つ京都・宇治で、凍霜害(とうそうがい)が増えているというのです。
凍霜害は、寒の戻りで茶の新芽が不良になってしまうもの。京都気候変動適応センターの安成哲三センター長は、「近年進んでいる全般的な気候の温暖化のなかで、なぜ凍霜害が増えているのか」について調査研究を行いました。
一番茶に被害をもたらす凍霜害
日本茶の栽培は、奈良〜平安時代初期にかけて中国に学んだ僧らが種子を持ち帰ったのが始まりとされています。茶葉を採るチャノキは亜熱帯性植物ですが日本の自然条件に合い、東北から沖縄までが栽培地域となっています。
京都は日本で最も古くから栽培が行われきた地域です。雨が比較的多く、土壌の水はけがよいなど条件に恵まれており、高品質な日本茶の生産地として知られています。宇治茶のなかでも香りやうま味が強くおいしいとされるのが、その年最初の摘み取りによる一番茶です。
ところが、近年宇治の一番茶に凍霜害が起きるようになってきました。凍霜害とは、新芽が低温により凍結したり霜で枯死したりするもので、一番茶の減収や品質低下につながります。
日本茶の名産地、宇治でひどい凍霜害が
今回の日本茶の凍霜害研究のきっかけとなったのが、2021年4月10日に発現した宇治での凍霜害でした。

「2021年7月の京都気候変動適応センター設立の際に、京都府・京都市地域で、どのような気候変動の影響があるかを農林水産業、生態系、都市域など、広くヒアリングを行うなか宇治のひどい凍霜害の報告があったのです。
京都府茶業研究所(以下、京都茶研)の研究者から『このような近年、凍霜害が増加しているようだ』というコメントがあり、調査研究を開始しました」(安成先生)
凍霜害のあった日、宇治では何が起きていたのでしょうか。
「2021年4月10日の宇治市の最低気温は-0.8℃。平年値より数度低く、4月で最も低温の日でした。
この日は日本列島全体が大きな移動性高気圧に覆われ、宇治市は晴天でした。夜間に放射冷却が起こり、さらに寒気団が北極海からカムチャツカ半島・オホーツク海方面を経て日本列島付近に南下しており、寒気が流入して『季節外れの強い低温』になったと考えられます」(安成先生)

「興味深かったのは、3月〜4月5日頃まで、高温傾向がひと月以上にわたって続いていたことです」(安成先生)
春は一番茶にとって非常に重要な、新芽が出る「萌芽期(ほうがき)」です。また、凍霜害は新芽が出た状態で、耐凍温度を下回って起きるものです。
そこで、過去にさかのぼって一番茶の萌芽期、凍霜害記録、その時の気象状況との関係を調べました。
凍霜害の気象条件とは
「萌芽期のデータもある1987〜2021年の36年間で、3月の月平均気温と4月の萌芽期の日付の関係を調べたところ、3月の平均気温が高いと、4月の萌芽期は早くなることがわかりました。特に3月の平均気温が8℃以上の時に、8℃未満の時に比べ、萌芽期が平均的に6日程度早くなります」(安成先生)
では、3月、4月の気温は変化しているのでしょうか。

「京都茶研での1969年〜2021年までの53年間の気温変化をみると、3月は気温が長期的にはっきり上昇している一方で、4月には変動傾向はみられませんでした。
凍霜害を引き起こす可能性が非常に高い、日最低気温が0℃未満になった日の頻度(ひんど)をみると、2〜3年に1回度程度、4月前半に1〜4回程度出現しています。
3月の暖かさで新芽の成長が促されて4月上旬に萌芽期が集中し、4月に0℃未満の『低温日』が発現すると、高い確率で凍霜害になると考えられます」(安成先生)
変化は“気候変動”によるものか?
これらの変化が、偶然が重なって起きたものなのか、それとも気候変動の影響なのかという疑問が残ります。
「京都茶研での3月の平均気温は、1990年頃からはっきり上昇していましたが、気象庁による日本全域の3月の平均気温も、1990年頃から明らかな上昇傾向を示しています。一方、日本全域の4月の平均気温は、上昇傾向はあるものの、月ごとにみた昇温率は1年の中でも最も小さいことが示されています。
また、京都茶研の日最低気温と、上空約1500mの気温(※)の長期変化を分析したところ、3〜4月の日最低気温の長期傾向はほぼ同様、あるいはより顕著に現れていました。
近年の気候温暖化にともなって、日本付近で特異的な季節変化が起きている可能性も強く示唆(しさ)されました」(安成先生)
※ヨーロッパ中期気象予報センター(ECMWF)の全球客観解析気象データ(ERA5)による京都府茶業研究所に最も近い格子点での850Paの気温
温暖化がもたらす影響を考える
「この調査研究によって、1990年以降の温暖化により、3月は気温の上昇が顕著(けんちょ)な一方、4月はむしろ下降傾向で、凍霜害が発現しやすい状況となっていることがわかりました。
しかも、これはこの地域特有の気象現象でなく、近年の気候温暖化による日本列島付近の大気循環の季節進行の特異な変化と関係していると考えられます」(安成先生)
温暖化の影響は茶栽培に限っても、病害虫の発生時期がずれて予防が困難になったり、夏季に高温・少雨となって生育が悪くなるなど、さまざまなリスクを生むとされています。
「地球温暖化に伴い、冬の寒さや夏の暑さがどう変わるかという視点の研究は非常に多くなされていますが、気温の季節推移(進行)がどう変化しているか、そのメカニズムは何か、という問題がこれまでほとんど研究されていないことも明らかになりました。
特に農業への影響を考えると、この問題は非常に重要です。今後さらにこの研究を進めていきます」(安成先生)
ウェザーニュースでは、気象情報会社の立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、皆さんと一緒に地球の未来を考えていきます。
参考資料
安成哲三ら「京都府宇治市における近年の茶の凍霜害の発現傾向と気候温暖化の関係」(日本茶業学会誌『茶業研究報告』第138号[2024年12月])にもとづく発表資料
あわせて読みたい
-

- 冷えやむくみに効果的? ふくらはぎをマッサージして全身の血流を良くしたい!
- 1. 床にあおむけになって片ひざを立てる。そのひざの上に反対側のふくらはぎの中心付近をのせる。 / (C)…
- (レタスクラブニュース)[スローライフ]
-

- 反則級のおしゃれサンダルで夏を迎えちゃおう‼【キーン】のサンダルがAmazonで売り出し中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[自然化粧品]
-

- ウェスティンホテル大阪でメロンアフタヌーンティー 半玉使うメロンパフェも
- ウェスティンホテル大阪(大阪市北区大淀中1)1階ロビーラウンジで5月7日、「メロンアフタヌーンティー」…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お茶]
-

- 「低投入、内部循環、自然共生」をモットーに、循環型農業とゼロ・ウェイストに取り組むローカルスーパーマーケット「渥美フーズ」
- 愛知県の渥美半島を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社渥美フーズ。地域環境に配慮した「ゼロ・…
- (Walkerplus)[農業]
-

- 朝4時に目撃した富裕層たちの行動とは? 早起きの”先取り”がもたらす「成功への道」
- 活動するのは朝がいちばんいい――。元ゴールドマン・サックス マネージング・ディレクターの田中渓氏が熟知…
- (All About)[生物多様性]
-

- 八戸の商業施設「エルロン」が1周年 「ちぃたん」によるパフォーマンスも
- 八戸駅西地区の複合商業施設「エルロン・ウエスト・ビレッジ」(八戸市尻内町)の開業1周年を祝うイベント…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[気候変動]
-

- 春日部の個人宅のバラ270種が見頃 咲き誇るバラに涙ぐむ来訪者も
- 春日部市藤塚の個人宅のバラ庭園が現在、見頃を迎えている。(春日部経済新聞) 【写真】5月8日時点のオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[植物]
-

- 9日(金)〜10日(土)は警報級の大雨や暴風のおそれ 来週は一気に夏の暑さ
- 明日9日(金)は、西から雨の範囲が広がり、西日本では警報級の暴風や大雨のおそれ。10日(土)は、関東など東…
- (tenki.jp)[気象]
-

- 渋谷の老舗「珈琲店トップ」道玄坂店が閉店へ 53年の歴史に幕
- 渋谷で創業し、75年以上にわたり営業を続ける老舗カフェ「珈琲(コーヒー)店トップ」の「道玄坂店」(渋…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[地球温暖化]
-

- 京丹後の料理教室「タベルテーブル」が移転 海外観光客に日本料理教える
- 料理教室&カフェ「tabel table(タベルテーブル)」(京丹後大宮町上常吉)が4月28日、移転を知らせるお…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[京都府]
-

- 明日は九州など非常に激しい雨 風も強まる予想 明後日は東日本で強雨に
- 2025/05/08 17:05 ウェザーニュース明日9日(金)は低気圧や前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込…
- (ウェザーニューズ)[ウェザーニュース]
キーワードからさがす
Copyright (c) 2025 Weathernews Inc. All Rights Reserved.