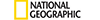「緑のgoo」は2025年6月17日(火)をもちましてサービスを終了いたします。
これまで長きにわたりご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
ペンギンの糞でオキアミの急旋回が通常の3倍に、研究

オキアミは南極海のポップコーンシュリンプだ。クジラからアザラシ、魚類、ペンギンまで、誰もが食べたがる。しかし、最新の研究によれば、小指ほどしかないこの半透明な甲殻類は、それほど無力な存在ではないようだ。
野生のナンキョクオキアミ(Euphausia superba)を水槽に入れて、アデリーペンギン(Pygoscelis adeliae)の糞を流し入れたところ、オキアミは通常より速く泳ぎ、より大きな角度で3倍多く方向転換することが明らかになった。論文は3月20日付けで学術誌「Frontiers in Marine Science」に発表された。
「彼らが回避行動をとっていることはすぐにわかりました」と、論文の筆頭著者で、オーストラリア、タスマニア大学の南極海洋科学者のニコル・ヘレシー氏は振り返る。「彼らはジグザグに泳ぎ始めました」
ときにはオキアミが全く泳がなくなり、水槽の反対側まで流されてしまうこともあった。流れに乗れば、捕食者から遠ざかることができる場合、エネルギーを節約できるとヘレシー氏は指摘する。
興味深いことに、ペンギンの糞があると、オキアミは食欲を失うようで、摂食の効率が通常の条件下より64%低下した。
南極周辺の海域にはナンキョクオキアミの成体が700兆匹も生息しており、今回の発見は、一帯の食物網に関する理解に大きな影響を与える可能性がある。ペンギンやクジラといったカリスマ性のある大型動物が注目されがちだが、南極の生きものすべてを結び付けているのがオキアミだとヘレシー氏は強調する。
アデリーペンギンから逃げる
オキアミには多くの捕食者がいるため、状況に応じて異なる回避行動が必要になると思われる。
オキアミと聞いたら、ピンク色の巨大な雲のような群れを思い浮かべるかもしれない。しかし、オキアミは単独で泳ぐこともある。どちらの状況にも、それぞれのリスクがある。
ザトウクジラやシロナガスクジラはオキアミの巨大な群れを狙う。最もコストパフォーマンスが高いからだ。一方、オキアミは数によって身の安全を確保している。
「(辛うじて)逃げ延びるオキアミもいるはずです」とヘネシー氏は話す。
次ページ:オキアミの行動から学べること
しかし、オキアミが水中でペンギンの糞を感知できるとわかったことは、ある大きな謎の答えを示唆している。ペンギンの糞が海に流れ込むと、オキアミの好物である藻類ブルームが引き起こされるにもかかわらず、オキアミがペンギンの大きなコロニーに近づかないのはそのためかもしれない。
オキアミが避ける緩衝地帯の存在は、捕食者が近くにいることをわかっているさらなる証拠となる。
「(オキアミが)どこに生息し、どれくらい陸に近づけるかに大きな影響を与えます」とヘネシー氏は話す。
ヘネシー氏によれば、ペンギンも気候変動の影響で、新しい地域に移動したり、通常より長く同じ地域にとどまったりしているという。ペンギンがいるとオキアミが食べる餌が減るなら、ペンギンのこうした変化はオキアミに悪影響を及ぼす可能性がある。
オキアミの行動から学べること
米オレゴン州立大学の海洋生態学者で、ナショナル ジオグラフィックのエクスプローラー(探求者)でもあるキム・バーナード氏は、この研究は興味深いとしながらも、ペンギンの糞に対するオキアミの反応が生態系に広く影響を引き起こすかどうかについては確信していない。
「広範な影響を引き起こすには、オキアミの生息域の大部分で常に、ペンギンの糞が高濃度で存在する必要があります。ですが、ペンギンの糞はコロニーの近くに集中しているため、その可能性は低いと思います」とバーナード氏は話す。「また、オキアミは長い間、ペンギンに対処しています」。なお、氏は今回の研究に参加していない。
バーナード氏はその一方で、今回の研究は捕食者の手掛かりとオキアミの行動の関連性についていくつかの洞察を提供していると述べている。
「生態学の理論である『恐れの景観』が思い浮かびます。種が直接的な捕食に反応するだけでなく、捕食のリスクにも反応して行動を変えることで、恐怖によって形づくられる目に見えない生態系の構造のようなものです」
一方、ヘレシー氏は、オキアミがアザラシやクジラといったほかの捕食者の糞にどう反応するかを調べ、今回の発見をさらに発展させていきたいと考えている。また、オキアミの回避行動を引き起こす下限があるかどうかを確かめるため、糞の濃度を変えて実験を行うことも考えている。
結局のところ、この小さくも重要な生物について学ぶべきことがまだたくさんあることは明らかだ。
「大きなもの、かわいいもの、ふわふわなものほど注目を集めないかもしれませんが、海にはたくさんの生きものがいます」とヘレシー氏は語る。「(オキアミの)研究も同じくらい重要です。なぜなら、彼らがいなければ、かわいいペンギンやアザラシも存在できないためです」
あわせて読みたい
-

- 大腸がんとも関連、不足がちなビタミンDを適切に補うには、研究
- 大腸がんとも関連、不足がちなビタミンDを適切に補うには、研究 ビタミンDは健康に欠かせない栄養素だ。骨…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 混ぜて焼くだけ!【マフィン】家にある材料ですぐに作れる
- マフィン / (C)Satoru/KADOKAWA管理栄養士、学術博士であり、また3人のお子さんのお父さんでもあるSatoru…
- (レタスクラブニュース)[健康食材]
-

- たまごっちが進化!待望の新作「Tamagotchi Paradise」が新登場
- 2025年7月12日(土)、バンダイ トイ事業部から、1996年に発売され累計出荷数9810万個(2025年3月時点)を突破…
- (Walkerplus)[生物多様性]
-

- 岐阜県飛騨地方でM4.5の地震 高山市で震度4 津波の心配なし
- 岐阜県飛騨地方でM4.5の地震 高山市で震度4 津波の心配なし2025/05/29 15:36 ウェザーニュース5月29日(木)…
- (ウェザーニューズ)[気候変動]
-

- 女性は定年後どんな生き方をすべき? ロールモデル不在の悩み
- 女性は定年後どんな生き方をすべき? / (C)りさねーぜ/KADOKAWA「年齢を重ねるのが怖い」「ひとりは寂…
- (レタスクラブニュース)[動物]
-

- 「松本市景観賞」募集 身近な「お気に入りの場所」気軽に応募を
- 松本市は現在、魅力ある地域の景観に貢献している建築物や広告物、市民活動を表彰する「第36回松本市景観…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[地球温暖化]
-

- 苦しい節約をやめて、メリハリのある適度な節約を目指すには?
- 節約生活をはじめる際、ただやみくもに我慢ばかりすると、ストレスが溜まり逆効果を招くことがあります。…
- (All About)[省エネ]
-

- AIは電力食い。5年後には日本の電力消費量をぶっちぎる
- AIは電力食い。5年後には日本の電力消費量をぶっちぎるImage: IMF|EA、OPEC、IMFの試算。2030年にはAIデ…
- (Gizmodo Japan)[エネルギー(ぼんやり学会)]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社