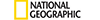「孤独な食事」は健康も幸福も蝕む、日本は最低レベルの孤食国

国連や米調査会社ギャラップなどがまとめた2025年版の「世界幸福度報告書(World Happiness Report)」によると、誰かと一緒に食事をとること(共食)は、幸福度の指標として、所得や雇用状態に匹敵するほど強力だという。
地中海、ラテンアメリカ、東南アジアといった地域では、料理の内容こそ違えど、「テーブルを囲んで食事を分かち合う」という習慣が文化に深く根付いており、まるで神聖な儀式のように大切にされている。人々は共に食事をし、皿は思いやりを持って手渡され、全員が食べ終わるまで誰ひとり席を立つことはない。
一方、世界では、皆で食卓を囲むことが珍しい行為になりつつある地域もある。昼食にまるまる1時間かけると言えば奇異な目で見られ、一緒にきちんとした食事をとるといった基本的な行為でさえ、贅沢として一蹴されてしまう。われわれの幸福に欠かせないはずの習慣が、これほど簡単に切り捨てられてしまったのはなぜなのだろうか。
食卓を囲む習慣、世界ではどうなっている?
報告書によれば、米国では4人に1人がすべての食事を1人でとっており、その割合は2003年以降、53%増えている。誰かと一緒に食事をする頻度のランキングでは、142の国と地域のうち米国は69位、英国は81位だ(編注:日本は133位)。
一方、セネガル、ガンビア、マレーシア、パラグアイといった国々は世界ランキングのトップを占めており、平均すると彼らは週に11回以上の食事を誰かと一緒にとっている(編注:日本は3.7回)。
誰かと一緒に食事をする割合が高い国の人々はまた、社会的に強く支えられていると感じ、孤独感が弱い傾向にある。この結果が示唆しているのは、社会の工業化が進み、共に食事をする機会が減っているのは、単なる生活習慣の変化ではなく、以下に述べるように公衆衛生上の懸念でもあるということだ。
脳への影響
2017年に学術誌「Adaptive Human Behavior and Physiology」に掲載された研究では、人と一緒に食事をとることが、脳内のエンドルフィン系を刺激することが示唆されている。この経路は、絆や信頼などに関わる神経化学物質であるオキシトシンやドーパミンと密接に関連している。食卓を共に囲むことは、会話と同じくらい、人と人とのつながりにとって極めて重要な行為であるようだ。
次ページ:孤独な食事で失われるもの
2024年に学術誌「Frontiers in Public Health」に掲載された研究によると、人と一緒に食事をする経験は、高齢者の孤独感や悲しみ、感情的な苦痛を軽くし、精神的な充足感の向上に役立つ可能性があるという。
2023年に学術誌「Clinical Nutrition」に掲載された研究では、定期的に人と一緒に食事をする青少年は、独りで食事をする同年代と比べて、ストレス、不安、抑うつの症状が少ないことが明らかになっている。
誰かと一緒に食事をすることは感情面の支えとなり、精神衛生上の困難を和らげる心地よい空間も提供すると、研究者は結論付けている。
もし、誰かと一緒に食事をすることが、現代にはびこる孤独に対抗する最も手軽で安価な解決策のひとつであるなら、その習慣を復活させる試みは、単なる懐古主義ではなく、今まさに必要とされていることだと言えるだろう。
孤独な食事で失われるもの
独りで食事をすることで、われわれは何を失うおそれがあるのか。その質問に、米ボストン大学の食文化学プログラムの責任者を務めるミーガン・エリアス氏は、会話の重要性を強調する。
「食事をしながら感覚的な経験を共有することで、われわれは他人をより“リアル”に感じるようになります」と氏は言う。エリアス氏が「日常生活の接着剤」と呼ぶそうした日々の交流が失われると、人は感情的にも社会的にもつながりを失うリスクを抱える。
誰かと一緒に食事をすることはまた、社会的なつながりの深さを測るいくつかの指標と密接に関係しているようだ。特筆すべきは、人と一緒に食事をする機会の多い国々では、社会的な支援やポジティブな助け合いのレベルが高く、孤独感のレベルは低いという事実だ。
たとえば、トルコには「ラク・ソフラス(ラクのテーブル)」という文化があり、人々は小皿料理を囲んで笑い合い、何時間にもわたって会話を楽しむ(ラクはブドウとアニスでつくる蒸留酒)。
同様にイタリアでは、日曜日に半日を費やしてゆったりと昼食をとり、一緒にパスタやロースト料理を味わう家庭が少なくない。ギリシャ各地のタベルナ(小さなレストラン)では、人々が一緒にメゼ(小皿料理)を囲むことで、互いに親近感を深めていく。
次ページ:一緒に食事をする習慣を復活させるには
このように、一緒に食事をすることで社会的な絆を強める行為を、人類学者たちは「コメンサリティー」と呼んでいる。上記のような地中海地域においては、もてなしそのものが癒やしの実践であり、食卓が孤独に対する自然の解毒剤となっている。
「食事や、食事を分かち合う行為は、個人としてもコミュニティーの一員としても、自身のアイデンティティーを築くうえで非常に重要な要素です」と、米ニューヨーク大学で食文化学を教えるファビオ・パラセコリ氏は言う。
「そうした帰属意識が欠落していると、その影響は感情面に表れます。物理的に誰かと一緒に食事をする行為は、自分は何者かを定義するうえで欠かせない要素なのです」
一緒に食事をする習慣を復活させるには
孤独を感じる人々が増えつつある中、誰かと一緒に食事をする習慣を日常に取り戻すには、どうすればよいのだろうか。
都市計画の専門家らは、集合住宅に共用のキッチンや食堂を設けることを提案する。また一部の政府機関では、高齢者と若者をつなぐための食事を基本としたプログラムに資金を提供している。
介護施設では、食事を独りではなく共同でとるやり方が取り入れられており、高齢者のメンタルヘルス、食欲、認知機能の改善のほか、孤独感の緩和や帰属意識の向上にもつながっているという研究もある。さらには、夕食を一緒にとるためのクラブやその仕組みなど、家庭料理を通じて見知らぬ人同士をつなぐ草の根的な取り組みも行われている。
こうした現代的な集まりは、形式こそさまざまだが、共通するメッセージがある。それは、食卓は今もなお、人と人とをつなぐ最もシンプルかつ力強い手段のひとつだということだ。
あわせて読みたい
-

- ローマ教皇埋葬の2000年の歴史、中世には「死体裁判」も
- ローマ教皇埋葬の2000年の歴史、中世には「死体裁判」も「永遠の都」と呼ばれる、イタリアの都市ローマ。…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 美しさと実用性が共演。【オリエント】の腕時計が生み出す圧倒的な満足感を、あなたの腕元で体感しよう!Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[自然化粧品]
-

- コーヒーで旅する日本/九州編|一息つくこと、立ち止まることの大切さを教えてくれる。「Cafe 一雨」にある余白
- 全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャ…
- (Walkerplus)[健康食材]
-

- 通勤もアウトドアも一つで完結。【ザノースフェイス】の高機能バッグが“ちょうどいい”を叶える新定番!Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[アウトドアグッズ]
-

- 関東は雨が降りやすい一日 昼間も気温上がらず
- 2025/05/19 07:11 ウェザーニュース今日19日(月)の関東は異なる方向の風の衝突によって発生した雲が広がり…
- (ウェザーニューズ)[海]
-

- 「母の日」に徳之島町地域女性連大運動会 9チーム対抗、笑顔絶えず
- 第51回徳之島町地域女性連大運動会」が「母の日」の5月11日、徳之島町勤労者体育センター(徳之島町亀津)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ボランティア]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社