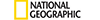ホホジロザメが消えた海、いったい何が起こったのか? 最新研究

魚雷のような体、6センチほどもある歯。世界最大の捕食サメは、とてつもなく恐ろしい姿をしている。あまりに恐ろしいので、ホホジロザメ(Carcharodon carcharias)のいない海を望む人もいるだろう。だが、3月25日付けで学術誌「Frontiers in Marine Science」で発表された論文で、このサメが消えた海に起こったことが明かになった。
南アフリカのフォールス湾に浮かぶシール島の周辺は、かつてホホジロザメのホットスポットだった。サメが水面まで出てきて獲物をつかまえる様子を見られるという、地球上でも数少ない場所のひとつだった。
「まるで『ジョーズ』です」。論文の筆頭著者で、シャーク・リサーチ・ファンデーション社の重役を務める海洋生態学者のニール・ハマーシュラーク氏はそう話す。「900キロのホホジロザメが、オットセイをくわえて水面から飛び上がるのです。こんな姿はほかでは見たことがありません」
ところが、そのサメがまったく姿を現さなくなった。研究者や保護活動家はシャチの侵入や人間が原因ではないかと考えた。だが、ハマーシュラーク氏らが2000年から島の周辺の生態系を調査していたおかげで、いくつかの驚くべき変化に気づくことができた。
ホホジロザメを見るならここしかない
ハマーシュラーク氏によると、20年前のシール島は「ホホジロザメを見るならここしかない」という場所だった。しかし、フォールス湾のホホジロザメは2010年ごろから減り始め、2015年以降に激減したのち、2018年に姿を消した。
ホホジロザメがいなくなった厳密な理由は謎のままだ。「この点については、まだ議論が続いています」と話すのは、サメを専門とする生物学者で、米マサチューセッツ州の海洋漁業部門に所属するグレッグ・スコマル氏だ。同氏は前述の研究には関与していない。
シャチが侵入してきたので逃げていったという説もある。シャチは数分でホホジロザメを狩り、栄養が豊富な肝臓を切り出すことができる。
次ページ:予想すらしなかったことを目の当たりに
ハマーシュラーク氏は、人間にも責任がありそうだと考えている。サメ捕獲ネットによって、年に25頭から30頭のホホジロザメが死んでいるからだ。
ホホジロザメが成熟するまでに、オスは20歳以上、メスは30歳以上と長い時間がかかるので、たとえ数頭の減少でも総数に大きく影響しかねない。ちなみに、一度に最大12頭ほどの子どもが生まれる。
予想すらしなかったことを目の当たりに
サメには、弱った動物や病気になった動物を取り除いて食物連鎖のバランスを保ち、海の環境の健全性を維持する役割があると考えられている。しかし、実際の環境でその効果を証明するのは難しい。
「こういった生態系への影響を解明するには、長期にわたるデータが必要になります。つまり、とても難しいのです」とスコマル氏は言う。
ハマーシュラーク氏らは、エコツーリズム企業と提携し、年間200日以上を完全にフォールス湾上で過ごせる環境を整えていた。そのうえで、ホホジロザメがいなくなる前、いなくなる過程、そしていなくなった後を網羅した20年分以上のデータを集めた。
「予想すらしなかったことを目の当たりにしました」と、ハマーシュラーク氏は述べる。
突然エビスザメ(Notorynchus cepedianus)が現れ、ときに1日15頭も観測されるようになった。通常、このサメはホホジロザメから身を隠すため、数キロ先の藻場にひそんでいる。「まったく見られなかったものが、2桁になりました。これには驚きました」
ミナミアフリカオットセイ(Arctocephalus pusillus)も増えた。サメに襲われる危険がなくなり、ケージダイビング体験者からエサをもらおうと、集団で浮かぶラフティングをすることが多くなった。「数年前なら、これは自殺行為でした」
オットセイもエビスザメもホホジロザメの獲物だったので、数が増えるのは当然だろう。たがハマーシュラーク氏らは、オットセイやエビスザメが食べる動物の数が変化したかどうかまで調べようとした。
次ページ:消えたホットスポット、これからどうなるのか
幸いにも、2012年に科学者のローレン・デボス氏が、別の研究のために魚の数を調べるカメラを設置していたことがわかった。ハマーシュラーク氏は同じ装置を借り、同じ手法で調査した。すると予想どおり、イワシやアジといったオットセイのエサ、ホシザメやタテスジトラザメといったエビスザメのエサは減っていた。
ホホジロザメが消え、その獲物が増え、さらにその獲物が減少するというジグザグな効果から浮かび上がるのは、汚染や開発といった問題が原因ではない可能性だ。
「生息環境が破壊されているなら、すべての数が減るはずです」とハマーシュラーク氏は言う。研究結果はそれとは違い、一部が減って一部が増えていた。
フォールス湾は狭く、存在する種の数もかなり少ないので、食物連鎖の影響を把握しやすかった。「ハマーシュラーク氏は、何が何を食べるかを知っているので、そのつながりを明らかにできたのです」とスコマル氏は言う。
生態系内の種の数が多いほど、ある動物がいなくなったときの影響を突きとめるのは難しくなる。たとえば、北米のメーン湾には数百種の動物が生息しているので、動物間の関係を突きとめるのは、はるかに難しい。
消えたホットスポット、これからどうなるのか
この変化の結果として起こりうるのは、オットセイやエビスザメの食べものがなくなることだ。すると現状の生態系は崩壊してしまうのだろうか? それはまだわからない。スコマル氏は、「その点が次の疑問になります。オットセイの数は多すぎるのでしょうか?」と言う。
シール島周辺で水面から飛び上がるホホジロザメは、もう過去のものだ。「ここにたくさんのホホジロザメがいたなんて、誰にもわからないでしょう」。ハマーシュラーク氏はそう述べる。
ハマーシュラーク氏は、生態系全体の変化を目の当たりにしたことで、サメの保護と、サメに安全な形で海水浴客を守ることの重要性を再認識している。
「シャチの行動を変えることはできませんが、捕獲ネットという旧式の方法を手放すことはできるのです」
あわせて読みたい
-

- 科学が教える「長生きのルール」7選、健康寿命で5年以上の差も
- 科学が教える「長生きのルール」7選、健康寿命で5年以上の差も 人間は昔から長寿に執着し、死から逃れよう…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 台北の夜市だけではない、台湾で訪れたい景勝地5選
- 台北の夜市だけではない、台湾で訪れたい景勝地5選 台湾への旅を、台北を訪れて、濃密な夜市やシロップの…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[海遊び]
-

- 絶品湯葉丼と南山梨の名産が詰まった「こしべんと」。宿坊&道の駅で山梨を味わう旅へ出かけよう
- 青い空と美しい山、澄んだ空気も旅の“ごちそう”に彩りを与えてくれる。 山に囲まれ、清流を抱く山梨。県南…
- (CREA WEB)[川遊び・沢遊び]
-

- ワッフルもクッキーも!発酵性食物繊維がおいしく超手軽に摂れる「Fibee(ファイビー)」が魅力的
- 発酵性食物繊維で腸ハッピー!Fibee(ファイビー)Fibee(ファイビー)ってご存知ですか?お酢や味…
- (レタスクラブニュース)[夏グルメ]
-

- ビーチの貝殻、持って帰らないで
- ビーチの貝殻、持って帰らないでImage: Shutterstock 2024年5月26日の記事を編集して再掲載しています。 …
- (Gizmodo Japan)[漁業]
-

- 「毎日21時に15分勉強」誰でもできる? 富裕層の成功を支える「習慣化」のメリット
- 習慣化してとにかく行動に移す――。元ゴールドマン・サックス マネージング・ディレクターの田中渓氏が熟知…
- (All About)[生物多様性]
-

- スヌーピーデザインの夏も快適に過ごせるゆったりパジャマが「ベルメゾン」から発売中!
- ゴールデンウィークも過ぎ、初夏の陽気が続く今日このごろ。朝晩はひんやりする日もあるけれど、そろそろ…
- (Walkerplus)[自然]
-

- 温湿度・照度感知&オートメーションで快適な暮らしを実現【スイッチボット】のスマートリモコンがAmazonに登場中‼
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[動物]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社