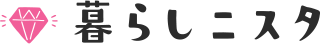「歳だから」と片づけると危険!気力がわかない、夜眠れない…。5月に増える「見えない不調」とは?
天候がよくなってきたこの時期は、いつも通りに過ごしているはずがなぜか憂鬱な気分になったり、新年度になって気合を入れていた家族が落ち込んでいる様子を見て心配したりと、五月病に振り回されやすい時期でもあります。
五月病の主な原因やなりやすい人の特徴、そして症状を放置するリスクを薬剤師の山形ゆかりさんに教えていただきました。自分や家族が春を楽しく過ごすための参考にしてください!
五月病とは
五月病の主な原因や症状、かかりやすい人や放置するリスクを紹介します。この時期に体調を崩しがちな人はチェックしてください。
主な原因と症状
五月病の主な原因は自律神経のバランスが崩れることです。年度が変わると就職や進学、異動などの環境の変化が起こりがち。そういった変化に対応するストレスによって、自律神経のバランスが崩れてしまいます。
自律神経のバランスが崩れると、食欲不振やイライラ、不眠などの症状が起きるようになります。五月病は厳密には医学的に定義された言葉ではありませんが、症状が重くて日常生活に支障が出る場合は心療内科もしくは精神科を受診してくださいね。
注意!なりやすい人の特徴
以下のような特徴を持つ人は、五月病になりやすいとされています。
・完璧主義
・周りに悩みを相談するのが苦手
・環境の変化でストレスを抱えやすい
自分もしくは家族にこのような性格の人がいる場合、環境の変化が多い時期は注意しましょう。
放置するリスク
「五月病」といわれていても、5月が終わり6月になれば自然と症状が治まるわけではありません。五月病を放置すると自律神経のバランスが崩れたままになり、自律神経失調症や適応障害を発症する可能性があります。五月病の症状が重い場合、放置せずに今から紹介する対策を試してください。
五月を乗り切るおすすめの対策

心療内科に行きたいけど、ちょっと抵抗がある、あるいは予約待ちで受診できるのは夏頃――という場合、まずはセルフケアをしましょう。周りの人に悩みを相談したり、軽い運動で気分転換をして寝つきをよくしたりするのがおすすめです。
体質からの根本改善を得意とする漢方薬の服用で、心身のバランスを整えるのもいいでしょう。
・不安や落ち込み、イライラを解消する「加味逍遙散(かみしょうようさん)」
・精神不安や不眠を改善する「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」
の服用という選択肢もあります。
監修/山形ゆかり●薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ。
あわせて読みたい
-

- Pixelを買ったら「まずやっておきたい」8つの設定
- Pixelを買ったら「まずやっておきたい」8つの設定Photo: 小野寺しんいち 新たなスマホの定番として人気を…
- (Gizmodo Japan)[自然化粧品]
-

- 【いて座】2025年5月の運勢! 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
- 2025年5月の12星座別占い。「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルで人気の気学風水鑑定家・生田目浩美.…
- (All About)[健康食材]
-
- 【100均】大きい計量カップ…ではありません!光熱費の節約にもなる意外な使い道に「なるほど~」。おひとり様にも嬉しいアイテムです!
- 100均を調査し、掘り出し物を見つける企画「100均パトロール」。今回は、ありそうでなかった便利なキッチ…
- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.