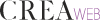「ライオンに嚙みつかれたシマウマは“恍惚”の表情を…」旭山動物園を日本一にした獣医師・小菅正夫が“死にゆく動物”を見て気づいたこと

動物本来の動きを見せる「行動展示」で、旭山動物園を一躍日本一にした元園長・小菅正夫さんが、10年ぶりとなる単著『聴診器からきこえる 動物と老いとケアのはなし』を書き下ろしました。
動物の看取りや余生、延命治療など、これまであまり語られることのなかった“動物園の裏側”を交えながら、動物の生死やQOL、高齢化する動物園の動物福祉について考えぬいた一冊です。
「動物から学ぶことはたくさんある」と小菅さんは語ります。「生きがいがわからず将来が不安」、「仕事や人間関係で悩んでいる」。という人は動物たちからヒントをもらいませんか。
今回は特別に、一部を抜粋してお届けします。
静かに死ぬ
獣医なので、動物の最期にはずいぶん立ち会いましたが、どの動物にも共通しているのは、痛いから、苦しいからといって大騒ぎしないことです。骨折しても平然としている。最後の最後まで「100%健康です」というような顔をして死んでいくのです。しかもみんな黙ってひっそりと死んでいきます。
おそらく野生動物だからでしょう。野生では、痛がったりすると、弱っていることを第三者に知られることになり、それは即、外敵の格好のターゲットにされるわけですから、きっと我慢するということが遺伝子の中に組み込まれているのでしょう。
それにしても痛みは人間と同じようにあるはずです。言葉は喋れないから確認はできませんが、神経などは人間と同じように走っているので、痛いはずなのです。
ただ、まれに痛みを表現することはあります。旭山動物園にいたシマウマにまつわる印象深かった出来事です。シマウマが動かないと飼育員から言われて、見に行ったんです。すると、胸を張ってぴしっとした姿勢で立っていました。一見、何も問題があるとは思えない。でも、言われたように動かないのです。視線もそれほど動かないし、後ろ足も一歩も出ない。
これはどこが悪いんだろう……。そう思って、私は一旦帰るふりをして、木に隠れるようにしてシマウマをじっと観察していました。すると、もう誰もいないとわかったときに、突然緊張を解いたようで、右前足を痛そうに浮かせたのです。
「あ、右前足が悪いんだな」とわかり、麻酔をかけてレントゲンで確認したら、指骨(しこつ)が折れていることがわかりました。驚いたことに、縦に3つに割れるという重傷です。何かの拍子にひねったのだと思いました。痛かったはずだけれども、誰かに見られている間は、「何でもありません」みたいな顔をしていたのです。ある意味、すごい“演技力”です。

もちろん手術をしました。昔からシマウマの麻酔は覚醒時に暴れて走り回り、どこかにぶつかって死んでしまうと言われていました。そこで、私は完全覚醒まで立ち上がれないように、コンパネに首と肩を平打ち縄で固定(柔道の袈裟固(けさがため)のように)しておき、しばらく自由に動けなくして時を待ちました。覚醒後に縄をほどいてやると、シマウマは普通に立ち上がって、手術は無事に成功しました。ちょっと鼻高々だった思い出です。
もう一つ、印象的だったシマウマのエピソード

シマウマといえばもう一つ、アフリカでライオンがシマウマに嚙みついたのを見たことがあります。シマウマの目がすごかった。嚙みつかれた直後は目を見張っているのですが、その目はどちらかというと痛みに苦しんでいるというよりも、「恍惚」の表情に見えたのです。
もしかしたら、動物は死ぬときに、痛みを上手く気持ちよさに変換させているのではないか、とさえ思いました。ドーパミンのような、脳が快くなる物質が大量に出て、痛みや苦しみを覆い隠してしまうのかもしれません。想像が過ぎますかね?
「痛み」は、何かを忌避するために必要なものです。死にゆく動物にとっては、痛みを感じる意味がないから、きっと脳が「痛み」を変換させて「恍惚」の状態にしているのではないかとさえ思えます。
認知症患者の初期症状で、本人の表情や言動に多幸感が見られるのは、ドーパミンバランスや感情処理のメカニズムに変化が起きていることと、短期記憶の保持が難しくなり、ネガティヴなことを覚えないからだと言われていますが、これも「老いや死への恐怖」を忌避するための脳のプログラムではないのかと、つい考えてしまいます。
人間中心に考えるのはやめたほうがいい
私はテレビや新聞に出ている動物関係の記事を見ると、いつもブツブツ言っているようです。「ようです」というのは、自覚が無いからで、妻によく指摘されるのです。
何が私をそんなにイライラさせるのか。
例えば、こんな記事です。
「昨日○時頃、国道○号線で、○△さんが運転するトラックと、体長160cmのクマが激突しました。運転手は病院に運ばれましたが、軽傷ということです」
そこで私のブツブツが始まるのです。
「おい、クマはどうなったんだよ。ひどい怪我をしているに決まっているじゃないか。車にぶっ飛ばされて、骨折しているに違いない。動けなくなって、どこかで死んでしまうんだよ。それをなんで言わないんだ」
「飛び出したのが、人間の子どもだったら、どうするんだ」
「被害者はクマだろう」
運転していた人もびっくりしたと思うけれど、クマにとっても突然の悲劇です。アナウンサーも「クマにとっては突然のことで驚いたことでしょう」とか一言コメントすればいいのに。
何事も人間中心に考えるのは、そろそろやめた方がいいと思っています。私はテレビ番組でコメンテーターを頼まれ、ニュースに関して意見を言うとき、いつも動物側に立ったコメントをするため、自らを「動物の弁護士」と自己紹介しています。
動物は言葉が喋れないので、私が代わりに動物の気持ちを語る「代弁者」でありたいと思っています。
小菅正夫(こすげ・まさお)
獣医師。札幌市環境局参与(円山動物園担当)、旭川市旭山動物園元園長。北海道大学客員教授。国立動物園をつくる会代表。北海道札幌市出身。北海道大学獣医学部卒業後、1973年に旭山動物園入園。飼育係長、副園長などを経て、1995年に園長に就任。一時は閉園の危機にあった園を再建し、日本最北にして“日本一の入場者を誇る動物園”に育て上げた。2004年には「あざらし館」が日経MJ賞を受賞。2009年に同園を定年退職後、名誉園長となる。2015年には、札幌市円山動物園のアドバイザー(参与)に就任し、現在に至る。2017年公開ドキュメンタリー映画『生きとし生けるもの』では監修を務める。著作に『〈旭山動物園〉革命―夢を実現した復活プロジェクト』(角川新書)、『15歳の寺子屋 ペンギンの教え』(講談社)、『僕が旭山動物園で出会った動物たちの子育て』(静山社)、『動物が教えてくれた人生で大切なこと。』(河出書房新社)など多数。
文=小菅正夫
イラスト=赤池佳江子
あわせて読みたい
-

- 24日は九州〜北海道で気圧低下に伴う頭痛やめまい注意 25日も東海〜北海道で低下
- 今日24日は、九州から北海道にかけて気圧が低下するでしょう。鹿児島から名古屋、新潟で影響度「大」、東…
- (tenki.jp)[LOHAS,北海道]
-

- 人気モデルYouTuberあみしぃが毎日5分でもしていること
- 石井亜美さん / (C)石井亜美/KADOKAWA「日本一親しみやすいモデル」として知られる、チャンネル登録者数5…
- (レタスクラブニュース)[スローライフ]
-

- 【山田杏奈、佐渡の神秘に触れる】“島外不出”の土「無名異土」を使った焼物はまさに佐渡の大地の恵み
- 無名異焼の窯元「北沢窯」を訪れた俳優の山田杏奈さん。 新潟県の北西部、日本海に浮かぶ佐渡島は沖縄本島…
- (CREA WEB)[まち歩き]
-

- 不要なものに家を占拠されてない? マインドを変え、老後に備えて家をすっきり
- 老後に備えて家をすっきり / (C)りさねーぜ/KADOKAWA「年齢を重ねるのが怖い」「ひとりは寂しい」「老…
- (レタスクラブニュース)[動物]
-

- 周囲を濡らさない!ワンタッチで逆折り開閉の晴雨兼用傘「NURASAN-J27W」
- 周囲を濡らさない!ワンタッチで逆折り開閉の晴雨兼用傘「NURASAN-J27W」GIF: 田中宏和 2025年4月17日の記…
- (Gizmodo Japan)[健康]
-

- 【プラダ】人気フレグランスから「ブランド初のヘアミスト」が登場! 初夏のプレゼントにもおすすめ
- 夏はフレグランスを楽しむ絶好のシーズン。プラダからはブランド初のヘアミスト「プラダ パラドックス ヘ…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.