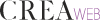【情熱大陸でも話題になった船上の助産師】自身のスキルと人間力が試される場所へ。助産師の小島毬奈さんが地中海の救助船に戻る理由

命がけで海を渡る――それはドラマでも映画でもなく、地中海でいまも続いている現実です。紛争や貧困から逃れるために、粗末なゴムボートや木造船で大海を渡ろうとする移民・難民は後を絶ちません。
そんな現場で活動しているのが、昨秋、「情熱大陸」(TBS系)でも話題になった日本人助産師・小島毬奈さんです。2016年から24年の8年間で、地中海の救助船に計11回乗り込み、医療チームの一員として働いてきました。
単純な善悪では語れない、肉体的・精神的にもハードな現場と、それでも小島さんが船に戻っていく理由を聞きました。
「カッコいいかも」から始まった海外への一歩

――まず、都内の病院の産婦人科で働いていた小島さんが、海外での人道支援活動へと方向転換した経緯を聞かせてください。
「そもそも日本の看護学校、助産学校、就職した病院にも、ずっとなじめなかったんです。年功序列の女社会、職場独自の謎ルール、有能な人ほど仕事が増え辞めてしまう現実にもがっかりしていました。
よく、入社3年くらいで最初の“辞めたいブーム”がくるって言うじゃないですか。ひと通りの仕事に慣れ、他でもやっていけるんじゃないかと思い始めて、自分に酔った感じで『あ〜、辞めたい!』って(笑)。でも、そう言う人ほど辞めない。
看護師も同様なのですが、『辞めたい』って言い続けていたら本当に辞めたくなっちゃったんです。夜勤のときも、こっそり『助産師 留学』とか『看護師 海外』とか検索するようになって。結局、4年3ヶ月で辞めることになりました」
高校時代をオーストラリアのメルボルンで過ごした小島さんは、病院を辞める前から、海外で働いてみたいという願望がうっすらとあったそう。
「特に国際協力とか人道支援に興味があったわけではありません。『海外で働くってカッコいいかも』と、ダメ元で『国境なき医師団(MSF)』に履歴書を送ってみたら、すぐ面接に進んで、まさかの合格。病院を辞めて半年後の2013年末、29歳のときです。当時は今よりもずっと応募のハードルが低く、ラッキーでした」
助産師としてのスキルを磨き、活かせる場所へ
医療職としての道を選ぶとき、小島さんが最初から目指していたのは助産師でした。日本で助産師になるには、まず看護師の資格を取り、さらに助産学校で専門課程を修了する必要があります。
――そもそも、なぜ助産師に?
「日本では助産師は女性しかなれませんし、数も看護師のおよそ3%というニッチなところに惹かれたのかもしれません。でも、いざ病院で働いてみると何事も医師主導で、助産師として学んだ知識や技術を活かせる場は限られ、モチベーションを維持するのが難しいと感じていました。
一方、海外の難民キャンプや紛争地域では産科医がいないことも多く、例えば帝王切開が必要かどうかといった命に直結する判断、レイプや売春などで望まない妊娠をした人に中絶薬を処方するのも私の仕事でした。責任は大きいけれど、そのぶんやりがいがありました」

――初めての派遣先、パキスタン・ペシャワールの病院はどうでした?
「日本では見たことがないような症例だらけでした。5キロ以上の巨大な新生児、子癇発作でベッドから落ちそうになっている人、地元の医院で分娩誘発剤をガンガン打たれて子宮破裂の状態で運ばれてくる人も。日本では医師がやる会陰切開や縫合も助産師がやるので、技術的にも学ぶことは多かったです」
小島さんはパキスタンのあとイラクの難民キャンプで働き、レバノンでは主にシリア難民の妊産婦に関わる仕事を経験。管理者として現地スタッフと関わる難しさ、言葉の壁、文化の違いに翻弄されながら、体当たりで仕事に挑みました。そして2016年に舞い込んできたのが、地中海の難民救助船での仕事でした。
――救助船の仕事と聞いて、どう思いましたか。
「はじめは救助船の停泊している港で働くのかなと思っていたんですよ。渡航前にもらう業務案内は、実際に行くと大幅に違っていることが多かったので。本当に船上で働くのかも、と思い始めたのは、乗船前のトレーニングを受けたオランダで、5メートルの高さからイマーションスーツ(防寒・防水救命衣)を着て水に飛び降りたときでした」
その後、イタリアのシチリア島から乗り込んだ救助船「アクエリアス号」では、3ヶ月で5000人超の救助にあたったといいます。

「たくさんの異職種の人とともに働き、刺激を受け、下船後すぐに『船に戻って働きたい』と思いました。まだまだ知りたいことや学びたいことがあったし、単純な善悪では語れないカオスな状況で力を試される、救助船での仕事は自分に合っているという実感がありました」
地中海まで救助船が出張って行くのはなぜか
――小島さんが乗る救助船は、どのような団体が運営しているのですか。
「公的機関ではなく、国際NGOや人道支援団体が寄付やクラウドファンディングをもとに運航しています。私が乗ったのは、国境なき医師団(MSF)と、フランスを拠点とする海難救助専門の人道支援団体SOSメディテラオネ(SOS)が共同運航するアクエリアス号や、ヨーロッパの民間団体が運営するシーウォッチ号。MSFを離れた後の2021年から24年は、SOSと国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)が共同運航するオーシャンバイキング号をメインに乗船しています」

――活動の目的は?
「地中海に面した北アフリカのリビアからイタリアへ渡ろうとする難民・移民を一人でも多く救助し、安全な港まで届けることです。彼らは、大海を渡るには粗末すぎるボートに救命胴衣もつけず、ぎゅうぎゅう詰めに乗せられます。
そのままイタリアへたどり着く可能性は、限りなくゼロに近いです。彼らの現実的な目的は、NGOの救助船が活動するリビア沖の捜索救助ゾーンまで、何とかしてたどり着くことです。NGOに救助されればラッキーですが、その前に船が沈没したり、リビアの沿岸警備隊に捕まって連れ戻され、過酷な拷問などが待つ収容所送りになるケースも少なくありません」

――国際移住機関(IOM)によると、2014年から2024年3月までの間に、地中海で死亡または行方不明となった難民・移民は約2万9,000人とされています。「死のルート」と呼ばれるほど危険なのに、リビアからイタリアへ行こうとする人が後を絶たないのはなぜでしょう。
「他に生き延びる道がないからです。もともとリビアはオイルマネーで潤い、外国人労働者、つまり移民の受け入れ先でした。ところが2011年、“アラブの春”をきっかけにカダフィー政権が崩壊すると、国の統治機能は失われ国境管理もゆるくなりました。密航業者や人身売買組織はそれ以前から存在していましたが、混乱に乗じてより活発になっています。
『ヨーロッパに行けばいい仕事がある』という密航業者の甘い言葉に誘われ、アフリカのみならず、シリア、イラン、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタンなどの紛争・貧困国から多くの人がリビアを目指してやってきます。
でも入国前に不法侵入で捕まったり、人質として拘束され家族に身代金を要求されることもあるし、入国できても過酷な環境で、暴力にさらされながら奴隷のように働かされる。そうしてようやく、ヨーロッパへ向かうボートに乗れるチャンスが訪れます。自国に帰っても仕事はなく、後戻りするという選択肢はありません」
――救助船の活動についても、賛否があるようですね。
「はい。移民・難民の主な受け入れ先であるイタリアでは、メディアが『不法移民を連れてくる悪い奴ら』と揶揄したり、『不法な移民ビジネスと結託している』といったデマで国民感情をあおり、それを口実に政治家がNGOを叩くこともあります。
救助した人たちを乗せたまま何日も洋上で待たされたり、活動停止に追い込まれることもあります。それでも、救助しなければ数百人単位で命が失われる可能性がある以上、いまそこにある命を助けるというのが救助船のスタンスです」

海上での人命救助は国際法上の義務とされており、救助そのものは合法です。ただ、救助された人の上陸先や亡命申請の扱いについては、法的なグレーゾーンや各国の政治的駆け引きが絡み、非常に複雑な問題となっています。
地上の病院勤務とは何もかも違う救助船での日々
――船にはどんな人たちが乗り、具体的にどんな活動をするのでしょうか。
「私のような助産師を含む医療チームのほか、救助専門チーム、エンジニア、調理スタッフ、NGOの広報担当やカメラマン、アクティビスト(活動家)、ジャーナリストなど、ささまざまな職種、国籍の人が乗っています。
まず、ヨーロッパ側の港から、リビア沖の探索救助ゾーン(SAR=Search and Rescue Zone)へ向かう航海中に、救助訓練を行います。小さい高速船を海に下ろして乗ったり、人形を落として海から引き上げたり。

救助ゾーンに着いたら捜索開始です。難民ボートの捜索は、主に船首から双眼鏡で行います。私たちのような救助船のほか、セスナで空から探すNGOや、衛星電話で救助船と連絡を取るNGOとGPSを共有し、協力し合って探していきます」

――ボートはすぐに見つかるものですか。
すぐに見つかるときもあれば、10日以上見つからないときもあるし、救助する人数も5人だったり、120人だったり。船に乗せた後は、下船可能な安全な港=プレイス・オブ・セイフティへと向かい、人々を下ろし、ゴミだらけになった船内を掃除。新たな食料や救助キットを搬入したら、ふたたび捜索救助ゾーンに戻り、次に救助すべきボートを探す。その繰り返しです。

これまでのプレイス・オブ・セイフティは、捜索救助ゾーンから約1日でたどり着くシチリア島だったのですが、現イタリア政権(首相は極右系政党のジョルジャ・メローニ氏)はこうした救助活動に厳しく、ラベンナ、リボルノといった救助船で4〜5日かかる遠隔港を指定されることが増えています。
一度救助した人々を下船させるまでは新たな救助はできず、その間の燃料、物資、人員コストもかかります。特に男性は屋根のないところで何日も雑魚寝になることも多く、ストレスによるケンカなどのトラブルや体調不良も増えます。

――船上で出産する人もいるのでしょうか。
臨月の妊婦や乳幼児連れの母親が乗ってくることはありますが、私が船上での出産に対応したのは、最初に乗ったアクエリアス号で1度だけです。そのときは600人の救助と分娩が重なりました。
産婦は床に敷いたヨガマットの上でうめき続け、その間にも次々と救助された人たちが乗船してくる。食事も睡眠もろくに取れていない産婦の陣痛は進まず、もうヘリコプターで搬送するしかないと決断した直後に、赤ちゃんの頭が見えはじめ、ものの数分で元気な男の子が生まれました。今でも、あの母子は元気でいるのかなと思い出すことがあります。

――小島さんは、医療以外の仕事もするのですか。
「はい。例えば、救助した人たちの食事はスタッフが当番制で作ります。私は自分が食べたくないものを人に食べさせるのはイヤだから、限られた食材でどう美味しく作るかを毎回考えていました。
5キロ炊きの炊飯器を3台同時に稼働させるのですが、そのままだと絶対炊きムラができるんですよ。たぶん、炊飯器の底に4つある熱源のどれかがダメになっているので、10分ごとに釜をぐいっと回して、均等に炊けるように工夫したり。日本人として、米をまずく炊くなんて許せないじゃないですか(笑)。

よく作るのは、米に豆やいろいろな保存食を加えた炊き込みご飯。おいしくするポイントは、油とニンニクをたっぷりと入れることです。醤油もあれば最高。そうすると、どんな具材でもだいたいおいしくなります。チキンストックなんかもケチッてちょっとしか使わない人もいるんですけど、私はバーッと入れちゃう。だから評判いいですよ。残飯がないと、よっしゃー!って思う(笑)」

救助する人、される人もさまざま
――もっと適当に作る人も?
スタッフの食事とは別なので、ものすごく雑に、とってもまずそうなものを作る人もいますね。みんながピュアな気持ちで人助けのために船に乗るわけではありませんから。欧米では、履歴書にこうした活動への参加を書くと箔が付くので、資格を1つ取るような感覚で救助船に乗る人もいます。また、ボランティア活動をすることが豊かな国に住む人間の責務だという考えから、年に1回程度、無報酬でこうした活動に参加する人も。
――小島さんには普通にお給料が出ているのですか。
はい。日本の病院でもらっていた金額に比べたらすごく安いですけれど。報酬がないところもたくさんあります。でも1年に1回しか参加しないような人は他に定職があるから、1、2ヶ月無報酬でもいいという考えなんですよね。動機が何であれ、ちゃんと働いてくれればそれでいいと思いますが、無報酬だと仕事の質が低下する傾向はあります。
――救助される側も単純な“弱者”ではない?
「やはり過酷な環境を生き抜いてきた人たちなので、ぬるま湯育ちの日本人から見ればものすごく図々しいと感じることも多いですよ。例えば食事はみんなに同じだけ配っているのに『もっとたくさん盛って』としつこかったり。

人生をかけて乗船する人が大半ではありますが、なかには、ヨーロッパへのビザが取れず飛行機に乗れないからと救助船を移動手段に使おうとする人とか、リビアの沿岸警備隊にお金を掴ませ、ちゃっかり見逃してもらっている人もいます」
――そんなこんながありながらも、救助船に戻る理由を聞かせてください。
「日本は本当に平和で安全で、夜道を歩いても襲われないし、道端に注射器が落ちていることもない。インフラも公共サービスも整っていて、ただ日本に生まれたというだけでそれを享受できるのは、本当にありがたいことだと思います。
でも、何ヶ月も日本に滞在していると、緊張感がなさすぎて脳が溶けるんじゃないかと思っちゃうんですよ。エンジンの回転数が落ちて、ボンヤリしちゃうというか。できれば今年の夏には、救助船に戻りたいと思っています。

救助船では、多様な背景を持つ人たちと接することで自分の至らなさや価値観の偏りを実感したり、逆に意外な才能にも気づくことも。何よりも人間力が試される場であり、自分が成長できる場所です。
それに加えて昔から海が好きで落ち着くのは、名前のせいかも知れません。『毬奈(marina)』も『小島』も海のイメージ(笑)。両親はともにごく普通のサラリーマンなのですが、そんな名前をつけてくれたことに感謝しています」
小島毬奈(こじま・まりな)
1984年、東京都生まれ。オーストラリア・メルボルンの高校を卒業し、看護学校、助産学校を経て、2009年に都内の病院の産婦人科に就職。2013年から海外の紛争地で助産師として医療活動を始める。2016年から地中海の捜索救助船で活動し、移民・難民救助船に8年間で11回乗務。その活動が注目され、2024年9月「情熱大陸」(TBS系)に出演し話題を呼ぶ。著書に『国境なき助産師が行く――難民救助の活動から見えてきたこと』 (ちくまプリマー新書)、『船上の助産師』(ほんの木)がある。
文=伊藤由起
写真=橋本 篤
写真提供=小島毬奈
あわせて読みたい
-

- お金をかけない「老後生活の楽しみ方」って?
- 皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、お金をかけない老後生活の楽しみ方に…
- (All About)[LOHAS,スローライフ,日常のスポーツ]
-

- ホテルニューオータニ、東京・大阪・博多の3ホテルで神崎恵さんの美容セミナー開催!
- ランチやディナーを愉しみながらホテルニューオータニの東京・大阪・博多3ホテルで、美容家 神崎恵さんの…
- (美容最新ニュース)[健康食材]
-

- 風が吹いても大丈夫。このアウトドアスクリーン、ペグ打てるからね
- 風が吹いても大丈夫。このアウトドアスクリーン、ペグ打てるからねImage: XGIMI もちろん、舗装されたベラ…
- (Gizmodo Japan)[キャンプ]
-

- 連休最終日の6日は西〜東日本で大雨 9日〜10日も大雨の恐れ 沖縄では雨の季節へ
- ゴールデンウィーク最終日である明後日6日(火:振替休日)は、雨の降る所が多く、西〜東日本を中心に大雨と…
- (tenki.jp)[田舎暮らし]
-

- 4日 東・北日本は所々で雨雲発達 関東は急な雨に注意 沖縄は警報級の大雨の恐れ
- 今日4日(日・みどりの日)は、関東や東北を中心に大気の状態が不安定。急な強い雨や落雷、突風などにご注意…
- (tenki.jp)[海]
-

- 難病の日に関連したチャリティーコンサート&ワークショップマルシェイベント「Colors of HOPE」が5月17日に開催、福祉施設やプロ集団が集結
- 一般社団法人LITTLE ARTISTS LEAGUE(リトルアーティストリーグ)は、2025年5月17日(土)に「象の鼻テラス」…
- (Walkerplus)[ボランティア,宇宙]
-

- 世田谷線 開通100周年! “信号待ち”をする若林踏切から招き猫電車まで、驚きのトリビア10選
- 東急世田谷線は、2025年5月1日で開通100周年を迎えた。これを祝した記念車両を4月29日から走らせているほ…
- (All About)[寄付]
-

- 神戸でコミュニティリンクの小野耕一さん講演 「人生の後半は撤退戦」
- イベント「White Club(ホワイトクラブ)」が4月23日、「Incubation Studio SoWelu(インキュベーション・…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[NPO・NGO]
-

- 関東は大気の状態が不安定に 午後は急な雷雨に注意
- 2025/05/04 08:00 ウェザーニュースみどりの日の今日は、西日本や東日本は晴れている所が多くなっています…
- (ウェザーニューズ)[東京都]
-

- EVOLVEから『EVOLVEサマーキット2025』が登場!
- 紫外線が強くなるこれからの季節にぴったりのアイテム株式会社Beが、日本総代理店を務めるイギリス発のラ…
- (美容最新ニュース)[美容]
-

- 5月4日の月が教えてくれるヒント 自己肯定感を高める
- 今日の月はWaxing Moon今日は上弦の月です。月は満ちていく期間に入っています。満月まであと9日。 上弦の…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
-

- 生ものアレルギーなのに「本場のお寿司を食べたい!」その答えは→「生もの抜きで!」破天荒な女性が寿司職人をギョッ!とさせたオーダー【作者に聞く】
- 破天荒な妻に今日も振り回されています / 画像提供:(C)ゆきたこーすけ/竹書房漫画家・ゆきたこーすけ(@k…
- (Walkerplus)[肉]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.