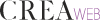「生きる気力が感じられなくて」慶応在学中にメジャーデビュー→32歳でバンド解散。ミュージシャン・古舘佑太郎がカトマンズで自己嫌悪のループから抜け出せたワケ
10代の頃からミュージシャンを生業としてきた古舘佑太郎さんが32歳でバンドを解散。人生に行き詰ったなかで、先輩ミュージシャンのサカナクション・山口一郎さんに「カトマンズに行け!」と命じられ、日本から追い出されるようにアジア9カ国を旅した記録『カトマンズに飛ばされて 旅嫌いな僕のアジア10カ国激闘日記』。
昔から自己肯定感が低く、なにをやっても自分を認められなかったという彼が、混沌のアジアを旅するなかで未知なる世界と対峙し、夜な夜な、自身の喜怒哀楽と内省をぶつけるように書き綴った。激闘の日々の先に見えてきたものとは――?
初めてCDを出してから、セールスに異様にこだわるように

――古舘さんは旅の日記の中で、自己肯定感の低さを繰り返し口にされています。そんな自分を意識するようになったのはいつ頃から?
昔からこじれたやつではあったんですが、それが自己否定にまで向かうようになったのは、最初のバンドでCDを出すぐらいからだと思います。誰のためでもなく、ただ好きで夢中でやっていた音楽が仕事になって、だんだん自分の中の価値基準が、自分ではなくお客さんやスタッフからの評価に変わったんですね。だからセールスに異様にこだわるようになって、もっと売れなきゃ、もっとみんなに伝わらなきゃって思考になって、音楽がどんどん「自分が信じるもの」ではなく「人に認めてもらうもの」に変わっていった。そこに価値基準があるから、思うように結果が出ないのは、イコール自分がダメなんだってことに繋がっていって、コンプレックスがどんどん雪だるま式に膨らんでいっちゃった。
――他人のジャッジに振り回されて、うまくいかない状況を自分の努力不足だと責められてる気がして、どんどん辛くなる構図は「日本社会あるある」な気もします。
僕もずっと自分の努力が足りないからダメなんだって自己否定を続けて、物質的には満たされてるはずなのに生きる気力が感じられなくなっていました。でも、旅に出てみたら、すごく貧しい暮らしをしているはずなのに、生きるエネルギーにあふれている人たちがたくさんいた。ネパールやバングラデシュに比べると、日本やヨーロッパの先進国では自殺者数が多いとも聞きます。それはなぜか、というのを僕なりに考えてみたんですけど、たぶん先進国は発展しているがゆえに、常に人との競争に晒されてるからだと思うんです。
32年間生きた経験が全然通用しないことが良かった

――確かに、すべての不幸は人と比べることから始まると言いますよね。
でも、ネパールで出会った若者たちは将来の夢とかなかったし、そもそも夢を持たなきゃとも思ってない。お金稼ぎにも興味がなくて、自分たちの街、自然、宗教、これを信じれば最高じゃん! みたいな、ぶれない強さがあった。もちろん、僕は競争社会を否定したいわけじゃない。どっちがいいとか優劣をつけたいわけでもないけど、旅に出る前の自分にとって、バンドをやめることは競争から降りることだった。そんな状態で旅に出て、競争社会の外側から自分を見ることができたのは大きかったと思います。旅の間はずっとひとりぼっちだったので、嫌でも自分としか会話できない。僕のことを知ってる人は誰もいないし、他人の価値基準を気にすることもない。そんな真っさらな「何者でもない自分」と向き合う時間が持てたことは、すごく大きかったです。
――日本にいると、どうしても他人の目からは逃れられないし、そんなふうに自分と向き合うことは難しいですよね。
どうしても東京にいると、自分が32年間生きてきた経験が思考の中に入り込んできて、あのときああだったからこんなふうになったとか、バンドマンとしてこれからどうしようとか、過去とか未来のことばかりに頭が行っちゃう。
でも、旅をしていると常に「今」を生きなきゃいけない。今この瞬間、押し売りから逃げるためにはどうしたらいいかとか、明日のこの電車に乗るためには今どうしたらいいかとか、そういう状況下では、これまで自分が積み重ねてきた経験値なんて全然通用しないんですよね。その場でとにかく走り回ってなんとかするしかない。そういう中で自分と向き合っていると、未来に対する不安でうじうじしていた自分がどんどん削ぎ落とされて、ダメな自分とか、自分が克服すべきものだと思ってたことも、受け入れられる方向に変わったんですね。
スマホのメモだと僕みたいな人間はすぐ嘘をつく

――今回の本は古舘さんが旅の間、書いていた日記が元になっています。旅の間、どんな心境で日記を書かれていたんでしょうか?
人に見せるためでなく、本当に自分のために書き始めて。ひとりでどうしようもない気持ちをぶつけるように書いていたんですが、気がつけば日記を書くことが自分の中で支えになってました。日記を書いていたから、2カ月間、ひとりで乗り切れたのかもしれないとも思います。
――カバーを取った本体の表紙には、実際に古舘さんが日記にしていたノートの写真が使われています。まさかの手書きで驚きましたが、手書きだからこそ吐き出せた感情の記録という気もします。
スマホのメモだといくらでも書き直せるから、僕みたいな人間はすぐ嘘をついたり、話を美化したりしそうだなと思って。手書きだったら気持ち悪いこと書いても直せないので手書きで、安宿のベッドで蕁麻疹に苦しみながら書き殴ってました。
――まさか本になるとも思わず?
思ってませんでしたね。音楽については、ずっと誰かに共感してほしい、認めてほしいと思ってやってたけど、旅については、誰かに読んで、共感してほしいとはまったく思ってなかったんです。書いた日記をSNSに上げていたのも、いいねが欲しいからじゃなく、こんな気持ちわかるわけないだろ!って吐き捨てるように上げてて、それがみんなの共感を生むなんてまったく思ってなかったので不思議でした。
これまでの僕は、もっとわかりやすい歌詞で、わかりやすいメロディで、みんながわかる普遍的なことを歌わないといけないと思って、それでも認められなくて苦しんできた。なのに、それとは真逆の気持ちで、自分のためだけに思いをSNSに吐き出したら、なぜかリアクションがバーッと返ってきて、みんなの日常の中に僕の旅が入り込んでいった。
山口一郎に言われた「お前は東京の坊ちゃんだ」という言葉の意味

――本当に、古舘さんの激闘と再生の日々がリアルに体感できて、今すぐ旅に出たくなります。
いや、これ読んで行きたいっていう人がいたら僕は全力で止めますよ! だって、同じルートなんかで行ったら絶対その人の方が僕よりスイスイ楽しく旅しちゃって、僕がポンコツだってことがバレるだけじゃないですか。一方で、僕みたいに自己肯定感が低くてままならない人には、こんな思いをして欲しくない。万が一、行ってなにかあっても責任取れませんし。僕はなんとか帰ってきましたけど、二度と行きたくない。おすすめはしませんね。
――おすすめはしないんですね(笑)。では、カトマンズにはすぐに行けないという人に、代わりにおすすめできることはありますか?
人それぞれだと思いますが、やったことがないことをやってみるのはいいと思います。別に旅でなくてもいい。富士山登るとか、大それたしんどいことである必要もない。知らないお店に入るとか、ビーズ作りをやってみるとか、本当に些細なことでいいので、自分の興味とは真逆のものに手を出してみることは、すごくおすすめします。
――今回の旅もまさにそれですよね。
だから一郎さんが僕にして欲しかったことって、結局それだと思うんです。
「お前は東京の坊ちゃんだ、自分の興味の中でしか生きてこなかった。世界はお前の知らないことで溢れている。それを見てこい」って言われたとき、僕はそれがどういうことだかわからなかった。でも、今はすごくわかる。自分のことが辛かったり、好きになれないということは、今までやってきたことの中にエラーが含まれているからで、今までと同じ生活の中でずっと解決策を考えていても、そこから抜け出すのは難しい。だったら自分のルーティーンとは違うものに手を出して、まったく因果関係がないところに振り切った方が絶対いい。それが僕にとっての「旅」なんですね。
古舘佑太郎(ふるたち・ゆうたろう)
1991年4月5日生まれ。東京都出身。2008年、バンド「The SALOVERS」を結成し、ボーカル・ギターとして活動スタート。2015年3月、同バンドの無期限活動休止後、ソロ活動を開始。2017年3月、新たなバンド「2」を結成。2021年6月に活動休止し、2022年2月22日にバンド名を「THE 2」に改め再開。2024年2月22日に解散。俳優としては、2014年、映画『日々ロック』でデビュー。以降、NHK連続テレビ小説『ひよっこ』、NHK大河ドラマ『光る君へ』、映画『ナラタージュ』などに出演。主演映画に『いちごの唄』『アイムクレイジー』などがある。
取材・文=井口啓子
写真=深野未季
あわせて読みたい
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品,旅,山]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[春グルメ]
-

- 富士山こどもの国で初の「ザクっとコロッケフェス」 ご当地コロッケ9店
- 「ザクっとコロッケフェス」が5月5日・6日の2日間、富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎)で初めて開催さ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[富士山]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[果物,東京都]
-

- 「祝英台が高校生に?」「青髭がラスボス化?」 神話×漫画の化学反応に読み手もびっくり!古典のぶっ飛びアレンジがクセになる【作者に聞く】
- 1700年前の中国がまるで現代の高校のよう!少女漫画テイストで昔話をアレンジゴールデンウィークのおうち…
- (Walkerplus)[花]
-

- 空気清浄・脱臭・除湿を1台でこなし、年中快適な空間に!より清潔性が増した、三菱電機「美空感」新モデル
- 三菱電機は、空気清浄、脱臭、除湿の3つの機能を1台に集約した空清脱臭除湿機「美空感」の新モデルとして…
- (GetNavi web)[エネルギー(ぼんやり学会)]
-

- GWのお出かけはここ!<サーティワンと日本橋三越本店が初コラボ>限定フレーバー&豪華サンデー、オリジナルグッズも見逃せない
- このゴールデンウィーク、サーティワン アイスクリームと日本橋三越本店が初のコラボレーションを実現! 4…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.