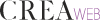突然“私”に何かあっても飼い猫はずっと幸せに暮らしてほしい。飼い主として今すぐできる〈セーフティネット〉とは?

発売前から話題をさらい、発売するや否やすぐに重版がかかった『私が死んだあとも愛する猫を守る本』(日東書院)。タイトルの通り、自分の死後、愛猫を路頭に迷わせないための知識や備え、セーフティネットを徹底解説しています。
猫飼いたちの心配や不安を解消するこの本を手がけたのは、たくさんのペットにまつわる書籍を執筆してきた富田園子さん。自分の死後を題材にした理由や、愛猫を守るために必要なセーフティネットについて伺いました。
自分が死んでしまったら、飼っている猫たちは……

――『私が死んだあとも愛する猫を守る本』を作ろうと思ったのはなぜですか?
富田園子さん(以下、富田) 幼い頃からずっと猫と一緒に暮らしてきたんですが、50歳という節目を迎えたことが大きいですね。東京都動物愛護相談センターの条件だと、猫を譲渡できるのは60歳まで。私自身も里親探しをする際には60歳以下の方を対象にしています。
改めてそういう条件を考えた時、自分が60歳になるまであと10年。高齢者と呼ばれる年齢が近づいていることを実感したし、猫と暮らせる時間は思ったよりも少ないのかもしれないと。
一人暮らしをしていた20代の頃は、自分が猫より先に死ぬなんて思ってもなかったんですが、50代になった途端、もし先に自分が死んでしまたら今飼っている猫たちはどうなるんだろうと。今は夫と2人暮らしで猫たちも元気なんですけど、愛する猫たちのために必ず考えないといけない問題だなと思ったんです。
――自分が死んだ後の愛猫を思う気持ちから、この本が生まれたのですね。
富田 過去に猫の飼育書を作った時に、自分がいなくなった場合のことも書いたんですけど、飼育書なのでそこまで全てを網羅できなかったんです。いつか「自分がいなくなった場合」に特化した本を作りたいと思っていたところ、猫に関する本を作りませんかとお声がけいただいて。
実は、当初は今回の本とは少し違った趣旨の企画だったんです。60歳を超えてから猫を迎えるのがタブーとされる中、それ以外の方法で猫ライフを楽しむというような。
すごく素敵だなぁと思いつつ、もう少し視点を「自分が死んだ後の猫」に向けたかったんです。なぜなら、突然猫を保護することになるかもしれないですし、60歳を超えてからも不意に猫を迎えることだって起こり得ると思ったので。それで担当の編集さんと何度も企画を揉んで、自分が死んだ後、愛猫を路頭に迷わせない仕組みづくりができるような本を作ることになったんです。
――確かに事前に仕組みづくりをしておけば、もし何かあった時に安心ですね。
富田 高齢の方だけでなく、特に1人暮らしの方には不可欠だと思います。健康で元気だとしても、事故や災害に巻き込まれる可能性はゼロではありません。万が一の時に家に帰れず、猫の存在に誰も気づかず放置されたら……。そうならないためにも、猫を飼う全ての人にセーフティネットの存在を知ってもらいたいですね。
猫を託せる人を見つけ、「合鍵」を渡しておく

――猫を飼う人がすぐにでも始めておくべきセーフティネットはありますか?
富田 すぐにでもやっていただきたいのは、頼れる人を見つけて合鍵を渡しておくこと。合鍵を預けることに抵抗感を抱く人は多いかもしれませんが、例えばご自身が亡くなってしまった場合、空腹のまま放置されている猫が部屋の中にいることがわかったとしても、現在の法律上は遺族の許可なしに中に入ることが難しい。
もしご遺族に許可をとれたとしても、合鍵を持ってない場合だってあります。健康で元気な若い世代の人だって、誰にでも「もしも」の時は起こり得ます。そんな場合に備えて、家族や親戚、友人たちの中から愛猫を託せる人を見つけ、打診してみるといいと思います。
――愛猫のためにも、合鍵を託す人探しは今すぐに始めた方が良さそうですね。親世代のシニア層にもセーフティーネットの存在の周知が必要だと感じました。だけど、セーフティネットを設けること=「死」を連想させるし、なんとなく伝えづらくて……。
富田 そういう声は多いのですが、私の友人は猫を飼っている高齢のおばさんに、この本をプレゼントしたと言っていました。直接は言いづらいですが、本だと渡しやすい。この本をきっかけに、お互いの思っていることを話し合うといいと思います。たとえ我が子だとしても、アレルギーがあったり、住んでいる家がペット不可だったりして、残された猫を引き取って飼ってくれるとは限りませんから。
本の冒頭にも書きましたが、実際飼い主が亡くなって、遺族が残された猫を保健所に連れて行くケースは少なくありません。2022年度では、9559匹の猫が飼い主や親族から持ち込まれています。里親が見つからなかったら、殺処分も行われます。
――そういう目を背けたくなるような現実が、本の冒頭で書かれていて胸がギュッとなりました。
富田 私自身、泣きながら書きました。殺処分の様子はYouTubeで見ることもできますし、以前見たこともあります。「人間の身勝手でごめんね」という気持ちが込み上げてきて、耐え難い現実です。だけどそういう現実を知ってもらい、もしも自分が死んだ場合の愛猫について考えていただきたかったんです。
セーフティネットがない状態で猫を飼うのは危険

――富田さんはこれまでにも猫に関する本をたくさん手がけています。今回この本を作るにあたり、新たな気づきとなったことはありましたか?
富田 私自身、1人暮らししていた時に、セーフティネットがない状態で猫を飼っていましたが、それはものすごく危険なことだったと改めて気づかされました。猫を保護せざる得なかったりと、突然猫を迎えることも少なくないので、お金がそこまでない状態で飼い始めることを責めるわけにいきません。猫を思っての行動だと思うので。ですが、飼うと決めたなら、その間に保険に加入したり、積立貯金をしたり、頼れる人を見つけたりと、セーフティネットを作ることはできるはず。愛する猫のため、仕組みを作っておくことの大切さを実感しました。
――そんな思いが共感を呼び、発売後すぐに重版がかかったんですね。
富田 正直、本を作り終えた時、「こんなにマジメな本、誰が買ってくれるんだろう」と不安になったんです(笑)。これまで私が作ってきた猫の本は、教養や雑学が含まれるものが多く、自分が生きていることが大前提。しかし、今回の本は自分の死を考えることにもなるし、内容だって結構シリアス。だから、こんなに本を手に取ってくださった方がいると聞いた時は、みなさんの猫を大切に思う気持ちに触れられた気がしました。そんな猫を愛する人たちにとって、この本がお役に立てていたら嬉しいですね。
――自分の死後も猫を大切に思う、猫愛にあふれている1冊を作った富田さん。ご自身にとって、猫はどんな存在なのでしょうか?
富田 小説家の村山由佳さんが大好きなのですが、ご本人も猫好きで猫にまつわるエッセイがあって、その中には「ある種の人間にとって猫は必要不可欠なものである」というようなことが書かれているんです。まさに私にとっても同じ。猫がいて当たり前というか、いないと物足りないというか。
保護猫のボランティア活動もしているんですが、猫って不思議なんですよね。一緒に暮らして3日もすれば、「昔からここにいましたけど?」みたいな顔をしていて。するっと人間の暮らしに入ってきてすぐ馴染む。それも魅力なんですが、やっぱり猫の良さは、やわらかくてあたたかくて撫でさせてくれるところですかね。旅行や出張で3日も猫に会っていないと、猫を早く撫でたいなって思わせるような、不思議な魅力に取りつかれています。
富田園子(とみた・そのこ)
ペット書籍を多く手掛けるライター、編集者。日本動物科学研究所会員。編集・執筆した本に『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)、『野良猫の拾い方』(大泉書店)、『教養としての猫』『猫とくらそう』(ともに西東社)など。

私が死んだあとも愛する猫を守る本
著者 富田園子 監修 磨田薫
定価 1,650円(税込)
日東書院
文=船橋麻貴
関連記事
- 「最期までお世話できないかも」 病気になった飼い主が保護猫“あずきちゃん”のために契約した〈ペット信託〉
- 【まめきちまめこ】「最近マンガの描き方に悩んでて…」大人気ブロガーが初めて明かす、愛猫2匹を“人間らしく”描く理由とは?
- 「きっかけは読者のコメントで…」まめきちまめこがギャグを封印し新境地へ!? 初の絵本『メロとタビのクッキーだいさくせん』制作秘話
- 「ザ・森東の猫、“専務”もわたしが保護した子なんです」俳優・円井わんが保護猫活動を通して猫の幸せのために願うこと
- 「看取る覚悟は最初からあった」肺に穴のあいた老猫(16)とあらぽんが過ごした6年間「10歳で家族に手放された子を僕が今から幸せにしたい」
あわせて読みたい
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS,スローライフ]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[旅]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[動物]
-

- 野毛山動物園、連休は開園延長 市電は老朽化で利用中止
- 野毛山動物園(横浜市西区老松町6)は園内で保存展示していた「横浜市交通局1500型電車1518号」の利用を、…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ボランティア]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東京都]
-

- 空気清浄・脱臭・除湿を1台でこなし、年中快適な空間に!より清潔性が増した、三菱電機「美空感」新モデル
- 三菱電機は、空気清浄、脱臭、除湿の3つの機能を1台に集約した空清脱臭除湿機「美空感」の新モデルとして…
- (GetNavi web)[アレルギー]
-

- 5月2日の月が教えてくれるヒント 親しくなりたい人を誘う
- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと11日。 月は蟹座で満ちていきます…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
-

- アウトドアや災害時にきっと持ってて良かったと思える“三角形”
- アウトドアや災害時にきっと持ってて良かったと思える“三角形”Photo: SUMA-KIYO 2024年6月3日の記事を編…
- (Gizmodo Japan)[いざというときのお役立ち]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.