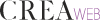大切なのは“おいしい”だけじゃない。世界を旅する岡根谷実里さんが語ったエキサイティングな“食”のリアル
『世界ひと皿紀行 料理が映す24の物語』は、「世界の台所探検家」を名乗る岡根谷実里さんが世界24カ所の家庭を訪れ、台所で一緒に料理を作って食べた記録だ。パレスチナのサハラブ、キルギスの姑の舌、ブルガリアのリュテニツァ、ペルーのパパ・エラダ、トンガのウム……。私たちの日常からはかけ離れた生活の中で生み出される、想像の斜め上をゆく料理の数々に驚き、興奮するうちに、気が付けば自分の中の「食べる」という概念がガラリと覆される。エキサイティングな食の冒険旅行をご堪能あれ。
「食」から知らない暮らしを知りたい

――岡根谷さんが世界の家庭の台所を訪れるようになったのは、なぜ?
もともと知らない世界に興味があって、バックパックで旅をしたり、国際協力に携わるなかで、自然に世界各地の家庭を訪れるようになりました。いろんな国のいろんな家庭を訪れていると、自分が知識として知っていた国や民族のイメージとは違う人にいっぱい出会う。
たとえば、北極圏の先住民族であるサーミ人は“伝統的な”トナカイ料理を食べているのかと思いきや、トナカイ肉をクリームパスタで食べたり、冷凍ピザを食べる日もある。この国はどうとか、この宗教はどうとか、自分がイメージしていたのとは違う世界があるのがおもしろくて、「食」を入り口に知らない暮らしを知りたいと思ったんです。
――作中に登場するのは、見たことも聞いたこともないエキゾチシズムをくすぐられる料理ばかり。目次を見るだけでワクワクします。印象深いのが、ブータンの農村で毎日お米と一緒に食べられている「エマダツィ」という唐辛子のチーズ煮の話。
辛そう! と思うんだけど、これが意外とはまる味で。毎日同じ味で飽きないかな? と思うんですが、よく考えると日本人も出汁と醤油味のおかずばかり食べてるし、朝から晩まで肉体労働をするブータンの農村では、濃い味付けでお米をたくさん食べるのは理にかなっている。そんな環境で彼らは、食に「おいしさ」や「目新しさ」よりも毎日お米をたくさん食べられるという「安定感」を大事にしているように思えたんですね。
「おいしい」は一要素にすぎない

――そんな生活を知ると、流行のグルメをSNSでチェックしたり、献立がマンネリにならないように必死でレシピを検索している自分が空虚に思えてきます。
「おいしい」とか「目新しい」も大事だけど、世界には食事に対して違うものを求める人もいる。私はいまオランダに住んでいるんですが、オランダ人の友人たちと話していると、「おいしい」よりも「雰囲気がいい」とか「効率がいい」という話ばかりする。日本では食べ物に関して「おいしい」という単一要素が重視されがちで、私が食べ物の話をしても「で、結局それっておいしいの?」と訊かれることが多いんですが、実は世界では「おいしい」という言葉自体、あまり口にしない国も多い。「おいしい」はあくまで人が食に求める一要素でしかないんですね。

――そういう意味で、パプアニューギニアの味がしないぷるぷる団子「ターニムサクサク」も衝撃でした。
ターニムサクサクはサゴヤシから採取したでんぷんで作られるわらび餅みたいな団子で、パプアニューギニアで主食とされている。現地の人はみんな「おいしいおいしい」って食べていて、私もどんな味がするんだろう? って、ワクワクしながら食べたら味が全くしない。え、私が感じられないだけ? と思ったら、味はないけどお腹がいっぱいになるからおいしいよと言われて。単に味が良いとか風味が良いとかではなく、お腹が満たされることを「おいしい」と表現するケースもあるんだ! と驚きました。
――読めば読むほど、自分が正義だと思っていた「おいしい」が、いかに狭い世界のものだったのか気付かされます。
私もおいしいものは好きですが、食べ物って「おいしい/おいしくない」だけじゃない。たとえば、ヨルダンのべドウィンという遊牧民は砂漠でパンを焼いて食べるんです。ヤギが逃げないか、ちゃんと草を食べてるか、注視しながら黙々と食べる。そのシーンで「おいしい」という言葉はめちゃくちゃそぐわないし、「食べる」って本質的にはこういうことなのかもと思います。
「世界の台所探検家」を名乗る理由

――岡根谷さんは「世界の台所探検家」を名乗っていますが、辺境の地の知らない家庭に飛び込んで一緒に料理をして食べる姿は、まさに「探検家」ですよね。
3回に一回は台所研究家って言われるんですけど、私の場合、対象を研究して普遍的な事実を見つけたいというよりは、何があるのかよくわからないけど行ってみて、一緒にわからなさを楽しみたい。なぜそれを食べるのか、食べておいしく感じないとしたら、それはなぜか。なぜ味がないのにおいしいって言ってるのか。その「なぜ」の部分がおもしろいわけで、料理よりもそこに興味がある。だから探検家なんです。
――これだけいろんな場所を探検していると、かなりハードな体験もあるのでは?
すごいダニに噛まれるとかはありますが、基本的には「楽しい」しかないですね。草原の家庭でトイレまで200メートル歩かないといけない――みたいな状況も、とらえ方一つで楽しめる。ハードにも見えることも、これもアリだなって受け入れてしまえる。
よく「食べられなかったものはないですか?」と訊かれるんですが、それもなくて。レストランでいきなり料理を出されると、口に合う合わないでジャッジしちゃうけど、そこで生活している人と一緒に作ると、日本では考えられないような料理でも、そんなに唐辛子を入れるんだ、でも結構おいしいな――と、主体的に楽しもうという方向になるんです。
そもそも料理に正解はない

――一方的な価値観でジャッジして拒絶するよりは、相手の懐に飛び込んで一緒に楽しむ方が断然おもしろいですよね。
なんか世界を単純化したがる圧力に抵抗したい気持ちがすごくあるんです。たとえば世間では「フランス人は食にこだわりがあって、毎朝焼きたてのバゲットを買う」みたいなことが言われがちだけれど、家庭ではけっこうレトルトを食べていたり、工業的なスーパーの食パンを食べていたりする。実際行ってみないとわからないし、「ここの人はこうだよね」みたいなラベルは貼りたくない。世界には多様な食べ物があって、多様な生活、多様な在り方があるということを見せることで、こういうのもアリなんだなってラクになってもらえたらいい。

――日本にいると、食べ物ひとつとっても、つい「◯◯でないと」という呪縛に陥りがちです。
たとえば今回、エッセイに出てくるレシピをいくつか紹介しているんですが、日本の方はよく「正解がわからない」と言う。そもそも料理に正解はない。自分がおいしいと思ったらそれが正解なんだけど、どこかに正解があると思っている。この国の味はこうだと決めたい、こうやったら大丈夫と信じたい、という気持ちがあるんですね。
確かに決められた方が安心ではあるけど、自分自身の「これがいい」というものを持てた方が満足して生きられる。無限にレパートリーを増やして毎日おいしい料理を提供しなければいけない――みたいな呪縛は、日本に限らず他の国にもある悩みだと思うんですが、うちはこれでいいんだ、毎日ハンバーグだろうと、ただ焼いただけの野菜だろうと、これで私は満足、という線を引けた方が幸せだし、生きやすくなると思うんです。
食べ物って実はドロドロした話も多い

――「食べること」は人間の根源だからこそ、根深く複雑でもあります。インドの北東部にあるナガランドという地域の豚肉のアクニ煮の回。「強烈な匂いの食は人を繋げもするが、一方で人の分断を生む」という話には深く考えさせられました。
ナガランドの家庭ではアクニという納豆を作っていて、カレーのようなスパイスではなく納豆を調味料として使う。さらにナガランドはキリスト教の地域なので豚肉を食べる。インドの中では異端ともいえる食文化がある地域なんですね。
豚肉を納豆で長時間煮込むというと匂いがすごそう! と思うんですが、実際は味噌煮込みみたいな旨味のある匂いで、日本人にとっては親しみのあるいい匂いなんです。私がいい匂い、お腹すいたーと言うと、彼らはすごく喜んでくれて一気に心の距離が縮まった。でもアクニの匂いはインド本土の人たちにとっては臭い以外の何物でもなくて、ナガランドはもともと貧しい地域だったこともあって「臭いものを食べる人たち」として差別を受けてきた。

――食べ物はときにはヘイトを加速させる一因にもなる。
よく「おいしいものを食べるって幸せだよね」とか「食べ物は人を繋ぐよね」と言うし、私もそうだと信じていましたが、世界を旅すればするほど、それって綺麗すぎる話だなと感じもしました。食べ物って実はドロドロした話も多い。たとえば、日本でこんなに牛乳が飲まれているのも、元をたどると戦後アメリカが国内で余っていた脱脂粉乳を日本の学校給食に押し付けたから――みたいな社会的・政治的背景があったりもする。
本自体は写真もたっぷり載せてますし、寝る前に気軽に読んでもらえる内容になってますが、いろんなレイヤーでの受け止め方ができる本になっていると思うので、世界にはこんな料理があるんだ、こんな暮らしもあるんだ――というところから、いろんな思いをめぐらせてもらえたらうれしいですね。
岡根谷実里(おかねや・みさと)
世界の台所探検家。1989年長野県生まれ。東京大学大学院工学系研究科修士修了後、クックパッド株式会社に勤務し、独立。世界各地の家庭の台所を訪れて一緒に料理をし、料理を通して見える暮らしや社会の様子を発信している。30以上の国と地域、170以上の家庭を訪問。講演、執筆、研究などを行う。京都芸術大学客員講師、立命館大学BKC社系研究機構客員協力研究員、大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)連携研究員。著書に『世界の台所探検 料理から暮らしと社会がみえる』(青幻舎)、『世界の食卓から社会が見える』(大和書房)など。
X @m_okaneya
文=井口啓子
撮影=佐藤 亘
あわせて読みたい
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り]
-

- タケノコの皮で簡単おやつ「チューチュー梅」 熱中症対策にも
- 2025/05/02 04:53 ウェザーニュース今が旬のタケノコ。この時期、店頭には皮付き生タケノコが並びます。生…
- (ウェザーニューズ)[スローフード,自然化粧品,健康食材,春グルメ,レシピ]
-

- 心斎橋「ホテル日航」にメロン半玉使ったパフェ 2種類セットで食べ比べも
- 「ホテル日航大阪」(大阪市中央区西心斎橋1、TEL 06-6244-1695)1階ティーラウンジ「ファウンテン」が5月…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術,旅,肉]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[野菜]
-

- 大芝高原「桑茶ミルクプリン」発売 3施設がコラボ、シルク文化の魅力発信
- 南箕輪村開発公社大芝高原(南箕輪村)と岡谷蚕糸博物館(岡谷市)、駒ケ根シルクミュージアム(駒ヶ根市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[長野県]
-

- 「夫との旅行はムリ!」“店構えでおいしいか分かる”と言い張る夫と2時間歩いた後の悲劇
- ゴールデンウイークを控え、旅行の計画を立てている人も多いだろう。だが、中には日常生活では問題がなく…
- (All About)[まちグルメ]
-

- 5月2日の月が教えてくれるヒント 親しくなりたい人を誘う
- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと11日。 月は蟹座で満ちていきます…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
-

- 【フブ】Vネック&チームロゴがポイント!ユニセックスで着用可能な注目アイテム、Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[新商品]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.