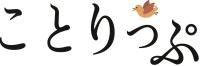かわいいご利益アイテムを求めて、異国情緒が香る宇治の禅寺「萬福寺」へ

昨年の大河ドラマを機に、人気継続中の『源氏物語』の舞台、宇治。観光中心部から少し離れた場所にたたずむ黄檗山「萬福寺」は、2024年12月、天王殿・大雄寶殿・法堂の3つの建物が同時に国宝に指定されて注目を集めました。桜、青もみじ、蓮、紅葉など四季折々の色彩に染まる境内には、どことなくエキゾチックな空気が漂います。話題の国宝建築や仏像の鑑賞と開運祈願にでかけませんか。
JR奈良線または京阪宇治線の黄檗駅から歩いて5分ほど。宇治観光の中心部からは北へ約2.5kmの閑静な一帯に、黄檗宗の大本山「萬福寺」の境内が広がります。
お寺のはじまりは、今から360余年前。インゲン豆や、スイカ、レンコン、タケノコ(孟宗竹)、煎茶などを日本にもたらした中国の僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師により開かれました。
三門、天王殿、大雄寶殿(だいおうほうでん)、法堂の4つの建物が一直線に並ぶ、禅寺の特徴的な伽藍配置。まずは三門をくぐった先の国宝3棟のうちの1棟、天王殿でお参りを。
四天王に見守られつつ、光り輝きながら中央にどっしりと座っておられるのは、七福神のひとり、布袋尊。その後ろに立つのは、守護神の韋駄天(いだてん)さん。お釈迦様のために夜な夜な走り回って食材を集めて朝食を用意したことが、「馳せ走る(=馳走)」の語源となり、「ご馳走さま」という言葉につながったのだとか。
天王殿の奥、本堂にあたるのが、境内で最大のスケールを誇る大雄寶殿(国宝)。世界三大銘木のひとつとされるチーク材を使った日本唯一の歴史的建造物です。
中央に本尊の釈迦如来坐像、左右に脇侍、周囲に十八羅漢像を安置。日本の仏様とは雰囲気の異なるお顔立ちも見どころです。
大雄寶殿と回廊でつながる斎堂の軒下には、木製の巨大な魚が。こちらは開梆(かいぱん)といって打ち鳴らして時を知らせるためのもの。木魚の原形といわれています。
開梆のすぐそばには、青銅製の雲版(うんぱん)も見られます。
斎堂から回廊づたいに、隠元禅師をお祀りする開山堂へも足を延ばしてみて。境内の建物はすべて屋根の付いた回廊で結ばれていて、天気に左右されずお勤めや法式を執り行えるようになっています。傘を使わず境内をめぐれるため、雨の日にお参りするのもおすすめです。
お参り後は、斎堂の隣にある売店へも立ち寄って。開梆や布袋さんをモチーフにしたお守りやご朱印、萬福寺限定「禅語おみくじ」など多彩なご利益アイテムが授かれます。
SNSではユーモアたっぷりの自虐的なつぶやきで親しまれていますが、ひとたび境内に身を置くと、背筋がしゃんと伸びるような凛とした空気が満ちています。魅力あふれる禅寺へ、お参りにでかけてみませんか。
あわせて読みたい
-

- 新生活の最初のご褒美でQOLを爆上げ!【UCC】のコーヒーメーカーがAmazonで販売中‼
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[お茶]
-

- 鞍手町歴史民俗博物館別館完成 炭鉱の歴史学べる施設へ
- 鞍手町歴史民俗博物館別館完成記念式典が5月7日、中央公民館(鞍手町小牧)で行われた。(宗像経済新聞) …
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[観光]
-

- 「剃る」も「整える」もパナソニックのボディシェーバーで完結。全身の体毛ケアができちゃうぞ
- 「剃る」も「整える」もパナソニックのボディシェーバーで完結。全身の体毛ケアができちゃうぞimage: Amaz…
- (Gizmodo Japan)[旅]
-

- 上品かつ目を引く、美しい青の文字盤!【シチズン】の腕時計がAmazonで売り出し中‼
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[春グルメ,気象]
-

- 今さら人に聞けない大人美容の正解『LDK』6月号
- 広告や口コミサイトに左右されない批評4月28日、使う人の目線で女性の暮らしに関する様々なモノをテストす…
- (美容最新ニュース)[夏グルメ]
-

- 西伊豆にコーヒースタンド「ほたるの風」 海望む展望デッキも設置
- 西伊豆町の大浜海岸近くでコーヒーや焼き菓子を提供するコーヒースタンド「ほたるの風」(西伊豆町仁科)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[果物]
-

- あのBEAMSが南山梨をプロデュ―ス!? 南山梨の朝を満喫する“朝活ツアー”で心も身体もリフレッシュ
- 身延山久遠寺。夕べの行脚(あんぎょ)をするお坊さんたち。 山梨と言えば、富士山や果物。だけではありま…
- (CREA WEB)[紅葉,紅葉狩り]
-

- 板橋で「母の日マルシェ」 子どもと一緒に楽しむ体験プログラムも
- 地域振興活動を手がける板橋駅まちづくり応援団が5月11日、ハイライフプラザいたばし(板橋区板橋1)2階で…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[花見]
-

- オールインクルーシブの絶景宿「焼津グランドホテル」で過ごす、贅沢な休日
- 静岡・焼津の高台にひっそりと佇む「焼津グランドホテル」。お食事やドリンク、アクティビティまでもが宿…
- (ことりっぷ)[ことりっぷ]
キーワードからさがす
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.