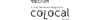京都の狭い路地の先にある長屋。減築して三角形の中庭をつくったbefore/afterは?
こんにちは。多田正治アトリエの多田正治と申します。2019年に連載をしておりまして、このたび5年ぶりに再開させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
私は設計事務所を京都に構えており、京都を中心に関西で建築設計をするかたわら、紀伊半島の熊野エリアでも10年にわたり地域に関わる活動をしています。前回はその様子を京都・熊野の2部構成でお送りしました(ご興味ある方は、ぜひバックナンバーも併せてご覧ください)。現在も変わらず、関西と熊野で活動をしていますので、引き続きそれぞれのプロジェクトについて紹介していこうと思います。
再開1回目の物件は、京都市中心地の細路地の奥にある長屋〈仏光寺の家〉。京都特有の風景を守りながら現代の住宅にリノベーションしていくプロセスをお届けします。
暮らす人の息づかいを感じる長屋京都市の中心地、四条駅の近くに〈佛光寺(ぶっこうじ)〉というお寺があります。南北を走る烏丸通りと東西を走る四条通り。京都市でもっとも賑わうこのふたつの通りに挟まれた繁華街にありながら、大きな境内に足を踏み入れると周辺の喧騒が嘘のような空間が広がるお寺です。ぼくの印象では神聖で静寂な空間というよりは、誰に対しても開かれた公園のような場所、という感じです。

佛光寺の境内の様子。(撮影:阿部彩音)
今回紹介するのはそんな佛光寺の近くにある住宅です。このエリアでは、繁華街から一本通りを中に入ると、住宅街になります。昔ながらの町家もあれば、新しく住宅、マンション、最近ではオフィスビルに建て替わっていたりもしている職住近接のまちです。

〈仏光寺の家〉の近隣のまち並み。(撮影:阿部彩音)
そのエリアの一角にある長屋を住宅として改修しました。立地は、「トンネル路地」と呼ばれる路地の先。幅の狭い、しかも頭上にはほかの家の2階がまたがっているような、まさにトンネルのような路地です。

トンネル路地を見る。奥の正面に見える建物が今回の物件。
この路地は、奥にある数戸の住宅のための生活道路です。路地を抜けた先には井戸(もう使えないですが)やお地蔵さまもあり、この路地自体が数戸の住人たちの共用の生活の場となっていることがうかがえます。
このようなトンネル路地や長屋がひしめき合う住宅地の風景から、古くから続く京都の暮らしの営みをいまでも感じることができます。

既存図面。トンネル路地の先にある長屋。枠内が該当部分。

トンネルを抜けた先の外観。

玄関から入るとツギハギだらけの内装が見える。

玄関をみる。中は薄暗い。

正面に見える白い壁が昔のユニットバス。今では信じられないぐらい小さい。

路地から見た外観。コンクリートの板で塞がれているが、足元に井戸がある。

2戸のうちのひとつ。納屋。
さて、この長屋の2区画分を合わせて住宅へと改修します。路地奥の長屋なので、以下の課題を解決する必要があります。
・周りが立て込んでいてプライバシーの確保が難しい。
・同じ理由で採光がとりにくい。
ここにお住まいになるのは、セミリタイアされた年配のご夫婦です。おふたりから普段の住まい方などをお聞きすると、「リビングにはあまりいない」「食卓にてふたりで語らうことがほとんど」とのこと。また「仕事は続けているので、独立した書斎がほしい」といった要望がありました。
住まい手の要望や物件の課題を突き合わせて考えた結果、「減築して、長屋を二分する三角形の庭を差し込む」というアイデアが生まれました。図にするとこんな感じです。

減築して三角形の中庭を差し込む。

改修後の1階平面図。かつての納戸はワークルーム(書斎)に変更。

中央部分(ピンクの点線部分)を一部減築して、中庭とブリッジを設置。2階にはベッドルームがある。
かつての納戸は独立したワークルームに変更し、中庭を挟んでダイニングを設置。それらふたつの空間は中庭に対して開口部をとることができるので、周囲の路地に対する外側はしっかりと閉じることができます。
ふたつの空間は、中庭を渡るブリッジでつながります。ブリッジは3〜4歩程度という短い距離ですが、「ブリッジを渡る」「中庭を越える」という体験は、意識を切り替え、なおかつワークルームの独立性を高めます。
先に完成した写真をお見せしてしまいますが、こんな仕上がりです。

ブリッジ内観。奥に見えるのがワークスペース。左右に坪庭が見える。

ブリッジ外観。手前は坪庭。ブリッジの下は地面が続いていて、上は空へとつながっている。
メインの考え方が決まり、なんとか設計を終えることができました。いよいよ工事に取りかかります。
狭い路地の先にある工事現場狭い路地のため、工事用の重機はもちろん、軽トラなども進入することができません。解体で出た廃材を搬出するのも、施工のための資材を搬入するのも、すべて人力。手運びです。小さな住宅ですが、どうしてもコストが余分にかかってしまいます。
そんなとき「その解体工事、私たちが引き受けます!」と声をあげてくれたのは、建築主の娘さん夫婦でした。DIYが得意なご夫婦だったこと、設計や施工の最終調整に手間取り、本格着工までたっぷり時間があったこと。そして世界はコロナ禍真っ只中で、サービス業に従事する娘さん夫婦は休業を余儀なくされていたこと。そんな事情が重なって、解体工事の大半をやってもらうことになりました。
こうして解体工事が終わったあとは、既存の軸組とぼくたちの設計の相違点の調整、寸法のチェックなどを行いました。

すっかりガランドウに。大工さんに仮の補強を入れてもらっています。

ここから出た廃材は、手作業で路地の外まで運びました。
「完成」という概念について考える戦前や戦後すぐの古い木造住宅をリノベーションすると、ほとんどの家がとても自由に、大胆に、増改築を繰り返して住み継がれてきたことがよくわかります。
現代の私たちの感覚では、新築の住宅に住み始めると、そこから次に増築したり改築したりするのは20年後や30年後。人生で生活が大きく変化する節目で、住まいに手を加える。そんな感じではないでしょうか。新築でもリノベーションでも、住宅が「完成」して住み始める。それと同時にその住宅への建設という行為がすべて終了すると考えているのだと思います。
しかし昔の人はそうではなかったのでしょう。家に手を加えるのはわりと日常的な行為で、自分たちが住みやすいように常にカスタマイズし続ける。「完成」という概念が希薄だったのだと思います。
さて、この〈仏光寺の家〉もそんな古い住宅の例に漏れず、自由に大胆に増改築されていました。
もともとあった柱や梁が切断され、別の方向へ梁が架けられ柱で支えられていたり、きれいに製材された材料ではなく、別のところで使われていた鴨居や敷居が転用されていたり。場当たり的に見えて、理にかなっているように感じます。時代ごとに複数の大工さんが作業を重ねてきた様子がうかがえて、これまでの試行錯誤を追体験しているような気になります。
そして今回は私たちがそこに手を加え、新しい試行錯誤を組み込んでいきます。解体工事であらわになった軸組に補強を加えたり、腐朽している部分を取り替えたり、随時更新していきました。

写真右上、手前から奥へと伸びている黒い既存梁が細かったので、その下から補強する梁を加えています。
歴代の増改築に呼応する改修この住宅の設計で工夫した点をもうひとつ紹介します。
度重なる増改築のなかで、この住宅は屋根を伸ばして家を大きくしているようでした。そのため部屋の一部は頭がぶつかるほど、軒先・天井が低かったのです。そのスペースの有効活用を考えた結果、冷蔵庫や食器棚などを設置することで、使える、そして見た目に圧迫感を与えない仕上がりにしています。

軒を伸ばしたため、頭がぶつかるほどに低くなっています。

食器棚、テレビを置くスペースにして使える空間になっています。
また、梁によって浴室の換気扇のダクトが抜けないため、2階のベッドルームのヘッドボードの中にダクトを通して迂回させるなど、目に見えない工夫が積み重なっています。

浴室の換気扇ダクトを2階へと迂回しています。

2階寝室。ヘッドボードの中を換気扇ダクトが通っています。
京都の暮らしと風景を継承していくリノベーション「減築による中庭」の構想やあらゆる工夫を重ねた設計を経て、工事は無事「完成」しました。
生活の中心であるダイニング・キッチンからはブリッジ越しにワークルームが見え、また寝室へと続く階段があります。階段は木やモルタルなどを使って仕上げを変えています。昇降中のちょっとした変化が、小さな住宅の中での豊かな空間体験につながります。

ダイニング・キッチンから中庭をみる。屋根の一部を減築しているので、自然光が入ってくる。(撮影:松村康平)

ダイニングの階段をみる。階段の一部でもあるモルタルの直方体は収納。(撮影:松村康平)

ダイニングとブリッジを低いアングルからみる。外の路地へとつながる。(撮影:松村康平)
もともと納屋だった場所はワークルームになっています。ブリッジやロフトを介してキッチン・ダイニングとつながっています。

ワークルームからダイニングを見る。ロフトにあがるハシゴはもともとの納屋にあったもの。改修前の納屋の写真に写り込んでいます。(撮影:松村康平)

この階段、白い雲の中に入っていくように見えないでしょうか?
白く抽象的な造形の空間を上がって2階の寝室へ。住宅が建て込んだ立地ですが、平屋の住宅が多く、2階からは視線が抜ける眺望があります。

寝室をみる。窓の外に古そうな木造住宅が見える。右側の白い部分は階段室。(撮影:松村康平)

路地からみる。この街区を見守るお地蔵様が鎮座しています。大切にお祀りされています。(撮影:松村康平)
繁華街の裏の、そして路地の奥にあるという、少し変わった立地の住まいのリノベーション。現代では、こういう立地の場合、すべて更地にしてマンションを建ててしまうというのが主流の考え方だと思います。
しかし、お地蔵さんがあったり井戸があったり、住まいの「完成」を意識せずに住み継いでいたり。長年、そこでともに暮らしてきた人たちの息づかいを感じるまちです。それをしっかり継承して遺していくことも大切なことだろうと、再認識したプロジェクトでした。
writer profile
Masaharu Tada
多田正治
ただ・まさはる●1976年京都生まれ。建築家。〈多田正治アトリエ〉主宰。大阪大学大学院修了後、〈坂本昭・設計工房CASA〉を経て、多田正治アトリエ設立。デザイン事務所〈ENDOSHOJIRO DESIGN〉とシェアするアトリエを京都に構えている。建築、展覧会、家具、書籍、グラフィックなど幅広く手がけ、ENDO SHOJIRO DESIGNと共同でのプロジェクトも行う。2014年から熊野に通い、活動のフィールドを広げ、分野、エリア、共同者を問わず横断的に活動を行っている。2024年より武庫川女子大学生活環境学科准教授。主な受賞歴に京都建築賞奨励賞(2017)など。
credit
編集:中島彩
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始
- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術]
-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ
- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- 竜王のアウトレットパークで「パンマルシェ」 全国のパン店が出店
- 全国のパン店が出店するイベント「パンマルシェ」が5月3日~5日、三井アウトレットパーク滋賀竜王(竜王町…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[京都府]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.