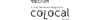「栗」の鬼皮・渋皮、捨てないで! 汚れた子ども服が“草木染め”でかわいく復活
こんにちは。「食べもの・お金・エネルギー」を自分たちでつくる〈いとしまシェアハウス〉のちはるです。
栗拾いをしたら、我が家で必ずつくる「栗の渋皮煮」。つくったことがある方はご存じかと思うのですが、渋皮ごと煮込んだ栗の煮汁って、すごく美しい色なのです! ビンテージワインのような深い赤茶色。あまりに美しいので、いつもこれで何か染められないかと考えていました。
そこで、今回はちょっと汚れがついてしまった子ども服をこの煮汁で草木染めし、復活させたいと思います!

栗の渋皮煮をつくると、赤茶色の美しい染液ができます。
大人の服を草木染めするには、それなりの量の煮汁が必要ですが、小さな子ども服なら、少ない量でOKなのがうれしいところ。
そして、既に汚れがついてしまっている服ならちょっと失敗しても「まあいっか」とおおらかな気持ちになれます(笑)。

白とピンクのTシャツで染まり具合を比べてみたいと思います。
染めるのは、テキスタイルデザイナーの友人からいただいたかわいいTシャツたち。
食べこぼしのシミが気になって、なんとなく手にとらなくなってしまったこの服たちを、栗染めで生まれ変わらせたいと思います。
栗の“部位”ごとで、染液の色が違う!
栗ご飯をつくったときに出る栗の皮も、染液の素材として使えます。
ひとことに栗といっても、部位によって色味の出方が違うのをご存じでしょうか?
渋皮:赤みの強い茶色
鬼皮:深い茶色
栗のイガ:黄が強い茶色
私の好みは、渋皮煮の際に出る赤茶色なのですが、これで服を染めるには大量の渋皮が必要なので、今回は使える素材を全部ミックスして使います。

栗の草木染めレシピ
<準備するもの>
・染める服や布
・栗の渋皮、鬼皮、イガ
・焼きミョウバン
・牛乳または豆乳
<染め方>
(1)布の下処理をする

タンパク質の成分は色素と反応しやすいため、布を牛乳や豆乳に浸すとよく染まります。
綿や麻などの植物繊維は染まりにくく、色落ちしやすい特徴があるため、色素が定着しやすいように下処理をしておきます。
その方法は、染める布を牛乳や豆乳に浸すというもの。牛乳(または豆乳)と水の分量は、1:1くらいが目安。染める布を20〜30分ほど浸したら、水で洗い流さず、よく絞って乾燥させます。
時間がない方はこのステップを飛ばしても大丈夫ですが、仕上がりの色は薄くなります。
(2)染液をつくる

栗の渋皮、鬼皮、イガを鍋に入れ、ひたひたになるまで水を入れたら火をつけて30分〜1時間ほど煮出します。色が抽出できたら、布でこして染液の完成!
色が出にくいときは、重曹をひとつまみ入れると色が出やすくなります。入れすぎると、布が染まりにくくなるので注意。
ちなみに、栗の渋皮煮をつくったときの煮汁を活用してもOKです。(今回、私は渋皮煮の煮汁に鬼皮やイガを足しました)
(3)布を染める

汚さないようにしていた白いTシャツを染液の入った鍋へ。なんだか悪いことをしているような気分でちょっとドキドキします。
布を染液に浸し、沸騰しないように弱火で20〜30分ほど煮ます。このとき、菜箸などで布を動かしながら煮ると、染めムラがつきにくくなります。
服へのダメージなどが気になる方は、煮ずに漬け置きでもOKですが、その場合は一晩ほどじっくり漬け置きしてください。
(4)染液を洗い流す

ピンク色だったTシャツがきれいな茶色に染まりました。プリント部分はそのまま残ってかわいい!
布を水洗いし、余分な染液を洗い落とします。色が薄いようなら、もう一度染液で煮ていき、好みの濃さになるまで(3)(4)を繰り返します。
(5)媒染液につける

水で洗うと、ずいぶん色が落ちました。
続いては、色を布に定着させる「色止め」をするため、媒染液につけます。草木染めは色止めをしないと色が落ちてしまうので、ここは大切なプロセス。
まず乾いている布の重量の5%の焼きミョウバンを用意し、少量のお湯で溶かします。ステンレス製のボウルに布を入れ、ひたひたになるまで水を入れたら焼きミョウバン液を入れて混ぜ、20分ほど漬け置きします。
ちなみに、媒染液の濃度が高いほど濃く染まるといわれています。
(6)乾燥させる

左が白いTシャツ、右がピンクのTシャツでした。鍋から出したときはもっと濃い茶色だったのですが、乾くと色が淡くなりました。
媒染液をよく洗い流したら、しっかりと乾かして完成! シミ部分もきれいに染まり、やさしい栗の色合いがかわいいTシャツに生まれ変わりました。
イラストなどが入った服で染め物をすると、印象がガラッと変わっておもしろいです。娘も気に入って大喜び!

こちらの服は、白から茶色に染めたことでちょっと大人っぽい印象になりました。

ベースの色がピンクだったこちらは、ちょっと明るめに染まりました。ピンクのプリント部分がきれいに残ってポップな感じの仕上がりに。こうして染まる部分と染まらない部分があるのも、自分で服を染める楽しさかもしれません。
栗の草木染めで感じたこと
栗の渋皮、鬼皮、イガで煮出した染液。
今回、自分のイメージした茶色を出すために、3回も染液で煮直しました。染液だけ見れば濃い色に感じたのですが、実際は薄い色にしか染まらず、濃く染めることの難しさ、草木染めの手間や大変さを実感。同時に、一度でしっかり染まる現代の染色技術、あらためてすごいなあ! と感じました。
服を染める楽しさも感じつつ、何よりうれしかったのは「汚れても濃い色で染めたらまだ使える」と思えるようになったこと! “染める”という選択で、捨てずに服を長く楽しめると思うと、すごくワクワクしました。
これからは、子どもが服を汚しても、前より穏やかな気持ちでいられそうです(笑)。
次回は、化学染料を使ってパキッとした色合いに染めるのも試してみたい!
information
いとしまシェアハウス
公式サイト
writer profile
CHIHARU HATAKEYAMA
畠山千春
はたけやま・ちはる●新米猟師兼ライター。3.11をきっかけに「自分の暮らしを自分でつくる」活動をスタート。2011年より鳥を絞めて食べるワークショップを開催。2013年狩猟免許取得、狩猟・皮なめしを行う。現在は福岡県にて食べもの、エネルギー、仕事を自分たちでつくる〈いとしまシェアハウス〉を運営。2014年『わたし、解体はじめました―狩猟女子の暮らしづくり』(木楽舎)。第9回ロハスデザイン大賞2014ヒト部門大賞受賞。ブログ:ちはるの森
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦
- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS]
-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに
- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り,植物,福岡県]
-

- スープもジュースもNG。飲み物すら制限するようになった「声」の命令
- 「食べるな」「口に入れるな」 / (C)もつお/KADOKAWA中高6年間を女子校で過ごした作者のもつおさん。元…
- (レタスクラブニュース)[健康食材]
-

- 日本橋三越内に「サーティワン三越」が期間限定オープン!日本橋の老舗や人気パティシエと夢のコラボフレーバーも誕生
- 「日本橋三越本店」と「サーティワン アイスクリーム」が初の協業をし、2025年4月30日に日本橋三越 本館1…
- (Walkerplus)[秋グルメ]
-

- 空気清浄・脱臭・除湿を1台でこなし、年中快適な空間に!より清潔性が増した、三菱電機「美空感」新モデル
- 三菱電機は、空気清浄、脱臭、除湿の3つの機能を1台に集約した空清脱臭除湿機「美空感」の新モデルとして…
- (GetNavi web)[エネルギー(ぼんやり学会)]
-

- お弁当で食中毒に!? 避けるべき意外なおかず・調理法【管理栄養士が解説】
- 【管理栄養士が解説】夏は雑菌が増えやすく、お弁当の食中毒リスクも高くなります。避けるべきおかずや調…
- (All About)[レシピ]
-

- 三井住友銀行成増支店が区内初の「オリーブラウンジ」に スタバも出店
- 三井住友銀行成増支店(板橋区成増2)が4月14日、銀行とカフェとシェアオフィスが一体となった「Olive LOU…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[シェアリングエコノミー]
-

- 飯田に「信州飯田アルプス食堂」 信州福味鶏など地元食材メニューを看板に
- 飲食店「信州飯田アルプス食堂」(飯田市中央通り3)が4月29日にオープンする。(飯田経済新聞) 長野県産…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東日本大震災]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.