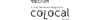精神科医が行く「初めての酒蔵見学」 酔わないわけにはいかなくて……
さまざまなクリエイターによる旅のリレーコラム連載。第41回は、精神科医の星野概念さん。
発酵、なかでも日本酒に興味があり、尊敬する醸造家に会えるならば、地方にまで足を運ぶことを厭わないという星野さん。
しかしながら、まだ酒蔵見学に行ったことがなく、実際の酒造りをしている醸造家にも会ったことなかった頃、ある酒蔵を行く機会を得る。
聞きたいことがたくさんあったようですが、初めての体験で緊張していたという星野さん。実りのある旅になったのだろうか。
発酵とメンタルヘルスは似ている旅の多くは、メンタルヘルスや発酵に導かれることが多いです。両者は僕のなかでは強いつながりがあります。目に見えない微細な変化が実は常に生じ続けていて、あるときそれが目視できたり、実感することができるものになるというのは多くの物事に共通したことかもしれません。僕はメンタルヘルスや発酵の学びを通してそれを感じています。
人のこころは簡単には変わりません。でも、長い年月を振り返ってみると、いろいろな物事に対する向き合い方は変化しているはずです。この変化に関係するのは年齢だけではありません。さまざまな経験や取り組んだ自己研鑽のような物事が、年月を経て本当に少しずつかたちになっているのだと思います。
酒づくりで考えてみると、タンクの中に入っているのが水と米だけだったはずなのに、実は地道に発酵のプロセスが進んでいて、目に見えない反応がタンクの中ではたくさん生じています。そしてあるとき、そんな少しずつの変化が形になり、タンクの中の液面にポコポコと反応が現れ始めるのです。
メンタルヘルスと発酵の重なりについては、これ以外にもたくさん感じていることがあり、僕はそれを追い求めて旅をしています。自分の活動地域ではなくても、メンタルヘルスの中で気になる取り組みをしている場所を見学できる機会があれば出かけていくし、尊敬する醸造家とコミュニケーションできる可能性があるならば、迷わず足を運んでいます。そんな旅が始まったときの体験を書こうと思います。
もう随分前のこと。日本酒に魅了され、日々いろいろな酒を知るなかで、酒がどのように生まれるのか知りたいと考えるようになりました。どうやらその過程を醸造と呼ぶらしく、発酵という現象が関係しているらしいこと知り、それらについての本を読むようになりました。
酒づくりは、杜氏と呼ばれるディレクターのもと、蔵人さんたちが力を合わせて行われる。発酵には菌がかかわっている。酒づくりには並行複発酵と呼ばれる、複数の菌がかわるがわる活躍する発酵のプロセスがあり、発酵のなかでも最も複雑なものらしい。並行複発酵のなかでまず活躍するのは麹菌。これは国を代表するカビで……。

このようなかたちで、酒づくりに関する知識が体系化されていくのが楽しく、酒のおもしろさを教えてくれた店の店主に身につけた知識を披露するようになりました。
そんな場で店主や、酒づくりに詳しい常連さんから聞く、酒づくりの現場を見学した話はとてもおもしろく、日に日に現場に足を運びたい気持ちが強くなっていきました。そのときの僕は、酒づくりに関して超頭でっかちで、知識はあるのに現場の実感をまったく知らないバランスの悪い状態だったのです。店主や常連さんは、そんな僕を秋田への蔵見学の旅に誘ってくれました。
当時の僕は、飛行機に乗るとき、毎回死を覚悟しながら乗っていたので、飛行機での行き来をすると聞いて若干ひるみましたが、千載一遇の機会を逃す手はありません。
蔵見学は僕にとって興奮の連続でした。学んだ知識、イラストや写真で眺めていた光景が目の前で展開されていくのです。さらに、酵母の顕微鏡写真をみせていただいたり、絶賛発酵中のタンクのかおりを嗅がせていただいたり、少しだけ試飲させていただいたり。
今思い出してもあのときの鮮烈な興奮の感覚は自分のなかに色濃く残り続けています。
2泊3日の蔵見学の初日の夜。その蔵を代表する蔵元さんとの会食が予定されていました。こんなスペシャル続きでいいのだろうかと興奮しつつ、会食の直前はとても緊張していました。そのせいか、末席でおとなしく……、なんてしていられるわけがありません。僕には実際に醸造にかかわっている人たちに聞いてみたいことが山ほどありました。本で読んでいるだけでは解消されない疑問を現場に身を置いている方々に質問できるうれしさ。
これは酒づくりに限ったことではありませんが、このときの僕はそのうれしさで舞い上がりすぎて視野狭窄。まわりが見えておらず、目の前の酒を飲み、目の前にいる酒づくりに従事している尊い人を質問攻めにしていたそうです。
していたそうです、と書いたのは、そのときの記憶がまったくないからです。先ほど書いた、この旅に誘ってくれた店主や常連さんの話に嘘がなければ、僕は蔵元さんをロックオンしたように話し続け、蔵元さんもそれにしっかりと答えてくれていたそうです。
その後に行った2軒目では、蔵元さんがすすめるどぶろくを皆で飲んだそうです。はい、覚えていません。そして最後に僕はカレーを食べていたそうです。はい、覚えていません。
店主や常連さんとは今でも仲良くしてもらっていますが、時々この人たちはふざけて事実ではないことを言います。でもきっとこのときのエピソードは嘘ではないのだと思います。
なぜなら、翌日、かなり酔いを持ち越していたからです。朝方近くに帰り、起きたのは集合時間の5分前。我ながらよく起きたと讃えたいくらいの状態でした。その日も蔵見学が予定されていましたが、そのときに考えていたのは「もうしばらく酒は飲まないでいいな」ということでした。

移動する車に乗り、皆で朝食を買うためにコンビニに寄りました。僕は朝食をとりたい状態ではなかったので水だけ購入したところ、当時使っていたポイントカードかなにかの特典が当たったと言われました。
当たった商品を取りに行ってくれた店員さんが戻ってきて「金麦(※発泡酒2 )が当たりました。水と同じ袋でいいですか」と言いました。き、金麦……。なんで今当たるのか。いや、ある意味大当たりともいえます。飲酒をするということの趣深さに思いを馳せながら袋を断り、右手に水、左手に金麦を握って車に戻ると、旅の仲間たちに「もう始めるんですか」と言われました。
この旅の体験も、自分をかたちづくる何かに必ずなっているはずです。仲間との絆、妙なくじ運のようなもの、発酵のふしぎ、あとなんだろう。忘れたものもたくさんあるけど、それも含めて貴重な体験。とっても感謝しています。
profile
Gainen Hoshino 星野概念
精神科医として働くかたわら、執筆や音楽活動も行う。いくつかの場所での連載や寄稿のほか、著作もあり。音楽活動はさまざま。著書に、いとうせいこう氏との共著 『ラブという薬』(2018)、『自由というサプリ』(2019)(ともにリトル・モア)、単著『ないようである、かもしれない〜発酵ラブな精神科医の妄言』(2021)(ミシマ社)、『こころをそのまま感じられたら』(2023)(講談社)がある。対話や養生、人がのびのびとできることについて考えている。
text
Gainen Hoshino
星野概念
あわせて読みたい
-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選
- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…
- (コロカル)[おでかけコロカル]
-

- 倉敷・鷲羽山レストハウスがリニューアル 「連れて行きたくなる場所」目指す
- 瀬戸内海や瀬戸大橋を一望できる鷲羽山展望台に隣接する「鷲羽山レストハウス」(倉敷市下津井田之浦、TEL…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材,旅]
-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目
- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒]
-

- 「夫との旅行はムリ!」“店構えでおいしいか分かる”と言い張る夫と2時間歩いた後の悲劇
- ゴールデンウイークを控え、旅行の計画を立てている人も多いだろう。だが、中には日常生活では問題がなく…
- (All About)[コンビニ]
キーワードからさがす
Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.