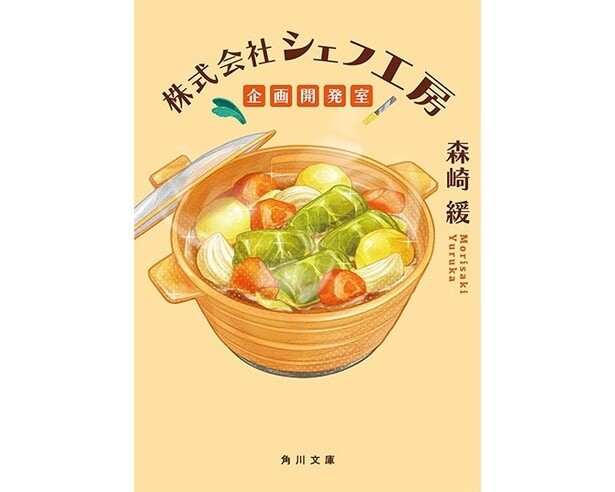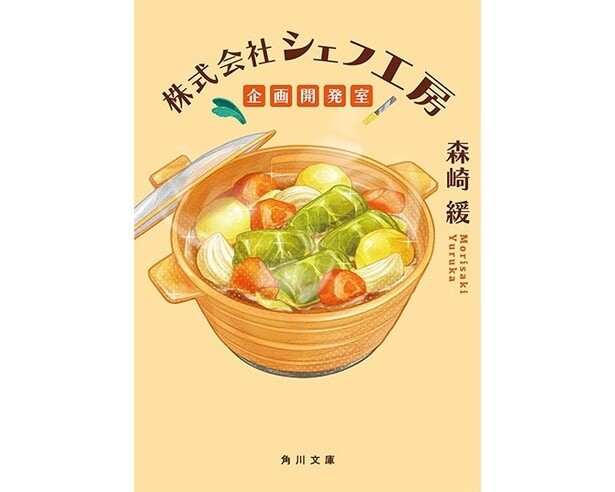
「株式会社シェフ工房 企画開発室」(森崎緩/KADOKAWA)第3回【全4回】
札幌にあるキッチン用品メーカー「シェフ工房」のアイディアグッズに魅了された新津七雪。憧れの「シェフ工房」に入社し製品への熱意が買われて企画開発室に配属される。個性豊かなメンバーに囲まれながら、新津は次のヒット商品を生み出すべく北海道での新生活をスタートする。「株式会社シェフ工房 企画開発室」は、「総務課の播上君のお弁当」シリーズで話題になった森崎緩氏の書き下ろし作品。魅力的な料理のレシピも満載!キッチン用品との出会いで人生を変えた主人公の成長物語をお届け!
※2023年9月28日掲載、ダ・ヴィンチWebの転載記事です
新入社員歓迎会兼ジンギスカンパーティーの会場は、円山公園という場所だった。
シェフ工房は札幌市北区にあるので、地下鉄南北線から東西線へと乗り継いでそこへ向かう。引っ越したての私は札幌の地理に明るくないので、企画開発室の皆さんに連れて行ってもらうことにした。
「地下鉄の乗り継ぎを覚えたら札幌のプロだよ。どこでも行けるよ」
そう話す深原室長は大きなビニール袋を提げている。中には金属製のジンギスカン鍋が何枚か、重ねてしまわれていた。この鍋もシェフ工房の製品だそうだ。
「落ち着いたらいろいろ歩き回ってみるのもいいかもな。遊べる場所も大分あるし」
五味さんもそんなアドバイスをくれた。カセットコンロを詰めた紙袋を両手に持って、ちょっと重そうだ。
円山公園駅を出ると、すうっと冷たい風が吹いてきた。四月三十日の午後六時前、ぎりぎり日没前の気温は思っていた以上に肌寒い。スーツの上にコートを着てきたのは正解だったようだ。
「夜になるとまだまだしばれるからね。気をつけないと」
出町さんがそう言うと、すかさず五味さんが説明を添える。
「『しばれる』っていうのは『すごく寒い』みたいな意味らしいよ」
実際、出町さん始め企画開発室の皆さんもダウンやウインドブレーカーをしっかり着込んでいた。ここまで厚着での野外バーベキューは私も経験がなく、俄然楽しみになってくる。
「北海道の方言って結構いろいろあるんですね」
まだまだ無知な私に対し、出町さんは申し訳なさそうに笑ってみせた。
「ごめんね、何が通じて何が通じないのか、まだわかってなくて。したけど優秀な通訳がいるから安心だっけさ」
「お蔭でバイリンガルになれました」
五味さんも楽しそうに声を弾ませている。せっかく札幌に来たのだし、私も是非、バイリンガルになってみたいと思う。
円山公園には日没前にもかかわらずそこそこの人出があった。赤々と燃えるような空の下にまだ五分咲き程度の桜並木が続いており、その下を花見客と思しき人々が絶えず行き交っている。桜の花びらはソメイヨシノよりも濃いめのピンク色で、エゾヤマザクラというらしい。しかし私の気分は花より団子、園内に入った直後から既にラム肉の焼ける独特の匂いが流れてきて、急速にお腹が空いてきた。
火気の使用が許されているのは公園の東側、桜の開花エリアのみだそうだ。今年の場所取りは営業一課の役目だということで、私たちが辿り着いた時には大きなブルーシートが敷かれ、数人の社員がこちらに手を振っていた。
野外でのジンギスカン経験がない私をよそに、深原室長たちはてきぱきと準備を始める。ブルーシートの上に等間隔でコンロを置き、その上にジンギスカン鍋をセットする。自社製品のジンギスカン鍋は鋳物で、中央が盛り上がった帽子のような形をしていた。この中央の山の辺りでラム肉を焼き、流れ落ちた脂を野菜に絡めて食べるそうだ。だからか鍋には脂を落とすための溝があり、周りに野菜を並べられるよう深めのつくりになっている。
鍋に牛脂を塗り始めた頃、ブルーシート上には出席者が大体揃った。コンロを囲んだ輪がいくつかできあがり、ラム肉やモヤシやキャベツをぎっしり載せた鍋がじゅうじゅうと音を立て、全員に何かしらの飲み物が行き渡って社長が乾杯の音頭を取る。
「新津さんの今後の活躍と、シェフ工房のますますの発展を願いまして――乾杯!」
「かんぱーい!」
そこからはもう大変だった。新入社員歓迎会の題目は伊達ではなく、私はいろんな人から声を掛けられ、挨拶もされ、焼けたばかりのお肉や飲み物を勧められまくった。今年度の新入社員は私一人ということで、実質主役みたいなものだ。
「新津さん、次何飲む?ビールも焼酎もウイスキーもあるよ」
コップが空になれば深原室長が飛んできて、声を掛けてくれるし、
「ほら、お肉焼けたよ。野菜も食べな、野菜も」
皿が空になれば五味さんがジンギスカンを盛りに来てくれるし、
「おにぎりも食べな。ジンタレとご飯って相性いいんだから!」
出町さんが美味しい塩おにぎりを持ってきてくれたりと、さながらVIP待遇の飲み会だった。
それでも企画開発室の皆さんとはここ一ヶ月だけで顔見知りとなっていたからいいものの、他の部署の方々はほとんど初対面みたいなものだ。そんな人たちに代わるがわる挨拶をされて、私は顔と名前を覚えるのにあたふたしていた。お酒も入っているから余計にだ。
「長野から来たんだって?はるばるすごいねえ」
「こっち来ること、ご両親は反対しなかった?」
「へえ、うちの製品のファンなんだ。そういうの嬉しいね」
いろんな人からいろんなことを聞かれて、一つ一つ正直に答える。そのついでに飲み物やお肉を勧められ、おにぎり以外にもおつまみやら、お菓子やらをたくさん分けてもらった。気がつけば私の皿は山盛りだし、座った膝の上からはみ出すくらい食べ物がいっぱい積まれている。滅多に飲まないウイスキーのお湯割りを堪能しつつ、私はジンギスカンを心ゆくまで味わった。
火を通したラム肉は柔らかく、豚や牛とは違う肉の食感がある。羊の肉なのに微かに牛のミルクのような匂いがするのが不思議だ。出町さん言うところのジンタレ――ジンギスカンのタレはすりおろし野菜の入ったやや甘めの味つけで、ラム肉はもちろんご飯とも確かによく合った。脂の染み込んだモヤシやキャベツはシャキシャキの歯ごたえで、これもまたタレとの相性がいい。
地元で食べたジンギスカンはタレに漬け込んでから焼くタイプだったけど、生肉を焼いてからタレにつけて食べるのも大変美味しい。長野も北海道もジンギスカンのルーツは似通っていて、元々は戦前、綿羊を食用にすることから始まったという話だ。そんな歴史があったからこそ今の美味しいひとときがある。私はラム肉と共に歴史の重みを嚙み締めた。
「今年もすごい歓待だな」
不意に、隣で男性の声がした。
ラム肉を頰張りながら顔を上げると、うっすら見覚えのある男性が隣に腰を下ろした。髪は柔らかそうなスパイラルパーマ、今にもあくびをしそうな眠たげな目の、どこかアンニュイな雰囲気の人だった。気だるげにネクタイをゆるめたその人が、やや同情的な口調で続ける。
「去年は俺が新津さんみたいな扱いだった。大丈夫?食べきれなかったら言って」
私もよく食べる方ではあったけど、おにぎりやおつまみの残りは持って帰ろうかと思い始めていた折だった。会釈と共にお礼を言っておく。
「ありがとうございます。ええと……」
確か、営業部の人だったはずだ。ぼんやりした記憶はあるものの、酔いも手伝ってかとっさに名前が出てこない。
すると男性は、首から提げていた社員証をこちらに掲げた。
「営業部の茨戸です。去年入社したばかりのぺーぺーだけど、よろしく」
社員証には確かに『営業部一課 茨戸 築』とある。ということは私の一年先輩だ。
「新津です、よろしくお願いします」
私が挨拶を返すと、茨戸さんは控えめに笑った。作っているという感じではないものの、省エネを心掛けたような笑い方だ。
「堀井部長が新津さんのこと褒めてたよ。『開発にすごく情熱的な新人が来たから見習いなさい』って送り出されてきたとこ」
彼が視線で示した先には、コップを傾けながらもこちらを窺う堀井部長の姿があった。私に気づくと静かに片手を上げてみせる。
「すごいな、部長にそこまで言ってもらえるなんて。俺なんて叱咤ばかりなのに」
茨戸さんの話し方は冗談みたいに軽かった。どこまで鵜吞みにしていいのかわからない気安さと、ともすれば笑い飛ばされそうな摑みどころのなさがあり、こういうタイプの人とは今まで接点がなかったなと思う。
「長野県から来たんだっけ。北海道はもう慣れた?」
「まだ一ヶ月なので、慣れた感じはしないですね。住み心地はすごくいいですけど」
長野市と札幌市は似たところがある。海に面さない内陸部であり、冬には雪が積もってウインタースポーツが盛ん、オリンピックの舞台になった点も同じだ。もっとも気温は札幌の方が断然低い。だから冬が来るのが楽しみな半面、少し怖かったりもする。都市として規模が大きいのは札幌の方だし、今住んでいる豊平区は何かと便利な立地なので暮らしやすさは実感していた。
一番感じているのは、シェフ工房に入社できたという喜びだ。仮にシェフ工房が札幌以外の都市にあったとしても、私は迷わずそこへ移り住んだことだろう。
「せっかく憧れの会社に入れたので、頑張って慣れたいと思っています」
そう続けた私に、茨戸さんは目を見開いた。透明なコップに注いだビールを一口飲んだ後、うろんげに聞き返してくる。
「憧れの会社?うちが?」
「はい。就活の段階で絶対に入りたいと思ってたんです」
「へえ……そうなんだ」
唸る茨戸さんの声からは、うっすらと懐疑的なニュアンスが感じられた。意味ありげな沈黙を挟み、尚も尋ねてくる。
「つまり、キッチン用品とかが好きということ?」
「はい。特に調理が便利になるやつとか、使いやすいやつとか大好きです」
「すごいな。じゃあ好きなことを仕事にしたのか」
答えを聞いて感心した表情を見せた後、茨戸さんは投げやりに続けた。
「俺はそこまでには至れてないな。営業用に製品知識が必要だから覚えたいと思ってるんだけど、未だに四苦八苦だ」
「茨戸さんは料理はされないんですか?」
「全く。まずいものを作るくらいなら外食でいいやって思うし」
きっぱりと言い切られて懐かしく思う。私も、自分で料理をするようになる前は同じ考えを持っていたからだ。
それで思わず笑ってしまい、茨戸さんが気まずそうにこちらを見る。
「昔から苦手なんだ。目玉焼きを作ろうとすれば黄身を潰して『なんだかわからない焼きに』なるし、焼きそばを作ろうとすればフライパンから具が逃げ出していく。今日のジンギスカンだって下手に触ったら肉を落としそうだから、さっきから食べる専門」
「わかります。私も昔は全くダメでした」
深く共感した上で、私は訴えた。
「ですがそういう方にこそシェフ工房の製品はぴったりなんです。『誰でもシェフの腕前に』のコンセプトに噓はありません。絶対料理上手になれますよ」
「本当に?俺みたいなのでも?」
「もちろん。私、今じゃ当たり前に自炊してます」
「それがうちの製品のお蔭だって?営業みたいなこと言うんだな」
自らも営業の人だというのに、茨戸さんは半信半疑、どころか九割くらい信じていないようだ。あからさまに腑に落ちない顔つきで呟く。
「確かに、シェフ工房のグッズで料理が上手くなったらいいとは思うけど。営業にだって役立つだろうし」
実際、料理が不得手な人からすればシェフ工房の製品もただの調理器具でしかなく、その素晴らしさはあまりよく伝わらないのかもしれない。
けど、もったいない。
料理が得意ではない人こそ、シェフ工房の製品を使うべきだと私は思う。
「シェフ工房の製品は料理を学びたての人にもぴったりの仕様なんです。使いやすいし安価だし、茨戸さんにもお勧めです」
重ねて告げると、釈然としない様子で聞き返された。
「じゃあ、うちの製品があれば俺でも料理が上手くなれるのか?」
「なれます」
「いつもはせいぜい作っても目玉焼きくらいのものだけど、それでも?」
「もちろんです」
私は二度、しっかりと頷く。
茨戸さんはそこで押し黙った。無気力そうな横顔は、これ以上話しても無駄だと言いたげにも映る。
ちょうどその時、深原室長がみんなに声を掛けた。
「そろそろ締めのうどんを配りますね!」
気がつけば目の前のジンギスカン鍋はだいぶ隙間ができていて、締めの麺を入れるいいタイミングのようだ。ラム肉の脂と旨味が染み込んだ鍋で炒めるうどんはさぞかし美味しく仕上がるだろう。
各鍋にうどんを配り終えた深原室長が、目の前の鍋にも投入しようとシリコントングを手に取った。
私はすかさず挙手をする。
「それ、私にやらせてください」
「新津さんが?今日の主役は座ってていいのに」
「たくさん美味しいもの食べさせてもらったので、少しは働きたいんです」
そう答えると、室長は目を丸くしつつもすぐにトングとうどんを手渡してくれた。
隣で茨戸さんも何事かという顔をしている。そんな彼にだけ聞こえるように、私は告げた。
「見ていてください。まずはこのトングの素晴らしさをお見せします」
シリコントングを握り締める。手に馴染む柔らかいシリコンの持ち手には滑り止めの溝もついていて、調理中に取り落とす心配がない。
トングの先端は真っ直ぐで、ぴったりと隙間なく合わせることができる。このお蔭でどんなものでも摑めるし、拾ったりひっくり返したりも容易だ。製品名は「かしわもちトング」といい、もちろん柏の葉のような形をしていることが由来だった。
「このトング、ラム肉はもちろん野菜もしっかり摑めるんです」
私は茨戸さんに説明しながら、ジンギスカン鍋の上に残った具材を一旦端に寄せる。薄切り肉も細いモヤシもくたっとなったキャベツも、このトングなら楽勝だった。
もちろんこの先端でうどんを強く摑むと、せっかくの麺が切れてしまう。そこでかしわもちの形が生きてくるのだ。
「見てください。トングの先端が波形になっているでしょう?」
トングを指し示すと、茨戸さんが覗き込むように見てくる。
「だから『かしわもちトング』なんだろ?」
「そうです。そしてその形が麺を炒める時にも活躍するんです」
ビニールから取り出したうどんは四角く固まっていた。そこに少しだけ水を加え、トングで丁寧にほぐしていく。トングの両脇は波形で、麺などをしっかりホールドできるようになっていた。
「ほら、麺を摑みやすいから炒めるのも楽なんです。それでいて切れてしまうこともないし、鍋を傷つける心配だってありません」
柔らかいシリコンでうどんを優しく摑み、鍋の上でじっくり炒める。ラム肉の脂をまとったうどんはてらてらと光り、ほんのり焦げ目を帯びていく。
「まるで実演販売みたいだ」
冗談でもない口調で呟いた茨戸さんに、私はトングを差し出した。
「やってみますか?」
「自社製品だし、触ったことはあるけど」
そう言いつつも意外とすんなり受け取った彼が、トングの端でうどんを摑む。炒めるというよりは持ち上げてみせてから言った。
「確かに、摑みやすさという点では他社製品より優れてるけど……」
「はい。長さを短くすることで、軽い力でも摑めるようにできていますよね。料理に慣れていないと力任せに炒めたりして具材が飛び出してしまうこともあるかと思いますが、このトングがあればそもそも力が要らないから、静かに炒められますよ」
トングもてこの原理を利用したものだから、作用点から支点までの距離が長くなるほど握力が必要になる。もちろん長くすることにもメリットはあり、例えば安全に揚げ物をしたい場合は長いトングの方がいい。かしわもちトングは短めなので、さっと炒めるものやひっくり返す作業に向いている。
「これが我が社のかしわもちトングの魅力です。出町さんが作られた傑作です」
私が胸を張るのとは対照的に、出町さんは照れたようで、なぜか縮こまってみせた。
「いえいえそんな……なんも大したことないんだけど……」
茨戸さんは黙ってトングの先を見つめている。考え込んでいるようにも見えるし、逡巡しているようでもあった。
「いい感じで火が通ったので、ぼちぼち食べ頃ですね」
私の言葉で我に返った茨戸さんが、炒めたうどんを周囲の人々へ配り始めた。皿を受け取っては盛りつける、その手つきはまだ覚束なさもあったものの、それでもトングがうどんを取りこぼすことはない。しっかり摑んで皿まで運んでくれる。
締めのうどんもジンギスカンのタレにつけて食べた。甘辛いタレにラム肉の脂がしみ込んだうどんは格別の美味しさで、あれだけいっぱい食べた後なのにするするとお腹に入ってしまった。
「うん、美味しい!」
出町さんがにこにこうどんを頰張ると、深原室長もしみじみと唸ってみせる。
「さすが新津さん、上手に炒めるねえ。いつもお弁当持ってきてるし、お料理上手だもんね!」
「私は大したことないです。すごいのはシェフ工房ですよ」
謙遜のつもりもなく私は言った。だけどこの場にいるのは全員がシェフ工房の社員だ。途端に歓声めいたどよめきが起こり、続いて拍手が起こり、私は急に恥ずかしくなり、俯きながらうどんを食べる羽目になった。うどんの売れ行きは好評で、みんなあっという間に平らげてしまい、ちょっと物足りなかったほどだ。
「……すごいのはうちの会社、か」
うどんを啜りながら呟く茨戸さんは、そのままじっと考え込んでいる。シェフ工房製品の素晴らしさが伝わっただろうか。私が満足感に微笑むと、茨戸さんはちらっとこっちを見た。
「本当にすごい新人が来たな」
「光栄なお言葉です」
照れつつ応じると、やがて茨戸さんは意を決したように語を継いだ。
「新津さん、もっと話聞きたいんだけど」
「構いませんよ。じゃあ次は――」
「場所移してもいい?この後、時間よければ」
時刻は午後八時を過ぎた辺り、締めのうどんも片づき、歓迎会もぼちぼちお開きが近い頃合いだった。