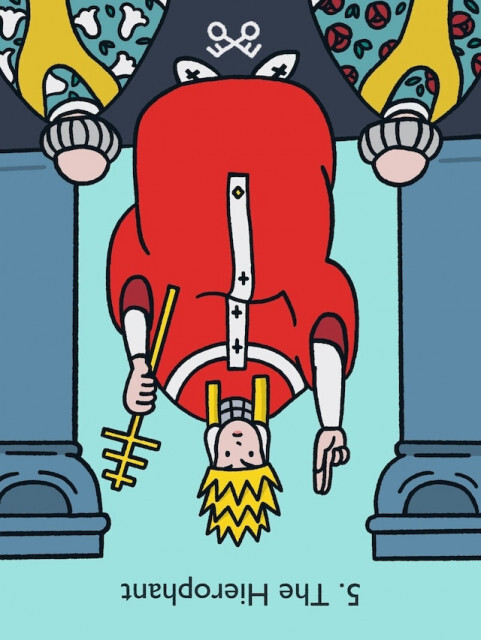これだけは知っていきたい!剪定のやり方(基礎)

剪定は適した位置で切ることが基本となります。切る位置は目的によって変わり、仕上げにもいくつかのタイプがあるので、仕上がりをイメージし、生長後の姿をシミュレーションしてから作業に取り組みましょう。
剪定後の枝の枝を切る位置生長
枝を切る位置については、大きくわけてふたつの方法があります。ひとつは枝の途中で切る方法。大きさや形を整えるときによく行う方法で枝葉を増やしたい場合を除いて、節の上で切るのが基本です。もうひとつは枝の付け根から切る方法で、これは交差枝やひこばえなどの不要な枝を切りたいときによく使います。
*枝の途中で切る
芽が出ている場合は、芽の少し上で切るのが基本。太い枝は斜めに切ると自然で美しい枝が生えるとされている。 【芽より先が長い】見栄えが悪く生長し、残した部分から枯れ込む可能性がある 【適切な切り方】芽から3~5mmを残す。芽の向きと同じように斜めに切るとよい
【適切な切り方】芽から3~5mmを残す。芽の向きと同じように斜めに切るとよい
 【芽に近すぎる】芽が乾燥して発芽しない、または枯れる可能性がある
【芽に近すぎる】芽が乾燥して発芽しない、または枯れる可能性がある

*枝の付け根で切る
枝の付け根で切るときは、できるだけ枝を残さないように気をつける。残すと、そこが枯れたり、また枝が生えてきてしまう。 【適切な切り方】立ち枝や内向枝、ひこばえは付け根から、枝が残らないように切る 【枝を残して切る】残した部分が枯れたり、イラストのように、また枝が生えてくることがある
【枝を残して切る】残した部分が枯れたり、イラストのように、また枝が生えてくることがある

剪定後の枝の生長
剪定は、「その後に枝がどのように伸びるのか」というイメージを持ちながら行うことも重要。別の見方をすると、剪定は思い通りの樹木の姿を実現するための作業と考えることもできます。作業時は芽の向きにも注意が必要です。枝が内側へと伸びていく芽を残すと、結局不要な枝となって、その枝を切ることになってしまいます。
*外芽と内芽
芽の先端が主幹から見て外側を向いているのが外芽、どちらかというと内側を向いているのが内芽。できるだけ外芽を残すのが剪定のポイント。 【内芽(うちめ)】
やがては立ち枝や内向枝などの不要な枝になる可能性が高い。樹種や状況にもより、完全にNGではないが内芽の上で切るのはあまり好ましくないことが多い
 【外芽(そとめ)】
【外芽(そとめ)】外芽の上で切ると、枝が流れるように伸びて自然な枝ぶりへと生長する。基本的に外芽で切るようにする

*切る位置とその後の生長
植物は先端に位置する芽や枝の生長が優先される性質がある。剪定した場合も枝先に近いほど、よく生長する。また、やや太い枝を節の上ではなく、節と節の間で剪定した場合は、枝数が増えることもある。 【節の上で剪定した場合】先端に残した芽から生える枝が、もっともよく生長する
 【太い枝を節と節の間で剪定した場合】樹種や環境にもよるが、切ったところから複数の枝が生えることもある
【太い枝を節と節の間で剪定した場合】樹種や環境にもよるが、切ったところから複数の枝が生えることもある

間引き剪定
枝数が多くなると、それだけの養分が必要になり、花つきや実つきが悪くなることがあります。そこで、文字通り枝を間引くのが「間引き剪定」です。方法としては切ったところから枝が生えてこないように根元から切り落とします。
*枝のつき方の違いによる剪定の仕方
枝のつき方は樹種によって異なり、大きくは「互生」、「対生」、「輪生」という3つにわけられる。間引き剪定では、そのタイプによって枝の残し方を考えるのが基本。 【互生(ごせい)】互生は枝が互い違いに生える。剪定時には左右をバランスよく残すとよい
 【対生(たいせい)】枝が対になって生えるのが対生。互い違いになるように残すと美しく自然な仕上がりになる
【対生(たいせい)】枝が対になって生えるのが対生。互い違いになるように残すと美しく自然な仕上がりになる
 【輪生(りんせい)】輪生とは同じところから3本以上の枝が生える性質のこと。2~3本を残すように切るのが基本
【輪生(りんせい)】輪生とは同じところから3本以上の枝が生える性質のこと。2~3本を残すように切るのが基本

*仕上がり
枝数を減らして、ふところ付近の日当たりや風通しがよくなれば間引き剪定は完了。全体的にバランスよく仕上げることも重要なので、ひと通りの作業が終わったら、一度離れて樹木を見るのもよい。 <仕上がり例>
写真は「カラタネオガタマ」の剪定前と剪定後。樹冠も小さくまとめたが、ここでは間引き剪定に注目。枝葉を減らして、主幹付近もうっすらと見えるようになった。
なお、このように間引き剪定で枝を透かす(枝数を少なくする)ことを「透かし剪定」といい、透かす加減もいくつかのタイプがある


切り戻し剪定
「切り戻し剪定」とは、枝を途中で切って、その切った部分から新しい枝を出させる剪定方法です。主に、大きさや形を整えるときに行いますが、同時に古い枝を新しい枝に切り変えて、「樹勢を回復する」、「花芽を増やす」などにも効果があります。
実施する際には、花芽の位置に注意しましょう。
*弱い剪定と強い剪定
剪定の世界では、枝先に近い部分から短めに切ることを「弱い」、長めに切ることを「強い」と表現する。
*仕上がり
植えている環境などに応じて、大きさや形を整える場合は、あらかじめ仕上がりの大きさをイメージしてから作業にとりかかること。太い枝の場合はノコギリを使うとよい。 <仕上がり例>放任して大きくなったヒイラギナンテンをコンパクトにまとめた例。必要があるなら、太い枝でも強めに切ってよい。
適した時期であれば、それによって樹木全体がダメージを受けることはあまりない

 <主幹の切り戻し>
<主幹の切り戻し>株立ちだが、高さを抑えるために伸びた枝を切り戻した

透かし剪定
一般的には「間引き剪定」や「切り戻し剪定」が剪定方法を表すのに対して、「透かし剪定」は仕上がりを指す言葉です。「透かし剪定」とは「伸びすぎ」、「混みすぎ」のところを透かす(枝数を少なくする)もので、程度により、「大透かし」、「中透かし」、「小透かし」という3つの段階にわけられます。
*透かし選定の程度
大胆に透かすのが「大透かし」、枝先を中心に細かく透かすのが「小透かし」、その中間が「中透かし」。樹木の種類や必要に応じて、どの程度まで透かすのかを選ぼう。 【剪定前】放任して、枝葉が混んでいる状態 【小透かし(こすかし)】樹形にあまり影響しない剪定。枝の更新と考えるとよい
【小透かし(こすかし)】樹形にあまり影響しない剪定。枝の更新と考えるとよい
 【中透かし(なかすかし)】剪定の対象は側枝が中心となる
【中透かし(なかすかし)】剪定の対象は側枝が中心となる
 【大透かし(おおすかし)】樹形に大きく影響する、大胆な剪定。主枝を付け根から切り落とすことも含まれる
【大透かし(おおすかし)】樹形に大きく影響する、大胆な剪定。主枝を付け根から切り落とすことも含まれる
 ■透かし剪定の考え方
■透かし剪定の考え方「大透かし」などの程度は、あくまでも目安で、厳密な区分はありません。剪定の専門家に依頼するときに、イメージを伝えるために覚えておくと便利です。
大透かしは樹形を大きく変えることになるので、行う前にしっかりと剪定後の姿を思い描いておきましょう。「大透かし→中透かし→小透かし」の順で行えば、より少ない手間で仕上げることができます。
■剪定に関する言葉
剪定は古くから行われてきた作業ですが、国内でとくに剪定の技術が重要視されるようになったのは明治時代からといわれています。
技術として完全に体系化されているわけではなく、同じ作業でも、別の言葉が使われることもあります。
たとえば、こちらでは「透かし剪定」として紹介していますが、これは「枝透かし」ともいいます。
また、「野透かし」という言葉もあり、これは「枝先をあまり切らないように意識しながら枝数を減らし、できるだけ自然に近い形で仕上げること」を指します。
刈り込み剪定
ここでいう「刈り込み剪定」とは、刈り込みバサミを使った剪定のことです。枝をまとめて切ることができるので、ひとつひとつの枝を順に切っていくよりも少ない手間、短い時間で仕上げることができるのがメリット。萌芽力が強く、枝をよく伸ばす樹木に向いている剪定方法です。
*刈り込みバサミの使い方
刈り込みバサミは使いやすい大きさのものを選ぶ。持つ位置を工夫すると疲れにくくなる。 【持つ位置】ハサミ側と柄側の重さのバランスがとれる位置で持つと、より疲れにくく作業できる 【刃の動かし方】一方の刃を固定して、もう一方だけを動かす。右利きなら、右手で刃を動かしたほうが作業しやすい
【刃の動かし方】一方の刃を固定して、もう一方だけを動かす。右利きなら、右手で刃を動かしたほうが作業しやすい 【切る位置が腰より上】刃が地面に向かって反るように持つ
【切る位置が腰より上】刃が地面に向かって反るように持つ
 【切る位置が腰より下】刃が自分に向かって反るように持つ
【切る位置が腰より下】刃が自分に向かって反るように持つ
 【切る位置が腰と同じ】刃が自分に向かって反るように持つ。動かす刃が上になるように持つとよい
【切る位置が腰と同じ】刃が自分に向かって反るように持つ。動かす刃が上になるように持つとよい
 ■刈り込み剪定の準備
■刈り込み剪定の準備事前の準備として、樹冠から大きくはみ出した太い枝をあらかじめ剪定バサミなどで切っておくと、よりスムーズに作業できます。
また、生け垣などをまっすぐに切る自信がなければ、水糸(仕上がりのラインの目安となる糸)を張っておくとよいでしょう。
庭木や・庭づくりについてもっと知りたい方におすすめ!
「庭木図鑑 新装版」では、今回紹介したレシピ以外にもたくさんの庭木や庭づくりに関する情報をわかりやすく丁寧に紹介しております。
あわせて読みたい
-

- 「雨の日のつるし飾り」の作り方
- にっこり笑うしずくと雲のモチーフは、窓辺に飾るのがお似合い!しとしと降り続く雨の日も、笑顔になれそ…
- (NUKUMORE)[手作り,レシピ,NUKUMORE]
-
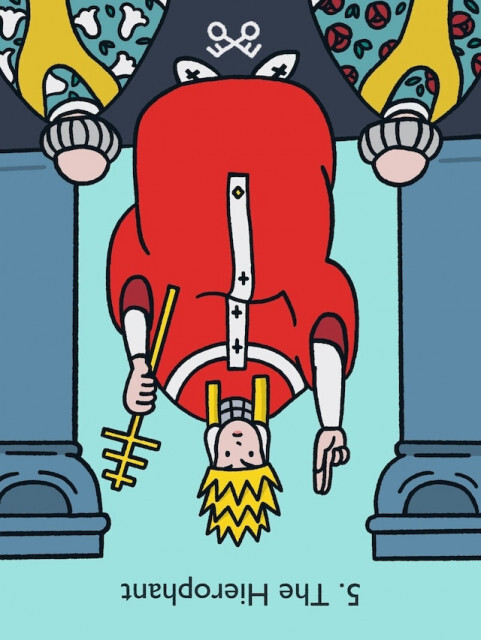
- 【いて座】2025年5月の運勢! 占い師・夜風の「タロット占い」
- 2025年5月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風…
- (All About)[自然化粧品]
-

- 赤坂の氷川公園で「ローズフェスティバル」 ガイドツアーやワークショップも
- 赤坂の氷川公園(港区赤坂6)で5月10日・11日、「ローズフェスティバル」が開催される。(赤坂経済新聞) …
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[植物]
キーワードからさがす
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。