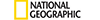教皇フランシスコはなぜ「ロックスター」のように愛されたのか

2013年3月の就任以来、世界中のカトリック教徒を導いてきたローマ教皇フランシスコ(88歳)が、4月21日、バチカンで死去した。彼の教皇選出は「初」づくしだった。南米の出身者として初、ヨーロッパ以外の生まれとしても過去1200年で初、そしてイエズス会の出身者としても初めての教皇だった。
就任後もさまざまな分野で新たな道を切り開き、バチカンに大きな変化をもたらした。教会指導部のエリート層と一般信徒との間に広がりつつあった深い溝に橋を架けることに注力し、長年受け継がれてきたカトリックの伝統や習慣に新風を吹き込んだ。
教皇への道のり
のちに教皇フランシスコとなるホルヘ・マリオ・ベルゴリオは1936年12月17日、アルゼンチンのブエノスアイレスで誕生した。若い頃に命に関わる肺疾患にかかり、肺の一部を切除した。化学技師としての訓練を受けたが、高校生のときに告解をした後、神に仕える者となるよう神の呼び出しを受けた。
1969年に正式にカトリック司祭として叙階され、母国アルゼンチンで神学を学び、さらにスペインで修練を受けた。
アルゼンチンに戻った後、1973年4月22日にイエズス会に対して最終誓願(修道会の会員として生涯を神にささげる誓い)を行い、その後まもなくアルゼンチン管区長に就任した。
1980年代から1990年代にかけて、母校であるサン・ミゲル神学校神学科・哲学科院長を務めたほか、自身の教育を続けるために国外で学び、教会の組織のなかでさまざまな役職についた。1998年にはブエノスアイレス大司教に、2001年には教皇ヨハネ・パウロ2世によって枢機卿(すうききょう)に叙任された。
次ページ:連帯を呼びかけ
連帯を呼びかけた「スラム街の司教」
聖職者としてのベルゴリオは、社会正義、地域社会への関与、キリスト教徒と非キリスト教徒との連帯を強調し続けた。贅沢に見えるものは全て拒否し、可能な限り公共交通機関を使い、前任者たちが住んでいたような豪華な住居ではなく、控えめな生活を選んだ。そして、ブエノスアイレスの最も貧しい地域での働きに力を注ぎ、「スラム街の司教」と呼ばれるようになった。
ベルゴリオの名が世界的に知られるようになったきっかけは、2001年10月に、世界代表司教会議(シノドス)で総書記を務めたことだった。この会議でベルゴリオは基調演説を行い、カトリック教会におけるさまざまな問題の指針となる報告書の監修を担当した。
同年9月11日に米同時多発テロ事件が発生した直後のこの会議を、高い能力をもって滞りなく進行させたことから、2005年にヨハネ・パウロ2世が死去した際には、新たな教皇の候補の一人と目されていた。そしてその8年後の2013年3月13日、ベネディクト16世の退位に伴って、ローマ・カトリック教会の第266代教皇として選出された。
就任時76歳だったベルゴリオは、アッシジの聖フランシスコに敬意を表し、フランシスコという教皇名を選んだ。ベルゴリオはのちに、コンクラーベで開票が行われている最中、その13世紀の聖人に思いを馳せていたと語っている。「私にとって彼は清貧の人であり、平和の人であり、万物を愛し、守る人なのです」
教皇フランシスコの公文書、声明、公式教令には、カトリック教会の現代化と、スキャンダルによって傷ついたバチカンの改革への願いが表れていた。4通の回勅(全司教に宛てた教会の教えに関する書簡)は、信仰と救い、環境と宗教との関係、世界中の全ての人々が協力することの必要性、そして心の大切さの再発見に重点を置いていた。教皇フランシスコはすぐにカトリック教徒にとって「ロックスター」的な存在となり、オンラインでも多くのフォロワーを獲得した。イベントに顔を出せば、教皇と写真を撮ろうとつめかけた群衆に取り囲まれた。
バチカンのなかでは、主にヨーロッパ人で構成されていた枢機卿団の多様化に取り組んだ。しかし、教皇自身が論争や批判にさらされることも少なからずあった。
その主な原因は教会内で起きていた性的虐待問題だったが、ほかにも同性愛や同性結婚、代理母に関する発言、教会における女性の地位向上への取り組み、離婚や避妊に対する柔軟な姿勢などで、教皇自身が称賛されたり批判を浴びたりした。
教皇フランシスコの後継者となる第267代教皇は、教皇不在の「使徒座空位」と呼ばれる期間を経て、枢機卿団の投票によって選出される。
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社