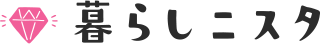できたて料理、何度になったら冷蔵庫に入れてもOK?「粗熱をとる」コツも!暑い日に役立ちますよ♪
調理した料理を冷蔵庫にしまうとき「粗熱を取ってから」しまいますよね。でも、真夏の暑い日にそのまま置いておくのはちょっと心配…。そこで今回は、「粗熱の取るコツ」をご紹介。
助家事さんが詳しく教えてくれました!
冷蔵庫に入れるために「粗熱をとる」目安温度は?

冷蔵庫の使い方などでよく目にするのは、「庫内の温度が下がらないように…」という言葉。食品が傷むのを避けるためです。
機能や設定温度など、使用している冷蔵庫の前提条件が違うので、一概に「何度のものを入れると影響がでる」とは断言できませんが、メーカーによってはその基準を「室温」としています。
※一般的な室温の目安は夏場は25~28度、冬場は18~25度です。
粗熱を取るための4つのコツ
これからの季節は30度以上の真夏日が増え、室温も湿度も上昇。できあがった料理をただ室温に置いていても、冷蔵庫に入れられる程にはなかなか粗熱も取れなくなります。
冷蔵や冷凍前に発生した菌は、冷蔵されると働きが鈍くなりますが、消滅するわけではありません。
冷凍庫でも、凍っている間菌は働きを止めますが、死滅してはいません。やはり冷蔵庫・冷凍庫で保存するまで菌を発生させないことが大切です。
1 冷蔵&冷凍庫内の整理

冷蔵庫は隙間なく食品を詰め込んでしまうと、冷気がうまく循環しません。不要なものなどが入っていないか、チェックして十分なスペースを確保しましょう。
冷凍庫は、ある程度物が詰まっている方が効率的に保冷されますが、夏場は冷凍庫の中が込み合いやすいので、新たに入れる場合は事前に整理しましょう。
2 できた料理は「平たい密閉器」に入れる

冷蔵でも、冷凍でも冷気は食品の外側から中心に向かって進みます。中心までの距離が短い方が早く冷蔵や冷凍されます。
背の高いサイコロ方型の容器にスープをいれた場合と、平たい豆腐のような型の容器にいれた場合は、サイコロ型の方が中心までの距離が遠くなってしまいます。
3 密閉器の蓋は「湯気がおさまってから」

湯気が出ている状態で、器型の密閉器に入れて蓋をしてしまうと、蓋が湯気で曇り、中にも水滴がついてしまいます。冷蔵する際、余計な水分は雑菌発生のもとになり、味も損ないます。

また、料理や食品を冷凍する場合では、料理や食品自体が冷凍されたのではなく「料理や食品に含まれる水分」が凍っています。
この凍った水分の結晶が大きく冷凍されてしまうほど、組織が傷みます。粗熱はしっかり取り、湯気で余計な水分を発生させないようにしましょう。
4 凍らせたペットボトルやタオルを保冷剤代わりに

蓋をした密閉器の上に保冷剤を置くことも効率的ですが、夏場は保冷剤が足りなくなることも。
そんな時には、水を入れて凍らせたペットボトルや、清潔な濡れタオルを密閉型の袋に入れて平らに凍らせたものも粗熱を取る保冷剤として使うことができます。
まとめ/暮らしニスタ編集部 ※人気記事を再編集して配信しています。
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.