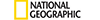剣を飲み込む、火の上を歩く インドの過激な奇術の背景に宗教あり

パラニヤマル・サンミュガムさんが次男を妊娠したとき、医師からは「帝王切開になる可能性が高い」と告げられた。しかし、母子にとって自然分娩のほうが安全だと信じたサンミュガムさんは、ヒンドゥー教の神カルティケヤに祈りを捧げた。
自然分娩で元気な子を授かることができたなら、パングニ・ウティラムの祭りで三叉槍(さんさそう、インドのシヴァ神を象徴するもの)を自らの体に刺して感謝を捧げる――彼女はそう誓った。パングニ・ウティラムは、願いをかなえてくれた神への敬意と感謝を示すため、信者たちが釘や棒、針を体に刺すヒンドゥー教の祭りだ。やがて、サンミュガムさんの願いは叶えられた。
「翌年、お腹に穴を開け、三叉槍を刺し通しました。これまでに13回やっていますが、そのたびに願いは叶えられました。体が許す限り、あと3回はやりたいと思っています」と、50歳になるサンミュガムさんは語る。
「痛みは感じません。抜くときも、肌に〈聖なる灰〉を振りかければ、出血はすぐに止まります。開いた穴も、1週間もすれば自然に塞がるんです」
インドには、こうした極端な信仰行為が行われる宗教的な祭りが他にもある。西ベンガル州で収穫前に催されるガジャンという祭りでは、男たちが鉄の棒や矢、フックを体に刺し、豊作を祈願する。火を使った儀式や釘のベッドに横たわるといった命知らずの行為も見られる。
タイプーサムという別のヒンドゥー教の祭りでは、信者たちが燃える炭の上を歩いたり、舌や頬、皮膚などに穴を開けたりすることで、神への信仰を示す。
ガルーダ・トゥッカムという儀式では、信者たちが鋭い金属製のフックを体に刺し、高くそびえる柱から逆さに吊るされる。また、インドのほか、フィジーやシンガポール、スリランカなどでも祝われるティミティという祭りでは、子どもを含む信者たちが、燃え盛る火の上を裸足で歩く。
「奇術ではありません。これは信仰です」と語るのは、信者のラム・ラクシュミー・テバルさん(39歳)。「人々は、体に穴を開けて棒や三叉槍を通します。背中に刺したフックで、オートリキシャや自動車、テンポー(三輪の乗合車)を引っ張るのです。神のご加護で、ケガをすることはありません」
宗教と奇術、インドに息づく数千年の歴史
「インドでは宗教と奇術は密接に結びつき、互いに影響を与えながら強め合ってきました」と、オーストラリアの歴史家であり、『Jadoowallahs, Jugglers and Jinns: A Magician History of India(ジャードーワッラー、ジャグラー、ジン:インド奇術の歴史)』の著者でもあるジョン・ズブレツキー氏は語る。舌を切って元に戻す、土中に埋められる、火の上を歩く、切断された手足を復元するといった数々の奇術は、ヒンドゥー教やイスラム教、仏教、ジャイナ教の修行や神話的な慣習に起源を持つという。
例えば「剣を飲む」という行為は、インドの聖職者たちが行ってきた伝統的な儀式であり、霊的な力や神々とのつながりを象徴するもので、その歴史は4000年に及ぶ。現在では、こうした儀式はパフォーマンスとして他国にも広がっている。
1970年代には、2つの雑誌『Swami(スワーミー、ヒンドゥー教の学者や宗教家などに対する尊称)』と『Mantra(マントラ、真言)』をまとめたアンソロジー『Swami Mantra』が登場し、こうした奇術が広く知られるきっかけとなった。紙面では、カミソリの刃を飲み込む、ガラスの電球を食べる、さらには銀の針を片方の目からもう一方へ通すなど、宗教的背景を持つ奇術の数々が紹介された。
次ページ:現代のインドにおける奇術と宗教
「インドにおける宗教と奇術の関係は、紀元前1700年から紀元前1500年ごろにまとめられたヒンドゥー教の経典『ヴェーダ』にまでさかのぼります」とズブレツキー氏は語る。インド医学の最古の文献とされる『アタルヴァヴェーダ』には、放浪の聖人たちは悪霊払いや呼吸法、儀式的な踊りを行い、敵に呪いをかけることもできたという記述がある。
そして、ズブレツキー氏は「何世紀にもわたり、奇術はインドの宗教儀式や宮廷生活の一部でもありました」と話す。
例えば、紀元前6世紀の仏教説話集『ジャータカ』には、蛇使いや剣を飲む芸人の描写が数多く見られる。ヒンドゥー教やイスラム教の貴族たちは、手品師や大道芸人、道化師を雇い、来客や宮廷の大臣、後宮の女性たち、遠方からの使節らをもてなすことが多かった。こうした芸人たちは、祭礼や宗教的儀式、さらには世俗的な儀式においても欠かせない存在だったのだ。
ズブレツキー氏によると、現代のヒンドゥーの奇術師たちは、パフォーマンスの冒頭で超自然的な力を持つ神インドラに敬意を表することがよくある。観客は演目にトリックがあることを承知しているが、インドラの名を唱えることで、単なる手品以上の何かであることをほのめかすのだ。
現代のインドにおける奇術と宗教
「初めて体に三叉槍を刺したのは9歳でした」と、サンミュガムさんは語る。体に不調があるときに、患部に三叉槍を刺すのはよくあることだという。彼女はこの儀式によって、人々の身体的、精神的、さらには経済的な悩みが取り除かれる様子を見てきた。
「私の義姉は、自分の家を持っていませんでした。それで彼女は『家族を守ってくださるのなら、これから一生、毎年自分の体に三叉槍を刺します』『自分の家を持てますように、息子がしっかり勉強してくれますように』と祈願しました。今、義姉の息子はエンジニアとして働き、家を1軒どころか7軒も建てています」とサンミュガムさんは言う。「そこに魔法なんてありません。信仰なのです」
奇術と宗教が密接に結びついていると考える人ばかりではない。世界的に有名なインド人奇術師であるイシャムディン・カーン氏は、自らを信心深い人間だと認めながらも、「自身のマジックは宗教とは無関係であり、長年の修練によって磨き上げた芸術だ」と語る。
1995年、カーン氏はニューデリーで、空中にまっすぐに立たせたロープを子どもが登っていくという大奇術を披露し、観客を驚かせた。このパフォーマンスは世界的に話題となり、英放送局のチャンネル4はカーン氏とこのロープマジックを「史上最も偉大なマジック50選」の20位に選出した。
ところがニューデリーでは、人々はカーン氏には超人的な力があるのではないかと思い込んでいた。カーン氏は、あるビジネスマンに「自分の娘が妻帯者と結婚しようとしている。その力でなんとか止めてほしい」と頼まれたことがあるという。
「私がスラムに住んでいるときにロープマジックを披露したことで、人々は私に何か特別な力があると思い込んでいます。あのトリックをマスターするために6年も懸命に練習したことを信じてくれません」と話すカーン氏は、「教育を受けた裕福な人々ですらそうなのです」と続ける。
ショーの後には、多くの人が近づいてきて、手相をみて未来を予言してほしい、と頼まれるそうだ。カーン氏は言う。「私がその気になれば、一晩で宗教指導者や大富豪になれるかもしれませんね」
あわせて読みたい
-

- 美食の国セネガルで、西アフリカとフランスのマリアージュを堪能
- 美食の国セネガルで、西アフリカとフランスのマリアージュを堪能行くべき理由:料理の旅を堪能しよう 西ア…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 「スパゲッティーのパンチョ」に新作トッピング、韓国屋台風ヤンニョム×チーズソーセージが期間限定で登場!
- ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」は、2025年5月16日より、期間限定トッピング「韓国風ヤンニ…
- (Walkerplus)[自然化粧品]
-

- 新潟の魅力を発信!“発酵・日本酒・もの作り”の体験型ストア「FARM8 STAND」が御茶ノ水駅構内にオープン
- 発酵食品や地域資源を活用した商品開発を行う株式会社FARM8は、JR御茶ノ水駅構内「エキュートエディション…
- (Walkerplus)[芸術,地域の魅力]
-

- 借金があっても家は買える? 5匹の猫のために貧乏作曲家が重大決心
- 借金があっても家は買える? 5匹の猫のために貧乏作曲家が重大決心 / (C)響介、ちとせ/ワニブックス激…
- (レタスクラブニュース)[新商品]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社