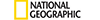かつては「神への冒涜」とされた食器、フォークの知られざる歴史

フォークは世界の食卓で広く使われている道具のひとつだ。普段、このありふれた日用品を意識することはほとんどない。しかしこのフォークには、実は何世紀にもわたって退廃、不道徳、傲慢の象徴だったという歴史がある。
歴史の大半においては、指こそが自然の食器だった。肉はナイフで切り、汁はスプーンですくうが、栄養を取るという行為は手を使うことなしに終えることはできなかった。しかし、フォークはそれをすっかり変えてしまった。
「フォークが登場したことで、食文化や食卓の大変革が始まったのです」と述べるのは、ローマの食人類学者ルチア・ガラッソ氏だ。フォークの登場によって、食事が秩序ある洗練された行為になったが、すべての人がその状態を歓迎したわけではなかった。
禁断の道具だったフォークがどこにでもある食器に変貌したことは、どんなシンプルな道具にも、大きな文化的影響力が秘められていることを示している。最初にビザンチン(東ローマ)帝国の宮廷で物議を醸してから、16世紀にイタリアのエリートたちに愛用されるようになるまで、フォークのまわりにはスキャンダルや反感、変化に対する恐怖が渦巻いていた。
フォークの登場は単なる食器の革新ではない。重大な文化の変化であり、社会的な交流や日々の食事に半永久的な影響を与えるものであり、真の文明開化とは何かという議論を巻き起こすものだった。
フォーク以前の時代
考古学的な証拠から、フォークに似た道具は古代エジプト、ギリシャ、ローマにもあったことがわかっている。しかしそれは、主に調理や配膳に使われ、食べるときに使うものではなかった。
たとえばローマの宴会では、手の込んだ銀の食器が使われることも多かったが、ナイフやスプーンを使うことはあっても、ほとんどのものは手で食べていた。
「何千年もの間、人は指で食べものを口に運んでいました」とガラッソ氏は説明する。「フォークがスプーンやナイフほど必要とされなかったのは、おそらくそのためでしょう。実際にフォークは最後に登場し、19世紀半ばに決定的に広まるまで、ところどころでしか使われていませんでした」
手で食べることが好まれたのは、それが便利だったというだけでなく、そのような文化になっていたからだ。ヨーロッパ全域で、食事のときは大きな皿に盛ったものを複数の人が一緒に食べるのが一般的だった。手とナイフで食事を取り分けることで、食卓での一体感や共有感が強まっていた。
次ページ:悪魔の槍
悪魔の槍
フォークにまつわる最初の大きなスキャンダルが起きたのは、11世紀のことだ。ビザンチン帝国の貴族の娘だったマリア・アルギユロポウリナは、ベネチアの総督の息子と結婚することになった。その結婚式の豪華な祝宴で、マリアは装飾が施された二叉の金のフォークを取り出すと、それを使って食べものを口に運んだ。
宴が終わると、ベネチアの聖職者が熱のこもった説教でこの行為を公然と批判した。「神はその叡智によって、人に自然のフォーク、つまり指を与えられました。ですから、金属のフォークを使うことは、神への冒涜にあたります」
聖職者にとっては、フォークは不要であるだけでなく、神の秩序を侮辱する行為だった。キリストとその弟子たちが最後の晩餐でしたように、食事は手で行うものであり、手と口の間に人が作った道具をはさむのは、神聖で自然な行為を妨害することだったのだ。
11世紀には、上流階級の間にフォークが広まりつつあったが、宗教指導者や文化純粋主義者たちは快く思わなかった。聖職者たちはそれを、社会的に誰が食事、権力、行動を統制するのかが変わりつつある危険な兆候だと恐れた。
宗教指導者たちにとっては、フォークが悪魔の槍に似ていることも見過ごせない点だった。このころ、三叉または四叉の槍を持つサタンがよく描かれており、フォークはそれらに不快なほどよく似ていたのだ。
ガラッソ氏によると、教会がフォークを受け入れなかった背景には、富や贅沢、不道徳に対する強い恐れもあった。「教会は質素な食卓を説いていました。手は食べものに直接触れ、貧富を問わずすべての人が持つ質素なものです。逆にフォークは、贅沢品の象徴であり、貴族の虚栄心のあらわれでした」
フォークが登場する前、食事とは文字どおり手を汚すことにほかならなかった。食の歴史に詳しい米パシフィック大学の歴史学教授ケネス・アルバラ氏はこう話す。
「中世の食卓は雑然としていましたが、社会的なやり取りによって成り立っていました。共有の皿に手をのばし、必要な量を切り分けるので、食べものともまわりの人々とも、直接的なつながりがあります。食事は親密な行為で、文字どおり同じ食べものに手をつけるのです」
たとえ王族であっても、共用の大皿から直接手で食べものを取り、食べるという乱雑で原始的な行為を通じて、人々と絆を育んでいた。
しかし、フォークが登場したことで、食卓に深い溝が生まれた。食べものは心を込めて手で分かち合うものではなくなり、刺して扱うだけのものになった。
フォークの突起は、食べものだけでなく、伝統も刺すことになった。富裕層や権力者にとっては、その点こそ重要だった。ヨーロッパの貴族や裕福な商人たちは、斬新なフォークをすぐに受け入れ、洗練されたこの道具を褒め称えた。そして、手を使って食べる人々との間に境界線を引き始めた。
次ページ:ヨーロッパ貴族に愛されたフォーク
ヨーロッパ貴族の流行に
反対派の抵抗にもかかわらず、フォークはヨーロッパの上流階級の食卓に確実に根づいていった。しかし、貴族の象徴となったことで、聖職者や庶民の反感を買うことにもなった。
ルネサンス期のイタリア貴族は、ビザンチンやアラブの文化に触れ、洗練された食器を目にする機会が多かったため、ヨーロッパのほかの地域よりも早くフォークを取り入れていた。それとともにイタリア料理自体も進化し、丁寧な扱いが求められるようになっていく。
すべりやすいパスタ、手の込んだ肉料理、シロップにつけた果実、砂糖に漬けた珍味などが流行したことで、フォークは単なる便利品を超えて、必需品となった。フォークの普及とともに料理が変化し、乾いて固く味の少ないものではなくなっていき、食の慣習や盛り付けの技術も変わっていった。
このような食の進化と同時に、さらに幅広い文化の変革が起こり、食事自体が構造的でフォーマルなものになっていく。アルバラ氏はこう述べる。
「フォークは、動物の基本的な行為である『食』との距離を表しています。フォークによって、食事の場に個人の境界ができました。つまり、文化がフォーマルさ、個人の空間、自制といった方向に向かったのです」
フォークの普及に重要な役割を果たしたのが、フィレンツェの有力な貴族メディチ家に生まれたカトリーヌ・ド・メディシスだ。1533年にフランスのアンリ2世のもとに嫁いだカトリーヌは、イタリア料理をフランスに広めただけでなく、テーブルマナーやエチケット、食器の使い方も広めた。それを象徴するのがフォークだった。
ガラッソ氏によると、当時フランスでも貴族がフォークを使い始めていたが、カトリーヌがやってきたことで、フォークはお墨付きを得たような形になり、ますます広まった。カトリーヌの豪華な晩餐と洗練されたマナーのおかげで、フォークは真新しいだけの道具ではなく、フランス貴族社会の中でほかとは一線を画す者が持つ、優雅さと上品さを示す象徴と見られるようになった。
ただし、貴族の支持を集めても、すぐに一般にまで広まったわけではない。英国や初期の米国では、とりわけ男性が抵抗した。フォークは男らしくなく、人と食べるという実際の行為を切り離すものだという考え方があったからだ。
「フランスのアンリ3世がフォークを使うのを見て、人々は『女みたいな服を着ているんだから、フォークを使うのも当然だ』と嘲笑したそうです」とアルバラ氏は言う。
しかし貴族の間で、皿やカップ、食器を人ごとに分けたいというニーズが高まってくると、フォークは単なる食器を超えてステータスシンボルとなり、富める者の地位を高め、敬虔な者を遠ざけ、洗練された者とそうでない者を分ける、排除のための道具となった。
次ページ:「フォーク以前」の食体験への回帰
「フォークはただ食べ方を変えただけではありません」とアルバラ氏は言う。「食卓でのあり方、ほかの人との関わり方、そして食べもの自体に対する考え方も変えたのです。フォークは、切り離すための道具です。人と食べものを切り離し、人と人を切り離す。そして人と一番基本的な本能を切り離すのです」
フォークの“現在地”
フォークがエリート層以外にも広まったのは、17世紀後半から18世紀にかけて、貿易やグローバル化が進み、食事が個人ごとに用意されるようになったためだ。19世紀には、ヨーロッパ全域と米国の一部で、フォークが標準的な食器になっていた。食事のエチケットが細かく定められていたフランスと英国では、とりわけフォークがよく使われていた。
日々使われるようになってからも、フォークの扱いは食文化に影響を与え続けた。たとえば、ビクトリア時代の食卓では、フォークやナイフの細かいエチケットが重視され、詳しいガイドが作られた。一方で、大量生産で多くの人のもとに行き渡るようになったことで、フォークは上流階級が使うものという感覚は失われていった。
皮肉にも、洗練されたイメージがあるせいで、今ではフォークを敬遠する人もいる。「決まったやり方でフォークを使わなければならない、という考え方は消えつつあります。ビクトリア時代の厳密な食事のエチケットが廃れたのと同じことですね」とアルバラ氏は言う。
今、料理の世界では、フォークの登場によって失われてしまったものに回帰しようという動きがある。それは、食べものに直接触れて共有するよろこびや、手で直接食べる感覚だ。
屋台やフードトラックなどのストリートフードや、知らない人同士が同じテーブルにつき、食を通して会話や共通の時間を楽しむ「コミュナル・ダイニング」など、食べものとの直接的、感覚的な関わり合いを引き立たせる体験も人気を集めている。
「世界の3人に1人は、今も手で食事をしています」とガラッソ氏は言う。「そして多くの西洋人も、手で食べることで得られる親密さやつながりといったものを再発見しています」
フォークによって、私たちの動物的な本能は抑制されるかもしれない。それでも、人はつながりを求めるものだ。食べるという行為は万国共通の言語であり、どんな道具をもってしても、完全に制御することはできない。
あわせて読みたい
-

- ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国
- ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国 毎年4月30日の夜、1万人近くが英国スコット…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 松本・岡田の古民家で「風のおとずれ」展 三代澤本寿の作品を体感できる空間
- 松本市出身の染織工芸家・三代澤本寿(1909-2002)の作品を展示する「風のおとずれ~三代澤本寿とその時間…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]
-

- 記念日・誕生日にも!プチ贅沢を楽しめるおすすめホテルビュッフェ6選
- 「パートナーの誕生日に食事をしたい」「記念日にちょっとしたお祝いがしたい」そんなときにおすすめなの…
- (ANGIE)[健康食材,果物,新商品]
-

- ゴールデンウィークの高速道路の運転で気をつける日や場所は? 雨や風による影響あり
- ゴールデンウィーク期間中の高速道路への気象影響について解説します。3日から7日にかけて、各地で低気圧…
- (tenki.jp)[アウトドアグッズ]
-

- 「生成AI」×「塗り絵」が、子どもの創造力を育む!?自分だけの塗り絵が生成できる知育アプリが誕生
- 子どもの創造力を育む!自分だけの塗り絵が生成できる知育アプリが誕生 / pearlinheart / PIXTA(ピクスタ)…
- (レタスクラブニュース)[動物]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社