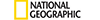男女の友情は成立する? サルに学ぶ「答えと意外なヒント」とは

ザンビアに暮らすキンダヒヒ(Papio kindae)のオスとメスの長期的な絆についての研究結果が、2025年1月21日付けで学術誌「American Journal of Biological Anthropology」に発表され、オスが一般的にメスに対して「いい奴」であり、メスと長期的な社会的絆を築くことが明らかになった。一方、他種のヒヒのオスは一般的に攻撃的で、交尾の機会を求めて競争し、社会的な優位性を争う特徴がある。このようなヒヒ社会では、友情は主にメス同士の間で最もよく見られる。
キンダヒヒのオスとメスの友情は、交尾につながることもあるが、メスが妊娠している、あるいは交尾ができない状況でも続く。このような友情は、キンダヒヒを他のヒヒとは一線を画す存在にしている。
「キンダヒヒのオスとメスの関係は、近縁の他のヒヒとは大きく異なっています」と、論文の筆頭著者で、カサンカ国立公園の群れを9年間観察した米マサチューセッツ大学アマースト校の霊長類学者アンナ・ウェイハー氏は言う。これはキンダヒヒに関する初の長期的な研究だ。
「キンダヒヒに関する初期の短い観察で、多くのオスがメスの毛づくろいをしていることがわかっていました」とウェイハー氏。「そのため、他のヒヒと何か違うかもしれないと、うすうす感じていました」
「いい奴」のサイモンと「不機嫌」なガーファンクル
ウェイハー氏によれば、野生のヒヒの同じ群れを10年以上観察していると、それぞれの個性が際立ってくるという。例えば、サイモンという名のヒヒは良き父親であり、メスのヒヒに対して「いい奴」だったのに対し、兄弟のガーファンクルは「不機嫌」だった。
「時間が経つにつれて、ヒヒのことがとてもよく分かるようになります」とウェイハー氏は言う。
科学者たちは、霊長類の社会的関係の強さを測るために毛づくろい行動に注目することが多いが、霊長類の毛づくろいはほとんど、他のメスと長期的な社会的絆を維持するおとなのメスたちの間で研究されてきた。霊長類のオスがメスの毛づくろいをするのは、通常、交尾の見込みがある場合だ。
しかし、ザンビアのキンダヒヒでは、異なる毛づくろいのパターンが現れた。43頭から89頭の個体識別可能なヒヒの群れを追跡した9年間にわたる行動データを統計モデルによって分析し、誰が交流を開始する傾向があるのかを特定した。その結果、オスとメスのやり取りの場合、オスが開始することが多いことが分かった。
次ページ:なぜオスとメスの友情が成立するのか
「これらのキンダヒヒのオスは、メスとの親密な関係や毛づくろいの関係を積極的に開始し、維持し、責任を負っているのです」と、米カリフォルニア州立大学フラトン校の生物学者で、今回の研究には参加していないナン・グエン氏は言う。「この研究は、キンダヒヒのオスが優しく、親切で、メスに対して非常に友好的であるという実証的な裏付けと証拠を提供してくれました」
オスとメスの友情は数年間続き、どちらかが群れを離れたり、死亡したりするまで終わらないことが多かった。
今回の研究対象となった群れが単なる「変わり者集団」なのか、それともこうした行動が広く見られるものなのかは、まだ確認されていないとグエン氏は言う。
ザンビアのヒヒの研究では、他種のヒヒと比較して、オス間の攻撃性が低いことも観察された。研究対象の群れに新たに入ってきたオスはあまり抵抗に遭うことなく、ゆっくりと社会的な階層が上がっていった。
これは、他のヒヒとは大きく異なる点だ。例えば、キイロヒヒ(Papio cynocephalus)の場合、アルファオス(最も順位の高いオス)は群れを攻撃的に乗っ取って、地位を獲得する。
「戦ったり、攻撃的になったりする代わりに、(キンダヒヒは)私たちが友情と呼ぶものを築くことに時間を費やしているのです」とウェイハー氏は言う。
こうしたオスとメスの長期的な友情は、最終的には交尾の機会につながる可能性もあるが、メスが交尾相手を選べるという点が、キンダヒヒを他の多くのヒヒと異なる存在にしているとウェイハー氏は補足する。
なぜオスとメスの友情が成立するのか
オスとメスが同じくらいの大きさであることが、こうした独自の社会的関係の説明になるかもしれない。
キンダヒヒは2013年まで、キイロヒヒ(Papio cynocephalus)の亜種に分類されていたが、遺伝的証拠により、独自の種であることが明らかになった。最近の研究では、キンダヒヒは身体的にも行動的にもキイロヒヒとは異なっていることも示されている。
キンダヒヒは体格がもっと小さく、オスもメスも同じくらいの大きさだ。
「(キイロ)ヒヒの場合、オスはメスよりもずっと大きいです。野外でキイロヒヒと一緒にいると、メスがオスを恐れているのがよくわかります」と、米デューク大学の生物学者で、今回の研究には参加していないマリア・クレイトン氏は言う。
メスに対して身体的威圧感が少ないため、キンダヒヒのオスがメスとの関係に多くの時間を割き、メスが交尾の選択肢を多く持つことは、クレイトン氏にとって驚きではない。
次ページ:「私たち人間の社会とある程度似ています」
「異なる交尾戦略がどのように機能するかを示す、非常に良い例です」とウェイハー氏は言い、霊長類は「生まれつき攻撃的」なのではなく、多様な交尾戦術が成功する可能性があると指摘する。
キンダヒヒの行動を研究することは、霊長類の進化を全体的に理解するのに役立つ。
DNAの研究により、キンダヒヒがヒヒの基本グループであることがわかっている。つまり、霊長類の進化系統樹において、キンダヒヒは現在も生存しているヒヒの中で最も古い種だと、ウェイハー氏は言う。キンダヒヒを観察することは、初期人類を含め、進化の圧力が他の霊長類の社会的な行動をどのように形成してきたのかを理解するのに役立つのだ。
「ヒヒの社会は、私たち人間の社会とある程度似ています」とグエン氏は言う。「キンダヒヒは私たちのように、多くの異なる生息地を獲得してきました」
ヒヒの進化も、初期人類の進化を形作ったプロセスと同様に、アフリカのサバンナ環境における気候変動と数の増加によって形作られてきたとウェイハー氏は言う。そのため、人類が社会構造を発展させた方法は、ヒヒと似ているかもしれない。
こうした類似点の研究から、人間の行動に関する理論を科学者が構築できることもある。
「なぜ社会的関係が有益なのか、そしてその結果、なぜ霊長類において社会的な関係が進化するのかについて、私たちに知見を与えてくれます」とクレイトン氏は言う。
ウェイハー氏によれば、カサンカ国立公園の研究対象の群れには、まだ調査すべきことがたくさんあるそうだ。
この群れで生まれたメスのヒヒの多くが性的に成熟しつつあるため、研究者たちはメスがどのようにオスの友人や性的パートナーを選ぶのか、そして何がメスの選択を動機づけているのかを観察できる。
「ヒヒには、オスは互いに非常に攻撃的で、メスには無関心であるというイメージが私たちにはあります」とグエン氏は言う。「私たちは最も大きな声で騒ぎ立てるという面でヒヒに注目しますが、優しさもありますし、オスのヒヒとしての振る舞い方には多くの多様性があるのです……私たちはそうしたヒヒのすべてを捉えきれていないことがあります。ヒヒの騒ぎ立てる点があまりにも興味深いからです……しかし、ヒヒの生活のより静かな面もまた興味深いのです」
あわせて読みたい
-

- ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国
- ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国 毎年4月30日の夜、1万人近くが英国スコット…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 豪華列車で楽しむマレーシア旅、4年ぶりに運行再開
- 豪華列車で楽しむマレーシア旅、4年ぶりに運行再開行くべき理由:豪華列車で旅しよう 新型コロナウイルス…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[国立公園]
-

- 「台風」去年に続き今年も4月まで発生なし でも油断せず
- 南の海上は年間を通して暖かく、冬や春も台風が発生することは珍しくありませんが、今年に入ってから、ま…
- (tenki.jp)[気候変動]
-

- ごはんの冷凍どうしてる?プラスチックの冷凍ご飯容器を卒業した理由
- こんにちは、えりです。愛知県在住の整理収納アドバイザーです。小学6年生と4年生の2児の母をしながら、パ…
- (レタスクラブニュース)[地球温暖化]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社