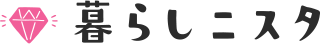「七夕」は本来、彦星と織姫の逢瀬を祝う日じゃないんですよ。開運・良縁を呼ぶために何をする?
日本の四季を彩る旧暦と二十四節気ゆかりの行事には、開運・良縁などを呼び、邪気や病を祓うヒントがいっぱい。暮らしの中でできること、少しずつ始めてみませんか?
今日は何の日?
今日7月7日は「七夕(七夕の節句)」。笹竹と短冊に願いをかける星祭りです。
彦星と織姫の逢瀬を祝う年中行事ですが、かつてはお盆の前に身を清め、厄を祓う風習として重要でした。
笹飾りは神様の依り代。七夕のしつらいを整える
古来、人々は松や竹のような常緑の植物を神様の依り代として大切にしてきました。七夕の笹竹もまた同じ。
生命力にあふれ、真っすぐ空に向かって伸びる笹竹に願い事を託します。
願い事を書く短冊にも秘密があります。いわゆる「五色の短冊」とは、赤・青・黄・白・黒の5色。古代中国の思想である陰陽五行説から生まれ、人が備えるべき五つの徳をあらわすともいわれています。
ほかにも短冊を明るく照らすための提灯や、裁縫や手芸の上達を願う紙衣など、それぞれの笹飾りのいわれをひも解いていくと、深い意味を知ることができます。
近ごろでは、生花店やスーパーの生花コーナーの片隅に、ほどよいサイズの笹竹が登場するようになりました。
折り紙で飾りをこしらえたり、願い事をあれこれ思案したりしていると、不思議と気持ちが華やぎます。
星伝説と棚機女神話
七夕は、天の川を隔てて暮らす彦星と織姫が年に一度の再会を果たすと伝わる日。
牛飼いの牽牛星(彦星)と機織りを生業とする織女星(織姫)にまつわる、古代中国の星伝説がもとになっています。
この話を伝え聞いた奈良時代の貴族たちは、二人にお供えをささげ、織姫のように裁縫や手芸が上達するよう願う「乞巧奠」という行事を行いました。
さらに衣を織る乙女を意味する「棚機女」がまざり合い、「七夕」の名前が生まれたと考えられています。
江戸時代になると庶民の間にも七夕行事が広まり、願い事をしたためた短冊や各種の飾りを、笹竹に吊り下げるようになりました。
その一方で七夕をお盆の準備期間ととらえ、お墓を掃除したり、水浴びをして身を清めたりする風習が残る地域もあります。
七夕の翌日に笹飾りを海や川に流す「七夕送り」も、お盆の前に災厄を祓っておくために行われていたならわしです。
福を呼ぶ習慣と小さな行事で
毎日をていねいに。ゆっくりと
福を呼ぶ、日本の小さな行事を1年分たっぷり紹介。日本古来の二十四節気に寄り添って、縁起よく暮らすためのヒントが満載です。

『福を呼ぶ四季の習慣 小さな日本の行事』本間美加子著 1,650円/主婦の友社
Amazonで詳しく見るあわせて読みたい
-

- ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、バラのブーケをテーマにしたパフェ
- 「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」(千代田区紀尾井町、TEL 03-3234-1111)36階の「All-Day Dining …
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[花]
-

- 現代の栄養学から見ても理にかなう古来の知恵 回復のためのレシピ
- 暮らしの知恵だった数々の“自然のくすり”4月23日、日本で古くから利用されてきた“自然のくすり”のレシピな…
- (美容最新ニュース)[植物]
-
- 月の食費2万円台の人が「スーパーで絶対に買う節約食材」3つ。迷う理由はありません!
- スーパーへ買い物に行くと、どれもこれも食材が高い!もはや「何を買えば節約になるのか分からない&hellip…
- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]
-

- 北習志野駅周辺「エビスきたなら商店会」 夏のイベントは5月開催に
- 北習志野駅からほど近い場所で60店舗ほどが加盟している「エビスきたなら商店会」で昨年まで7月に開催して…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[七夕]
-

- アウトドアからビジネスシーンまで幅広く活躍!【シチズン】の腕時計がAmazonにて登場!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[新商品]
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.