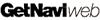スマートホームとは? 3大メリットから活用方法まで専門家が徹底解説【2025年最新版】
スマートホームとは、インターネットを通じて遠隔操作できる家電や住宅設備を備えた住まいのこと。この記事では、その魅力やメリット・デメリット、必要な機器、活用事例などについて、IT・家電ジャーナリストの安蔵靖志さんに解説していただきます。

スマートホームとは
スマートホームは、BluetoothやWi-Fiなどの通信機能を使って住宅内の家電やセンサー、設備などが相互に連携し、スマホアプリや音声アシスタントを内蔵するスマートスピーカーなどを用いて家のさまざまな機能を管理・制御・自動化できる機器やサービスの総称です。
既存の家電を遠隔操作できるようにするスマートリモコンを使ってエアコンを外出先から操作したり、既存の玄関錠に取り付けるスマートロックによってカギなしで玄関ドアを開閉できるようにしたりと、日々の暮らしをより便利で快適にできるのが魅力です。
スマートホーム機器は、「単体でスマホアプリなどから操作できるスマート家電」と「既存の家電や設備をスマート化(スマートホームに対応)する機器」の二つに大きく分かれます。
スマート家電はWi-Fi通信機能を内蔵することでインターネットに接続し、スマホアプリやスマートスピーカーなどから遠隔操作や自動化が可能。エアコンなどはスマート化が進んでいるカテゴリーの一つですが、導入するためには買い替えや新規購入が必要になります。
他方、既存の家電や設備をスマート化する製品にはスマートリモコンやスイッチロボットなどがあります。スマートリモコンの場合、赤外線リモコンによる操作が可能な機器や設備なら、ほぼすべてスマホアプリから操作できるようになるため、買い替えが不要。スイッチロボットを使えば、照明スイッチや給湯機器のスイッチなどを遠隔操作で押せるようになります。
今後は多くの機器や家電がスマートホームに対応していくと思われますが、スマートホーム化のためにわざわざ家電や設備を買い替えたくないという人には、こうした既存の物をスマート化する機器を導入するのが最も近道でしょう。
スマートホームの普及を加速させる「Matter」
スマートホームはアマゾンやグーグル、アップルなどの企業がそれぞれ独自企画を打ち出したことで互換性が乏しかったこともあって、普及がまだまだ進んでいない状況にあります。しかし、国際的な規格団体であるCSA(Connectivity Standards Alliance)が2022年にスマートホーム共通規格「Matter(マター)」を策定したことで共通化が進み始めました。CSAには多くのスマートホーム関連企業が参画しており、今後さらなる普及が進むと考えられます。
スマートホームの導入に必要な機器

スマートホームの導入に必要な機器を具体的に紹介していきましょう。
スマートリモコン
既存の家電をスマート化するだけでなく、さまざまな機器をインターネットに接続する「ハブ」の役割も担うのが、スマートリモコンです。家電を赤外線で操作する学習リモコン機能に加えて、温湿度センサーや照度センサーなどによって室内環境をセンシング(感知)できる機能を備える製品もあります。
また、スマートホーム機器の中には単体でインターネットに接続できず、Bluetooth通信経由でスマホと連携する製品があります。スマートリモコンはそのような機器を遠隔操作するためのハブとして機能する場合もあります。

スマートスピーカー/スマートディスプレイ
音声アシスタントを搭載し、声で家電や設備を操作できるようにしてくれるのがスマートスピーカーとスマートディスプレイです。
プラットフォームは大きくアマゾン、グーグル、アップルの3社に分かれており、アマゾンは「Amazon Alexa」アプリに対応する「Amazon Echo」シリーズ、グーグルは「Google Home」アプリに対応する「Google Nest」シリーズ、アップルは「ホーム」アプリに対応する「Home Pod」シリーズを展開しています。

どのスマート家電もスマホアプリで機器を管理・操作できて、スマホの音声アシスタント機能を利用することで音声操作もできるため、スマートスピーカーやスマートディスプレイは必須ではありません。
しかし、ハンズフリーで音声操作したり、音楽やラジオを聴いたり、離れた家族との遠隔コミュニケーションや見守りに利用できたりと、スマートスピーカーやスマートディスプレイにはさまざまなメリットがあります。
おすすめのスマートホーム機器
各メーカーのスマートホーム機器は、そのメーカーが用意するスマートホーム管理アプリで管理および操作ができるようになっています。
アマゾン、グーグル、アップルのプラットフォームと連携することで、Amazon AlexaアプリやGoogle Homeアプリ、ホームアプリなどで一括管理ができるものの、メーカーごとのアプリのほうがより細かい操作が可能です。そのため、メーカーが異なる製品をバラバラに購入するよりも、どこかのブランドでまとめたほうが管理しやすくなります。
そのような観点から、複数のスマートホーム機器を提供している主要なメーカーを三つ紹介しましょう。
1: SwitchBot「SwitchBot」ブランド
スマートリモコンから各種センサー、カメラ、照明、スマートロック、スマートカーテン、ロボット掃除機など、かなり幅広い製品群を展開するスマートホーム機器の大手ブランドです。
2: TP-LINK「Tao」ブランド
スマートリモコンから各種センサー、カメラ、照明、スマートドアホン、ロボット掃除機まで幅広く展開するブランドです。
3: Aqara「Aqara」ブランド
スマートリモコンから各種センサー、カメラ、照明、スマートカーテン、スマートドアホンなどを展開するブランドです。転倒検知する高度な人感センサーなども販売しているのが特徴です。
これらのブランドから一つだけを選ぶ必要はありませんが、自分の用途に合わせて主軸となるブランドを決めることがおすすめです。
スマートホームのメリット・デメリット

スマートホームのメリットとデメリットを押さえておきましょう。
スマートホームの主なメリットは、家の「快適性」「利便性」「安全性」を向上させることです。スマートエアコンを導入すると室内環境を快適に保つことが可能。外出先から家電を遠隔操作することで利便性がアップします。スマートロックやセキュリティカメラなどを導入することで防犯対策を強化し、安全性も高めることができます。具体的な事例については後ほど詳しく紹介します。
反対に、スマートホーム導入のデメリットとして挙げられるのが初期コスト。スマート家電もしくはスマート化機器を購入しなければならないうえ、アプリの導入や初期設定が必要になります。スマートホーム機器をスマートスピーカーで利用するために機能を連携させる設定なども必要になり、大きなハードルになることがあります。
また、BluetoothやWi-Fi通信がうまく行かなかったり、クラウドサービスに接続できなくなったりするとスマートホーム機器を使えなくなるのもリスクの一つです。

スマートホームの活用事例
スマートホームの活用方法を快適性、利便性、安全性の三つの観点から紹介しましょう。
【快適性】エアコンの遠隔操作やカーテンの自動化
スマートエアコンの導入もしくはスマートリモコンを利用してエアコンをスマート化することで、快適な住環境を保つことができます。例えば、夏の暑い日に外出先から遠隔操作でエアコンの冷房をオンにすることで帰宅前に室温を下げ、涼しい自宅に帰ることができます。ペットがいる家庭の場合、センサーで室温上昇を検知したら自動的に冷房をオンにするといった使い方もできます。
給湯器や床暖房のスイッチにSwitchBotを取り付ければ、帰宅前にお風呂のお湯はりをしたり、部屋を暖めておいたりすることも可能です。

カーテンレールにスマートカーテンを取り付けることでカーテンの開閉を自動化すれば、起床時刻に合わせてカーテンを開けることで日の光によって目覚めることもできます。

【利便性】家事の自動化と音声操作
スマートホーム機器を導入すると、家事の自動化や、生活におけるちょっとした利便性の向上なども実現します。
例えば、ロボット掃除機を導入することで日々の掃除をお任せできて、帰宅前に遠隔操作で掃除機がけを指示するといった使い方があります。遠隔操作が可能なスマート洗濯機なら、ちょうど帰宅時に洗濯・乾燥が終了するように指示することで、効率的に洗濯物をたたんでしまうこともできるようになります。


また、音声アシスタントを搭載するスマートスピーカーやスマートディスプレイ(ディスプレイを搭載したスマートスピーカー)を導入したり、スマホの音声アシスタント機能を利用したりすることで、声をかけるだけで家電を操作することも可能です。
例えば、「アレクサ、テレビを消して」「アレクサ、エアコンを消して」などとリクエストすることで、スマホやリモコンを取り出すことなく家電を操作できます。
安蔵さんは、給湯器のスイッチに取り付けたスイッチロボットを押す動作を「お湯はり」という命令にして保存することで、「アレクサ、お湯はり」と言うだけでお風呂のお湯はりができるように設定しているそう。「わざわざ離れた場所にある給湯器まで歩いていくことなく、お風呂のお湯はりができるのはかなり便利」と言います。
【安全性】防犯強化や熱中症対策
スマートホーム機器は防犯対策や見守りなど安全性向上にもつながります。例えば、屋外や室内にセキュリティカメラを設置することで侵入者や不審者対策ができる一方、スマホと連携できる「スマートドアホン」を導入することで外出先から訪問者を確認したり応対したりできるようになります。

玄関錠に取り付けるスマートロックを導入すれば、カギを持たずに施錠や解錠ができるようになるだけでなく、カギの閉め忘れを防ぐことで侵入者対策にもつながります。指紋認証や暗証番号認証などに対応するスマートロックであれば、子どもにカギを持たせなくて済むため、カギの紛失も未然に防げます。
特に一戸建ての場合、侵入者対策のための屋外カメラやスマートドアホン、施錠対策のためのスマートロックの導入がおすすめです。
なお、スマートエアコンの導入は家の快適性を向上させるだけではなく、熱中症対策にもつながります。暑い日でも家の中でより安全に過ごすことができるでしょう。

スマートホームに関するよくある質問

Q: どこから導入すればいい?
A: スマートホームを導入するためには、家電をスマート化できるスマートリモコンの導入から始めましょう。Bluetooth通信機能しか持たないスマートホーム機器を遠隔操作可能にするハブにもなるため、一家に1台は必要です。スマートリモコンは赤外線で家電を操作するため、操作したい家電が設置されている部屋ごとに設置する必要があります。それに加えて、スマートロックやスマート照明など、必要な機器をそろえるといいでしょう。

Q: 初期費用やランニングコストはいくら?
A: 初期費用はスマートリモコンをはじめとして、必要な機器の購入費がかかります。スマートホーム機器の遠隔操作はアプリやクラウドサーバー経由で行いますが、基本的にランニングコストはかかりません。ただし、一部の製品については月額費用がかかる場合もありますので、製品を購入する際にはチェックしてみてください。
Q: 機器の定期的なアップデートは必要?
A: 各種スマートホーム機器はインターネット経由で遠隔操作ができるため、スマートホームアプリのID・パスワードをしっかりと管理しましょう。また、アプリを定期的にアップデートするだけでなく、アプリに促された場合はスマートホーム機器のファームウェア(本体内ソフトウェア)のアップデートも適宜実施してください。
Q: 音声アシスタントが誤作動する場合はある?
A: アマゾンは「アレクサ」、グーグルは「オッケーグーグル」、アップルは「ヘイ、シリ」といったように、「ウェイクワード」と呼ばれるワードで音声アシスタントを呼び出すことができます。
このウェイクワードは変更することも可能ですが、どうしても誤作動してしまう場合があります。何も話していないのに「今日の天気は……」などとスマートスピーカーが話し出すなんてこともたまにはあります。
ただし、スマートホーム機器を操作するためにはある程度の長さの言葉を話す必要があるため、機器が誤作動してしまうことはほとんどないでしょう。
Q: 停電時にスマートホーム機器はどうなる?
A: 停電時には電化製品が作動しないため、スマートホーム機器も使えなくなってしまいます。停電が復旧してネットワーク環境が元に戻ったら、停電前と同じように使えるようになります。
【まとめ】最初の一歩を踏み出そう!
これまで見てきたように、スマートリモコンを導入するだけでもスマートホーム生活をスタートできます。最初は数千円もあれば開始できるので、ぜひ快適で利便性が高く、生活の安心・安全性も高められるスマートホーム生活を始めてみてください。
【解説者】

安蔵 靖志 Anzo Yasushi
ITジャーナリスト・家電エバンジェリスト。一般財団法人家電製品協会認定 家電製品総合アドバイザー、スマートマスター。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。X
スマートホームの今とモノがわかる!「スマートホームの始め方」特集

あわせて読みたい
-

- 【情熱大陸でも話題になった船上の助産師】自身のスキルと人間力が試される場所へ。助産師の小島毬奈さんが地中海の救助船に戻る理由
- 地中海で活動する難民救助船から見えてくる世界とは。 命がけで海を渡る――それはドラマでも映画でもなく、…
- (CREA WEB)[日常のスポーツ]
-

- 「でも」「だって」「どうせ」が口ぐせの人は要注意!貧乏を抜け出すための習慣とは?
- 「どうせ私なんて……」「でもそんな余裕ないし……」「だって無理でしょ?」。日々の言葉づかいは、思ってい…
- (All About)[動物]
-

- シンプルで使いやすい!【キューアンドキュー スマイルソーラー】の防水ソーラー腕時計がAmazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[気象]
-

- 連休最終日の6日は西〜東日本で大雨 9日〜10日も大雨の恐れ 沖縄では雨の季節へ
- ゴールデンウィーク最終日である明後日6日(火:振替休日)は、雨の降る所が多く、西〜東日本を中心に大雨と…
- (tenki.jp)[健康]
-

- リミットレス・ペンダントに驚きの声が続々!「記憶力の悪い人にピッタリ」
- 「過去24時間で1万個が売られて、今後数週間で世界中に配送される」と海外で注目を集めるウェアラブルデバ…
- (GetNavi web)[GetNavi web]
キーワードからさがす
(C)ONE PUBLISHING